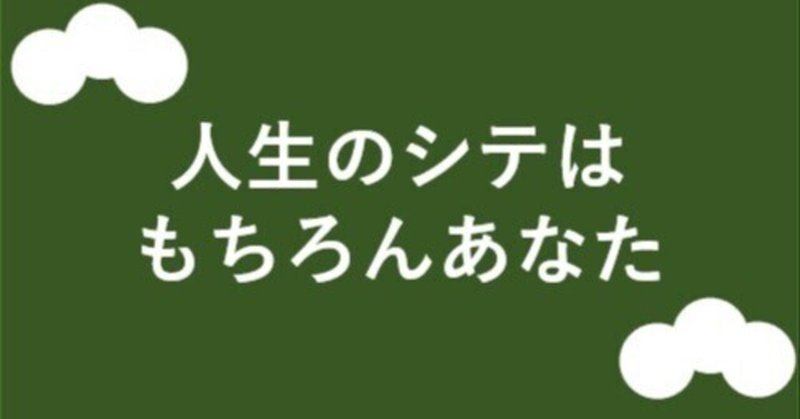
【中編小説】猿楽町口伝
1
あんなビルが建っちまいましたけど、数年前まではあそこには果物屋だの薬局だの履物屋だの狭い軒の店が何件か連なってましてね、そん中になかなかくせのある古本屋があったんですわ。狭い間口の両側に天井までの本棚があって、そこに本がぱんぱんに詰まってるから、脚立で上がって上のほうのをちょっとでも無理して抜いたら崩れてくるんじゃないかってひやひやなんですわ。店の主人はそんなのに手を貸すこともなく奥のカウンターの中で黙々と分厚い本読みながらこっちも向かずに「気を付けてね」なんていいくさってねぇ。
・・・はい、アナゴですねぇ。今日は金沢八景の小柴から活きのいいのが入ってますよ。握りにしますか?
その主人も去年死んじまっちゃったんですがね。いつも黒い丸首のセーター着てねぇ、きっと何枚か持ってたんでしょう、寒い日には首にマフラーなんかを巻くんですわ。たまには母ちゃんから借りてきたんだろう花柄のスカーフを巻いたりする日もあってね。そんな日はたぶんお目当ての女学生でも来る日だったんだろうなぁ。髪の毛はいつも駿河台坂の途中にある床屋でこざっぱりさせて、まあ独特の洒落心を持ってる奴でした。カウンターの中は日中でも薄暗いのに根が生えてるみたいに一日中ずっと座って本読んでてね、あたしが店の仕込みに行く前に顔出すと、縁の太い黒い眼鏡をずり下げて見上げながら言うんだ「おや、脳みそがかゆくなったか? どうだお茶飲んでくかい?」なんてね。あたしはどっちかというとあの本の古臭いにおいが好きでつい寄っちゃうわけだけど、しばらく本読んでないのが顔に出てたのかねえ、本読んでないと脳みそがかゆくなるって言い方で馬鹿にするんですよ、奴は。
店名は家伝文庫ってんです。花伝ってのは風姿花伝の花伝なんだそうで。そう、さすがよくご存じですね、能の世阿弥が残した奥義書のことですわ。奴はべつに能の関係者でも何でもないんだけど、この中の言葉が心に響くってことで名前にしたらしいんですねぇ。なんで世阿弥かって? そりゃここが猿楽町だからですわ。奴はもうちょっと下町のほうの生まれだけど、ここに店持って自分の好きな本並べて売ってるうちに、ここら辺は観世派の屋敷があったから猿楽町って呼ばれるようになったって知ってさ、猿楽ってのは後の能ですからね、そんでどんどん興味持っていって関係する本集めてるうちに棚の本がそんなのばっかりになっていってね、それで店の名前も変えちまったんですわ。昔は駿河堂とか言ってた気がするがな…。奴によると能は秀吉や義満や家康なんかの時の権力者にもてはやされて、衣装はじめいろんなもんが上等なものになっていったんだけど、そもそも猿楽も初めのころはそんなんじゃなくて民間の娯楽だったそうなんです。当時の観阿弥世阿弥もあんな能楽堂の磨き上げられた舞台じゃなくて寺の境内や屋敷なんかにも呼ばれて演じてたってわけです。今は能楽師たちの中には人間国宝なんて言われる人もいて雲上の人みたいに感じるけど、元を正せば宮大工なんかと同じように日本伝統を継承してくれているありがたい人たちなんですわ。
・・・・おい正太、酒井さんところに赤だしお出しして。それと、干瓢そろそろ冷めたから移しといて!
ええ、お客さんが言うようにここら辺は古本屋以外にも本の卸問屋、まあ取次っていうんですけどね、そういう店が小さいけどたくさんあったんですよ。それぞれ得意なジャンルの新刊を置いて書店からの注文を待つんですわ。何しろ出版社ってのは全国に6000社あったんですから、そうやって捌かなきゃ日の目を見ない本だらけになっちまう。一般の書店もいろんなジャンルのものを並べてなんぼなわけだから、そんな6000もの出版社とやり取りなんか到底しきれないですわね。だから中間に入って「ウチなら医学書はどんどん売りますよっ」て言っとけば、そういう本作ってる出版社から新刊が集まってくるんですわ。本作るほうも真剣ですよぉ。何しろ読む人の知識を上回る内容にしないと欲しがられないですから。その時にそのジャンルに一番詳しい専門家に話聞いてなるべく早いうちに本にする。それを新聞なんかで宣伝する。それ見て読みたいって世間の声を聞いて書店が取次に注文するわけです。出版社も在庫を切らしたらせっかくすぐに読みたい気持ちを逃しちまうから、余裕もって刷っておく。でも、そん時読みたい人の目の前にすぐ用意できないと、もう飽きられて余っちまうんですわ。
奴、しきりに言ってましたよ、棚にこんだけすばらしい話たちが並んでるのに誰も読んでくれやしない、それが本当に悲しいって。これじゃあ美味しいものを箱に入れたまま店頭に置いてるみたいだって。箱を開けて中身を見せて、どんだけ美味しそうか、どんだけ美味しいかアピールしなくちゃいけないのに方法が見つけられずにいるって。知りたいって知的欲求に十分に応えられる内容がゴロゴロあるのに、あとから後からどんどんやってくるのに、ろくすっぽ読まれもしないでどんどん棚に積まれていくのを奴は「知が地層のように溜まっていって知層になるんだ。かれこれ千年以上積み重なって今の知層は相当分厚くなってるぞ」って言ってねぇ。そんな知層の中にも、さらにとっておきのがあってね、大体そういうのは棚の上のほうに置いてあるんだけど、カウンターに持って行っても奴は絶対売らねえんですよ。本を抱きしめてね「これは置いとくけど売るつもりはねえ」っていうんです。見せびらかすために店に置いといたんですねえ。奴らしいわ。
2
こっちの世界に来ちまったが、無念だらけで成仏出来ちゃいねえよお。あんなに集めた本たちは結局瓦礫と一緒にダンプカーの荷台に積まれちまったんだからな。そりゃまあ相当に古いもんばっかりだったけど、れっきとした本だよ。内容は何も古びちゃいないよ。確かにネットで売るには本が傷んでりゃあ状態解説のところに「中古商品 傷だらけ」と書くしかないから、まず売れないだろ。店頭でよっぽど中を読みたくなった客しか買わんだろうな。それにしても瓦礫と一緒ってのは悲しすぎるよ。俺にとっちゃ本ってのはなんでも知りたいことに答えてくれて、新しいことを教えてくれた掛け替えのない存在なんだよ。それをただの壁紙みたいに考えやがったんだろうな、そりゃおんなじ紙だけど本には無限の知恵が刷り込んであるんだ。そもそも、あれだけ本を集めたのに読んでくれたのはほんの少しの人たちだったのも悲しいわ。風姿花伝なんて、果たして世の中の何人の人が読んでくれたんだろ? 能の専門書だと思って手を出しやしないんだろうけど、世阿弥は相当考え抜いてあの風姿花伝を書いたんだよ。あの中に人生訓がちりばめられている。
読まなきゃなあ本ってのは。置いといても何の価値も生まれない、シミが湧いて朽ちるのみだ。シミって、あの斑模様のことじゃないぞ、紙魚と書いてシミだ。魚みたいにくねくね動くから紙の魚だ。本の中で7年くらい生きるっていうんだから、本が立派な住まいなんだな。本の中に住めるなんて幸せなことじゃないか。まあ今はそんな風に思う奴はもはや少ないんだろうなぁ。そういう奴らは普段時間を費やすのはテレビやスマホだろ? ページをめくって文字を追いかけるなんてことやりゃしないわな。そんな奴らにスマホでも読めますよって電子書籍を勧めても「やっぱり本は紙じゃないと」とか天邪鬼なこと言って、さらに本を遠ざけるんだ。そういった意味じゃあ、本は今や鰹節やスルメなんかの乾物と似たようなものなんじゃないかな。「やっぱり昔ながらのものっていいよね」とか言いながら相当気が向いた時しか手を出しやしない。鰹節なんて今や削り節の小分けパックが主流で、丸の状態から削る奴なんか板前さんくらいしかいないんじゃないか? 読書が鰹節を削るみたいなことになってしまってるんだわ。
本の中身もパックされたみたいにタブレットの中の電子書店で数百数千の本の表紙が並べられてるけど、見せられるものが多すぎて開かれすらしないものが大半だ。どっかで聞いたことがあるようなタイトルのものなんて気にも留められないんだな。そんだけ競争相手がたくさんいる中で、相も変わらず同じことをやってちゃいけないんだ。いつの時代も人々は飽きっぽいんだ。つまらなきゃあっさりと削除される。だから常に新しくて珍しいことを提供しなきゃいけないわけだが、世阿弥はそれを”珍しきは花”と言って尊重したんだ。毎回同じ演目では飽きられるから新しく珍しいものをここぞというときに繰り出さなくてはいけないってことだ。さらに、いつでもそういった事態に対応できる心構えをしておくことが大事で、それが”秘すれば花”だ。繰り出しまくっちゃいけない、ずっと隠しておいてここぞのときにきちんと出すことが大事なんだ。ここぞってのには2つあってな、男時(おどき)って言って、こっちに勢いがあるときのことで、それに対して女時(めどき)、これはあっちに勢いがあるときのことだ。今は備えよ、そして場の機をとらえてどうやって花を咲かせるか考えることが大事なんだ。世阿弥は新しい作品を効率よく生み出して珍しくて飽きさせない方法をいろいろ発明したんだよ。ほら、漫才師のミルクボーイってやつらの芸風はワンパターンなんだが、素材を変えるとなんだか聞けちまうじゃないか。それはいうなればマーケティングなんだな。コトラーやドラッカーなんかが言ってるのと一緒だ。”名所教え”とか”遠見”って観光旅行感覚を入れてみたり、”複式夢幻能”とか”二ツ切の能”なんかの方法で夢を巧みに使って物語の視覚化装置にしてみたりした。それを演じる時には源氏物語などよく知られた物語の本説から連歌のように利用することで観客がイメージできる領域の中で能を進めたんだな。他にも”冷えに冷えたり”って、渋い芸風のことをそう呼んだらしいんだけど、渋さなんかも追及していたんだ。”花と面白きと珍しきと、これ三つは同じ心なり”って、今でもその重要さは何も変わっちゃいない。私はいろんな人たちの自費出版なんかも吟味して店頭に置いたがな、宣伝なんて何もされていない本だけにいかにこの本の存在を知らすかってのが重要なんだ。店頭で大事なのは興味を持ってもらって目次でも書き出しでもいいからとにかく手に取って見てもらうことだ。棚に並んでる中から背表紙のタイトルに興味を持ってもらって、そこから右手の人差し指を背表紙の上にひっかけて棚から引っ張り出さない限りその先、人の目に触れることは無いんだわ。今じゃあアマゾンなんかの電子書店だと背表紙じゃなくて表紙を並べてくれるから、書店でいえば平積みだよな、そりゃ装丁を工夫できるから目につくかもしれないけどさ、うちみたいな狭い古本屋は平積みにできるようなスペースはないから背表紙、つまりタイトル勝負だ。そんでもって返本なんてシステムもなくて棚に挿しておくしかないから、選ばれずにそこに居残ってる本たちは数十年経てばさすがに朽ちていくわな。ここまで朽ちかけてりゃさすがに申し訳なくてアマゾンにも出せないわ。
3
あたしゃ神田須田町で生まれましてね。なんだか寿司屋の典型みたいですが、親や先祖は海運の仕事だったんです。海運って言っても、正確には日本橋川の鎌倉河岸で材木なんかの荷揚げをしてただけだから、そんなおっきなもんじゃなかったんです。でも、親父の頃まではまだその仕事は残ってて、親父は荷揚げの棟梁だったそうだから、まあ生活に窮してはいなかったんですね。だから河岸で融通の利いたもんをちょくちょく持って帰ってくれたんです。千葉の浅利だとか、芝のアナゴだとかキスだとか。そんなのを母ちゃんが刺身で食わせてくれるもんだから、この通り今は寿司握ってんです。あ、これまでは結構大変でしたよ。当然仕入れや捌きや握りを教えてくれる人なんかいないから、近所の寿司屋に親から口きいてもらって15で丁稚に入ってさ、それから10年ほど働いたらその寿司屋が地上げにかかってね、亭主はそんとき78だったからもう店を畳んじまったんです。25じゃあまだ店も持てねえし、何よりまだまだ修行が足りねえ。何件か戸をたたいたんだけど、雇う余裕はねえってみんな断られて、しょうがねえから神田を出ていっそ銀座にってことででっかい寿司屋に入ったら全国から修行に来てんですよ。俺なんかそん中じゃ年が上のほうだから年下の先輩は教えるのを敬遠してねぇ、しょうがねえから見て盗もうってことにしたんです。とにかく見て、頭に叩き込んで、そのうち仕込みまではやらせてもらえた。それから5年したら一通りのことは覚えた。金もそこそこ溜まったから、ちっちゃな店を持つことにしたんです。夢の自分の店ですよ。ただね、握りは全然経験がないわけですよ。店を開くまでひたすら練習しましたね。自分で満足いくもんになるまで、半年かかりました。それまでは暖簾を出さずに細々と知り合いを呼んで、気持ちだけでも置いてってもらえるとありがたいって、大したネタも置けてないのに図々しいですよね。でも中にはいらっしゃったんです、こんなにもらえないってくらい大盤振る舞いにお金を置いて行ってくれる人がいて、「将来はタダメシ食えそうだわ」なんて冗談ぽく言ってね。その人は今でもいらっしゃいますがお代はもらってません。そりゃもらえないですよぉ、あんなに支えてもらったんだから。それでもその人、毎年正月明けに神田明神のでっかい熊手を持ってきてくれるんです、あ、そうそうあそこにある熊手ですわ。派手に1万円札が何枚も挟んであるでしょ、あの状態で持ってきてくれるんです。もうずっと頭が上がらないですわ。
・・・おい正太、仲田さんにアガリお出しして!
あたしゃね、この仕事飽きたことが無いんですよ。季節のものが入ってくりゃ、それに合ったものを考えられるし、最近は輸送技術も上がって地方の新鮮なものが河岸に入るから、それで何を創ろうかって考えてると飽きるどころか、勉強の毎日でっさ。どこの寿司屋にもあるお任せってのは、特に私らには楽しくてねぇ。河岸で何を仕入れるかってのは店それぞれの割にはそんなにネタの種類は変わらなくてね、それらをどうお届けするかってことにみな亭主たちは工夫を凝らすんでっさ。それも毎日同じじゃあ常連さんは愛想尽かしちまうから、こっちも必死でねぇ。錦町の旦那のところがアナゴ推しのときゃ、うちは控えるんで。そん代わりウチが新子やるときは他には譲らねえ、江戸前の新子はウチしかねえってくらいお客さんにいいもん出して、そうするとお客さんが口コミで広めてくれるんですわ。最近は新子もひと手間かけてね、おっと、その内容は言えませんよ、それで常連さんにも飽きずに食べてもらってます。あ、それとねぇ、ちょっと待ってください。そのガリでもつまみに数分待ってください。その生姜も江戸川区の親戚の畑で採ったもんなんですよ。…お待たせいたしやした。ちょっとこれを食べてみてください。味はついてるんでそのままね。どうです? わかりましたか、サヨリの昆布〆にちょっと煙りをかけたんですわ、燻製みたいな香りがするでしょ。繊細な魚だからこそ、ちょっとした変化に気づくんですわ。その変化は私の独りよがりじゃいけない、実は先月お客さんに、淡白な味が淡白だって実感できるのは、微妙なクセがあるからだ、なんて言われてね。確かに水は味がないと思ってても、名水って言われるような山の湧水を飲むとやっぱり味があるんですわ。その土地の味なんでしょうね。じゃあこの三崎のサヨリは何だろうって考えて、そうだあのハーブだって。休みの日に三浦半島にドライブに行ったら岬の灯台の周りにローズマリーが群生してたんですわ。ちょうど摘んできてたのがあったから、早速陽に干して乾燥させたやつを燻製にするみたいに火にかけていったらいい香りが出るんですわ。その煙の上を一瞬だけ通過させるんです。それで終わり。
4
老舗って言われる店はみな努力してるわな。時代時代の気分に反しないよう打ち出しに強弱をつけ、でも決して媚びずに持ち前のオリジナリティを守りながら伝統と革新の間を振り子のように行き来しているんだ。だから生き残ってきたんだ。ガラスの茶室や真っ赤な鉄瓶なんて常識外だし、カリフォルニアロールなんてのも寿司って言えるのかと思ってたけど、意外にもアボカドが酢飯に合うんだな。乾物だって最近は振り子を反対側に振ってる。煮干をミルで砕いてふりかけにするんじゃ普通だが、コブサラダのドレッシングにするなんてすごくいいじゃないか。あんなにアミノ酸が凝縮したシーズニングは世界にほとんどないよな。じゃあ、本はどうなんだ? 代り映えしない菓子箱みたいに中身が違うんだからいいでしょ、って顔して書店に並んでる。そのまんまでいいのかい? 暗いところで読んじゃ目が悪くなるよなんて母親に言われながら読んでた頃と何一つ変わってないじゃないか。
母親って言えばね、私の母親はよく本を読む人だった。兜町の証券会社に勤める父親はほとんど家に居なかったから、家事がひと段落したら、いつも庭の見える椅子に座って本を読んでいた。女学生の頃から本をいつも手に抱えていたような子だったそうで、学校の図書館は教室以上に時間を過ごした場所だったと言っていた。だから母親の寝かしつけはいつもわくわくしながら聞いてたのを覚えてるよ。何しろふつうは絵本か何かの読み聞かせなんだろうけど、うちの母親は違ってね、私は泰二っていう名だが、たいちゃんとひこうきとか、たいちゃんとぴーまんなんて感じで毎晩即興で話を創って聞かせてくれんだ。私の腕あたりを布団の上からとんとんしながら話てくれたんだが、話が大きく動く時にはとんとんが少し強くなるんだ。それでこっちもどきどきしてねえ。今思えばあの話たち、原稿の字数にしたら2000〜3000字くらいのもんだったんじゃないかな。よく即興で毎晩話を創り出したよな。だって、今日は何がいい?って聞いてきて、私がどら焼きとか言うとわかったって言って布団の上の手をとんとん動かし始めて、1分も経たないうちに語りが始まるんだ。…とてもあついなつのひ、たいちゃんはおともだちとこうえんであそんでいました…なんて、必ず私が主人公だから、よく主人公になりきって話に入り込めなんて言うけど、この場合は入り込むんじゃなくて最初から話に入っているんだ。ほかの母親にはなかなか真似のできない、相当特別な物語だよな。そんなんだから、夢中で聞いたね。話が終わっても気が昂ってて、ちっとも眠くなんかなっていないから次の話しをリクエストするんだわ、子供だから母親が疲れてるんじゃないのかとか全然気にせずにな。それでもすぐに今まで聞いたことのない話が出てくるんだなこれが。すごい引き出しの数だよ。小学校低学年までそんなんだったから、覚えているだろう3歳からでも6年間くらいとして、少なくとも2000日以上だから、あのアラビアンナイト、いわゆる千夜一夜物語の倍だわ。まあ、こっちの物語たちは私だけしか知らないのだがな。
せっかく本になってるんだから、せっかくのいい話なんだからせめても誰かに読んでもらいたいじゃないか。すごく美味しいものが箱に閉じ込められたまま棚に放置されてるんじゃあもったいなさすぎるよ。POPってのも書いてみたよ。茶の湯なんかじゃよく言われるけど、能の世界も作法、道具、舞台、衣装、面…いろんなものにこだわって出来上がっている総合芸術だから、読むべきジャンルの本は山ほどあるんだよ。そこから私がこう読み繋いでいったら世界が広がりますよってのをちっちゃな紙に書き込んでね。店内はそんなもんだらけになっておかしなことになっちまったんで控えたわ。推しが多いと迷うもんなあ。その次はSNSにも上げてみた。でも見てくれる人がいなきゃどうにもならないんだ。まさに俺のレコメンドが店の本たちのようにじっとネットの奥に籠っちまうんだ。いや、本のほうがまだ出されたままになってるからいい。俺のSNS投稿はあっさりと過去のものになって闇に葬り去られちまうんだ。こうなると何をやっても焼石に水だよ。だから、あそこで漫然と毎日店を開けてるだけになっちまったんだ。そしたらな、ある日演劇の勉強をしているっていう明治大学の女学生が来て「ここの推薦文はいつもためになるんです。その本の周辺の知識が書いてあるから、次に読みたい本がどんどん出てくるんです」って。俺はそんなこと意識せずに書いてたんだよ。そしたら案の定「でも…」って。そりゃそんな褒められ続けることなんてないわな。その子が言うには「読みたいけどこれ以上視力が落ちたら読書どころじゃなくなる」って。その子はもともと視力がかなり弱いそうなんだ。愕然としたね。俺は知りたいことをどんどん用意すればそれでいいと思ってたんだ。みんなの知識を超える本たちを提示し続ければな。でもそうじゃないってことに気がついたんだ。それこそ世阿弥の”離見の見”だよ。観客目線で自分の演技を見ることを身につけなければいけない。観客によって見られる演者の舞い姿が離見だ。その反対は我見、演者の眼で見た己れの姿だ。もし観客目線を自分の物として見ることができれば、おのずと自分のことがよく分かってきて、演者と観客が同じ気持ちでいられるってことなんだわ。世阿弥は能の極意を後世に次ぐ意味で風姿花伝を書いたわけだが、演目を書くにあたっては自分の思いを物語にし、それを読ませるのでなく舞台上で演じることで思いを伝える手段を持ったということなんだろ。たくさんの話を書いては花を持たせながら演じていったんだからな。美味しいものを箱に入れたままにせずにあの手この手で人に見せていった、そこが素晴らしいんだ。50半ばでは伝書「花鏡」で”初心忘るべからず”と書いた。この言葉は世阿弥のものだったんだよ。若い時から老後まで、それぞれの時期において初心はある。若い時はうぬぼれず、壮年には努力して頂点に立っておき、老後には老いてこそふさわしい芸をせよと。さらに言った、”住するところなきが花”と。決して現状に安住してはいけないとな。
5
あたしゃ文章は書けないんでね、何とか自分の気持ちを現せないかって考えてね、絵もだめ、書もだめ、それじゃあってんで写真を始めたんですよ。あれならカメラがあれば形にできるじゃねえかってね。確かに写真にはなりましたよ、でも写真家って人たちが撮ってるようなひきつけられるもんにならねえんだ。記念撮影みたいのから抜け出せねえ。こりゃ何だろうって、本を読んだらさ、露出だのシャッタースピードだのホワイトバランスだのいっぺんにいろんなことを設定して、光の具合を測定して、場合によってはレフ板ってので光を当てて、しかも決定的瞬間にシャッターを押さなきゃいけないんだ。これは奥が深いよ。それから夢中で撮りまくったね。今みたいにデジカメじゃないからさ、フィルム買って現像に出して、いくらかかったかわかりゃしない。でもそのうちにわかってくるんだ。この状況をこんな風な1枚にしたいっていうときのそれらすべての設定がね。ダイヤルでほしい数値に合わせていくもんなんだけど、こんな曇天の中で風を受けてすべてが同じ方に靡く仙石原のススキなんて、ダイヤルも見ないでこのくらいダイヤルを動かしたくらいの露出の暗さがいい、なんて自分の体の一部みたいになっていくんだよ。するとさ、ススキが全部が靡いてる中に、なぜか一本だけ直立になってるススキがあったんだよ。ファインダーからは見えなかったな。それがさ、お釈迦さまが生まれた時に天上天下唯我独尊って言った姿みたいに見えるんだ。これは一瞬の偶然だよ。これが写真なんだな。そりゃ絵にすればいくらだってそういうのは描けるよ。でも写真ってところが大事なんだ。写真は人間の目で見たままがあると思いながら見ることが前提だけど、そこに一瞬のハプニングが写るんだ。そこがいい。カメラ雑誌で誰かのインタビュー記事を読んでたら、この世の一瞬とはその時の物理現象の観測者になったということで、物質を構成する素粒子がその時どういう状態にあったか、ということらしいんだ。俺もすぐにはわからなかったよ。で読んだね量子物理学の本をさ。ボームだのシュレディンガーだのランドールだの。読めば読むうちに、なんか仏教の般若心経に似てないか?って、今度はそっちの本を読んでたら、仏教のルーツはヒンドゥ教の前身のウパニシャッドだって、どんどん遡っていってね。なんでこんなにも昔に今の先端の量子物理学が書かれているんだって、もうわけわかんなくなってさ。結局、自分の中でこう方をつけたのよ。この世の摂理は一つなんだと。言い方や解釈はいろいろあるけど、神様ってのはその摂理のことなんじゃないかって思ってるよ今は。
6
昌平の旦那、さすがにわかってるじゃないか。あっちの世界でひとりで嘆いてばっかりいたところにお前さんの昔話が聞こえてきたんで来てみたわ。物事の成り立ちなんていろんなことをいろんな人が言うかもしれないけど、お前さんの言う通り結局は一つしかないんだ。そんな摂理の中で私たちはこっちにきてもちゃんと存在し続けているよ。こっちの世界ではお前さんたちみたいに体を持っていないから、やれ膝が痛いだの、腹が減っただのは一切関係ない。そして、思ったことがそのままその通りに運ばれるから、いろんなことに悩むことなんてないんだよ。いいだろ。移動みたいな物理的なこともないから、光以上の速さで好きなところに行ける。行けるというより望んだとたんにそこに居るという感じだ。お前さん、よく脳みそ痒がってたじゃないか。あれはお前さんの意識が好きなところに居ないからなんだ。私なんかはいつも本読んでいろんな事考えて狭い範囲に停滞しないで動きまくっていたから痒くないんだ。お前さんの場合は寿司のことばっかり考えてそこにはまり込んでたからなぁ。でも、今のお前さんは違う。停滞せずにいつもいろんなことを考え、ちゃんとイメージができてる。写真撮るときだってやみくもにシャッター押すんじゃなくて、その景色がどう写ったらイメージに近づくか、その一瞬のチャンスを狙うわけじゃないか。イメージができてないといつも偶然を待つことになる。仙石原のススキみたいにイメージに偶然が重なったら傑作となるんだな。誰にだって撮れるってもんじゃない。なかなか大した表現者だよあんたは。それはさておき私もあのローズマリーのサヨリ食べてみたかったわ。
7
おいおい、ひょっとしてお前さんは家伝文庫の旦那か? どこからあんたの話が聞こえてきてるのかわからんが、そのぶっきらぼうなところは相変わらずだな。サヨリなんていつでも食わしてやるけど、まあその状態じゃあ食えんだろうがな。しかもそうやって絡んでくるとこを見ると成仏できてねえな? あたしゃあんたの店があったところを通るたびに手え合わせてますよ。そりゃそうでしょ。お前さんの無念みたいな空気がどんよりと漂ってるんだもの。ひょっとしたらお前さんというより、本たちの怨念かもしれないねえ。知層に埋まった数千数万のな。天然ガスみてえにプスプス猿楽町一帯に燻ぶってんだよなぁ。しかし本読まなくなったからなのか、今の人たちはみんな過去に学ぶことを忘れちまったのかねえ。古くせえ道徳なんて知ったこっちゃねえみたいに、みんな勝手なんだよ。自分のことしか考えちゃいない。それこそ我見だよ。駅のホームにいる奴らがドアが開いたら我先に電車の中に入っていく姿なんて見ちゃいられないわ。誰が考えたって降りる人が優先だろ。みんな我先に座りたいって自分のことしか考えてないからああなるんだ。それとな、通路を手引きのちっこいスーツケースみたいなのを引いてあっちこっち行ったり立ち止まったりする奴。誰だって歩く時にゃ目線を前のほうにしか置いてないだろ、前の人との適正距離ってのは体に刷り込まれてるもんだけど、こんくらいだと思って進むと前の人が実はそんなのを引っ張っててつまずきそうになるんだわ。松葉杖の人なんかがそれにひっかかったら大変なことになっちまうぞ。なんというか周りの人への気遣いみたいなのもなくなってるんだよねえ。
8
旦那も苦労が多いねえ。でもね、そうやってカウンターが埋まってんだから、あんたは間違ってなかったんだよ、生き方をね。努力も気遣いも感謝もたくさん積み重ねてきた。それでもって、信頼も真心もほかに負けないものを作り上げたんだよ。まさに人生の花を咲かせたんだよ。あんたいつもいい本を持っていってたよな。みんながベストセラーみたいなのを買っていくんじゃ面白くねえが、あんたみたいに茶の本持ってった後に岩石図鑑をレジに出されたら唸っちまうよ。ああそっちまで興味が広がっていったんだななんて思って面白くてしょうがねえ。そうやって懐深くしとくと余裕ができる。余裕ができりゃ他人に優しくなれる。私はスマホゲームみたいに疑似体験に時間を費やすんじゃなくて、あんたみたいに知らないリアル世界を旅していなくちゃいけないって思ってるよ。あんたのところにお客さんが絶えないのは、うまい寿司食いたいのはもちろんだろうけど、あんたの話が聞きたいんだよ。そうだよな、何の話ししてもあんた独自の考えが返ってくるんだからな。経済のことを経済学者が語るんじゃ普通だが、寿司屋の主人が白身の注文が増えると景気が下向く、なんて言い出したら誰だって聞きたくなるじゃないか。だからあんたはそのまんまでいい、世間に疑問をもって説教臭くそれを人に話して、自らできることを率先してやってればいいよ。じゃあな。またお前さんのことが気になったら話しかけるよ。
9
ありがとよ旦那、本当に…。あ、すみませんねぇ。一瞬何かが頭の中を駆け巡ちまったんですわ。あ、干瓢巻のワサビを効かせた奴でしたよね…。あたしゃ、こんな年になっても寿司握るくらいしか取り柄はありませんけど、何十年も握ってきてやっと最近わかったことがあるんですよ。はい、干瓢お待ち。それはね、何にでも終わりはないってことですわ。極みなんて言葉はありますが、本当にそれが完璧なのかねえって思っちまいます。あ、あたしは完璧主義じゃありませんよ。だからいつだってもっと先に道があるんじゃないか、いや道がどんどん延びていくんじゃないかって思えるんですわ。ゴールが見えないってのは疲れますがね、ゆっくり進んでりゃ気になんないです。こつこつとやってりゃあいいんです。それからね、どうしたって人は死んじまいますが、死んだって終わりじゃないんです。死んだ後には体はなくなっちまうけど、意識は残るんです、きっと。般若心経にもあるでしょう、色即是空、空即是色ってね。在ると思うものはない、無いと思うものは在る。目に見えない素粒子が意識として作用している、ってあたしは思いますよ。その意識はあっちの世界でこっちのことをずっと気にして見守っているんじゃないかって気がするんです。それが何かの拍子にこっちにも伝わって、その亡き人のことを思い出すんですわ。だって、未だに坊ちゃん読めば漱石を思い出すでしょう。そうやって漱石の意識は残り続けてるんです。え、お客さんは文豪じゃないって? そうじゃないんです。何だって自分の中で抱え込まずに外に伝えることで残るんです。あたしは思いを寿司に込めて毎日お客さんに伝えてるつもりです。お客さんだって今みたいにお連れの方にお気持ちを伝えてらっしゃる。漱石は小説だったけど、あたしは寿司、お客さんは会話。何だっていいんです。あたしは死ぬまで握って、あっちに行ったらまた寿司みたいなのをやろうと思うんです。あ、あっちってのは何だって自由自在らしいですよ。思ったところにいつでも行けるそうで…。え、じゃあいつでも昌平寿司に行けるって? ありがたいことおっしゃいますね。あたしの握ってきた寿司もまんざら無駄じゃなかったんですかねえ…。本当にありがたい話です。
・・・・おい正太、手拭い持ってこい。ワサビ舐めたわけでもないのに涙が出ていけねえや。おい、早く持ってこい! (完)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
