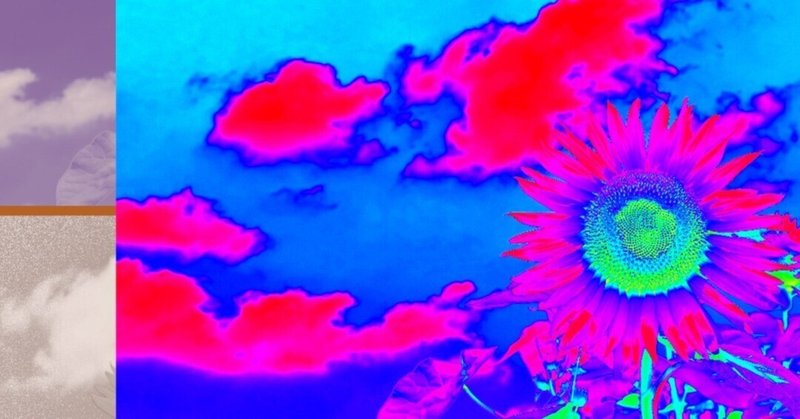
辛い過去も、解釈をリサイクルすれば壁を越える道具になる 第6話【エッセイ】
前回までのあらすじ。
高校を卒業して働き始めたものの、モヤモヤしたものが消えず、音楽をやるためにオーディションを受けて通るも、音楽以外のレッスンばかりで意味を見いだせずに辞め、バイトをしながら音楽をやるも自己否定を改善できずに中途半端な時期が続く。
そんな中、一冊の本に出会って人生が変わり始めたが、自己否定は改善されずにメンタルは蝕まれていた。しかしあるひらめきが、思わぬ方向へと導く。
1、自己否定との戦い
某ブラック企業を退職する数ヶ月前。
私は、この会社で頑張っても未来はない、じゃあ何をすればいいのだろうと、ずっと考えていました。紙に、自分が何をしたいか、どうしたいかを書き出し、考える。でも、どれもしっくりこない。それまでに、Webデザインをやったり、プログラミングをしたり、イラストを描いたり、いろいろ試しましたが、どれも深く追求するには至りませんでした。
「はぁ……」
いくら考えてもでてこない。どうすればいい……そんなふうに思っていたある日、会社の最寄り駅から会社に向かって歩いているとき、ふと言葉が降りてきました。
『ストーリーテラー』
本当に突然に、これまでまったく考えていなかった、自分の思考の外にあったものが、急にひらめいた……というより、感覚的には降りてきたという感じでした。
おいおい、なんかスピリチュアルだなと思ったかもしれませんし、確かに不思議なことではありますが、今思い返しても、突然降りてきたと表現するのが一番しっくりきます。
しかし私は、
ストーリーテラー? え? なんでそんな…それって人に向かって何かを話すってことだよな? 俺が? そんなことできるわけがない……
ひらめきの一瞬の間に、悪魔がマシンガンのように矢継ぎ早に囁きます。迷惑な話ですが、当時の自分を考えると、もっともな反応です。人と話すことも得意ではない、喋ることも得意ではない、何を語ればいいかも分からない……そんな状態なのだから、無理と考えるのは当然です。
ですが、新鮮さはありました。
私はひとまず、持ち歩いているノートに『ストーリーテラー』と書いて、具体的に何をすればいいかについては後で考えようと思い、ひとまずそのまま会社に行き、いつも通り仕事をしました。
考え続けた結果、あることを思いつきます。当時私は、日本の歴史の本を何冊も読んでいました。それで分かったことは、自分が学生のころにもっていた歴史認識は間違っていて、教科書には正しい歴史は書かれていなかったということです。
勉強はできなかった私ですが、本を読む前にもっていた歴史認識は教科書的なもので、自分でもおかしなことを言っていたのを、少しですが覚えています。
そういったことから、正しい歴史を語り、広げていくことと、ストーリーテラーが繋がったのです。といっても、すぐにそんなことできるはずもありません。
人と話すことすら苦手なのに、多くの人に、それも歴史について語るなど……じゃあ何ならできるか? どうやって練習すればいいか? そう考えた結果、Youtubeで動画を出すことを思いつきます。朗読をして、まずは話すこと、見ず知らずの人たちに聞かせることに慣れる。
そう考え、朗読動画を出すようになり、やがて私は、自分で物語を書くようになりました。2015年から書き始め、毎月最低一本の作品を書き、今に至るまで、7年ほど継続しています。
聞いてくれる人も増え、絶対に書けないと思っていた小説(※ここはもっと強調して良いかも)を書くようになり、自信が出てきて当然だと思いますが、相変わらず私の心は自己否定的で、ある日自分を追いつめすぎて、楽しくてしかなたないはずの物語創作が、書くことすら困難になるほど心が壊れかけ、仕事に行くことにも支障が出るぐらいでした。
たくさん本を読み、たくさんの物語を書いているにも関わらず、なぜこんな気持ちになるのか、なぜ自分を追いつめてしまうか……そんなふうに考えていたとき、一冊の本に出会います。
何がキッカケで見つけたのか、ハッキリ覚えてはいませんが、あるWebサイト……このサイトの名前も覚えてはいません……で紹介されていた『なぜあなたは自分を愛してくれない人を好きになるのか』というタイトルの本で、女性向けに書かれたものですが、その内容は、男が読んでも参考になること満載です。
なぜあなたは「愛してくれない人」を好きになるのか
その本の中に書かれているもっとも大切なこと。
それが、子供のころからずっと私を苦しめてきた自己否定から、心を解き放ってくれたのです。
2、受け入れるという優しさ
本に書かれている一番大切なこと。
それは……
自己受容。
英語だと、セルフアクセプタンスと言います。
一言でいえば、自分を受け入れるということです。自己肯定感と同じようなものに聞こえるかもしれませんが、何でもかんでも肯定するというより、人間には、誰でも良いところダメなところがある。自分もそう。良いもダメも含めて自分。だから、全部受け止めよう(受容しよう)ということです。
この考え方が、私の心を救ってくれました。自己否定が強かったころの私は、自分のダメなところばかり見て、それをひたすら責めていました。自分で自分にパワハラしているようなものです。しかも、自分で自分になので、逃げ場はありません。24時間、少しでもダメなところを見せれば、すぐ責められます。
だからダメなんだよ。
何やってんだよ。
もっと頑張らないとダメだろ。
と。
そんなことをしていたら、心が病むに決まっています。どんなにメンタルが安定していて、モチベーションを高く保つことができる人でも、落ち込むこともあれば、今日はいいやってサボってしまうことだってある。それが人間です。
でも自己否定が強いと、それを許せなくなります。完璧にやらないと……そう、完璧主義の罠にハマってしまうのです。
完璧などないので、自分であっても他人であっても、求めたら不幸になります。完璧な自分を求める限り、それは達成できない目標であり、そもそも目標の立て方がおかしいということになるのです。
自己受容は違います。
良くないなと思う習慣があれば、それを改善する努力はしても、できないとき、うまくいかないときがあることを認識して、そんなときもあるよと、思いやりのある言葉を自分にかけることができます。
この、自分への思いやりも大切で、セルフコンパッションと言います。甘やかすのではなく、頑張っている自分、頑張れなくて落ち込んでいる自分、どちらであっても、思いやりを伝える。
自己を受容し、自分への思いやりをもつことで、私の心はどんどん安定していきました。自分を責めることなく、日々前に進めたの努力をして、できないときがあっても自分を責めない。そのほうが、習慣化しやすくなります。
本当に、文字通り救われたのです。
ですが、これだけでは、このエッセイの1話目で書いた「自然体の自信」は生まれません。自信を得るためには、あることが重要です。それは……
3、積み重ねる
自己受容と同じぐらい大切なのは、積み重ねです。日々、目標や目的達成のために必要なことをする。
当たり前のように思うかもしれませんが、それが中々できないのが人間というもの。そして積み重ねは、意志の力だけではどうにもできないところが厄介です。意志の力だけで継続できる人もいるかもしれませんが、少数だと思います。私も無理です。
そこで重要なのが、自己受容であり、自分への思いやりです。こうすると決めても、仕事、勉学、人付き合いなど、予定外のことは日々起こります。だから、決めたことができないこともある。
それを責めてもしかたありません。自分の責任ではないことでできないこともあるし、疲労感が強いときもあれば、体調を崩すこともあります。
加えて、人間は目標を設定するとき、実際にできることより多くのことを設定してしまう性質があります(これによって起こるのが計画錯誤)。
万全なのにできない場合は、そもそも目標設定に問題があるか、集中力が続かないなら、集中の仕方を知らない、寝不足などの理由も考えられます。当然、それぞれ対策も違うわけで、ただただできない自分を責めるのは乱暴ですし、何より自分への思いやりがありません。
こういうときやる気が出ないことが多いなと、自分のダメな部分を受け止め、できないことがあっても、そんなときもあるよ、次はどうやればうまくいかなと言ってあげられる思いやり。それがあって初めて、習慣化は可能になります。
毎日同じようにできなくても、もし一時間本を読もうと思って、時間がなくなってしまったら、10分読む。そうやって、予定通りにできなかったときにどうするかということも考えて、とにかく継続すること。そうやって続けていけば、習慣化は可能です。
目標達成を邪魔するものをまとめるなら、
①目標設定に無理がある
②完璧を求めている
③自分を責めてしまう
この3つだと思います。
この3つを排除すれば、目標達成のための行動を習慣化できます。だから目標が必ず達成できるわけではないですが、行動し続けなければ、何も変わりません。
そして、そうやって積み重ねることで、無理のない、もとうなんて考える必要もなく、自信が出てきます。自信満々とも違う、自然体の自信。もっとも堂々としていて、余裕があって、自然な自信。
そうやって得た自然体の自信ですが、それでも落ち込むこともあれば、自信をなくしそうになるときもあります。次回は、そんなときにどうするかをお伝えします。
私が大事にしていること、これからも大事にしていくだろうこと、です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
