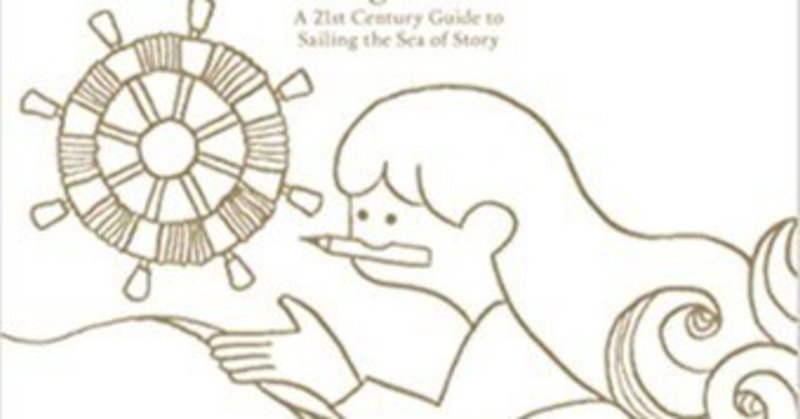
短編:練習06
腹部にかすかな痛みを感じたとき、私はそれを気のせいだと思い込もうとした。内臓の鳴るぽこぽこという音、その震えを痛みと勘違いしたのだと。少しじっとしていれば痛いと感じたものはきっと引いていく。
けれども駄目だった。叩きつけるような芝先生の板書の音だけが響く教室でほかに刺激的なこともないものだから私は自分の体の痛みとまともに向き合わなくちゃならなかった。まだ激痛ではなく、例えるなら臍にゆっくりと突起物を差し込まれていくような寒気のする居心地の悪さに近い。強い痛みはまだない。しかし呼吸は浅くなり、誤魔化しようのない腹部の違和感から意識を背けることが出来ない。このまま痛みが引かないのであればいずれ教室を出ていくことになるのは間違いない。そのためにしなくてはならないこと、がいっぺんに思い浮かんで私はたちまち怯む。午後の静まりかえった教室で挙手して芝先生を呼び、出ていきたい旨を伝える。わざわざ授業を抜け出すほどの理由を説明しなければ間違いなく先生は機嫌を損ねる。お腹が痛いんです。腹を下したのかな。教室の誰かはそんなことを思いもするだろう。私は椅子を鳴らして立ち上がり、もたもたと鞄からナイロン地のポーチを取り出して教室を出ていく。痛みもかなりきつくなってきて、背中を丸めている。教室後ろの扉は建付けが悪いから何かを叩きつけたのかってくらい開閉に大きな音をたてるのだ。私に意識を払っていない人でさえその音で振り返るに違いない。教室を出ていこうとするなら、これらのことが今から起きるのだ。うんざりだった。別にここから抜け出したからって痛みが引くわけじゃない。本当にうんざりだった。
サポートいただけると助かります。やる気や、今度買う駄菓子に繋がります。
