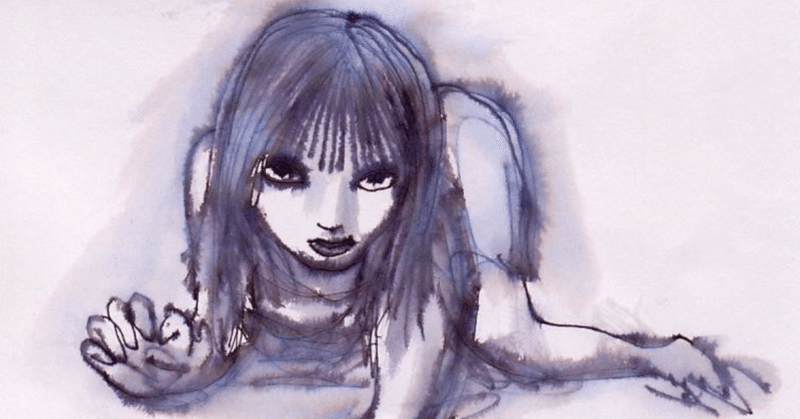
【受賞作発表】ひらづみ短編コンテストvol,2 お題「ゾンビ」
【優秀作】七月九日十九時五十分@池袋東口駅前ロータリー(中型犬)
はいはい、この階段をね、階段を上ると、おー、皆様、すごい数の、すごい皆様、あ、これ、これ入ってますか、あーあー、あ、あはい、ありがとうございます。
池袋駅にお集まりの皆様。そして、この演説をスマホで見ている全国の皆様。
明日、歴史が変わります。
いえ、皆様が皆様の力で、ごめんなさい、声がもう、あ、ありがとうございます。
歴史を、歴史を、変えるのです。
ゾンビは、単純作業労働や疑似人体実験など産業利用されるだけでなく、情操教育の一環としての学校での飼育や家庭におけるペットなど、えー、様々な場面で私たちの暮らしを豊かにしてくれています。
あー、そちらのお嬢さんも連れてらっしゃる。素敵な家族ですね。ありがとう。
人類の長い歴史の中で、ゾンビが単に人間にとって有害だった時期があったのも事実。
しかし今や、人間から移行するゾンビはワクチンの開発によりいなくなりました。ゾンビ同士を繁殖させることで生み出されているゾンビは、もはや人間の敵ではなく、仲間。仲間です。そうですよね、あー、拍手ありがとうございます。
しかしながら、う、しかしながら、長年、ゾンビは、虐待の対象になったり、人間では考えられない苦痛を強いられてきました。
これは、とても、とてもとても悲しいことです。あー、ありがとうございます。皆様の拍手こそ希望です。
人間の生活を豊かにするために、え、はい、そうなんです、ゾンビを利用することはもちろん素晴らしいことですが、なるべくゾンビの感じる苦痛を減らしてあげたい。それが、人間の自然な感情じゃないでしょうか。
動物愛護法はあるのに、なぜゾンビ愛護法はないのか、これは、私たちの大きな過ちです。しかし、私たち人間は、過ちを正すことができます。
私たちの仲間であるゾンビを守るための法整備を実現するため、私たち、人間と動物とゾンビのこころを守る党は、全力を尽くします。あー、温かい拍手、ありがとうございます。
明日の参議院議員選挙の比例代表では、「ゾンビ」または「こころ」と記載いただき、ともに明るい未来を作り上げましょう。
ゾンビの虐待を明確に禁止し、ゾンビの苦痛を伴う利用を制限する法改正だけでなく、痛みのないゾンビの殺戮を可能とする密閉型毒ガス施設の整備、ゾンビ肉の食品加工施設、ゾンビの骨を使った知育玩具の製造工場など、私たちの仲間であるゾンビ、そして私たちの生活のため、多くの研究開発や設備投資に費用が必要ですが、私たち人間と動物とゾンビのこころを守る党は、決して皆様の税金に頼るようなことはありません。
我が党が投資家の皆様からお預かりした資金を原資に立ち上げたゾンビみらいファンドからベンチャー企業に出資することで、産業全体の発展と社会の課題解決、投資家への適切なリターンの実施を行ってまいります。
ゾンビとともに未来を!
ありがとう、今拍手をしているあなたがこの世界の主役です!
私たち人間と動物とゾンビのこころを守る党に、あなたの大切な一票をお預けください。
必ずあなたの生活を豊かにします。
また、ゾンビみらいファンドへの出資は、第四期の募集を開始しております。一口十万円。第一期から第三期では平均して年率十%の配当を実現しております。
ゾンビとともに未来を!
ゾンビとともに未来を!
「ゾンビ」と書いて、歴史を変えましょう!
ありがとう!
ありがとう!
【佳作】ええ塩梅(坂口雄城)
病院から、おばあちゃんが死んで動き出したと電話があった。
ちょうど正月で和歌山の実家に帰っていた私は、父と一緒に病院へ向かった。母は昨日から友人達と伊勢神宮へ初詣に行っており、ラインを入れると、今からすぐに帰りますと返事があった。着くのは昼過ぎになるらしい。
「お前もせっかくの休みやのに、ゆっくり出来やんな」
車を運転しながら父が言った。私は呟くように「ううん」と言って、首を横に振った。おばあちゃんには昨日も病院で会った。閉じたままの瞼を指で押し広げ、「帰ったで」と告げると、ほんの少しだけ喉元が動いたのを覚えている。脳梗塞で倒れて以来、おばあちゃんは二年間寝たきりだった。
面会用入り口で名前を告げると、すぐに病室へ通された。
死んだおばあちゃんは、背中を丸めてベッドに腰をかけていた。恵比寿様のように垂れた目はうっすらと瞼が開いていたが、私達には気づかず、ほぅと心地よさげにため息をつきながら、左右の腕や脇腹のあたりをゆっくりと撫でていた。
「おーおー、ばあさん動いてるなぁ」
父はそう言って、照れくさそうに「ええ気なもんやで」と付け加えた。
「山口さんよかったねぇ。息子さんもお孫さんも来てくれて。お家帰れるねぇ」
愛想の良い二人組みの看護婦が、点滴や尿道カテーテルなどを片付けている。薄く血のついたガーゼやタオルもあった。父は彼女等に頭を下げ、おばあちゃんに少し声をかけてから、医師の話を聞くために部屋を出た。私はおばあちゃんの横に腰をおろした。おばあちゃんは両手を顔に当て、そのままゆっくりと顎の下まで撫でおろすと、またほぅと息を吐いた。小さく、鼻歌のようなものまで歌っている。ただ、手に触れてみると、やはり冷たくなっていた。
「ほんまに、温泉入っているみたいでしょう?」
看護婦の一人が、ニコニコと顔を丸めながら言った。
父が部屋に戻ったので、私達は着替えやオムツなどの荷物をまとめ、おばあちゃんの手を引いて一緒に病院を出た。車の中でもおばあちゃんは時々息を吐いたり鼻歌のようなものを歌ったりしていたが、やがて肺の中に残っていた空気がなくなると、後はとろりと目を閉じて、心地よさを噛みしめるように、顔中のしわを押しのけて笑みを浮かべた。
家に戻り、仏間でおばあちゃんを裸にした。病院で指示された通りに防臭剤をふきつけながら、煮溶けた餅のように大きく垂れたおっぱいを見ていると、子供の頃、おばあちゃんと二人で白浜の温泉へ行った時のことを思い出した。私が学校に行けなくなっていた時期のことだ。昼間から露天風呂につかりながら、おばあちゃんは恵比寿様のように目尻を垂れ下げ、時々ほぅと息をついては、鼻歌を歌った。
「あー、ええ塩梅よなあ」
ほんの一瞬、なめらかな湯の暖かさと共に、柔らかく膨らみのあったお婆ちゃんの身体や、甲高い声が鮮明に蘇った。私は瞬きをして涙を払い落とした。おばあちゃんの肩とお尻には赤黒く膿んだような床ずれができており、特にお尻の方は皮が擦り切れ肉が見えていた。爪は全て樹皮のように黄色くささくれ立ち、左足の小指はつい最近爪が剥がれたらしく、まだ血が滲んでいた。おばあちゃんに服を着せながら、父も俯いて瞬きをしているのが見えた。
しばらくして母から連絡があり、父が駅まで迎えに行った。私は仏間の縁側に座椅子を並べ、おばあちゃんと一緒に座った。ガラス戸越しの陽が、ぬるい湯のように心地よかった。父が消し忘れた居間のテレビから、正月のお笑い番組が聞こえている。家の前の小道を、老人が二人で歩いているのが見えた。一人はおばあちゃんより少し若いが、どうやら死んでいるようだった。
老衰で死んだ人間が動くようになって、もう何年も経つ。最初は地獄がいっぱいになったのだと騒がれたりもしたが、今ではみんな、極楽が現世にまで広がり始めたのだと考えている。生きる苦労を済ませた老人たちは、誰に何の害を加えるでもなく、ただ「ええ塩梅」の顔をしてあちこちに佇んでいる。それはちょうど、温泉に入っている時のような顔だった。
「ええ塩梅やなぁ、おばあちゃん」
私は、自分が職場に行けなくなっていることを、おばあちゃんに話した。
おばあちゃんは背中を丸めて、ゆっくりと身体を左右にゆすっている。音は出ていないが、鼻歌を歌っている様子だった。椅子にもたれて目を閉じると、私もおばあちゃんと一緒に、白浜の温泉にでも入っているような気持ちになった。
【佳作】ウィズ・ゾンビ(清水喜文)
世界保健機関が初めて『ゾンビ』について言及したのは、世界人口の十分の一がそれに感染した頃であった。
車の陰に隠れながら、鈴木康介は腕時計に目を落とした。
「あと十分」
目的の建物は目の前にある。通常なら一分もかからない距離だ。
「通常なら……か」
自撮りモードに設定したスマホを持ち上げ、建物側の様子を伺う。画面には十数名のゾンビが映っていた。
鈴木には、どうしても建物に辿り着かなければならない理由があった。しかも十分以内に。
鈴木は呼吸を整えると、車の陰から飛び出した。
一番近くにいたゾンビが反応して手を伸ばしてくる。ラグビー経験者の鈴木は、難なくそれを躱すと勢いよく駆け出した。
建物の玄関先には五名のゾンビたちがいた。近づいてくる獲物に気づき、動き始める。
鈴木はゾンビたちに全速力で近づき、直前で右に方向転換する。彼らが追いかけてくるのを背中で感じながら、鈴木は前方に別のゾンビたちが集まってくるのを待った。
前方からも後方からもゾンビたちが迫ってくる。鈴木の頬に汗が流れた。ゾンビたちは、その息づかいが聞こえそうな距離までに近づいてくる。
その瞬間、鈴木は再度右に方向転換した。そのまま、ぐるりと回りこむ形で建物の玄関に向かう。
狙い通り、玄関先にはゾンビはいない。
鈴木が玄関に辿り着くタイミングで、扉が開いた。中にいた誰かが明けてくれたのだろう。
建物に転がり込みながら、鈴木は腕時計に目をやった。
二十三時五十二分。
鈴木は息を吐くと、そこにいた男に視線を向ける。
「……鈴木です」
男はデスクに置いてあった端末に目を落とすと、にこりと微笑んだ。
「全国旅行支援キャンペーンでご予約された鈴木様ですね。お待ちしておりました」
【佳作】ゾンビの正体は(伊瀬ハヤテ)
それは爆発的な感染力を持っていた。
一度感染すれば思考が鈍り、自身の欲望のままに人を襲ってしまう『ゾンビ』へと成り果ててしまう。
そのウイルスが初めて発見されたのは数年前、某国で小さな村が壊滅したことが原因だった。
初めは他所ごとだと達観、楽観していた我々だったが我が国にゾンビが現れたことで事態は一変した。
「某国の出身者が怪しい」
我々は徹底的に自国の民以外を排除した。
ゾンビが発見された某国の民のみならず、髪色が、瞳の色が、肌の色が自国のそれと違う者はみんな排除した。
空港を閉し、港を破壊した。ゾンビが発見される以前より我が国に住んでいたものも排除した。元は他国の民だ。どうなったって知るものか。
しかし、それでもゾンビは増える一方だった。
「水商売をしているものが怪しい」
我々は徹底的に夜の街で働くものを排除した。
ウイルスの感染経路は未だ不明のままだが、他者との接触が激しいこと、また感染者に性風俗店の勤務者が数名いたことからこの説に異を唱える者はいなかった。さらに水商売の奴らは不健全で不潔なものばかり、いなくなってむしろ好都合だ、と世間はこの説を推した。
しかし、それでもゾンビは増える一方だった。
「若者が怪しい。若者は稚拙な思考の元、外出自粛を無視し、ウイルスの感染を拡げているからだ」
そう記事を書いてすぐに、近隣の公園から騒ぐ若者の声は消えた。ここ最近の不眠の原因が排除され、私は清々しい思いで目覚めの紅茶を啜る。
私は、自身の仕事に誇りを持っている。
人々は未だ正体不明のウイルスに恐怖している。
政府は信用ならない。特効薬も効き目があるのかわからない。
であれば、筆をとることしかできない私にできることは人々に攻撃の対象を与えることだ。
「感染したくない」「ゾンビなんていなければ」
恐怖は不安だ。そして不安は、人を攻撃的にする。
不安に駆られた人々を野放しにするよりも、攻撃対象を与えることでコントロールする。
それが世のためということだ。
私は紅茶の入ったカップを持ったまま外に出て、ポストから自分の記事が書かれた新聞を取ると脇に手紙が入っているのに気がついた。
私の記事のせいで仕事を失った、責任を取れと汚い字で殴り書かれた元風俗嬢からの手紙には最後にこう書かれていた。
「あなたがやっていることはただ悪戯に人々の不安を煽っているに過ぎない。今もなおゾンビが増え続けていることが何よりの証拠だ」
私はいつも通りに手紙を破り捨てる。
ゾンビが増えている? そんなことは私の知るところではない。
それに仕事を失ったことを私のせいにされても困る。
悪いのはゾンビだ。
そして排除に賛同したこの世であり、そんな世の煽りで仕事を失ってしまう自身の無能さを恨んで欲しい。
家に戻ろうとすると道に顔を覆う大きなマスクをした少女が立っていた。
マスクなんて本当に感染を防ぐか怪しい代物をつけて、愚かな。私は踵を返し自宅に戻ろうとすると、少女はおもむろに私に向かって指を差す。
「紅茶を飲む人が怪しい。ゾンビは紅茶を好むらしいから」
少女は大きな声で叫ぶと、周囲にいた人々の視線が一気に私を指す。
「マスクをしていない。ゾンビの証拠だ」「くまがひどい。ゾンビの証拠だ」「ゾンビだ。排除しよう」
途端に顔をマスクで覆った無数の人々が私を取り囲む。
「違う! 私は感染していない! そもそもそんなエビデンスはあるのか!?」
「ゾンビが紅茶を飲んでいたという話を聞いたことがある」
「だからって私を排除するのか!? そんなのは馬鹿げている!」
「言い逃れか? ますます怪しいぞ」
「違う! 私は!」
私の叫ぶ声は人々の暴力とカップの割れる音の中にかき消えた。
「助かりたい」「感染したくない」
殴り、蹴り、叩き、踏み、刺し、焼き、薬を撒き、怒り、笑う人々。その本能のまま、自身の欲望のままに私を襲う姿はまるで、いつかニュースで見た光景と重なって。
あぁそうか。これが、ゾンビの正体か。
薄れゆく意識の中でマスクの奥で輝く少女の瞳が綺麗な青だったことに、私は今更気がついた。
私は死んだ。
しかし、それでもゾンビは増える一方だった。
そして、我が国が初めてゾンビによって壊滅した国となった。
【佳作】意外と不幸じゃない日々に(Iyo.)
休み前最後の授業は、異様なほど活気があった。
そわそわと落ち着かない教室の空気が今にも弾けそうな中、チャイムが鳴る。
『カッカッ』と、黒板とチョークがぶつかる音がして顔をあげると、そこには『家族の手』と書かれていた。
「黒板に書いたのは、三学期最初の授業で取り扱うテーマです。どんな構図にするか、年明け最初の授業までに考えてきてください」
浮足立つ生徒たちが次々と立ち上がる中、美術の先生が声を張り上げた。
『家族の手』と言われてぼんやり思い出したのは、真っ黒な母の手だ。
唯一記憶に残るそれは、水分という水分は感じられず干からびてカサカサとしていた。皮と骨が一体化したような真っ黒な手は、子どもながらに少し怖かったのを覚えている。
特殊な実験室でしばらく生命維持していた母も、私が五歳になる頃に亡くなった。
私が生まれる前に流行した原因不明のウィルスは、感染すると身体がじわじわと壊死していくものだったらしい。壊死していく患者の様相がさながらゾンビのようで、巷では「ゾンビウィルス」として猛威をふるった。不運にもウィルスに罹患した母のお腹には、ちょうど私が宿っていた。
母だけでなく私の命も危ぶまれたが、医療機関の懸命の処置もあり私は生まれ、奇跡的に抗体を持っていた私の血から特効薬が生まれた———と、聞かされたのは、ずいぶん後になってからだ。
『家族の手』と言われて、あの真っ黒の手を描いたら、余計な心配をかけてしまうだろうか。下手に心配されたらいやだなあ、などと考えながら帰り支度をする。マフラーを巻いてふと見下ろす教室の窓の外は、ぼんやりと白っぽかった。
自転車置き場に行くと、アツコが「おーい」と私の自転車横で手を振る。
「あれ、ごめん待たせた? 早かったね」
「五限目が自習だったから、一瞬で終わった。最後なんだった?美術?」
「そうそう。なんか宿題出た」
「え、だる。私のクラスは出なかったなあ」
「まあ構図を考えてくるだけだから、大した宿題じゃないんだけどね」
自転車のスタンドを蹴り上げる。いつも通りアツコは徒歩で、私は自転車を押しながら帰途につく。
暖房のついた教室で火照っていた頬に、ひんやりと冷たい風が心地よい。自転車を押して歩く川沿いに、車輪がカラカラ回る音が響く。前かごには、乱暴に放り込まれた鞄と500mlのペットボトル。体操着。それらをぼーっと眺めながら、また少しだけ母親のことを思い出す。真っ黒な、動かない手。私の『家族の手』。
「うちのクラス、次の美術の課題が『家族の手』なんだけどさ、」
「うん」
「世間一般と私のイメージが、だいぶ違うと思うんだよねえ」
横に並ぶアツコに、私はぼそっとつぶやいた。
「いいんじゃない? 記憶の通り描けば」
「ゾンビみたいな手?」
「うん。『これが母の手です!』って」
本当のことじゃん、と、まったく嫌味なくアツコは笑った。つられて私も笑ってしまう。
「そうだよね、別に嘘じゃないもんね」
『そうだよ、嘘じゃないんだから』と、私の言葉を繰り返すようにアツコが相槌を打つ。
育て親である祖父母の手を描けば、それで済むはずだ。けれど、ふと思い出すあの真っ黒な手をなかったことにするのは、なんだか少し淋しかった。母の記憶がほぼない私にとって、あの『真っ黒な手』は、唯一思い出せる『母の一部』だったんだなあ、と、ふと思う。
「もしさ、先生に呼び出されたり、心配されたりしたら、どうしよう」
「そうしたらさ、『記憶のとおり描きました』ってお母さんの写真持っていこうよ」
職員室までついていこうか、と、何でもないことみたいにアツコは言った。私を特別扱いしない、哀れんだり同情したりしないアツコ。私の持っている記憶を否定しないアツコに、たぶん私は何度も救われている。
「もしお母さんが生きてたら、アツコを会わせたかったなあ」
「私も会いたかったなー。アツコのお母さん。」
話しながらアツコと目が合う。なぜだか急に可笑しくて、二人同時に吹き出した。笑って、笑い続けて、そうして吐き出した分の息を慌てて吸う。冷たい空気が肺に入っていく。吸い込んだ冷たい冬の空気に、体の中が洗われたような気がした。
ふと見上げると、川向うに見える冬の夕暮れが美しかった。私とアツコの笑い声はまだ土手に響いている。
『淋しいこともあるけど、意外と不幸じゃないよ』と、あの真っ黒な手を想う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
