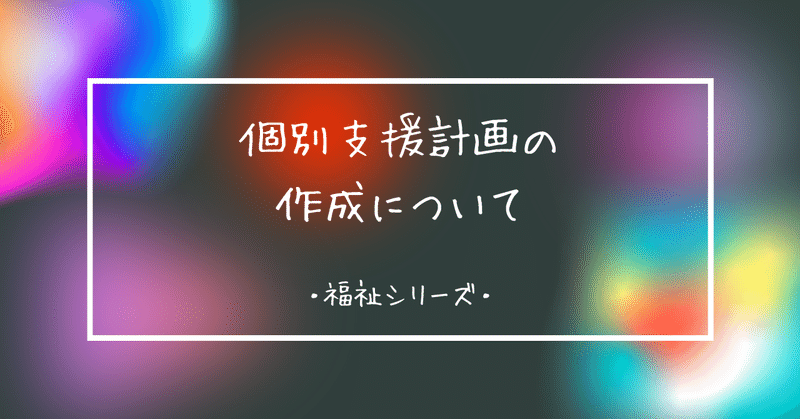
個別支援計画の作成について
今回は、個別支援計画の作成について記していきます。
主に就労移行支援の個別支援計画書についてみていきます。
必要性
個別支援計画は、作成しないと事業所に減算が入ります。
なので、事業所は必ず作成します。
というのは、極端な話ですが。
個別支援計画を作る必要性としては、
利用者の現在のニーズを把握して、
それを支援の根拠として、
客観的に可視化して、
利用者と支援が支援の方向性を共有することで、
利用者の目標目的を実現していくことにあります。
サービス等利用計画との関係
障害福祉サービスを利用する際に、
サービス等利用計画を作成するはずです。
個別支援計画は、サービス等利用計画にも連動していきます。
サービス等利用計画は、利用者の生活全般にわたり、
利用者が希望する生活が営めるように、
さまざまなサービスなどを用いて支援し、
支援者の分担や役割を整理していくものです。
個別支援計画は、そのサービスの事業所ごとに
その専門的なサービスの支援について、
利用者のニーズと支援者の支援方針を整理して、
利用者の目標目的の達成のために、具体的な方法を示すものです。
利用者のニーズ
個別支援計画の基本は、利用者のニーズがなにかを把握することです。
ニーズとは、本人の願いといった意味です。
利用者本人がやりたいこと、叶えたいことなどがニーズとなります。
長期目標と短期目標
個別支援計画には、長期的な目標と短期的な目標も記載します。
支援者が、利用者のニーズを満たすためになにをしていくかを
ここで明確にしていきます。
就労移行支援の場合、長期目標は2年、短期目標は3ヶ月のことが多いです。
記載方法
原則として、個別支援計画のフォーマットなどはありません。
事業所ごとに書式は自由に設定できます。
自治体によっては、指定のフォーマットがあるところもあります。
記載内容は、たとえば下記の項目が考えられます。
・利用者氏名
・事業所名称
・サービス管理責任者氏名
・利用者の目標
・支援目標
・長期目標
・短期目標 など
注意点としては、具体的に分かり易く記載するということでしょうか。
具体的にとは、固有名詞や数値など使用していくということです。
分かり易くとは、平易な言葉づかいで誰が見ても分かるものということです。
このnoteはどうなのでしょうか。難しいですね。
あとは、なるべく未来志向で前向きなものが良いと思われます。
また、指導的だったり命令的だったりする書き方は、
利用者本人のニーズを達成する個別支援計画の趣旨とはズレてきますので、
避けた方が良いでしょう。
モニタリング
個別支援計画は、定期的にモニタリングしていきます。
就労移行支援の場合は、短期目標と同じく3ヶ月ごとが多いです。
モニタリングで、目標の達成度合いを確認したりします。
また、軌道修正や新しい目標ができた場合も追加修正していきます。
新しい個別支援計画に落とし込み、また目標に向かって進んでいきます。
まとめ
個別支援計画は、事業所が作成します。
利用者のニーズに合わせて、具体的に目標を定めます。
モニタリングで、途中確認しながら、利用者支援をしていきます。
河野羊
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
