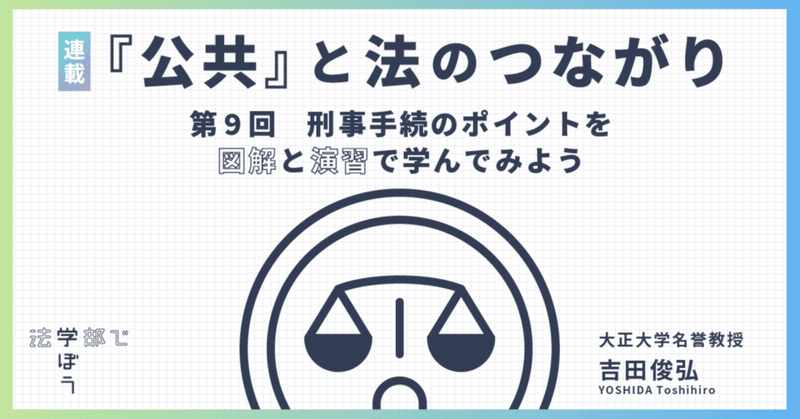
連載「『公共』と法のつながり」第9回 刑事手続のポイントを図解と演習で学んでみよう
筆者
大正大学名誉教授 吉田俊弘(よしだ・としひろ)
【略歴】
東京都立高校教諭(公民科)、筑波大学附属駒場中高等学校教諭(社会科・公民科)、大正大学教授を経て、現在は早稲田大学、東京大学、東京都立大学、東京経済大学、法政大学において非常勤講師を務める。
近著は、横大道聡=吉田俊弘『憲法のリテラシー――問いから始める15のレッスン』(有斐閣、2022年)、文科省検定済教科書『公共』(教育図書、2023年)の監修・執筆にも携わる。
【1】はじめに
ゴールデンウィークを挟んでの再開となりましたが、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。今回は、第7回と第8回の刑事手続に関する学習内容をまとめたうえで、1つだけ演習問題に取り組んでみましょう。また、新科目「公共」の演習問題を作るために大学の法学入門書の活用方法も紹介します。今回もがんばってまいりましょう。
【2】証拠裁判主義と犯罪事実の証明――裁判員になったら考えなければならないこと
立証責任というのは、事実を証明するべき責任を負うのは当事者のどちらかを定めた裁判のルールです。民事裁判では、問題となっている事実によって、原告が立証責任を負う場合もありますし、被告が立証責任を負う場合もあります。これに対し、刑事裁判では、犯罪事実の立証責任はもっぱら検察官が負担し、被告人が無実を証明する必要はありません。被告人が有罪であることを示す証拠がなければ、被告人は無罪だと考えなければならないのです(=「無罪の推定」)。したがって、もし裁判員に選ばれたら、検察官から提出された有罪であることを示す証拠が被告人の「無罪の推定」を覆すほどのレベルに達しているかどうかを判断しなければなりません。連載第7回では、そのときの証明の水準は、一般人から見て、被告人が犯罪を行ったことについて疑いを差し挟まない程度の証明(=合理的な疑いを超える証明)がなされていることが求められている、ということを学びました。
将来、裁判員に選出されたなら、検察官の提出した有罪の証拠に合理的な疑いが認められるかどうかを検討し、疑いが残らなければ有罪、少しでも疑いが残れば無罪と判断することになります(=「疑わしきは被告人の利益に」の原則)。
刑事訴訟法317条は、「事実の認定は、証拠による」と規定しています。ここに書かれている証拠とは、裁判上、事実認定の基礎とすることのできる資料、すなわち証明の手段であることを意味します(註1)。このときに用いられる証拠としてはすぐに犯行に使われた凶器などを思い浮かべますが、それだけではなく、鑑定人の鑑定結果を書いた書類、証人や被害者の供述なども含まれます。
その際、注意していただきたいのは、「事実の認定は、証拠による」とは、犯罪事実の証明は、証拠能力(註2)を備え、かつ、公判廷における適法な証拠調べの手続を経た証拠によるものでなければならないということです。そこで、「公共」の授業では、適正手続の理解を深めることと関わって、この証拠裁判主義について検討してみてはどうでしょうか。まず、証拠裁判主義と犯罪事実の証明について図解を基に解説しましょう。
〈天秤の傾きで学ぶ事実の認定〉

上図のように、刑事訴訟は「無罪の推定」の原則が妥当し、犯罪事実の証明責任は検察官が負っています。検察官は、目撃者の証言や凶器などの証拠を提出し、被告人の犯罪事実を証明しようとします。弁護人は、被告人の権利・利益を擁護します。

〈A〉の事件では、検察官の出したa、b、cの証拠では「合理的な疑いを超える証明」に届いていません。図の天秤は、有罪の認定に傾いていますが、犯罪の証明があったとはいえません。このとき、裁判官は有罪の認定はできないのです。これが、「疑わしきは被告人の利益に」の原則です。

〈B〉の事件では、検察官による立証が合理的な疑いを差し挟む余地のない程度にまで到達しています。裁判官が犯罪の証明がなされたと判断したときに、有罪判決がくだされることになります。
※証拠の数で有罪が決まるわけではないので注意してください。
【3】 演習問題にチャレンジ――事例を読み、問いに答えてください
警察官が深夜にパトロールしていると、足取りのおぼつかないCがふらふらと歩いていました。警察官は覚醒剤の所持を疑い、職務質問を行いましたが、Cが不服らしい態度をとったため、同意を得ないまま上着のポケットに手をつっこみ、覚醒剤を発見しました。警察官はその場で覚醒剤を押収し、覚醒剤不法所持の疑いでCを逮捕しました。
さて、この場で押収された覚醒剤は、Cを被告人とする刑事裁判において有罪の証拠として認められるでしょうか。あなたは、次のアとイのうち、どちらの意見が正当であると考えますか。その理由もあわせて述べてください。参照条文は下記の通りです。
ア 参照条文を読むと、警察官が令状を持たず、被疑者の同意も得ないまま覚醒剤を押収するのは違法であり、この覚醒剤を証拠とすることは認められない。
イ たとえ証拠物の押収手続が違法であったとしても、押収した証拠物それ自体の性質や形状に変化はないことから、証拠物としての価値は十分に認められる。
〈参照条文〉
〇日本国憲法35条① 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
② 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
〇刑事訴訟法218条① 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
②~⑥ 〔略〕
刑事裁判では、裁判官が証拠に基づいて事実を認定することになりますが、証拠であれば何でもよいというわけではありません。証拠能力のない証拠は、事実認定の根拠としては用いることができないのです。ただし、捜査機関による証拠物の収集手続に違法があった場合、その証拠能力がどうなるかについては憲法や刑事訴訟法に直接の規定はないため、この扱いについては争いがあります。
1つの考えが「ア」のような考え方です。「ア」は、憲法35条や刑事訴訟法218条1項の令状主義を重視し、捜査機関による証拠収集の手続に重大な違法がある場合に、これを裁判の証拠として用いることは許されないとする考え方です。ひとたび違法に獲得された証拠を認めてしまうと、この事件に限らず将来にわたり違法な捜査が継続される余地が生まれてしまいます。今後とも違法な捜査を抑制するためには、違法に収集された証拠を有罪認定のための証拠として用いてはならない、というのです。
これに対し、「イ」の考え方は、押収手続が違法であったとしても、押収した証拠物の性質や形状に変化はないことに着目します。つまり、違法に収集された証拠であったとしても、これを用いることができれば、犯罪の真相究明に大きく貢献することができる、というわけです。違法に収集された証拠であるという理由だけで証拠能力をすべて否定してしまうと、かりに真犯人であっても無罪となってしまうかもしれず、真実の発見ができなくなる可能性があるという点に配慮した考え方であるといえるでしょう。
このような見解の違いがなぜ生まれるのか、その理由に着目したうえで、刑事訴訟法1条が、刑事手続の目的について「公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現する」と規定している意味を考えてみましょう。真実の発見を目指しながら、不当な人権侵害がないように、適正に刑罰権を行使するための手続を法が定めていることの意味を深く考えていくのです。
それでは、実際に最高裁判所は、どのような判断を示しているのでしょうか。本事例と同種の事案で警察官の違法行為によって証拠物(ここでは覚醒剤所持の罪の重要証拠である覚醒剤をさします)が発見されたケースにおいて、最高裁判所の示した考え方を紹介しておきましょう。
「証拠物の押収等の手続に、憲法35条及びこれを受けた刑訴法218条1項等の所期する令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが、将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合においては、その証拠能力は否定されるものと解すべきである。」
これを読むと、最高裁判所は、違法があった以上は、それによって得られたとされる証拠はすべて例外なく排除すべきである、とは言っていません。しかし、①証拠収集手続が令状主義の基本に反するような重大な違法があり(違法の重大性)、②これを証拠として認めることが、将来の違法捜査の抑制の見地から相当でない(排除相当性)場合に、その証拠能力が否定される、と判断しているのですね(これを違法収集証拠排除法則といいます)。ここには、「適正な手続」の要請が「事案の真相を明らかに」するという目的に優位することもあるとの考え方があらわれています(註3)。
【4】高校「公共」教科書と大学生向け入門書を組み合わせて演習問題をつくってみましょう!
今回は、演習問題を1つだけ紹介しましたが、「公共」の教科書に書いてある内容をもとに演習問題をつくることができます。例えば、多くの高校の教科書には「①何人も、自己に不利益な供述を強要されない。②強制、拷問若しくは強迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。③何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない」(日本国憲法38条)に関連する内容が紹介されています。これを大学生向けの法学入門のテキストの記述内容とタイアップして使えば、刑事手続が規定されていることの意義を深く理解することが可能になります。
そこで、井田良『基礎から学ぶ刑事法〔第6版補訂版〕』(有斐閣、2022年)に書いてある、【ちょっと考えてみよう】という小さな演習を用いて考えてみましょう。
「捜査官が、勾留中の被疑者の取調べにあたり、共犯者(被疑者の妻)はすでに自白しているとだまして被疑者を説得し、ついに自白させたというとき、その自白は証拠として使えるか。」
この問題を高校生に出題するならば、最初に、憲法38条に列挙されている「強制、拷問若しくは強迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白」は、なぜ「証拠とすることができない」のかを考えてもらいます。これは、人権侵害によってなされた自白であり、任意になされたものではないことに気付いてもらえばよいでしょう。そのうえでこの問いのように「だまされて行った自白」をどのように評価するか、検討してみましょう。
高校生は意見交換するうちに、被疑者の自白が“自分から進んで行った自白ではない”ことに気づくと思いますので、そのような“任意にされたものでない自白”を証拠として認めてもよいかどうか、さらに検討を進めていきます。そのうえで、刑事訴訟法319条1項の「強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない」(強調筆者)という規定を紹介し、ここにも注意を促すように学習を進めていきます。そこで、最後に、井田さんのテキストにある、「共犯者たる妻がすでに自白したとだまされて行った自白は任意性に疑いがあり証拠となしえない」(同書254頁)との記述を読み合わせてみると、高校生の理解は深まっていくのではないでしょうか。
このように、「公共」の授業で用いる演習問題は、大学のテキストなどを参考にして作成することができます。連載第10回で参考文献も紹介しますが、近年の法学関係のテキストは、判例や具体例などがたくさん掲載されていますから、そのもっとも基礎的な事例を用いれば、高校の授業でも十分に活用できる問題をつくることができるでしょう。いろいろなテキストを活用してぜひチャレンジしてみてください。
【5】おわりに
連載第7回~第9回は、刑事手続関連のテーマを中心に取り上げました。第7回では、戸塚史也弁護士との対談を通して、刑事手続の基本的な考え方を紹介し、今回は、証拠裁判主義と事実の認定に関する解説、さらには、その応用編として演習問題を取り上げてみました。
今回のテーマを取り上げるに際しては、難しい刑事手続の仕組みと制度をわかりやすく解説するために大胆にも図解を試みたり、「公共」の授業にも使える大学生向けの法学のテキストの活用法についても言及したりしました。法と教育の研究と実践において悩ましい論点の一つは、法学における精緻な理論と学習におけるわかりやすさとがどこまで両立できるかという問題です。もし実際に授業で活用していただけるようでしたら、その成果や問題点などをご教示いただければ幸いです。さらに改善を加え、新しい教材づくりや学習方法の開発に取り組んでいきたいと思います。ご助言などよろしくお願いします。
【註】
証拠能力とは、厳格な照明の資料として用いることができる法律上の資格を意味し、証拠能力のない証拠は事実認定の根拠に用いてはなりません。三井=酒巻・前掲註1)262頁。
市川正人ほか『現代の裁判〔第8版〕』(有斐閣、2023年)34頁参照。なお、この事案の結論としては、最高裁判所は、違法の重大性と証拠として許容することの不当性とのいずれも否定し、証拠能力を認めました。事案の詳細についてもっと知りたい場合は、川出敏裕「証拠排除の要件」刑事訴訟法判例百選〔第11版〕(2024年)204-205頁を参照してください。
【連載テーマ予定】
Ⅰ 「契約」の基礎 〔連載第1回~第3回〕
Ⅱ 「契約」の応用:消費者契約と労働契約を中心に 〔連載第4回~第6回〕
Ⅲ 「刑事法と刑事手続」の基礎と問題提起 〔連載第7回~〕
Ⅳ 「憲法」:「公共」の憲法学習の特徴と教材づくり
Ⅴ 「校則」:身近なルールから法の教育へ
★大好評第7回「弁護士と学ぶ刑事手続の基礎」はこちら
▼「法学部で学ぼうプロジェクト」のポータルサイト
▼公式YouTubeチャンネル
▼「『法学部』が面白いほどよくわかる」電子書籍好評発売中です!(Amazon購入ページへジャンプします)
*よかったら、note記事のスキ・フォロー、YouTubeのご視聴・コメント等で応援してください♪
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

