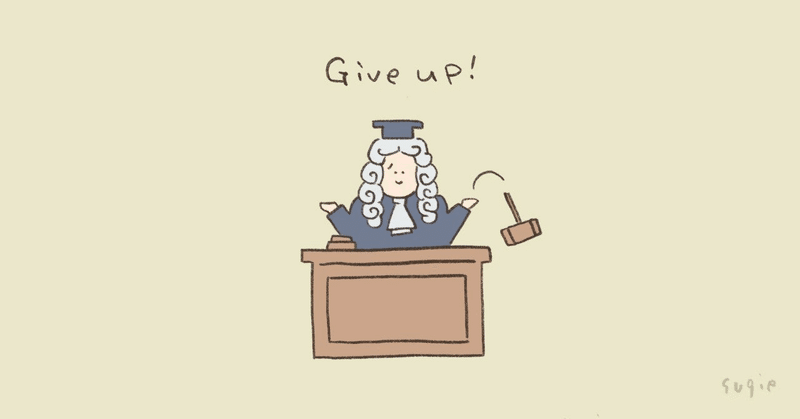
法廷映画のセオリー(映画「赦し」を観て)
「落下の解剖学」を鑑賞後に、前日WOWOWオンデマンドで観た「赦し」の感想を記す人間もなかなか珍しいような。
「赦し」
(監督:アンシュル・チョウハン、2022年)
──
かつて17歳で同級生を殺害した女性。裁判官から情状酌量の余地を与えられず、未成年にも関わらず懲役20年の実刑判決を言い渡されたが、7年が経過し「罪が重すぎる」と再審申請がなされたところから物語は始まる。
罪を犯した女性と、最愛の娘を亡くした父と母。父と母は事件をきっかけに離婚し、今は別々の生活を送っている。
事件の被害者は、もちろん亡くなった(当時の女子高生)人間だ。しかし物語が進むにつれ、加害者は被害者によって執拗ないじめ・暴力行為が行なわれていたことが明らかになっていく。激昂する父と、穏やかに生活したい母。娘を信じたい気持ちと、誠実に(みえる)加害者の更生を願う社会。それぞれの思惑が交差しながら、物語で描かれていない「ある人」が犠牲になっていることが明かされる。
こうした話を観ると、真実とはいかに儚く、「全体の一部」に収斂されていると思い知らされる。反省の色を示したとて、それが本心なのか、罪を軽くしたい利己的な気持ちなのかは分からない。松浦りょうの佇まいからはどちらとも判断できるような気がして、でもそれはあくまで、どこまでも観る者の主観に過ぎない。
法廷映画がたびたび生まれるのは、ここに人間の「揺らぎ」が映るからだろう。誰が何を信じるのか、そもそも罪とは何なのか。
検察官も弁護士も、あくまで自らの主張を通すために行動する。そこに真実なんていささかも気にしてないようにも見える。だが、一見相反する意見があったときに、それをぶつけてひとつの結論を導こうとするとき、彼らのようなアプローチこそがより真実に近い判断が炙られるのかもしれない。分からない。
分からないが、これからもたびたび法廷映画を観ることになるのは間違いない。「あいつ、本当は罪を犯してるぜ」なんて短絡的な見方だけではいけないだろう。
「全体の一部」で軽率に判断を下さない知性を、きっと、いつだって試されているのだから。
──
冒頭に「落下の解剖学」を言及しましたが、今年を代表する秀作であることは間違いありません。
こちらも併せて、ぜひ映画館で鑑賞してみてください。
#映画
#映画レビュー
#映画感想文
#赦し
#アンシュル・チョウハン
#アントワーン・フークア (監督)
#ランド・コルター (脚本)
#尚玄
#MEGUMI
#松浦りょう
#藤森慎吾
#WOWOWオンデマンド で観ました
記事をお読みいただき、ありがとうございます。 サポートいただくのも嬉しいですが、noteを感想付きでシェアいただけるのも感激してしまいます。
