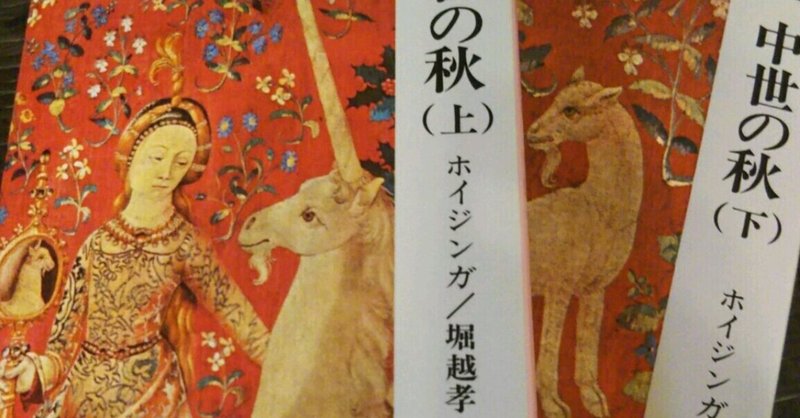
これからのこと
定職につき、結婚し、家も買い、さて、そろそろ次のステージに行くかと考えた時に、ふと、自分はこの先何を残して死んでいくのか、という問いに、どっぷりと浸かっている。
健康にも恵まれ、仕事はまあまあ順調だし、このまま行けばそれなりに満足な人生になるんじゃないかと思いつつ、やはり、まだ自分は一生を捧げるようなものに出会えていない気がしてくる。
ハンナ・アーレントは『人間の条件』の中で、人間の社会活動の中でも、消費活動で消費される宿命にある刹那的な「労働」と、レガシーとして人類史に刻まれる「仕事」とを、敢然と区別する必要を説いている。生真面目なサラリーマンがどんなに一日中汗を流したとしても、人間の歴史に刻まれる成果物を残すことはまずない。生産性などと言われるが、結局のところ、労働者としての生産性とは、資本家の取り分を増やす活動に転嫁されるのみで、成果物もすぐさま消費され、後には何も残らないのが常である。頑張って仕事をして、会社や役所に定年まで勤めたとしても、これが私の成果です、と言えるようなものを残せる人は少ない。多くの場合、やれ年収だ、ステータスだ、と言いながら、その実、労働者としての人生でレガシーを残せる可能性は小さい。
では、未来に残せるレガシーとして、子供を持つとか、あるいは、学術論文など書いたらよいのでは、とも思う。有機体として子孫を残す活動と、「ミーム」を後世に残す活動と。そのうち2つか1つはそのうち実現したいと思っているが、果たして、それが自分の生きた証になるのだろうか、と、疑問に思わないでもない。
よく、子供を持つことが自分の子孫繁栄につながる、ひいては、「イエ」を存続することに繋がると純朴に考えている人たちがいる。自分の遺伝子を後世に残すことで生物体としての自分の存在意義を示したいと考えている人たちがいる。まあ、愚かな考え方だと思う。
自分に子供が生まれたとして、その子供が更に自分の遺伝子を次世代に繋いでくれる保証などない。長い目で見れば、どんなに立派な家系の人でも、ペットショップで売られている血統書つきの犬や猫でも、その個体固有の遺伝子の連鎖はいつかは途絶える。我々は、確かに、約16±4万年前にアフリカに生存していたと推定されるミトコンドリア・イブの末裔かもしれないが、我々がミトコンドリア・イブになれるわけではない。我々にとって、母親は常に存在する自明な存在であるが、我々自身に継承者が現れるかどうかは自明のことではない。これはしばしば思うのだけど、自分の親と自分はどこまでも時間平面的に平等な実存を与えられている、と、漠然と考えている人が多すぎる。そんなものは幻想である。
自分が与えられたものを子にも当たり前に与えてあげたい。自分と親とが実存的に同じ条件を与えられていると思っているからそういう考え方が出てくるのだと思うけども、そもそも、すべての生命にとって、親がいることは自明だが、子がいることは自明ではない。この「条件の格差」を考慮に入れないで、親が自分に与えてくれたものは自分も子に対して当たり前に与えることができると考えることほど愚かなことはないと思っている。
すべての生命は、親がいるという意味では平等だが、それ以上でもないし、以下でもない。
そもそも「自分の遺伝子を残す」活動に、営みに、自分の純粋な欲求以外に従えるものがあるとしても、それは単にエゴでしかない。要するに、人類史に自分の遺伝子の爪痕を残せると考えている人らは、壮大な誇大妄想に陥っているに過ぎない(精子バンクや卵子冷凍の技術の進展はあるいはこの誇大妄想を多少現実に近づけてくれるかもしれないけれど。)。
ならば、知的営みにおいてなんらかの爪痕を残すことが、自分の生きた証になるのかと言えば、そうとも言い切れない。記録というものは、誰かに読まれてこそ価値のあるものになる。誰にも読まれない記録というものを思考実験として存在させることはできるけれども、そんなものは実際には存在しないに等しい。
ギルガメシュ叙事詩は、たまたま面白い部分だけが落書きとして残されて今に伝えられているという逸話がある。この話の学術的な信憑性はともかくとして、面白くなかったギルガメシュ叙事詩は現に我々の歴史の中で存在しないことになっているわけで、これは、キリスト教の聖書にしても、コーランにしても、論語にしてもそうであろう。面白くなかったものは、たぶん、みんな忘れてしまったのである。
現在、本邦の学術機関で生産され続けている学術論文の多くは、この、「面白くないお話」と同じ運命を辿ることになる。アーカイブされているのだから、そんなはずはない、と思う人がいるかもしれないが、記録というものは、読まれるまでは存在しないのと同じである。今現在、納本制度が採用されている我が国の国立国会図書館において、どれだけの知的営みが日の目を見ずに眠っているか、誰も知らない。その大半はおそらく、永遠に日の目をみないままに忘れ去られることになるだろう。たまたまニッチな分野の成果が偶然に該博な研究者の目にとまることがなければ。
ブログだって、日記だって、無名作家の小説だって、日の目をみないポスドクの未発表原稿だって、いつかは忘れさられていく。というか、自分が死んだ後のことなんて考えても無駄であろう。しかしそれを考えずに生きていける人は、まあ、意外と少数派なのではないかと私は思う。
歴史家のホブズボームは『20世紀の歴史』の中で、20世紀の後半は、社会から「歴史性」が急速に希薄化していく時代になった、と述べている。グローバル化の進展は、「文明の衝突」とも見えるような軋轢を生じさせもするけれど、同時に、人間の価値意識の「標準化」が進み、ジェンダーや、人権や、あらゆる差別に対する対抗するイデオロギーとして、西洋において発展してきたリベラルな人文知の知的モデルが社会に浸透し、参照されるようになっていく。良くも悪くもグローバル・スタンダードがもてはやされ、世界は「フラット化」していく。標準化の進展は、世界各地のローカルな社会が内包してきた歴史や文化の様々な「しがらみ」を希釈化していく。進歩や発展に対して前のめりになった社会の有様は、「加速主義」的な思想によって更に強調される。進歩は正義だ、技術は福音だ、と、まるで19世紀のエヴァンジェリストたちが唱えたお題目が再び形を変えて現れているかのようで。20世紀の終わりに冷戦という「大きな物語」の構造が崩壊した後、「ESG」という新たな大きな物語も出現し、21世紀の第二の四半期における支配的なイデオロギーとなった。みなが、「未来」という大きな物語を夢見ているように、見える。
というか、ESGという大きな物語も、先進国における成長率の鈍化と人口の漸減という現象を抜きにしては考えられない。目の前の社会に対する希望が閉ざされようとしている時に、別の物語が必要とされたのだ。物語というのは、フィクションであるし、フィクションに過ぎないとも言える。今、先進国に住んでいる若者が夢を見るとするなら、何らかの形でこのイデオロギーとうまく折り合いをつけていくしかない、と、私は思う。
オリンピックだって、金儲け主義だという批判があるけれども、そもそも金儲け主義でない祭典なんてものがこの21世紀に産まれてくるのか、それはある種の「宗教」と何が違うのか、などと考えたりもする。オリンピアの昔に還るなら、純粋な宗教的行事に還るのもオツなものかもしれないけれど。
ESG以外に金のなる木がないからそれを信仰するしかないのだろうか。私は別に、それでも構わないと思っている。何にせよ、信仰があるということはよいことである。ここまで書いてきて思うのだけど、私は本質的に人間というものを信じていないのかもしれない。
世のため人のために働くことは素晴らしい。それには同意する。その先に「未来」という大きな物語があることも、素晴らしい。書くことは、書かないよりかは幾分マシだろう。ならば書くべきである。何がしかの痕跡を残せると信じて書くのはいい。そこには多少はマシな希望があるのかもしれない。子供だって、いないよりはいるほうが「マシ」かもしれない。その子供が未来を作れるかどうかなど、知らないけれど。
これと同様の虚無感は、不動産市場に対しても抱くことがある。やれ、資産価値だの、持ち家だの賃貸だの、戸建てだのマンションだの、板マンだのタワマンだのとくだらない論争をしている。封建領主にもなりたいのだろうか。
中世イングランドの地主(騎士、聖職者など)の家系、つまりは、ノルマン・コンクエストの英雄たちの末裔が、どんな歴史をたどったか。ジェントルマン資本主義論で言われているように、彼らは19世紀から20世紀の世紀転換期にかけて、土地を失い、金融資本家に転換していかざるを得なかった。日本の大地主だってみな、莫大な相続税を払えずに多くが資産を分散させている。たかだか一代限りのエリートサラリーマンが馬も飼えないような僅少な土地を有したところで、孫の世代ともなればそんなものはお荷物にしかならないだろう。その孫だって、どうなっているか知らん。血筋ほどあてにならないものはない。我が国最高の家系である天皇家だって存続の危機に瀕しているわけだから、我々庶民なら猶更である。土地と家を結び付け、それを取得し、相続させることに価値を見出しても無駄である。資本主義のルールは常に「流動性」を追求するからだ。才能ある子孫が現れても、そんな遺伝的変異が続くわけもなく、世代間で見れば知能指数なども平均回帰するだろうから、自分の家系が3代続くなどと考えないほうがよいわけである。
自分がタワマンに住んでいてこういうことを言うのも何だけども、資産価値の追求というものは所詮、一代限りの博打と変わらない。ちょっと得をするくらいがちょうどいいのであって、労働者階級がどんなに背伸びをしたところで、未来に価値ある何かを残せるわけでもない。しこしこと、誰も読まない論文を書いていたほうがまだマシだろう(私はいずれそうする。)。
端的に言えば、何もかもにうんざりしている。どす黒い感情ばかりが抑えようもなく流れてくるけれども、しょせん、人間など「糞袋」(浅田次郎『壬生儀史伝』の斎藤一の言)に過ぎないのだから、糞袋としては満足な人生を歩めればそれでいい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
