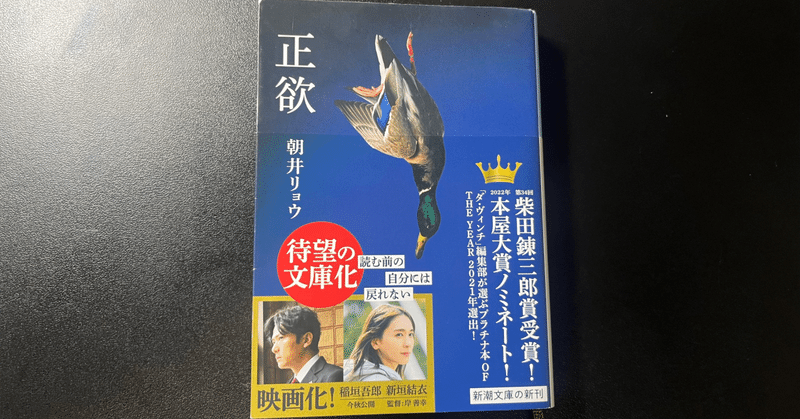
なぜ話し合うのか ― 朝井リョウ『正欲』
「受け入れること」「理解すること」は傲慢なのではないか。
朝井リョウさん著『正欲』読了後にまずそう考えた。そして同時になぜ人は話し合うのか、何のために話し合うのかと疑問に思った。相手を理解する為か?はたまた意見の違う相手を受け入れる為か?
私はその両者は違うと思う。少なくとも、この作品を読んだ後はそれらに対して手放しで賛成することはできません。
この作品を読んで考えたことをざっくばらんに綴ります。
ネタバレがありますのであしからず。
また、用語使用に関しては最大限の注意を払っておりますが、不快に思われる方がいらっしゃいましたら、お詫び申し上げます。
『正欲』あらすじ
自分が想像できる"多様性"だけ礼賛して、秩序整えた気になって、そりゃ気持ちいいよな――。息子が不登校になった検事・啓喜。初めての恋に気づく女子大生・八重子。ひとつの秘密を抱える契約社員・夏月。ある事故死をきっかけにそれぞれの人生が重なり始める。だがその繋がりは、"多様性を尊重する時代"にとって、ひどく不都合なものだった。
『正欲』を読んだら、Toni MorrisonのBelovedを読んだときと似た感情になった。
アメリカ文学の中でも名作として知られる黒人女性作家Toni Morrison著Beloved。
私はBelovedを初めて読んだとき、そしてたぶん今も読んだときに「分からない」という気持ちになります。この感情は登場人物の黒人たちに対してです。差別はダメ、無くさなければならない。そんな月並みの感想しか出てこず、登場人物たちが抱える真の苦しみや苦悩が「分からない」というもどかしさと悔しさ、そして、これ以上この作品に踏み込むことを僕は許されていないという畏怖の気持ちが沸き起こります。
これと同じような、似たような気持ちが『正欲』を読みながら私の中に生じました。本作の主な登場人物は以下の通りです。
■寺井啓喜:検事。妻と不登校になりYouTube活動を始める息子と3人暮らし。いわゆる「普通」のルートから外れていく息子を「普通」へ戻したいと焦る。
■桐生夏月:岡山駅直結のイオンモールの寝具店で働く契約社員。いわゆる「特殊性癖」を持つ。のちに同じく「特殊性癖」を持つ旧友佐々木佳道と暮らし始める。
■神戸八重子:両親と兄と暮らす女子大生。大学祭の実行委員として、ミスコンを廃止し「ダイバーシティフェス」という「繋がり」をテーマにしたイベントの提案・企画をする。男性に対して苦手意識を持つ。
この3人の人生が並行して進み、その補助線として小学生男児に対するわいせつ事件が絡み合いながら物語が展開されます。
「分からない」という気持ちになった最大の要因は2つあると思います。
①各登場人物が抱えるバックグラウンドへ共感ができないことと
②作品の1つのテーマである性的志向や性についての話題が現実とリンクしており、ファンタジーではなく現実世界の出来事として本作を解釈したこと
現実世界で実際に問題になっているテーマであるからこそ、Belovedと同じように安易に登場人物への共感や理解を示すことができないという気持ちになったのだと思います。
ただ、「分からない」で思考を止めることは良いことなのでしょうか。人間は実体験をもとにして物事を解釈する傾向がある為、経験していないことは「分からない」というのが正直なところでしょう。しかし、そこで思考を止めるのではなく、無理に理解するのではなく、何かできることがあるのではないでしょうか。その「何か」はまだ明確にはなっていません。
今は、自分の無知さを痛感するというレベルで留まっています。実際に経験していないことを評価できないし、それが善か悪かの判断もできないと現状では考えています。だから、その事象に対していかに無知であるかを知ることが自分ができる最大限の行動であると思っています。
「キチガイ」「無敵の人」「あり得る/あり得ない」などの言葉の危うさ
Oscar Wildeの戯曲An Ideal Husbandを読むと、物事の二面性、つまり立場や階級や環境が変わればその物事や事象に対する見方が変わることに気づきます。
『正欲』では「キチガイ」「無敵の人」「あり得る/あり得ない」という言葉が登場します。
これらのほとんどがいわゆる「普通」や「マジョリティ」に属する人たちが、それ以外の人たちに向けて放つ言葉です。
見方や視点が変われば全く「キチガイ」「無敵の人」ではないし、「あり得る/あり得ない」は変化します。自分の視点だけに固執して、相手の価値観を評価する発言はとても危険です。自分にとっての当り前は相手にとっては当たり前ではないことを肝に銘じておく必要があると思います。ただ、人間は自分の立場や視点で物事を判断しがちであることも忘れてはいけないと思います。自分の言動を俯瞰することは難しいけれど、物事には二面性があることを意識したいです。
なぜ人は話し合うのか ― 「受け入れる」「理解する」の傲慢さ
結局、見方が変われば全く「キチガイ」「無敵の人」ではないし、「あり得る/あり得ない」は変化するし、人間は自分の立場や視点から物事を判断する傾向があると思います。だからこそ、いわゆる「マイノリティ」の方を「受け入れる」「理解する」為に話し合うという行為や言葉は、マジョリティがマイノリティの存在を認知する、またマジョリティがマイノリティを包含するという「マジョリティ>マイノリティ」の力関係を基にした、マジョリティに属する人びとの偏った視点からの傲慢な言動なのではないでしょうか。
マジョリティを規制して、マイノリティを礼賛することは「マジョリティ>マイノリティ」を基にしていることを示していると思います。
この構図は、神戸八重子とその友人諸橋大也の関係性に顕著に表れています。かねてより大也が周囲の友人らと仲良くできていないことを心配していた八重子はもっと大也の力になりたいと思い、大也のことを理解したいという趣旨の言葉をかけます。しかし、大也は、いわゆる「特殊性癖」を持つ自分が理解されるマイノリティ側であり、八重子は理解するマジョリティ側になっていることを指摘し、その構図に対して嫌悪感をあらわにします。
「自分はあくまで理解する側だって思ってる奴らが一番嫌いだ」
自転車を漕ぐ老人の背中はもう随分と小さい。
「お前らが上機嫌でやってるのは、こういうことだよ」
だけど、その上体が機嫌よく揺れているのはわかる。
「どんな人間だって自由に生きられる世界を! ただしまじでヤバイ奴は除く」
風が吹く。
「差別はダメ! でも小児性愛者や凶悪犯は隔離されてほしいし倫理的にアウトな言動をした人も社会的に消えるべき」
八重子の顔面に掛かる髪の毛は、まるで斜線のようだ。
「俺はゲイじゃない。お前らみたいな、私は理解者って顔してる奴が想像すらしないような人間だよ。俺と同じ性的志向の人は、性欲を満たそうとして逮捕された。窃盗と建築物侵入容疑で」
八重子の表情が、書き間違いを葬るために引くような斜線によって、見えなくなる。
「お前らみたいな奴らほど、優しいと見せかけて強く線を引く言葉を使う。私は差別をしませんとか、マイノリティに理解がありますとか、理解がないと判断した人には謝罪しろとかしっかり学べとか時代遅れだとか老害だとか」
また風が増えて、線が増える。
「理解がありますってなんだよ。お前らが理解してたってしてなくたって、俺は変わらずここにいる。そもそもわかってもらいたいなんて思ってないんだよ、俺は」
お前に。大也は強く念じる。
「お前らが想像できないような人間はこの世界にいっぱいいる。理解されることを望んでいない人間だっていっぱいいる。俺は自分のこと、気持ち悪いって思う人がいて当然だと思ってる」
大也にそう言われても、八重子は下記のように「話していこう」と言います。
何から話していいのか分からないなら、何からでも話していこうよ!もっとこうして話せばよかったんだよ、きっと。私も色々勘違いしてたし、今でも誤解してることいっぱいあると思う。でも、もうあなたが抱えてるものを理解したいとか思うのはやめる。ただ、人とは違うものを抱えながら生きていくってことについては、きっともっと話し合えることがあるよ。
男性嫌悪の気持ちを持つ八重子は、大也に対してはその感情を抱かなかったからこそ、大也のことをもっと知りたいと思ったのでしょう。
この場面で、八重子は「理解したい」と思うことの乱暴さに気づき、自身の行動を改めようとしています。つまり、八重子は自分の無知さを自覚したと考えます。そのうえで、「話そうよ」と大也に提案するのです。男性嫌悪の気持ちを持つ八重子とって、大也はその感情を抱かせない人物つまり、八重子に変化をもたらす大切な人だからこそ、大也のことをもっと知りたいと思ったのでしょう。そして、自身の言動を改めし大也と話したいと言っているのだと思います。このように自分を見つめ直す八重子の姿勢は、自分が相手についていかに無知であったかを知ることが、相手との良好な関係性を築く第一歩になることを暗示しているように思えます。
私は、自分がいかに無知で偏った見方をしていたかを知り、相手との関係構築の一歩を踏み出す為に話すのだと考えています。自分は他人を完璧に理解していないという前提に立つ。そして、評価したり、善悪のジャッジしたりする為ではなく、自分の視野がいかに狭いものであったかに気づくために話し合い、意見交換する。
ただ、「話す」という行為自体、抵抗感がある方もたくさんいると思います。それは、やはり「マジョリティ>マイノリティ」の構図が浸透しているからだと思います。
キレイゴトであればなんぼでも言えますが、現実社会に蔓延る問題として認識する必要がありそうです。
自分がいかに無知で偏った見方をしていたかを知り、相手との関係構築の一歩を踏み出す為に話す。
たぶんこれも単なるキレイゴトなのかもしれません。
それでも、自分だけはこのスタンスを貫きたいなと思います。
1人の力は小さくても、やってみる価値はあるはずです。
タイトル『正欲』とは
複数の人間で社会を構成し、生きていく為には、一定のルールや秩序が必要だと思います。
だからみんな自分が一番正しくありたい。社会的に正しくあることで、自分の価値観をルールにしたい。そういう思いがあるのではないでしょうか。
この社会で自分が一番正しい存在でありたいという欲求。
それが『正欲』だと私は考えました。
心揺さぶられる作品たちを是非。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
