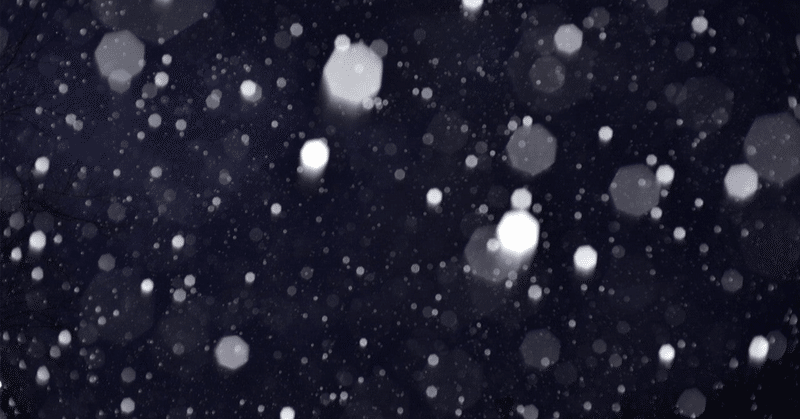
【短編小説】北極星
「自分がどこにいて、何をなすべきで、どこへ向かっている人間なのか、東京では分かったフリをしていないと生きていけないけど、よくよく考えたら、たぶん本当は迷い続けているのだ。」
東京でヘアメイクとして細々と生計を立てる雪。父が倒れたという連絡を受け故郷へと帰るさなか、子どもの頃に山で小熊に会った時のことを回想する。
母から電話があったのは、パリから帰ってきた次の日のことだ。キャリーケースから中身を取り出して整理するのも面倒で、ベッドでごろごろしていた。
そんなに頻繁に連絡を取り合っているわけではないので、スマホのディスプレイに「母」と出た時点で、電話をかけてくるよほどの何かがあったのだと知れる。いやな予感しかしなかった。誰かが病気で倒れたか、死んだか。じっちゃが2年前に死んだばかりなので、可能性があるとしたら高血圧気味の父だろう──ということまでゼロコンマ数秒のうちに考える。
「ああ、ごめんねえ、仕事中だったっけ」
久々に聞く母の声は小さく、恐ろしく繊細に聞こえた。実家にいたころ、彼女の喋り方はそこそこ「近代的」だと思っていた。じっちゃですらそこまで訛ってないほうだったから。でも、今電話口で彼女が喋るのを聞いて、やっぱりどう考えたって訛っていると思った。懐かしいだなんて、そんなセンチメンタルな感情とは東京に出てきてから無縁のはずだったのに、彼女の話す声を聞いていると、まるで受話器の向こう側に引き込まれるように生まれ育った場所の記憶が強烈に蘇ってくる。どこまでも、どこまでもつづく田んぼと、灰色の国道四号線。伏せって眠る巨人の背中のように盛り上がり連なる青い山脈。山の水と土の匂い、夏の草いきれ。冬にはどっさり積もる真っ白な雪。
「いや、大丈夫、今日は休み」
「そう、あのね、お父さん昨日の夜、倒れて」
「えっ」
その情報に驚いたというか、わたしは自分の予感が的中したことのほうに驚いた。
母の声はくぐもっていた。喉が絞られていて、口先だけで喋っているみたいだ。さっきまで泣いていたのかもしれない。
「うん、今、病院」
「え、大丈夫だったの」
「ちょっと様子見で入院するみだいだけど、うん、心配いらねって」
「なんで」
「糖尿」
「ああ……」
じっちゃも糖尿だった。じっちゃはもともと相撲をやっていたほどの巨漢だったらしいけど、糖尿をやってガリガリに痩せてしまった。わたしが物心ついてから知っているのはその痩せているバージョンのじっちゃだ。父も体が大きくて太っているけど、これからじっちゃのように痩せていってしまうのだろうか。それはあまりにも現実味がなかった。うちの男たちはなぜかみんな肥満体質で、4つ年上の兄も太っている。
「そんで、雪、最近はどうなのよ、あんた体の具合とかは」
電話の向こうから聞こえて来る音で、母が車に乗ったんだということがわかった。バタン、とドアが鳴る。
「うん、元気だけど」
「まぁだ仕事頑張ってんだなぁ」
「うん。昨日パリから帰ってきたばっかりでさ」
「え?どこ?」
「パリ」
「どこのパリ?」
「フランスのパリ」
3秒くらい沈黙が落ちた。
「へえーっ、何しに行っだのよ」
「仕事で」
「へえーっ、そう、へぇえ」
母はしきりに感嘆している。
言わなければよかったかも、と思った。ひとえに、わたしの虚栄心が口をつかせた。海外で働いてるんだよ、ってこれが父に伝わったら、父の口から職場と漁協の人たちに伝わって、その子どもたち、つまりわたしの同級生にも瞬く間に知れ渡る。田舎ってそういうところだ。
一年ほど前に帰った時には、中学校の同級生が新幹線の駅から一番近いコンビニでレジ打ちをしていて、彼が少し興奮しながら、「豊田は芸能人と毎日会う仕事をしてるって母ちゃんが」と言ってきた。思い出しただけで、とてつもなく惨めな気持ちになってくる。昨日までの高揚感──初めて訪れたパリで出会った素晴らしい人たち、ファッションウィーク中のきらびやかな街の雰囲気、聞かされていたよりもずっと優しかった街のタクシーの運転手たち、ランウェイのバックヤードでの緊張感や、デザイナーをはじめブランドの人たちと交わした祝杯、アフターパーティのざわめき──そんなものが、途端に陳腐なものに成り下がってしまった気がした。わたしがたった今、母に一言告げるだけで、そうしてしまった。
「そっだら雪、今度はいつ帰って来るのよ」
明日の天気でも確認するみたいな気安さを装って、母が言った。結局それが言いたかったのだとういうことは、途中からずっとわかっていた。
*
じっちゃの黒いワゴン車の鍵には、熊の手の剥製がついていた。
「2歳くらいの子熊だ」
東京から人が来るたびに、それを見せびらかして得意そうな顔をするのだった。子熊の手だといってもそれは可愛らしいもんじゃない。小学校を卒業する頃になって、わたしの手はようやくその子熊の手の大きさを追い越した。そんなものが運転をするときにはいつもぶらぶらダッシュボードの下で揺れているのだから、今だったら冷静に邪魔なんじゃないのとつっこむところだ。
「ほれ、爪がついとって、子供でこれだ、大人の手にぶっだだかれだら、ひとたまりもねべ」
鋭い鉤爪が飛び出していて、ゴワゴワした毛の裏側には硬い肉球がついていた。じっちゃの車の鍵には他にもいろんなものがジャラジャラついていて、熊の手の次に必ず見せるのが「熊のちんこ」だった。
「熊のちんこには骨があるのよ。これが、耳かくのにはちょうどいんだ」
どこかに貼り付けられたまま忘れ去られたセロテープみたいに黄ばんだ色をした骨は、少しだけ先細りになっていて、たしかに竹の耳かきの形状に似ていなくもなかった。
わたしたち家族が住んでいたのは空港の近くだった。まわりは国道とそれに沿って広がる田んぼしかなかったけど、ちょっと内陸の方の道に入るとすぐに山の入口があって、そこから先はもう熊の住処だった。どこもかしこも熊だらけだった。
「山さ入っだらそごはもう熊の家だ。俺だづがお邪魔する立場なんだ」
とじっちゃはよく言っていたけど、威勢良く熊よけの火花を空に向かってパァンパァンと打ち上げたり、「熊撃退スプレー」を素早く噴射する練習の様子なんかを見ていると、そこまで殊勝な心掛けをほんとうに持っていたのかどうかは怪しい。
漁業協同組合の会長をやっていたじっちゃは、よく地元の小学校に呼ばれて、川の上流でヤマメの放流の指導なんかをしていたから、山に頻繁に入る身として熊対策には人一倍熱心だった。わたしと兄は、休日は家でテレビばかり観ている車の販売所勤めの父より、定年退職して暇を持て余しているじっちゃと、土地改良区のおじさんたちによく構ってもらったので、自然と山に入ることも多かった。
東京だと一年のうちそう何度もニュースになることはないけど、わたしたちの身の回りでは、いつもどこかしらで誰かが熊に遭遇していた。誰かが会った話に尾ひれがついて、次の日には同じ話なのに違う人が会ったことになっていたりもした。
こういう熊の話は、東京の人にはとても面白がられる。
「それで、雪ちゃんは、熊に会ったことあるの」
そう言われると、いつも話すエピソードがある。
わたしが小学校に上がってすぐくらいの頃だ。わたしと兄はじっちゃの運転する車に乗っていた。すると、山道を走っていた時にいきなりアスファルトの道路に黒い塊が飛び出してきて車に激突した。車はものすごい勢いで揺れたけど、じっちゃがブレーキを踏まない間にそれは消えてしまった。若いオスの熊だったとじっちゃが興奮気味に言った。
「ほれ見でみぃ、こんな凹んで」
黒いワゴン車のバンパーがべこっと凹んでいるのを、わたしと兄は興味深く眺めた。
「熊はな、車にぶつかったぐれじゃ死なねのよ。顔が入っだばあとは全部入るようなっでるから。丈夫なんだがら」
じっちゃの方言と身振り手振りを真似して飲み会で披露すると、ほぼ間違いなくウケる。
そういう感じで、当たり障りのない熊情報を東京で吹聴してきたわたしだけど、でも、ほんとうはもっとヤバいやつがある。これは、じっちゃにも、兄にも言ったことがない話だ。
5歳の時、兄の年代の子供たちがボーイスカウトのキャンプに行くのについて行かされた。親は、夏休みにわたしの面倒を見るのが億劫だったんだろう。
じっちゃもボーイスカウトの偉い人に頼まれて、「市の自然の豊かさを子供たちに伝える」という役割のために同行していた。結局わたしは、兄にも、その友達の男の子たちにも、彼らの相手をするためにかかりっきりになっているじっちゃにも相手にされなくてずいぶんつまらない思いをした。じっちゃも結局、男の子が好きなんだと思った。自分が女なんだということを強く意識したのはこの時が初めてだ。
そういうわけで、暇を持て余したわたしは、男の子たちがテントを張っているのをよそに、少し離れた場所でしゃがみこんで石を積んで遊んでいた。大きな石から順々に積んでいって、バランスをとりながら、少しずつ大きさを小さくした石を乗せていくのだ。4つほど積んで、我ながらうまくいっていると思って、もう一つ載せるための小さな石を探そうとしていたら、ガサ、と草の揺れる音がして、ふと顔を上げたら、ほんの3、4メートルくらい先のフキの茂みの中に「それ」がいた。
最初は犬かと思った。でも違った。秋田犬ほどの大きさの、見事な赤毛の子熊だった。川べりで水でも浴びたせいなのか、雨上がりの濡れた草木の中を歩いてきたからなのか、赤い毛はところどころ束になって体の流れに沿って巻き付いていた。そんなところまではっきり見えたのを、今でも覚えている。
この平地にキャンプを張る時、じっちゃが大はりきりで熊よけの火花を鳴らしていたのに、そんなものまったく意に介さず森の入り口まで出てきてしまったのか。ころころと太った子熊はぬいぐるみのように人畜無害に見えた。
「子熊を見かけたら──」家でも、幼稚園でも、口を酸っぱくして言われることだ。「子熊を見かけたら要注意。必ず近くに親熊がいる」。親熊が出てきてしまったら、目をそらさずに、刺激をしないようにゆっくりと後ずさりすること。走って逃げるのはダメだ。熊は動くものを本能的に追いかける習性があるから。
五歳だったわたしでも、これまで習ってきた注意事項は容易に思い出すことができたのに、いざ遭遇してしまったらただその場に釘付けになるばかりで、どれも行動に移すことができずに呆然とするしかなかった。結局そういうことなのだ。不測の事態に陥ったら、人間にできることはほとんどない。
赤毛の子熊はビー玉のようにきらきらと潤んだ目でわたしのほうをじっと見ていた。わたしも見つめ返した。見つめ合っているうちに不思議な一体感すら覚え始めて、だんだん自分はもともと熊だったんじゃないかと思えるくらいだった。ゆうに5分ほどはそうやって見つめ合っていた気がする。子熊はすこし首を傾げてから(そういう動作が熊にあるのかわからないけど)、ふいっと目を背けて、またがさがさと草の音を立てながら森の中に消えていった。結局、親熊は現れなかった。
子熊の姿が見えなくなってから、急に、自分の背後でキャンプに勤しむ男の子たちの声が大きく耳に入ってくるようになって、まるで夢から覚めていくような心地がした。熊を見たって、じっちゃに言ったら信じるだろうか。なんだか信じてくれない気がした。五歳だったわたしはすでに、大人というやつがとにかく子どもの言うことをなんでもかんでも嘘だと思って、まともに相手にしてくれないことを知っていた。子熊が出たのに親熊が現れなくて、しかもその子熊がなんにもせずに立ち去ったなんて、あまり聞いたことがない話なだけになおさらだと思った。だから、わたしはこの子熊に会ったことを自分だけの秘密にしようと心に決めた。
その日の夜、じっちゃとボーイスカウトのリーダーたちは、男の子たちを集めてテントの外で天体観測を行なった。夜空は濃い緑と青が入り混じったような不思議な色をしていて、星たちは、まるでわたしのお道具箱の中できらきら光る色とりどりのビーズだった。
「空を見るときはまず『ひとつ星』を探すんだ」
ひとつ星? だれかがおうむ返しに聞いた。
「北極星だ、ほれ」
じっちゃは細い指で、濃紺の夜空にひときわ大きく輝く星を示してみせた。
「どごへいっても、どんな季節でも北の空で光ってる星だ。これがあれば迷うごだね。むかすはあの星を見て、みぃんな海を航海すたんだ」
わたしは、結局一日中誰からも持て余されて暇をしていたので、ふてくされながら空を見上げていた。男の子たちはみんな星には興味がなさそうだった。ぎゃあぎゃあはしゃいで、じっちゃの話も、聞いているんだか聞いていないんだかわからない。年長のスカウトや、大人たちが躍起になって静かにさせようとしている。大人のだれかがじっちゃに気を利かせて声をあげた。
「ほら、高学年は学校でやっただろう。北極星はなんの星座の星だろう?」
だれも答えられなかった。男の子たちの騒ぐ声や、先生たちが叱りつける声を聞きながら、わたしはいつのまにか眠りに落ちていた。
あの日の遭遇のことを、わたしは結局誰にも言わずに大人になった。自分以外の人間に知らせることが、なぜか勿体無いような気がしたのだ。
一人だけ、この話をしようと思った人がいる。東京に出てきて、はじめてできた彼氏だ。わたしはまだ十九歳で、彼はコンサル会社で働いている二十歳ほど歳上の人だった。
彼は東京出身で、渋谷で働いていて、細身のスーツが似合う男だった。田舎娘には、彼のやることなすこと全てが輝いて見えた。付き合って半年ほど経った時に、お互いの子どもの頃の話になって、わたしはすっかり彼に参っていたから、自分の胸の中にしまっていた宝物のようなその思い出を語ろうとした。その前段として、じっちゃの車の鍵にくっついていた熊の手のキーホルダーと、熊のちんこの骨の話をしたら、それまで穏やかな表情で聞いていた彼がなんだか困った顔になって、「その骨に触らされたってこと? それって児童虐待なんじゃないの?」と言った。
児童虐待。わたしはその言葉を聞いた瞬間頭が真っ白になって、次に何を言おうとしていたのかも忘れてしまった。
とりあえず、笑いながら「そんなんじゃないよ」みたいに受け流したような記憶がある。彼は純粋な心配からそんなことを言ったんだろう。下ネタを言いながら子どもをからかうっていうのは、たしかに捉え方によってはまずいかもしれないけど、でもどう考えたって「児童虐待」は自分のじっちゃとは結びつかない言葉だった。自分の軽率な発言のせいで、彼氏にとんでもない誤解を植え付けてしまったかもしれないと、それからわたしはしばらく、じっちゃに対する罪悪感にも似た感情に悩まされた。その彼とは、知り合って一年経たないくらいの時に、お互いの忙しさにかまけて自然消滅した。東京に出てきて最初に付き合った歳上の彼氏と結婚する、なんていうロマンチックなストーリーに勝手に盛り上がっていたのは、今となっては青臭い思い出だ。それから、未成年と付き合うことを厭わない四十代の男を伴侶に選ばなくて、今は本当によかったと思っている。青臭いどころか、ほとんど黒歴史だ。
そういうわけで、結局のところ、今でも、あの赤毛の子熊とのことはわたしだけが知っている秘密だ。
*
母は「帰って来い」とは言わなかったが、父親が病気で倒れたというのに何もしないというのは、さすがに薄情なんじゃないかと思った。ちょっと顔を出して、日帰りで東京に戻るか。儀式のようなものだ。母にそう電話で伝えると、「泊まっていかないの」と聞くので、「仕事が忙しいから」と適当なことを言う。わたしは高校を卒業して東京に出てきてから今に至るまで、十年以上、実家には一泊もしたことはないのに、毎度このやりとりが発生する。
母の電話を切ってすぐ、ベッドに寝そべりながらスマホでJRのページを開くと、Googleカレンダーと睨めっこをしながら、母が教えてくれた退院日の翌日に合わせて新幹線のチケットを手に入れた。こういうことはすぐに片付けておかないと、億劫になってどんどん先延ばしになってしまう。
購入が完了したJRのブラウザはそのままに、わたしは別のブラウザを立ち上げて取り止めもなくネットサーフィンを始めてしまった。バレードのフレグランスキャンドルが1万560円。バレンシアガの2017年プレフォールのコレクションで見かけた目の覚めるようなセルリアンブルーの「トライアングル」バッグが22万5800円。
一瞬の微睡の間に、自分が実は高校を卒業していなかったというホラーのような夢を見ていた。スマホが顔の上に落ちてきて、「いてっ」と言いながら目が覚めた。
翌日は朝一番から雑誌の撮影があった。カバーを飾るモデルのヘアメイクだ。まだ20代になったばかりの彼女は、コットンキャンディーのような甘く軽やかな声で、「ずっと夏のままだと思ってたのに肌が乾燥しはじめて、やっと秋を実感しました」とかわいいことを言う。スキンケアについていくつかアドバイスをすると、たいそうありがたがられた。
午後3時ごろ、赤坂にある広告代理店のロビーに併設されているスターバックスで、担当者と落ち合う。店内の飾り付けがハロウィン仕様になっていた。真っ赤なパンツにベビーピンクのタートルネックを着ている女性がいて、その絶妙な組み合わせに唸ってしまう。こういうことが気になるのは職業柄だ。
高校生のわたしは、「赤坂のカフェで取引先とミーティング」などというオシャレな生活を手に入れることができるくらいだったら、悪魔に魂を売ることも厭わなかっただろう。しかし、何かが欲しいと願っても、その何かを手に入れる頃には過去の自分の切実な気持ちなんてすっかり忘れて、今度はまったく別のものが欲しくなっている。バレードのキャンドルにバレンシアガのバッグ。東京で生きるということは、想像を絶するほどに楽しく、同じくらい難儀だ。
打ち合わせが終わったのは夕方で、そこから表参道にタクシーで移動する。移動中、電話でアシスタントといくつかやりとりをした。次の撮影日の確認、担当するスタイリストの名前。おそらく使われるであろう服のブランド名をメモして、準備するべき道具の参考にする。明治通り沿いを表参道ヒルズの前で降ろしてもらうと、路面店のショーウィンドウを覗きがてらキャットストリートを歩き、バンクギャラリーを目指す。
ネオンを反射して夜空が濃紺に烟っている。くぐもった音楽と人々の喧騒がこぼれてくる気配が近づいてくる。すでに「顔だけ出した」「義理は果たした」という体の知人が歩いてくるので、すれ違うたびに手を振る。
バンクギャラリーの入口には黒ずくめのPR会社の人間たちがいて、そのうちの顔見知りが親しげにわたしの名前を呼びながら「きてくれてありがとうございます!」と言った。インビテーションを渡す。胃袋から爪までを振動させるベースの重低音。ライトの落とされた暗い会場には、網膜が切り裂かれそうなほどに激しいショッキングピンクのネオンが走る。ディスプレイテーブルの上にコスメが展示されていて、揃いの制服を着たブランドの人間たちが来訪者に説明を重ねていた。フォトブースの前では、カメラを構えた各媒体のフラッシュの中にインフルエンサーたちの挑戦的な眼差しが光る。
メゾンブランドのコスメラインから新しく発表された、リップスティックのお披露目イベントだ。よく同じ案件に居合わせる仲のいいスタイリスト、千佳ちゃんが声をかけてきた。最近流行りの「WE SHOULD ALL BE FEMINISTS」のTシャツに黄色いファーコートを羽織った彼女は、わたしのイエローグリーンのセットアップスーツを褒める。「カラー診断」というのをやっているブースを覗き、一緒にシャンパンを飲みながら、ああでもない、こうでもないと言い合い会場を巡るのは楽しかった。音楽がうるさいので、些細なことを言い合うのでも大声になる。大声で喋っている自分が途中からおかしくなってくる。こんな大声を出してまで伝えることなんて、本当はあるのだろうか。
見知った顔に一通り挨拶を終えて会場を出た。よく隠れてタバコを吸う路地裏に足を踏み入れると、同じことを考えていたらしい同業の人間たちが数人いるのが目につく。よく見ると、取り巻きのような人々に隠されるような場所で実際に吸っているのは一人で、それは瀬島うららだった。
あ、と思って、「あ」というのが顔に出てしまったなと思った。何度かメイクを担当したことがある。そういえば、優等生らしいパブリックイメージとはうらはらに、この人はタバコを吸うのだった。一年ほど前、女性誌の「サスティナブルな暮らし」特集の撮影で香川県を訪れた時、一緒に中華屋の屋外の喫煙所でタバコを吸ったことがある。
マネージャーがわたしのヒールの音に振り返り、一瞬目を逸らしかけて、彼も「あ」という顔になった。
「豊田さん」
わたしはこんばんは、と挨拶をした。瀬島うららとも目が合ったが、彼女はいまいちわたしのことが思い出せないのか、ぼんやりした反応ですぐに逸らされてしまった。路地裏の上には星も見えない東京の空が細長く切り取られていて、薄暗がりの中で瀬島うららの肌は乳白色のガラスのように光っていた。そして鮮烈に浮かび上がる、真っ赤なリップ。茶色いファーコートの下にオーガンジー素材の黒いドレスを着ていて、足元は小枝のように華奢なピンヒールだった。
東京で仕事をして知ったことのうちの一つに、「芸能人は驚くほど小さい」というのがある。比喩ではなく文字通りの意味で。女性は特に。みんな顔はアボカドをひっくり返したような感じで、指先は魚の骨のように細い。人間ではなく繊細な粉を纏った妖精のように見える。テレビの画面や雑誌の誌面を通すと、たぶんどんな人間でも必要以上に大きく見えてしまうのだ。
この前はお世話になりました、という挨拶をマネージャーと交わしながら、わたしは「やってしまったな」と思っていた。目が合ってしまったので、変に見知った仲である以上踵を返すのも変な気がした。それで仕方なくタバコを取り出して吸うことにしたが、実は彼らは胸の中で「いやそこは空気を読んで立ち去れよ」とでも思っているかもしれない。芸能人なのだから、人目を憚ってここにいるのは明らかだ。やっぱり「邪魔しちゃってすみません」と立ち去るべきだったか。
はたから見ると、つれなのか、そうじゃないのか微妙な距離感でタバコをくゆらせているわたしに向かって、いきなり瀬島うららが声を上げた。
「思い出した、ハイライトの豊田さんだ」
彼女が指差しているのはわたしの指がつまんでいるタバコだ。「変わったの吸ってますね」と、彼女に以前言われたことを思い出した。その時わたしは、自分がハイライトを吸っているのは、子どもの頃に兄の本棚にあった『最遊記』という漫画のキャラクターに影響されて……というくだらない話をした。女優相手に何を話せばいいのかわからなくて、沈黙を埋めなければと焦った記憶がある。
瀬島うららが、この前やってもらったメイクはとても気に入った、という話をする。社交辞令とは知りながらも、わたしは素直にお礼を言った。うれしかった。さらに彼女は香川県での撮影を振り返り、その時の思い出をわたしと共有してくれた。
「あの時は暑くて大変でしたよね。小豆島のお土産のオリーブオイルがすごく美味しくって、ドレッシングにしてあっという間に使い切っちゃいました」
もう30も半ばをすぎているはずなのに、なんという透明感だろうと思う。声まで透明だ。心もきっと透明。わたしが小学生の頃、連続テレビ小説の女子中学生役で一世を風靡した瀬島うららは、今は中堅どころの女優となって、年齢と比例するようにメディアの露出も減っているように思う。民法のテレビドラマで頻繁に見かけるということはないが、大河ドラマでちょい役だけど重要な歴史的人物を演じて「やっぱりこの人は演技派だよね」と視聴者に安心感を与え去っていく感じ。さいきんでは社会貢献活動に熱心らしく、国連だかユニセフだかそういう感じの団体の親善大使のようなことをやっていると聞いた。それから、サステナブルをテーマにしたオーガニックコスメブランドを立ち上げたというのもニュースになっていて、わたしもレセプションに呼ばれたことがある。そこで一緒になった千佳ちゃんが、「この業界の女は30すぎるとみんなオーガニックババアになんのよ」と訳知り顔で耳打ちをしてきたので、笑いを堪えるのに必死だった。
「豊田さん、もしかしてパリ行ってました?」
「あ、そうなんです。なんでわかったんですか」
「ほら、豊田さんがヘアメイクしたブランド、わたしもデザイナーが知り合いで。話に聞いてたんですよ」
「そうでしたか」
「でも、よかったですね、パリコレが選挙までに戻ってこれるスケジュールで。不在者投票とか、いろいろ申請するの面倒ですもんね」
選挙? まるで別次元の言語を聞いたのかと思って大いに面食らい喉が詰まる。しかし咄嗟の判断で曖昧に笑って「本当にそうですね」と頷いた。
瀬島うららとその仲間たちは、そろそろ行きますよ、というマネージャーの一言でぞろぞろと裏路地から退散の準備を始める。表に止まっていたベンツのSUVはこの人のものだったか、とその時に思い至った。
「豊田さん、よかったらこれ使いません?」
わたしの前を横切る時、瀬島うららが取り出したのはイベントで配布されていたお土産の小さな紙袋だった。こういうパーティでは必ず来場者に配られるから、わたしも自分のものを持っている。瀬島うららからは、ゼラニウムに香木が混じったような、スモーキーで重たい香りがする。
「わたし、自分がブランドやってるっていうのもあるけど、さいきんオーガニックしか使わなくなったんです。こういうメゾンってどんどんコングロマリッドになっちゃって、利益追求型でしょ。グローバル規模でめちゃくちゃ環境破壊してるし、正直、そういうのってどうかなって思うんですよ」
どうしたんだろう、急に。内心呆気に取られながら、わたしはひとまず紙袋を受け取った。そして、「じゃあ今度お仕事する時は、おすすめのオーガニックブランド揃えときますね」などと乾いた口を動かして言う。彼女は嬉しそうに顔を綻ばせて、じゃあね、と手を振りながら取り巻きと一緒に消えていった。
タバコの残りも少なくなったところで、わたしはスマホで「コングロマリッド」を検索する。Wikipediaの記事によると──「コングロマリット(英: Conglomerate)は、狭義には、多業種間にまたがる巨大企業のこと。ただ、今日では、多業種間にまたがらない巨大企業もコングロマリットと呼ばれることも少なくない」。
続いて、「選挙 2017年」と検索すると、第四十八回衆議院議員選挙、と出てきた。投開票日は10月22日。「改憲論議活発化か」という記事の見出し。しかし、まさかいつもと変わらない日常の中で瀬島うららの口から「選挙」などという言葉を聞くなどとは思いもよらず、混乱で脳みそがピリピリした。何が何やら、意味がわからない。わたしは生まれてこのかた選挙に行ったことがない。この国の首相が、幼稚園の園長先生みたいな顔をしていることは知っている。そういえば、東京に来た当初は、母から「あんたの投票用紙がこっちに届いている」と連絡が来ていたような、いないような。しかし「住民票を移しなさい」とは言われないので、億劫に思ったまま、10年経った今も、何もしていない。
この日のイベントに来場した瀬島うららのスナップを、わたしは次の日にFashionsnap.comの記事で見つける。
*
実家に帰るだけなのに、わたしはパリで買ってきたマルジェラを履く。マルジェラだって極東の国のド田舎でアスファルトを踏むのは不本意だろう。髪を結えると新幹線の座席に当たってゴワゴワするので、ロブカットを丁寧にブローした。新幹線でメールチェックなどをしていると、すぐに気分が悪くなってしまって早々にノートパソコンを閉じる。
東京駅を出発して、2時間半かけて列島を北上。ふるさとに近い新幹線の駅に到着したのは昼過ぎだった。
改札を出るとまず空気が違う。ひんやりと冷たくて潤んでいて、吸い込むと肺が透明になる。まず目につくのは広大すぎる駐車場だ。グレーのアスファルトが気が遠くなりそうなほどに続いていて、遠くに白いレゴブロックのような建物がぽつり、ぽつりと並んでいるのが見える。ステーキハウス。レンタカー屋。平日の昼間ということもあるのかもしれないが、それにしたって人気がなく、まるでゾンビ映画に出てくるゴーストタウンのようだった。空には重たいグレーの雲が垂れ込めている。
まずは一服しようと思っていたら、母の白いN-BOXが吸い寄せられるように目の前にやってきて、飛び上がりそうになった。なぜ、と一瞬思って、新幹線が到着する時間を告げていたからだ、と思い至り、安心した。わたしたちはゾンビに襲撃された街の唯一の生存者だった。
「あんたその髪!」
母が悲鳴をあげる。わたしは息だけで笑って、顔にかかった髪をかきあげた。根本は黒髪で、真ん中あたりから毛先にかけてアッシュブルーに染めている。この前帰ってきた時に自分の髪が何色だったのか忘れてしまった。早く乗れと言われ、ほとんど押し込まれるように助手席に座る。母はバタバタと駆けて運転席の側に周り、シートベルトを閉めるのもそこそこにいきなり発車させた。
「あんた、お父ちゃん腰抜かすわ」
運転しながら忙しなく周囲に視線をめぐらせていて、誰かから見られることを警戒しているらしかった。まるで護送される囚人の気分だ。
「わざわざごめん、タクシーで行こうと思ってたのに」
「バカなこと言って」
滑り出したN-BOXが角を曲がって県道を走り始めると、道の遠く遠くにごつごつと青がけぶった山脈が聳え立つのが見え、帰ってきたのだな、と思う。雲がかかっているせいで山のてっぺんが見えない。
母は黒く長い髪をキラキラのラインストーンがついたクリップでまとめ上げている。化粧っ気はないが綺麗な肌だ。黒いパーカーはピッタリと上半身に張り付き、体のラインをあらわにしていて、少し太ったかもしれないと思う。わたしがちらちらと母を見やっているのと同じくらい、母もわたしのことを伺ってくるのを感じる。
「それでお父さんはどうなの、様子は」
口火を切ると、母はまるで許可を得るのを待っていたかのような勢いで話し出した。
「意識はしっかりしてる。もう退院して、高血圧をなんとかする薬をもらって、今飲んでるところなんだわ。お医者さんは、食生活を改善していきましょうとかなんとか言ってらったなぁ」
そうだろうな、とわたしは思った。父は水代わりにビールを飲む人だった。ビールを飲まない時にはファンタを飲む。
「それにしてもあんた、パリ行ったって、仕事だったの」
父のために家に来たのに、父の話はすぐに終わってしまう。
「そうだよ、もう話したでしょ」
「だからぁ、仕事ったって何しに行くのよ」
「東京のブランドがパリのコレクションに出るから、そのヘアメイクをしたの」
「へえーっ」
風船から空気の抜けるような相槌だった。灰色の県道の左右には金色の稲穂が実った田んぼが続く。ほとんどこの世の終わりのような景色だった。この道を自転車で行き来していたセーラー服姿の自分を見つけるような気がして、いっしゅん恐ろしくなる。
「お兄ちゃんが」母が少し、喉を詰まらせた。
「お兄ちゃんが、もうぜんぜん出て来こないのよ。雪、ちょっとその、パリの話なんてしてやったらどうなのよ」
「は?」
意味がわからなくて、思わず険まじりの声になってしまった。
「どういうこと?」
「ほらあ、お兄ちゃんはずぅっとああして部屋にいるわけだから、気晴らしに東京とかパリの話をしたらどうかねぇと思って」
「そんなの兄貴怒るよ。つか、部屋から出てくんの?」
「そりゃ、お兄ちゃんだってトイレ行ったりお風呂入ったりするし」
母は、わたしの物分かりの悪さがおかしいとでも言うように笑いながら答えたが、そんな人間として当たり前の営みを誇らしげに語られても困る。
「まったく会話がないってことじゃないんだよね。独りでご飯食べたりもしてるみたいだしね。とにかく雪がいてくれたら喜ぶでしょ」
「喜ぶわけないじゃん」
「なんでよ」
「なんでも。東京で働いてる偉そうな女がなんか言ってると思うだけだよ」
「まぁた、あんたは」母はうんざりしたような声を上げる。
「なんでそんな意地悪なことばっかり言うのよ、お兄ちゃんと仲良かったでしょ」
「母さん、わたしもう27だから。兄貴は31。大人でしょ。大人になった兄貴と妹がいつまでも仲良しこよしってのも変な話じゃん」
「ほんっとうにもう、あんたとお兄ちゃんが逆だったら良がったのにねぇ」
「……あたしが引きこもりの方が良かったってこと?」
「そうじゃなくて、ただ、あんたはいつまで経っても東京から帰ってこないし、この辺にはうちの他にそんな女の子はいないから──」
わたしは何も言わずにため息をつき、くったりとシートに背をもたせかけて、変わり映えのしない景色に視線を流した。母は、わたしが「もうこれ以上の話は無駄」という雰囲気を醸し出しているのに気づいているのか、気づいていてあえて知らないふりをしているのか、わたしの高校時代の同級生にもうひとり子どもが生まれた、という話をしだした。
*
兄貴は東京の大学に行った。わたしでも名前は知っている中堅の私立大学の社会学部。親は東京で一人暮らしをする兄貴に毎月せっせと仕送りをした。わたしは兄貴が羨ましかった。大学受験すら許されなかったからだ。東京に進学するなんてもっての他だった。
地元で就職しろと言われたが、それを振り切ってほとんど自暴自棄のような勢いで東京に出てきた。それと入れ替わるように、卒業した兄貴が地元に帰ってきた。実家に帰ってこい、という圧力もかねてからあったらしいが、東京での就活がうまくいかず、エントリーを出していた企業は全滅したという話は聞いていた。いわゆるUターン就職というやつで兄貴は地元のメーカーに滑り込むことに成功し、営業として働き始めたようだった。わたしはそんな兄を負け犬だと思った。
東京から逃げ帰ってきた彼への腹いせのように、わたしは頑なに東京に居座り続けた。アパレルショップ、居酒屋、コンビニ、スナック、ティッシュ配り、住宅展示場の呼び込み、ありとあらゆるアルバイトを経験し、時に掛け持ちし、20歳の年に知人の伝手で知り合ったヘアメイクアーティストのアシスタントを始めた。アシスタント業はほぼ無給に近かったが、バイトを続けながらなんとかしがみついた。
育ちは悪い、金はない、学歴もない、コネもない、そんな田舎の小娘は、大都市では吹けば飛ばされそうなほど無力な存在なのだとわかっていた。わたしはあの頃、ただ生きているだけで毎日怯えていた。早く怯えずに済む自分を手に入れたくて、なんとか生きる術が欲しかった。わたしの体に、わたしの魂にビタっとくっついて、死ぬまで決して離れていかない確かな技術が。師匠はわたしに、「負けん気と根性だけはピカイチ」と言ってくれた。
3年ほど経ち、わたしがヘアメイクアーティストとして師匠の元を独立した年には、兄貴はすでに会社をやめて実家に引きこもっていた。兄貴の職場は今流行りの(母の言葉だ)ブラック企業で、上司のパワハラも酷かったのだという。2011年、震災があった年からすでに兄は休みがちになっていたらしい。
兄貴は昔から、とりたてて成績がいいわけでもなく、スポーツができるわけでもない平々凡々な人間のくせに、どういうわけかプライドだけは高かった。少しオタク気質なところがあって、同級生たちが知らない映画を見るのが趣味だった。キューブリックの『時計じかけのオレンジ』と『2001年宇宙の旅』をこよなく愛していた──いや、そういえば、地元でキューブリックなんて言っても誰にも通じなかったのに、東京では違った。わたしはマーベル作品が好きなのだが、「マーベルなんて映画じゃないよ」と断言して得意げにキューブリックの話をし出す男がやたらとたくさんいるのだ。つまり、兄は映画の好みも凡庸だったということだ。しかし、兄の田舎を見下すような態度にわたしも影響を受けたのは確かで、兄が聞く音楽や、雑誌や、映画は、独房で一筋の光を届ける小さな窓のようになって、わたしの東京への憧れを育んだ。
「お兄ちゃん、朝の7時に出ていって、夜中の1時に帰ってくるんだよ」
兄の職場のブラックぶりについて、母は死にかけのような声で一度電話してきたことがあったが、わたしは、正直「だからなんだ」と思った。わたしだって同じような境遇だったし、師匠は感情の起伏が激しい人だったので(ファッション業界の人間というのは、アーティスト気質と言ってしまえば聞こえはいいが、自律神経のおかしいタイプが多い)、不条理な理由で怒鳴られることはしょっちゅうだった。
わたしはただ、兄貴の弱さを軽蔑した。親にお金をもらって東京に出してもらったくせに。弱いままで生きていけるほど世の中は甘くない。弱く生まれついたなら強くならないといけない。それができないなら朽ちていけばいい。誰からも惜しまれず、忘れ去られて死んでいけばいい。冷たい色の国道四号線があの世まで続いていそうな、わたしたちの故郷で。
去年の正月ぶりに帰ってきた実家は、いつもと同じ、仏壇の線香と古新聞の匂いがする。玄関を上がってすぐの場所に打ち捨てられた藤娘のショーケース。隣にはビニール紐で括られた週刊少年ジャンプが積み上がっている──兄貴の習慣は小学生の頃から変わらない──。反対側には、口がべろべろ開いたダンボールが置いてあって、中身は弘前の親戚から送られてきた大量のりんごだ。
マルジェラのTabiブーツを脱いで上がると、母が「なあに、これ」と指差して笑う。履き潰されたアシックスと、ゴム長靴と、ぼろぼろのクロックスに並ぶわたしのマルジェラ。
リビングのマッサージチェアに父が座って、スマホをいじりながらテレビを観ていた。わたしが帰ってきたのを見ると首だけ傾けて「おう」と言う。たぶんFacebookをいじっているのだろう。
父は漁協の会長だったじっちゃの威光を借りてずっと漁協のSNS担当をしていて、三十人も見ていないFacebookのアカウントを毎日更新するのに忙しい。川の清掃や、イワナ、ヤマメの放流活動といった本業の広報だけでなく、たまに自分の健康診断結果や自作のミノーなどのどうでもいい個人情報をアップしており、確実にアカウントを私物化していた。「⁉️」と「♪」の絵文字を多用してやたらとテンションが高く、典型的なネット弁慶だ。しかも一人称はなぜか「小生」。当然、糖尿病で倒れたという今回の出来事も投稿しているのだろう。漁協はよくこの男を野放しにしていられるものだなと思う。
「お父さん昨日退院したばっかだから」
いろんな鍵がついたキーチェーンをじゃらじゃら鳴らして、オープンキッチンのカウンターに起きながら母が言う。「良かったねお父さん、雪わざわざ帰ってきてくれたよ」
リクライニングされたマッサージチェアの上に伸び上がる父はたっぷり肥えている。色素が沈着した黒い肌。わたしは宗谷岬に群れを成すというトドを思い起こす。
「仕事忙しいか」と父は言った。
「まあ、ぼちぼち」
「ものすごい髪だなぁ」
「んだからさぁ」と母がすかさず相槌を打つ。
父はわたしの姿をしばらくみやって、「あんま母さん困らすんでね」と言った。わたしはなんと言ったらいいのかわからない。わかり合おうという努力を続ける気概がわたしにないから、年に一回しか帰省しないのだ。その帰省すらなくなる時はやってくるのだろうか。母も父もいなくなって、わたしにはひきこもりの兄だけが残されるのだろうか。
母が気忙しく「うどん食べる?」と言う。日頃は糖質制限をしているので、あまり気乗りがしなかったが、断るのもどうかと思って、ありがとう、と言う。
リビングと襖で隔てられている畳の部屋に入り、仏壇の前に座った。仏壇の上を見上げると、長押にいろんな写真が飾ってある。じっちゃの遺影。じっちゃよりだいぶ前に亡くなったばっちゃと、そのまた父母の写真も。さらに、じっちゃが生前にもらった「農林水産振興協会長賞」の賞状と、授賞式の時のじっちゃの写真が載った地方紙の切り抜きが入った大仰な額縁、それから──。
おりんを無造作にチンチーンと叩く。音の余韻の中で手を合わせた。じっちゃの遺影の傍に、昔彼の車の鍵にぶら下がっていた熊の子の手のキーホルダーが置かれている。それから、あのちんこの骨も。27歳になった今のわたしが熊の子の手を見て、「こんなにちっちゃかったけ」と思うなんていうイベントは起こらなかった。普通に、今見てもデカいと思った。
「あんたほら、できるまでにヨーグルトとか食べてたら」母が部屋の入り口に立って、わたしに声をかけてくる。
「いらない。ビールある?」
「あったと思うけどねぇ。ちょっと待って、お父さん随分前に買い込んでたけど、倒れて飲めながったやつが確か」
母が冷蔵庫を開ける隣に立つと、その中身の物量に圧倒された──サランラップが被さった焼き鮭、小さいのが四個セットになったヨーグルト、大量のヤクルト、ファンタのグレープとオレンジ、積み上げられた玉うどん、スーパーのお惣菜パック、二枚ほど残ったヤマザキの食パン。全体的にうっすらと漬物臭がして、わたしはうんざりしながら顔を背けた。まるで食べ物の墓場だ。
「ごめん、やっぱりいらない」
「え、そう?」
*
「女がそったにはだらがなくてもいがべや」
わたしが病院に見舞った時、死にかけのじっちゃがそう言った。それが、彼がわたしにかけた最後の言葉になった。故郷の家族は、「こういう有名な雑誌」に出てくる「こういう有名なモデル」にメイクをする仕事をしている、とわたしがどれだけ説明しても、こちらが望む反応をまるで返してくれない。母は「帰って来い」と言わない代わりに、わたしが仕事の話をすると「まだ頑張ってんだなぁ」と言う。
母がうどんをつくっている間、タバコを吸うために外に出る。車が停めてある屋外の車庫には、剪定を放棄されたトネリコやつつじがモサモサと生い茂り、母のN-BOXは巨大なブロッコリーに衝突してめり込んでいるように見えた。
周囲に背の高い建物は皆無で、空はおっこちてきそうなほどに広い。何もない、本当に何もないのだという事実がのしかかってきて、それが妙にわたしを息苦しくさせる。近くの道を車が通ったようで、側溝に被さったコンクリートがゴトンゴトンと音を立てた。
タバコの煙をくゆらせながら手持ち無沙汰にスマホをいじると、メールがいくつか来ている。どれもすぐに反応しなければならないものではなさそうだったが、東京に残してきた仕事に無性に追いすがりたくて、わたしは頭をフル回転させながらあっという間にメールを処理し終えてしまった。
ふとアニメの音声が聞こえてくることに気づく。上を見上げると、二階の南に面した部屋の窓が空いている。レースのカーテンがかかっていて中が見えない。兄貴の部屋だ。なんのアニメだろう、と耳を澄ませていたら、判明する前に母の「できたよお」という声がした。
わたしはタバコをもみ消して、庭のホースリールのそばに置かれていたブリキの灰皿の中に吸い殻をねじ込んだ。
母は鰹節から出汁を取らない。わたしは子どもの頃から味の素の顆粒出汁で育った。うどんのつゆは顆粒出汁とめんつゆの味がする。天かすとかまぼこと刻み葱。リビングルームのテーブルで食べ始めると、母はテーブルの角を挟んだ隣に座ってお茶を飲み、煎餅を齧り始めた。
「あんた何時に帰るっていってたっけ」
「5時12分の新幹線」
「えっ、お夕ご飯食べて帰らないの!」
昼ごはんを食べている目の前でそんな話をする。
「ごめん、明日の仕事朝早いんだよね。広告の撮影」
「へぇーっ」
また「へぇーっ」だ。父が見ているテレビの音がうるさい。ここからは死角になって父の姿は隠れており、無駄に大きな液晶テレビで全国放送が映し出されているのだけが見える。
「今日は選挙戦最後の日曜日で、党首らによる批判合戦が激しくなってきています」
アナウンサーの声。わたしは瀬島うららが、選挙がどうのと言っていたことを思い出した。マイクに向かってがなりたてているようなおじさんの声──「憲法をこれだけ蔑ろにした政権はかつてないんじゃないでしょうか。安保法制、秘密法、共謀罪、どれもこれもが憲法違反の法律です。権力が、憲法を無視して暴走している」──今度はおばさんだ──「一握りの安倍政治を、人々の暮らしを見ない安倍政治、人間をモノとして扱う労働法制の規制緩和を本当に変えていきましょう。変えてまいります、税金の取り方と使い道を変えましょう」。
父がチャンネルを変えた。バラエティ番組で声を張りあげる芸人たち。
うどんが美味しい。今、東京で自分の周囲にいるのが健康に気を遣う人たちばかりなので、影響されてたまに化学調味料を気にするようなそぶりを見せたりするが、わたしの味覚はとっくの昔に味の素に調教されていたのだった。
食べ終わって皿を洗おうとすると、母は「シンクに置いといて」と言う。昔は皿洗いをしろとうるさかったのに、たまに実家に帰るとこうも優しい。
「あ、お土産持ってきたの忘れてた」
わたしは新幹線に乗る前に東京駅の大丸で見繕ってきたお土産を手渡す。いちおう、病人の父の見舞いという体で訪れているので、お菓子などではなく体に良さそうな無添加のスープセットにした。母は「おしゃれだわあ」と顔を綻ばせて喜んでいる。
「それからこれもあげる。いい色だから使いなよ」
瀬島うららと会ったパーティで、彼女が「よかったらこれ使いません?」と渡してきたものだ。母は当然瀬島うららを知っているだろうから、このリップスティックを手に入れた本当の経緯を説明するのはややこしくなるだけだと思ってやめた。ハイブランドのロゴが印字されたパッケージに、母は浮き足だったような、驚いたような「えぇっ」という声を上げたが、わたしが蓋を外して色を見せると「ヤダァ」と恥ずかしそうに口元を押さえた。
「やだ、こんな濃い色普段使わないもの」
確かに、わたしが本当に彼女のために自分で色を選んだとしたらこの赤にはしなかっただろう。母ほどビビッドな赤い口紅から縁遠い人はいない。常日頃からして化粧っ気がなく、ペンシルでくっきりと描いた山なりの眉毛だけが、まるで何かの信仰かのように九十年代から持ち越されていた。
突然、煎餅を片手にちょっとはにかんだ様子の母に対して、鳩尾がきゅうと収縮するほどの愛おしさと憐れみが湧き上がってくるのを感じた。昔の写真で、誰かの結婚式か何かで肩パッドの入ったジャケットを着て、白いファンデーションに濃い色の口紅を塗った母の姿を見たことがあった。あんたのお母さん昔は美人だったのよ、といろんな人が言うのを聞いたことがある。幼いわたしはそんな言葉をなんの疑問も持たずに受け入れたが、それは写真の中の女性と自分の母を全くの別人だと捉えていたからだ。無関心な夫と、いつまで経っても手も金もかかる息子と日常を生き、東京から一向に帰ってこない娘にいつまでも関心を寄せすぎる、宝くじ売り場の女。
わたしは自分のフィリップ・リムのバッグの中からポーチを取り出してジップを開けた。いつも持ち歩いているミニサイズの拭き取り用メイク落としを折り畳んだティッシュに浸し、自分がつけていたクリアピンクのグロスを落とした。
「お手本見してあげるから」
乾いた唇をリップバームでコーティングし、コンシーラーを左手の甲に出して、唇の輪郭をぼかすように叩いていく。
「赤に慣れてない人がいきなり満遍なくリップ塗るとびっくりしちゃうから、まずは輪郭をぼかして、中央からちょっとずつ乗せてくの──ちょっと使うね」
リップスティックを手の甲に押し付けて二、三度往復させる。手の甲のパレットから、右の薬指で色を取り、唇の中央から重ねていった。母は最初おっかなびっくり、といった雰囲気で肩をすくめていたがが、やがてわたしの一挙一動に瞳をくるくるさせ始める。上下の唇を巻き込んで何度か馴染ませ、仕上がりに納得すると、わたしは母に向かって笑いかけた。
「ね、かわいいでしょ」
「へぇ、口紅だけで随分印象変わるもんねぇ」
深く頷くものの、すぐに茶化すような雰囲気になってわたしの目の前で手をひらひらさせる。
「いやでも、あんた、そりゃ、あんたみたいな若い子はどんな色つけたって似合うわよ」
「母さんも似合うって。これ、水っぽくてツヤっとするタイプだから。マットじゃないからそんなにクドくないし」
「そうなのぉ?」
「つけてあげる」
わたしは椅子に座ったまま脚を引きずって母の近くににじり寄った。
「やだよう、もう」
「いいから、ほら」
母をいなしているうちに思いついたことがあって、わたしはメイク落としを手に取った。
「リップ以外もやったげよっか、母さん」
「えええ?」
おかしい半分、戸惑い半分といった母に言うことを聞いてもらうべく、左の指を彼女の顎に添えて少し上を向かせた。
「大丈夫、ちょっとアイメイクするだけ」
「ほんとぉ?」
母は少女のようにころころと笑った。ここだけ突然、まるで高校の教室になったみたいだった。昼休みの窓際の席。椅子の背もたれに肘をついて、こっちを見ているクラスメート。長く綺麗に伸ばしているのにマニキュアには彩られていない生の爪(マニキュアは禁止)。その綺麗な指が突っ込まれてかちゃかちゃと音を立てるわたしたちの化粧ポーチ。
メイク落としでわたしはまず、母の眉毛を落とした。すると、眉尻以外にほとんど痕跡がなくなり、青白い皮膚が現れる。目を閉じて、と囁きかけると素直に言うとおりにした。化粧を施されることを待っている女は、年齢も立場も関係なくみんな同じ顔をするのだと思った。わたしはきっとその顔が好きなのだ。胸に小さな炎を灯し、ほんのちょっと先を生きる未来の自分に思いを馳せているその顔が。
肌全体は綺麗なので、コンシーラーでシミやくすんでいる部分だけ薄く補正する。ルースパウダーをまとわせたブラシで、顔全体に優しく掃きかけた。母の目元と口元が、むず痒そうにぴくぴく動く。チークは、ブロンズに近いローズ系を持ってきていて、よかった、と思う。どんな色の肌にも馴染む。ささっとブラシを往復させると、母の肌が自然な血色を帯びる。
アイメイクをする時、母の瞼や目尻に細やかな皺が寄っているのを見て、老けたのだな、と思った。まるで芍薬の薄い花びらのようだった。「ちょっと上向いて」「目開けて」「下向いて」──逐一発せられるわたしの指示に、母は従順だった。東京でわたしの食い扶持を稼ぎ続けてきた指先は澱みなく動き、「豊田雪の母」を一人の人間にする。この人も孤独に苛まれ、喜びを知り、時に泣き濡れ、夢を見て、誰かを愛し、誰かに愛されてきたのだという当然のことに、わたしは今更気づくのだ。
眉毛は腕の見せ所だった。毛がほとんど生えていない眼窩の際の青白い皮膚に軽くコンシーラーをはたき、極細のアイブロウペンシルで目頭から毛の流れを描いていく。それからパウダーで全体をぼかしていくと、なんとか自然な眉毛になった。
アイラインは細い黒で、無理に跳ね上げずに目尻に沿わせる。ビューラーでまつ毛を上向きにし、そこに細かなファイバーのマスカラをつけると、母は今しがた長い眠りから覚めたかのようにぱちぱちと瞬きをする。わたしは、家族を疎み、距離を置き続けてきたここ数年の東京での暮らしのことを思う。向き合うことができなかった。少しでも気を許して振り返れば、絡め取られてしまうような気がして。
「ねぇ、母さん」彼女の唇の輪郭にコンシーラーを重ねながら、ふと、自分自身に向かって話しかけるようにつぶやいた。
「なに」
「お兄ちゃんのこと、どうすんの」
わたしから兄の話を投げかけるのは、初めてのことだった。母は面食らったようで、一瞬瞼を震わせた。それでも、わたしの歩み寄りが嬉しいのか、複雑な表情を浮かべる。
「わかんねぇなぁ、もう」
「わかんねぇ、って……」
「何が起きてんのかもうさっぱりで。でも、お兄ちゃんだって辛いんだよ、職場でいじめられて、嫌な思いして。ちょっとくれ休憩すたってそんなバチが当たるもんでもないと思っけど」
「ちょっと、って、いつまで」
「もう、わかんねぇのよ」
わかんない、という、子どものように無責任に繰り返す母を見ていて、この人の世界の、あまりにも小さく限られていることを思う。
「お金に困ってないなら、いいだろうけどさ」
「困ってないって言われるとそれもどうなんだか……お父さんが働いてるうちはって思ってっけど、倒れた時はもう一瞬頭真っ白んなって」
母が抱いた恐怖に全く寄り添えなかった自分を、わたしは今、初めて恥じた。わたしは母を心の底から軽蔑していて、それと同時に、軽蔑している自分自身のことが、昔から消えてなくなりたいほどに嫌いだった。
「雪、お兄ちゃんの車ないの、気づかなかった?」
「え?」
「しばらく使わねっていうからもう売っちゃった。車が家にあるとご近所の人たちがね、長男どうした、って言ってくるもんだから、しばらく母ちゃん、公民館まで毎朝お兄ちゃんの車停めに行ったりしてね……」
わたしは母の唇に赤いリップを薬指でトントン乗せながら、斜め上に炸裂する彼女の献身がおかしくて、思わず笑ってしまった。笑うべきではなかったのかもしれない。でも、笑うわたしを見て、母も釣られておかしそうに笑った。わたしが笑ったのを見て、これは面白いことなんだと初めて発見したみたいに。
わたしは母の頬と顎に手のふんわりとひらを当てて、左右から顔の仕上がりを確認した。
「うん、できた」
バッグの中からアルミの折りたたみミラーを取り出し、母の前にかざす。母は鏡の中の自分の姿を認めるや否や、「えぇっ」と声を上げて目を見開き、顎に手をやりながらいろんな角度から検証を始めた。
「すごい、なんにぇこれ、へぇーっ、眉毛すごい、えぇえーっ」
わたしはその様子に少しこそばゆくなりながら、「だからあ」と相槌をうった。
昔は美人だった、と言われていた頃の母の写真よりも、わたしは今の彼女の方が美しいと思った。それにしても、「昔は美人だった」ってなんてひどい言葉なんだろう。美人であることを捨てなければならなかったんだとしたら、それは母のせいではなかったし、そもそも美人かどうかなんて関係なく、人間の美しさというものは誰かが奪えるものでもない。
そんなようなことを、わたしは学んだのだ。たぶん。東京で。
「なんにぇ、これ」
母はまだ鏡を見て興奮している。その目が潤んでいるのを見て、わたしはなんと言ったらいいのかわからない。喜びなのか、悲しみなのか、怒りなのか、判然としない感情が膨れ上がり、熱くて大きな塊になって喉を塞ぐ。苦しいということだけがわかる。
「かわいいじゃん」
首を傾けて母の顔を覗き込むと、母は娘の視線が恥ずかしいようで、少女のように肩をすくめながらも幸福そうだった。
その時、階段が軋む音がして、わたしと母の体に同時に緊張が走った。
「お兄ちゃんだ」その母の声で、たった今、さっきまでわたしと彼女の間に横たわっていた魔法のような心地よさに亀裂が入る。
一階の部屋の入り口に姿を現した兄は、わたしと母の方を見ることもなく台所に吸い込まれていった。冷蔵庫が開き、物色する音。母は立ち上がり、兄から見えないように不自然に顔を俯かせながら、「お兄ちゃん、雪来てくれたよ」と声をかける。兄は何も言わない。当然だ──だからなんだ、という話だ。兄と妹が呼吸をするようにあたりまえに共有しているその感情の機微を、この人はいつになっても理解してくれない。こっちからすれば、なんで理解できないのかが理解できない。
兄の風貌をぼんやりと見てわたしは、また太ったかな、と思った。コシの強そうな黒髪は元気に跳ねていて、皮膚にはぽつり、ぽつりと無精髭が散らばっている。着ている服はなんの変哲もない黒のスウェットで、とくべつ不潔な感じはしない。彼が今の格好で家の近所を歩いていたとしても、引きこもっているなんてご近所さんは夢にも思わないだろう。
兄が目当てのものを手にし──パックに入ったヨーグルトだった──台所から出てきた時、彼の視線が一瞬、母の顔をとらえたのがわかった。ギョッとしたような表情になって、それからわたしの姿を見てさらにギョッとしたようだった(髪の色に驚いたのだろうか)。邂逅はたった一分にも満たず、気がつけば、兄は道端で人間に一瞬目撃された無害な野生動物のようにすでにわたしと母の目の前から消えていた。階段の軋む音。父が変わらずリビングで見ているバラエティ番組の恐ろしく空虚な笑い声の効果音。
母は力が抜けたように椅子に座り、それから虚な目でお茶を一口飲んだ。わたしは座ったまま何も言えなかった。
兄は怯えていた。傷ついた瞳。驚くべき孤独。
*
震災があった年、わたしは20歳だった。撮影の途中で、恵比寿のスタジオにいた。仕事中で良かった。一人きりだったら、わたしは多分、どうしたらいいのかわからなかった。
撮影は急遽取りやめになって、みんなが情報収集のためにてんやわんやだった。スタジオの管理人が慌てて事務所を解放してくれて、テレビを見ればとんでもないことが起きていることだけがわかり、不安ばかりが募る。わたしの実家が東北だということを知っていた師匠が、呆然とテレビを見るわたしの背中をさすってくれた。口は悪ければ手も出るし、とにかく厳しい人だったけど、たぶん、あの時の手のひらから伝わってくる熱がマイナスの全部を帳消しにした。当時わたしが持っていたのはまだガラケーで、電話も繋がらず、メールも送信失敗になり、実家の誰とも連絡が取れなかった。うちは内陸だ。まさかあんなところまで津波は届くまい──。
「あんたこれ、中野まで帰れないわね」と、師匠が言った。電車も動いておらず、タクシーも捕まらず(そもそも捕まえられたとて、お金がなかった)、どうしようもなかったので、祐天寺に住んでいた師匠が家に泊めてくれた。二人で三十分ほどかけて西郷山通りを歩いた。
今思い出してもほんとうにバカなことをしたと思うが、心配で気が狂いそうになってしまったわたしは、3月11日の夜、兄のTwitterの裏垢にDMを送ってしまった。おそらく誰からもバレていないと思っていただろうに、妹からメッセージを受けとった兄はどんな気持ちだっただろう。あの時のことについて、本人と改めて話したことはない。
「兄貴も母さんも父さんもじっちゃも無事ですか。わたしは東京で、師匠の家にいて大丈夫です」
意外にも早く、兄から返信が来た。
「みんな無事です。いろんなものが倒れてめちゃくちゃですが、家も無事です」
エロゲーや、キューブリックや、靖国参拝の是非や、鳥インフルエンザについて熱く語っていた、アニメの女の子のアイコンの主はほんとうに兄だったのだということがわかってしまって妙な気持ちになったが、それよりも安堵の方が強かった。しかし、その深夜のうちに母のケータイとのメール通信が復活したので、わたしは、早まらなければ良かったと後悔した。兄の裏垢は、3月12日には消滅していた。
結局、頻繁なやり取りは欠かさなかったが、わたしは次の年になるまで実家には帰らなかった。母は「無理しなくていい」と言った。言外に、原発のことを心配しているのだろうとわかった。
起こってしまった出来事に対して拍子抜けするくらい、わたしの忙しい毎日はそれまでと変わらずに続いていた(「ACジャパン」の「ポポポポーン」のCMをうんざりするほど見させられる以外は)。
ある日、仕事帰りに夜の山手線に乗っていたら、わたしが立つ目の前の座席に座っていた男の二人連れの会話が耳に入った。三十半ばくらいの、今風の細見のスーツに身をつつんだ会社員らしき風貌だった。
「けっきょくだれと行ったの?」
「おれと、渡部と貝原と、貝原の嫁」
「貝原の嫁?」
「いや、とにかく謎の三人なんだけど、人数まとまってないと入れなかったから」
「どんな感じだったの、現地の雰囲気というか」
「いやもう、めちゃくちゃだよ。一番何がすごいって、瓦礫とヘドロで」
漏れ聞こえてくるそれが、被災地のボランティアの様子だということがわかった。なぜか、体がギッ、と硬くなった。
「まあでもとにかく、行って良かったわ。なんか、人生変わったっつーか──」
聞いていられなくて、わたしは衝動的に次の駅で電車を降り、車両を変えた。
お前の人生変えるために被災地は存在してるわけじゃねぇんだよ。
自分こそ何も知らないくせに、家族はみんな無事で、家にも損害が出なかったのに、わたしはなぜあそこまで腹が立ったのだろうか。
*
じつは、わたしは8歳の時、故郷で瀬島うららに会っている。
当時、瀬島うららは連続テレビ小説の女子中学生役で彗星の如くお茶の間に登場した、大ブレイク中の女優だった。20年前だから、彼女は10代の半ばで、高校生だったはずだ。そんな時の人が、「人間よりも熊のほうが多い」と地元民が自虐するド田舎にやってきたのだ。
ことの経緯はこうだった。当時、瀬島うららがCMに出演していた大手飲料メーカーの天然水ブランドが、うちの近所を採水地としており、そのタイアップ記事の取材が行われることになった。子どもだったから詳しいことはよくわからなかったが、その時漁協のトップだったじっちゃを初め、漁協の重役たちが、瀬島うららにヤマメの稚魚の放流の様子を案内するという大役を仰せつかったらしいのである。
あまり感情を表に出さないじっちゃに変わって、大騒ぎしていたのが父だった。飲料メーカーから連絡が来るや否や、漁協の関係者に片っ端から電話をかけ、「詳しくは言えないが東京から女優さんが来る」「〇〇川の〇〇のあたりには当日誰も来ないように」「定例の清掃活動は延期」「関係者以外は口外しないように」と、まるで政府要人付きのSPのような暗躍ぶりを見せた。出演するのはあくまでもじっちゃなのだが、漁協の関係者として自分もちゃっかり現場に立ち入る段取りを組んでいたのである。
夏の入り口の、あの日も曇り空だった。あの時、瀬島うららがいた現場に、わたしと兄もついていくことができたのは父の計らいだったのだろうか。わたしたちきょうだいは漁協の集まりやイベントごとに連れ回されることには慣れっこになっていたから、その時も「いつものやつ」くらいの気持ちでいたのではなかったか。
土地改良区の植樹をしているエリアで、じっちゃと父、見知った漁協の関係者のおじさんたちが「東京から来た人たち」の相手をしているのを遠目に見ながら、わたしと兄はじっちゃの黒いワゴンの周辺をうろうろしながら遊んでいた。大人たちの邪魔をしてはいけない、と仰せつかっていたからだ。
瀬島うららの名前は、小学2年生のわたしでも知っていた。6年生の兄も当然そのはずで、車の座席で手持ち無沙汰にゲームボーイ(懐かしの)を弄りながらも、ちらちらと大人たちの方を気にしていた。瀬島うららがやってくる一時間ほど前から「東京から来た人たち」はじっちゃと土地改良区で何やら話し合っていて、今思えばあの人たちは、飲料メーカーの宣伝部門、広告代理店、制作会社の人たちといった、現在わたしが日常的によく仕事で会う人たちだったはずだ。子ども心に、東京の人たちはやっぱり違う、と思った記憶がある。それはファッションだったのか、メイクだったのか、それとも、目には見えない雰囲気だったのか。
あの日を迎えるまでの一ヶ月ほど、まるで当事者であるかのように大騒ぎしていた父は、「東京から来た人たち」と直接会話をすることもなく、格好をつけてタバコを吸いながら一団を遠巻きに眺めていた。そして、時おり熊よけの火花を突然打ち鳴らして「東京から来た人たち」を不用意に驚かせ、注目を集めたことに満足するとまたタバコを吸い始めた。もたれかかってくるような広い広い空に響き渡る乾いた破裂音。
やがて瀬島うららが、これまたたくさんの「東京から来た人たち」と共にやってきて、ようやくじっちゃの出番になった。あの時も、彼女を見て、小さい人だなと思った記憶がある。遠かったので声は聞こえなかったが、じっちゃが植樹を記念した木碑を指差して何かを説明した時、瀬島うららが「えっ」と驚いたような声を上げたのは聞こえた。おおかた、じっちゃが「あの木が削れているのは熊のせい」とでも言ったのだろう。じっちゃは瀬島うららに、熊の子の手とちんこの骨は見せたのだろうか。
それから大人数でぞろぞろ川べりに場所を移し、ヤマメの稚魚を放流した。じっちゃがバケツを傾け、黒い稚魚がビチビチと透き通った水に解き放たれていく様子を瀬島うららは熱心に見つめ、いろいろなことをじっちゃに質問した。その様子をカメラマンがかけずりまわり、あらゆる角度からシャッターを切った。
父は長靴を履いて川の浅瀬に入り、ヤマメを放流したその下流の方でこっそりガラケーで瀬島うららの写真を取ろうとして制作会社の人間に注意されていた。気まずさを押し隠すようなニヤニヤ笑いを浮かべながら、撮っていないよ、とでも言いたげなジェスチャーをする父を、わたしは邪魔にならないところで石を積み上げながら見ていた。あんなにもみじめな人間の姿を、わたしは27になった今でも見たことがない。
記念撮影しましょう、と、多分飲料メーカーの人が言い出して、瀬島うららを中心に、飲料メーカーと、漁協のおじさんたちが一緒に写真に映ることになった。
「キッズたちもおいでよ」
ものすごく綺麗な女の人が、笑いながらわたしと兄に話しかけてきた。この撮影の間中、ずっと周辺をうろちょろしていたから、じっちゃの孫かどうかはわからなくても漁協の誰かの家の子どもなのだということは察せられたのだろう。写真の中に子どもがいたほうが見栄えがいいと判断されたのかもしれない。わたしは、差し伸べられた彼女の手を取った。ひんやりしていて、気持ちが良かった。きっと、代理店か制作会社の人だったと思う。それから、反対側にやや尻込みする兄の手を取って、カメラの前に並ぶ人たちに向かって歩いて行った。中心にいた瀬島うららが確かにわたしを見て、「こんにちは」と笑って自分の隣にくるように腕を広げてきた。瀬島うららだ、とわたしは思った。彼女の体の周りには金色のオーロラのようなものがきらめていて、傍に立つと、今まで嗅いだことのないような、とんでもなくいい匂いがした。
「えっと、あの人は……」
誰かが、父の姿を差しておずおずと言った。父は川縁からやや遠くに停められた自分の車のそばでタバコをふかしていて、写真に入る気はないという静かな意思表示をしていた。誰かが馬鹿にするように言った。「なんでぃやあれぁよぉ、いいふりこいでよ」。わたしと繋いだままの兄の手に、ぎゅう、と力が込められた。わたしはその言葉が、じっちゃに聞こえたかどうかが気になったが、振り返ることはできなかった。恥ずかしくて、恥ずかしくて、動いたら涙がこぼれてしまいそうで、微動だにできなかった。漁協の人間が示し合わせたように何も言わないので、やたらと明るいカメラマンが何かを察して「撮りますよ!」と目の前の被写体たちに向かって──おそらく父にも聞こえるように──声を張り上げた。
「何枚か撮っていきまーす!」
それから数回カシャッ、という音が響き渡る中で、父をどうするかという問題意識はにわかに空気の中に霧散していった。
「みなさん、顔がちょっと硬いかなあ」
カメラマンのおどけた声に、笑い声が上がる。
「子どもたちも笑ってみようか! ね、にっこにこでいきましょう!」
瀬島うららのいい匂い。兄は手にべっとりとかいていた汗。わたしと兄は、何度もカメラマンに「にこ〜っ!」と笑顔を促された。
そんな思い出。
*
じっちゃの遺影。じっちゃよりだいぶ前に亡くなったばっちゃと、そのまた父母の写真も。さらに、じっちゃが生前にもらった「農林水産振興協会長賞」の賞状と、授賞式の時のじっちゃの写真が載った地方紙の切り抜きが入った大仰な額縁。
その隣に並ぶ、瀬島うららを囲んで撮った、20年前のあの日の集合写真。
わたしは仏壇の前に座って写真を見上げる。
8歳のわたしと、12歳の兄。わたしはぴくりとも笑っていなかった。ぱっつんと切った前髪の下から、ほとんど睨み据えると言っても過言ではないような、子どもらしからぬ壮絶な表情をしていた。思えば、昔から「可愛げがない」とことあるごとに言われ、特に何をしているわけでもないのに学校の先生から目をつけられることが多かった。
「かわいぐねぇやつ」
思わず呟いて、自分で自分がおかしくなった。誰に教わったのだか、八歳のわたしはすでに、大人を軽蔑するということを知っていた。
わたしの隣に立つ12歳の兄は、まるで泣き出す寸前のような顔をしている。これが彼の笑顔だったのかもしれない。少なくとも、隣にいる妹のように睨みをきかせているというわけではなく、見ようによっては笑顔に見えなくもない。手を繋いで立つ、小さな兄と妹。
10代の瀬島うららは、美しかった。ちょうど腰の位置になるわたしの肩に手を添えて微笑んでいた。彼女の記憶からはもう消し去られた、とるに足らない出来事だろう。仕事で初めて瀬島うららのメイクを担当することが決まったとき、「実はわたし……」と自己紹介する気もなかった。思い出して欲しいとも思わない。あの時の父を思い出されたらたまらない。
今、東京で生計を立てている自分は、彼女が生きる世界の一員になれているのだろうか──いや、そんなふうには思えなかった。東京を夢見ていた頃、わたしはよく「iモード」で瀬島うららのことを検索していた。彼女は東京の世田谷の生まれで、父は大手銀行の常務取締役だった。小学校から高校まで、セレブの子ども御用達と言われる世田谷の有名な私立学園で育つ。3歳から乗馬を始め、連続テレビ小説で有名になり始めた頃、乗馬の国内大会で入賞したほどの実力者だった。当時、彼女が生粋のお嬢様であることはテレビのワイドショーなどでもよく話題になっていた。
わたしは、瀬島うららがリップスティックをくれた時に言っていた言葉を思い出していた。オーガニックとか、コングロマリットとか、選挙とか、なんとかかんとか。こっちがやっと自転車の乗り方を覚えたと思ったら、もう向こうはロケットに乗って成層圏を突破している。最初から、追いつけるわけがあるはずもない。
リビングからはまだ父が見ているテレビの音がする。兄の心の痛みが天からの声のようになって降ってきて、耳鳴りがするほどだった。この土地で育った子どもであるということ。人間のみじめさと、情けなさを知っていること。恥ずかしさ。逃げ出して、叫び出したくなるような恥ずかしさ。
ここでは、途方もない大自然だけが、人生にうちのめされた子どもにはなんの答えもくれないくせにでかい顔をして広がっている。自分が誰からも必要とされないなんて、そんなの絶対に許せないから、わたしは自分の周りのありとあらゆる人間を睨み据えながらついに東京の人間になってしまった。兄はたぶん、東京の人間には心を開かない。わたしは、自分がどこの誰になれば兄を救えるのか、それがさっぱりわからない。でも、この家にいたくない、ということだけがわかる。はっきりとわかる。
*
母が駅まで送る、というので、お言葉に甘えることにする。帰りがけに、「あんたこれ持って帰りなさい」とあげたはずの赤いリップスティックを返そうとするので、いいから、と押し戻す。
「似合ってるよ、その色、本当に」
「だってあんた、持ってても、いつつけろっていうのよ」
「毎日つけるんだよ、似合ってるんだから。毎日赤いリップして何が悪いの」
母は泣きそうな顔になる。その泣きそうな顔は、写真の中の12歳の兄に驚くほど似ている。
「お兄ちゃんねえ」
玄関でマルジェラを履くわたしの背中に、母がぼんやりと語りかけてきた。
「誰よりも早起きでね、収集日別に、毎日家中のゴミまとめて投げてくれるしね、ゴミ箱にもちゃあんと新しいふくろも被せてくれるんだよねぇ」
黙々と作業する兄の真面目な横顔は容易に想像できて、わたしは「うん」と言う。
母がN-BOXを道路に出している間、果てしない夜の帳を見上げる。五時を過ぎたばかりの10月の空で、星に詳しくないわたしが視認できるのは宵の明星だけだ。
「空を見るときはまず『ひとつ星』を探すんだ。どごへいっても、どんな季節でも北の空で光ってる。北極星があれば迷うごだね。むかすはあの星を見て、みーんな海を航海すたんだ」
じっちゃは空を指さしてそう語っていたけれど、こんなところで道標が見えたところでどうしようもないから、探すつもりもない。でも、高校生のわたしは灰色の国道四号線はあの世に繋がっていそう、なんて思っていたけど、あの世じゃなくて東京に繋がってるんだってことは、今知っている。
新幹線の駅内の売店でわたしはビールを買い込み、新幹線の中で飲み始めた。新幹線の車窓から見えるのは真っ暗闇なので、必然、車内の自分の顔が鏡のように映っている。怯えていた兄と、今のわたしはそんなに変わらないんじゃないかと思う。生活が安定するようになっても、わたしはどこかで、やっぱり毎日怯えている。
東京では星なんか見えない。北極星ですらどこにあるのかわからない。突き刺すような電飾が雲に反射して、空はいつも靄がかかったみたいに群青色に光っている。自分がどこにいて、何をなすべきで、どこへ向かっている人間なのか、東京では分かったフリをしていないと生きていけないけど、よくよく考えたら、たぶん本当は迷い続けているのだ。
東京駅が近づき、わたしは窓の外に広がるビル群の電飾をぶちまけたような光の氾濫に心の底から安堵する。地上の星たち。孤独に生きている人間たちそのもののような、いくつものきらめき。今はもう東京がわたしにとっての故郷みたいなもので、それがつまり、わたしは故郷を永遠に失ったのだ、ということを意味していても、心の底から安堵してしまうのはなぜだろう。
降車して、そのままJRを乗り継いで家に帰ればいいのに、わたしは意味もなく八重洲口から外に出た。高いビルを見上げる。酔ってほてった頬に、つんと尖った秋の空気が心地いい。わけもなく泣きたい。今、なんとか生きている自分が愛おしくて。選挙カーがマイクで割れた演説を振り撒きながら駆け抜けていくのが聞こえる。「このまま安倍政権に国を任せて良いのでしょうか。国民の皆さんの決断が試される時です、東京駅をご利用の皆さん、こんばんは、お騒がせしております──」。気を抜くとすぐに押し流されそうになる日々の中で、信じられるのは誰かが掲げる道標なんかじゃない。自分だけだ。自分だけ。
ふと、5歳の時に出会ったあの小熊は、今何歳くらいになるんだろうかと考える。本州の熊は40歳くらいまで生きるとどこかで聞いたことがある。
わたししか知らない、秘密の相棒。あの森のどこかで、彼女(勝手にメスだと思っている)がまだ生きていてくれたら、どんなにか素敵だろうと考える。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
