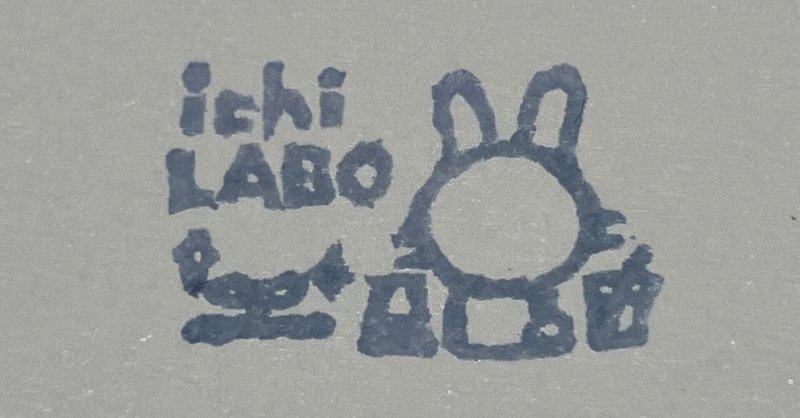
【勉強】『立秋』
今年の目標、『二十四節気』について一年を通して学ぶ15回目、『立秋(りっしゅう)』。
●言葉の意味
今日、2023年8月8日は、二十四節気の『立秋(りっしゅう)』。
早速、『立秋』について調べてみます。
八月に入って早8日目。
暦の上では秋らしいですよ!
いやぁついに『秋』という字が入りましたね。
ここ数日は猛暑&ゲリラ豪雨&台風のニュースばかりで、私の中で『穏やかな気候』というイメージのある秋とはだいぶかけ離れた様子ですが、もうすぐ秋めいてくるということでしょうか。
蝉の大合唱が聞こえ、太陽の照りつけるthe夏の散歩道…とももうそろそろお別れなのでしょうか。
体調を崩さない程度ではありますが、今のうちにこのジリジリと焼かれるような感覚すらする『夏』らしい夏をしっかりと肌で味わっておくのも悪くないなと思った今日この頃です。
この頃よく空を見上げるんです。
暑いし眩しいのだけれど、清々しいほどに晴れ渡った空。その一部に、夏らしい密度の濃そうな少し縦にのびたモコモコとした大きな雲の塊(積雲というらしいです)が見えると「あぁ夏だなぁ」と感じるのです。
春の時期に見られる青い空も気持ちがいいのですが、それとはまた違った気持ちよさがあります。
日頃足元やスマホにばかり落としがちな目線を、たまには晴れ渡った青空に向けてみていただけたらと思います。
空を見上げると日頃の悩みが吹き飛ぶなどという言い回しもありますが、「確かになぁ〜」と納得してしまうこと請け合いです。
(沖縄県や九州地方の皆様は只今台風の影響で難しいと思いますが…どうか皆様のお住まいの地域に被害が少ないことを心から願っております。)
ここまで書いていて私っていつ夏らしい雲なんて知ったんだろう?と疑問が…。
私は確かに理科が好きでした。しかし成績は…笑
これは習ったというより、今までの体験・経験なのだと思いました。
私は昔から空を眺めるのが好きでした。
雲の名前までは知らないけれど、雲の形から過去の記憶が引っ張り出されてきて、暑い日だったという記憶も一緒に呼び起こされた。
だから、積雲を見て「夏だなぁ」と感じたのだと思う。
私は感覚で物事を記憶している人間らしいことと、空と雲が好きだということが私的大発見でした笑。
旬のものについても記載があった。
花:
ひまわり(英語「Sunflower」)
どこの地域でも太陽の花として親しまれている。
つゆくさ
「着き草」とも呼ぶ。蛍を飼うときに、籠につゆくさを入れることから「蛍草」とも。
果物:
桃
七月から九月が旬。
八月八日から十日は、八九十(はくとう)の語呂合わせから、白桃の日。
野菜:玉蜀黍(とうもろこし)
ひげが茶色く、ふさふさしているものは栄養価が高く美味しいとされている。
行事:エイサー
お盆の行事として沖縄県で行われる。
本来は青年男女が無行息災などを願い、エイサーを踊りながら、集落内を練り歩いていたが、戦後は各地のエイサーが集まり大会が行われるようになった。
(同じく『暦生活』より)
ひまわり、トウモロコシはthe夏!というイメージ。
とうもろこしは我が子達が大好きなのでしょっちゅう夕飯に登場するし、ホール缶は常々常備している食材の一つだ。
ちなみに葉やひげがついたままの状態でもよく購入するのだが、その食べ方には若干のこだわりがあって、時間はかかるのだけれど綺麗に食べることには自信がある(披露することのない特技笑)
桃は好きだけれどもっとお手頃なバナナやキウイに手が伸びがち…。一年に一度は生の桃を食べたいなと思う。旬のうちに買おうっと。
露草はあの手が切れそうなシュッ!とした単子用類の葉だよな…?という位の認識しかない。(出た!私らしい変な記憶の仕方笑)
確かに蛍とセットなイメージだ。
エイサーは言葉としては聞いたことがあるけれど意味などは知らなかった。
沖縄らしい赤っぽい色使いの服を着た踊りというイメージ。
確かに青年と言われる若い人のイメージがある!
各地のお神輿やお祭りに参加する方のイメージはお年を召した方も多いイメージだが、確かにエイサーにはそのイメージはないかも!知らなかったぁ!新たな発見!
●発想
『立秋』というワードや、その意味・漢字、この時期の旬のものなどから連想するイメージや出来事を思い出したり想像したりしてみる。
まだ暑い
ひまわり
露草
蛍
トウモロコシ
桃
エイサー
夏の終わり
●創作
先程した空の話から…
頭でハッキリと理解しているわけではないが、過去の経験から体が覚えている記憶というものもある。
それは頭での思考をすっ飛ばし、脊髄反射を利用して心にダイレクトに感情をつれてくる。
その場合の感情は、思考を経たそれよりも色濃く強い。
そこにこそ他の人とは違うあなたの色や特徴が隠れているに違いない。
●余談…
「暦の上は…」というセリフを「意味がない」という人が私の知り合いにいるのです。
人それぞれの考え方や感覚がありますので、それらを否定するつもりは全くありませんが、私はそれらを学ぶことが楽しいと感じるので、その感覚を共有できず更に「意味がない」という悲しい一言で突き放されてしまうことをとても残念に思いました。
ここで改めて二十四節気を学ぶことについて考えたいのですが、確かに、『暦の上では〇〇』という内容と、肌で感じる季節感には大きな差があると感じることもあります。
しかし、二十四節気を学んで、過去の風習や習慣、時期的な旬のものを知ることで、
自分との感覚や思い出から何か感じることがあったり、「その差はなぜ生まれたのか?」という原因をあぁでもないこうでもないと勝手に思いを巡らせることが私は楽しいと思うし、自分を含めた人間もしくは自然など自分を取りまく環境を見直し改めて考えることにも繋がると思うのです。
何だかもっともらしく語りましたが笑、
感覚を共有できることの有り難みや、素晴らしさ、尊さを思い知らされた一件でしたので、書き残しておきたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
