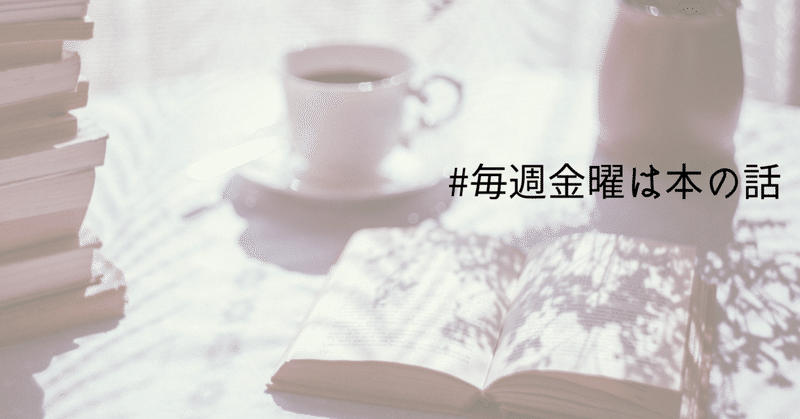
【金曜:本の話③】感想~切りとれ、あの祈る手を(1)
こんにちは、アスカです。
熱くなったり涼しくなったり忙しいですね。
このまま梅雨になるのでしょうか。
さて今日こそ、書く書く詐欺していた本の感想を書き始めます。
ただし一回では終わりません。
今月中に終わらせるつもりでしたがおそらく無理でしょう。
そのくらいどうしたらいいかわからん本です。
筆者の佐々木中氏については説明を以下に引用します。
1973年青森県生。哲学者・理論宗教学者・作家。東京大学文学部卒業、同博士課程修了、博士(文学)。主な著書に『定本 夜戦と永遠』(上・下)『切りとれ、あの祈る手を』『九夏前夜』『踊れわれわれの夜を、そして世界に朝を迎えよ』他多数。
なお、感想部分はちょっと硬い調子で書こうと思います。
よろしくお願いいたします。
<前段>
私が本書に出会ったのは、もう13年ほど前になる。ふらりと立ち寄った書店で、偶然目に止まったのだ。
筆者のことはまったく知らず(なお現在も、知っているというほどではない)、装丁と、帯にある「取りて読め。筆を執れ。そして革命は起こった。」という言葉に惹かれて手に取った。私がハードカバーの本を「ジャケ買い」するのは非常に珍しい。そもそもハードカバーは持ち歩くのに難があるからよほどのことがない限り手にしないのである。
つまり、本書は「よほどのこと」であり、手に取った時の私も「よほどのことがある」という予感を抱えていたような気がする。
そして読み始めてみれば止まらない。線を引いて読んだ。いまでこそ「言語化」という言葉が市民権を得ているが、13年前では少なくともメジャーなものではなかった。ただ、「自分が漠然と抱いていた概念が、そこにすっきりと言葉として綴られ連なっていた」、これをいまは「言語化」と呼ぶだろう。
同時に、頭の裏側に貼り付いていて見えていなかった何かに気付かされた、そんな感覚を得た。
本書のサブタイトルは「<本>と<革命>をめぐる五つの夜話」、筆者の口上を本にしたものである。
筆者の一貫した主張は「革命は文学によって生まれる」。世界史におけるいくつかの革命とその背景にあった文学活動を挙げ、革命は読むことから始まると言う。
私は読書感想文というのが大変不得意だが、とりわけ「読むこと」の重要性を訴えるこの本は「感想」には不向きであるように思う。
本についてにしろ、そうでないにしろ、何かを書くことについて、恐怖と隣り合わせの細心の注意を払うようになる。部分を抜き出すようにして感想を書くことは、筆者の最も嫌う部類の反応なのではないかと思ってしまう。確信を持てないのは、私個人の読解力と理解力のせいか、それとも筆者の言う通り「本なんて読めるわけがない」からなのか。
ただ、答えが出てから感想を書こうと思えばその時は一生訪れない、という確信だけはある。
これも筆者の言葉を借りれば、「読んでしまったから」書かざるを得ないのだ。いつ書くのかと考えたり、許可を待っている意味はない。
読んだので、書く。それならば本書の趣旨に反すまいと、自分に言い聞かせる。
<「情報それ自体が堕落なのだ」>
第一夜「文学の勝利」では、「情報」について多く言及される。
もちろんこの話題がすべてを占めるわけではなく、あくまで、読んだ私の意識に最も強く触れてきたのがここだったというだけである。
筆者は、自身が「情報を遮断した」生き方を選択していると言い、また以下のように述べる。
(丸々引用してしまうのは、文章の繋がりを省いて伝わり方が変わってしまうことを、私が恐れたためである。)
ジル・ドゥルーズの力強い言葉がありますね。「堕落した情報があるのではなく、情報それ自体が堕落なのだ」と。ハイデガーも、「情報」とは「命令」という意味だと言っている。そうです。みんな、命令を聞き逃していないかという恐怖に突き動かされているのです。情報を集めるということは、命令を集めるということです。いつもいつも気を張り詰めて、命令に耳を澄ましているということです。具体的な誰かの手下に、あるいはメディアの匿名性の下に隠れた誰でもない誰かの手下に嬉々として成り下がることです。素晴らしいですね。命令に従ってさえいれば、自分が正しいと思い込める訳ですから。自分が間違っていないと思い込める訳ですから。
繰り返しになるが、本書が発行されてから13年が経つ。その間に「誰もが情報の発信者になれる」環境はすっかり定着した。昨今はSNSの普及で、情報の発信者はより細分化されているように感じる。「情報=命令」とするのなら、日々すさまじい数の命令が発され、ぶつかりあっていることになる。これまでになかったような軋轢やら対立が生じるのは、無理もない話なのだろう。
おびただしい数の人間が、かわるがわる情報を発信する。ありとあらゆる時間が情報にうめつくされる。命令に従っていれば自分は正しいと思うことができる、はずだが、そもそもどの命令が正しいのかの判断が困難になっている時代である。
そんな時代になるかなり前(いまから30年ほど前?)に、筆者は「情報」を拒絶することを選択したという。
「誰の「手下」にもなってはいけないし、「命令」なら誰の物だって聞いてはならない(P13 L1~2)」として生きることにした。それは特権的なことではないのだと断った上で、「そのかわりに「この拒絶は下にひきずりおろしつづける、その者を、一生涯。(P13 L7)」とする。
情報は命令だと解釈できるものの、そもそも情報がなければ判断の基準自体を失うことになるのだ。外から見ると何もしていないに等しく、自分でも自分が正しいのかわからなくなる。
それでも筆者が拒絶を選んだのは、ひとつに、情報を求めて日々を暮らす人の姿を「燥(はしゃ)ぎながら深く何か不安に濡れているように」感じたからであったという。
<燥ぎながら深く何か不安に濡れているように見えた。>
”燥ぎながら深く何か不安に濡れているように見えた。”(P16 L1)
初見時、私は線を引きながら読んだ。今回読み直してみると、おおよそ同じところに惹かれたが、ここは線を引いていなかった箇所である。
この一節は、「専門家」と「批評家」について語られている部分に登場する。大学の一般教養カリキュラムを例として、知に携わるものを「すべてについてすべてを知っているという幻想に縋る=批評家」「ひとつについてすべてを知っているという幻想に縋る=専門家」と分類し、しかしいずれも等しく情報の奴隷となっており、それが知の「縮小再生産」に繋がっているというのである。
その「縮小再生産」の過程に、人々はしがみついている。さまざまなクローズド・サークルの中で、情報を得て自分をアップデートすると感じることで成長したと思い、達成感(あるいは万能感)を得ている。しかしそれは、筆者には「燥ぎながら深く何か不安に濡れているように見えた」。
13年ぶりにこの文章を目にした私には、とある事例が思い当たっていた。オンラインサロンである。
私もオンラインサロンに入ってみたことがある。何せ怠け癖があり己に甘いので、同じ目的を持つ人たちとつながりを持てば、それが矯正されるのではないかと思ったのだ。
だが、実際に入ってみると異様に空々しくて、ゾッとしてすぐに辞めてしまった。その時の感覚がまさに、「燥ぎながら深く何か不安に濡れているように見えた」という言葉で表わされたのだ。
参加者は夢を語る。それを称えあい、共に頑張ろうと励ましあう。それ自体は素晴らしい。仲間と何かを目指すことが否定されるいわれはないのだ。ただ、私には、彼らが病人の顔色でそう言っているように感じられた。病んでいるように見えた。表面では明るくまるで希望しか見えないかのように振舞っている、しかしその根源には深い不安がある。不安に濡れて顔はじっとりと青ざめている。晴天下で幽鬼に囲まれているような心地で居たたまれず、私は逃げた。
場所が悪かったのかと、その後もいくつか試したのだ。しかしどこでも同じだった。縮小再生産、不安だけが育っているように見えた。これならば一人の方がましではないかと思った。
筆者は「それが問題ではない」と言い添えるが、私には「知の序列」という言葉が強く響く。
「翻訳が悪い」とか「もっとわかりやすく書け」とか、初級があって中級があって上級があるというような、知の序列の問題として考える。そうしたある種の劣等感や怒りに漬け込んで益体もない入門書やビジネス書などを売りさばいて、読者を搾取する輩が後を絶たないわけです。
私は世の中にあふれる検定の「級」があまり好きではない。特に「準●級」と出されると一歩引いてしまう。公式テキストやらが全ページカラーだったりやたらとやわらかい雰囲気がすると、それだけでその検定そのものに対して嫌悪感まで抱いてしまうような、ひねくれた人間である。
そんな私は、筆者のこの言葉にはまったく同感だった。オンラインサロンを見ていても同じことを感じたのだ。
こんな実例がある。
私は双極性障害という“病気”のため半年ほど通院した。そこで、公的制度を利用しながら治療を受けた。治療内容を詳しく書くのは省くが、「知識習得」が主眼であったため、座学を受けることがほとんどであった。
そんな治療期間が終わった少し後に、ある知人と話す機会があった。その人はとあるセミナーに参加しているという。詳しく聞いてみると、まさしく私が病院で聞いたような内容を、十倍以上のお金を払って「学んで」いた。恐ろしい話だと思った。
自分の力だけでは得られない情報というのは確かにある。それを外部に求めるのも間違ったことではない。しかし、その情報=命令に、基準のない対価が付けられているのだ。
よりよい自分になるために、そうして良い人生を、自分を認められるような人生を送るためにこれを知っていなければならない、という気持ちに漬け込んだ「搾取」だと思った。
果たして、そこで学びとることは何につながるのだろう。一時的に自分が新しいものになったような気持ちになるのかもしれない。しかしそこから「次はこれ」「こういうものもある」と導かれていくのは、さながら運命の出会いであるかのように錯覚しながら搾取され続けているだけなのではないか、と思ってしまう。いつまでも終わらないエスカレーターに乗っていて、終わりが見えない。階ごとに降りるチャンスはあっても、「降りるチャンス」について考えを巡らせることなくそのまま次の階へ足を向けてしまう。
情報を得るだけの読みを読書と呼ぶのに抵抗があるのと同じように、この「知の序列」に乗っていることは成長と呼んでいいのだろうかと考えてしまう。
もちろん、私の場合はそもそもコミュニケーション能力に難があり、コミュニケーションが主体となるようなオンラインサロンの類のものとは合わなかっただけなのかもしれない、とは思っている。実際にそういったコミュニティに参加して、大成する人もいるのだろう。それが新しい価値をこの世に生み出し、誰かの役に立つのならそんな素晴らしいことはない。
であれば、ただただ私の視野狭窄を披露しているだけの話で、恥をかくのは私だけなのだから別にいい。
しかし、やはり大部分は縮小再生産だったりはしないのか、多くを失っているのではないかと思ってしまう。
そして、本書のこの言葉に行き当たるのだ。
そこで「命令など知らない」と言うことはできないのでしょうか。そんなことは知ったことではない、と言うことはできないのでしょうか。命令を拒絶することはもはや不可能になったのでしょうか。それが無知と愚かしさに、「下に」、「ひきずりおろしつづける」ものであるとしても。
語りつくせないので来週も続く。
まだ第一章から抜け出せないかもしれません。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
2023年5月19日
アスカ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
