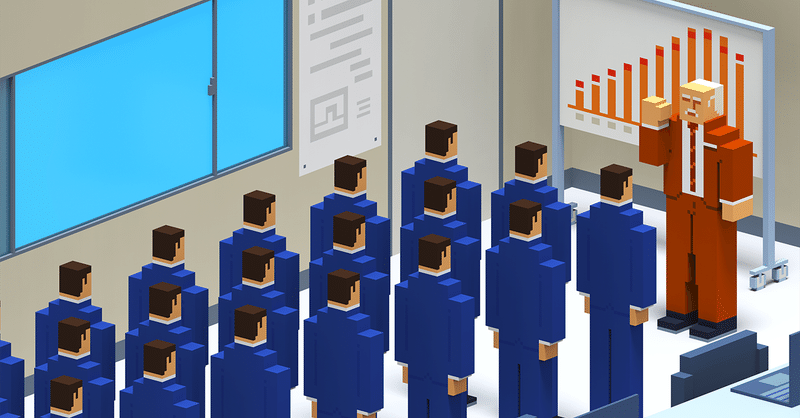
トップダウンとボトムアップ
トップダウン。
この言葉を聞いてどう感じるだろうか。
パワハラ、ブラック企業、オーナー企業、創業社長、
なんとなく、ネガティブな印象が多いようにも感じるのではないだろうか。
そこに働く社員たちの人格はもはやない、ぐらいの勝手なイメージがある。
一方でカリスマ社長、リーダーシップ、経営センス。推進力…。
こんな言葉にするとグイグイ引っ張っていくタイプの経営者の印象にもなる。
そして、こういったグイグイタイプの経営者もおそらくはトップダウンで物事を決めることは多いのではないかと思う。
ただ、前者との違いはこういった経営者の元に集まる社員たちは、そのカリスマ性に心を惹かれていることが多いので、人格どうのこうのというよりトップダウンを求めていたりもする。
何が言いたいかというと、トップダウン=時代遅れの独裁経営、では決してないということ。
トップダウンでも成果を出し続けている企業も、社員の満足度の高い企業もある。
逆にボトムアップだからといって、社員がみんな活き活きと働いているとは限らない。
トップダウンだから衰退していく、ボトムアップだから成長するというそんな単純な話ではないし、どちらが良いという話でもない。
企業の成熟度合いや文化、経営理念とか方針によっても見解が分かれるだろうし、何が最適かは判断が難しい。
ぼく自身の経験の中で、今思えば”トップダウン型”組織と”ボトムアップ型”組織両方を経験しているようにも感じる。
今回はそれぞれの組織の中で、良いところ、悪いところや社員の立ち回り方、組織としての在り方みたいなところを考えてみようと思う。
トップダウン型組織
文字通りトップの力が強く、経営会議や取締役会などはもちろん当たり前のようにあるし、ワンマン経営とは異なるものの良くも悪くもトップの影響力がとにかく強い。
創業社長や事業に想い入れの強い社長は、誰よりも事業のことは詳しいし、想い入れも強いのでトップダウンになるのもある意味しょうがない部分もあるようにも思う。
トップダウンの良いところは、トップの意思が明確で社員全員がこれから会社がどこへ向かっていくのかを理解しやすい。
社員が同じ方向を向いて仕事がしやすいので、会社に一体感が生まれる。
創業期や成長期の組織であれば、成長の過程を経験することができ個人の成長に繋がったり、社内の結束度も高い。
一方で、右肩あがりの成長が安定成長へシフトしていく成熟期やなかなかこれまで通りのやり方では成長が見込めなくなってくる衰退期に入ってくると、大きな変革がときに必要となってくる。
これまでと同じようにトップがこの変革を起こせるかというと、やはりそこは想い入れも強いことや長きに渡って成長をしてきたいわば成功のプロセスを捨てることへの抵抗はどうしてもでてきてしまうもの。
つまり、成熟期、衰退期を迎えるとなかなかトップダウンでは効果が出づらいという局面が出てくるのかもしれない。
成長期にはトップについていけばどうにかなると思っていた社員たちが、トップの言うことがそんなに効果がでなくなってくると、トップに対する不満が徐々に出てきたり、経営が厳しい状況でも我関せずの社員が出てきたり。
会社の業績は全てトップの責任。
成果が出せないトップには不満が溜まるし、社員たちはもう、思考停止でトップに従うことしかできなくなっていて結果的に変革などなかなか起こしづらいという状況に陥るのかもしれない。
ボトムアップ型組織
トップダウンとは反対に、トップの推進力というよりは各部門で問題点や課題を解決していくためにトップに相談、説得をしながら発展を目指す。
誤解してはいけないのは、トップにリーダーシップがないとか意思がないというわけではないということ。
トップダウンとは逆で事業が成熟してくる安定成長期に入ると、いかに効率的に事業を推進していくかというフェーズに入ってくる。
この時期に成長期と同じように、外への推進力を強くしてもなかなかこれまでと同じような成果を出せなくなってくる。
そうなると成果に対するコストが増えていくため、今度はコストの適正化が必要となる。
つまりはコストダウンや生産性の向上、人材育成などに力を入れていくことになり、ベクトルの方向が外よりも内に向かうことが多い。
成長期から比べると一見地味だが、ここがうまくいかないと企業として長生きはできない。
ボトムアップ型組織=成熟期以降の企業とは必ずしも言い切れないが、グイグイ成長するスタートアップ企業がボトムアップ型であるとはなかなか想像しづらいので、ある程度は合っているのかもしれない。
正しい組織の在り方
一つの企業の中であっても事業やタイミングによってトップダウン型が最適なのか、ボトムアップ型が最適なのかは異なるだろう。
正確にいえば、そもそもどちらかにわけられるものでもなく、どちらかというとトップダウン型が優位、だったりちょうど中間だったり、部署ごとでも異なったりと千差万別というのが正しいところだろう。
当社を例にとれば、ぼくが中途で入社した10年前は間違いなくトップダウン型。会社発足時から営業を引っ張ってきた人が2代目社長として、まさにグイグイ成長を続けていた。
発足時から携わっている分、社長が社内のあらゆるスキームに詳しく、ときに社長自ら粘り強い交渉で取引を勝ち取ったり、後から聞いた話ではかなりの修羅場の商談も一度や二度ではなかったそうだ。
そんなカリスマ社長がグイグイ引っ張っていたトップダウン時代から、3代目の社長交代を機にボトムアップ期へと突入する。
当社は某グループ企業の子会社ということで、社員の半数は親会社からの出向社員。
社長も例に漏れず出向であり、成長が緩やかになる成熟期に入った段階での社長交代となった。
ちょうどその頃は急成長期から安定成長期への転換のタイミング。
成長はし続けているものの緩やかな右肩あがりの状態で、まさに守備力の強化が求められている時期でもあった。
これまでは、200点取られても201点取って勝つ、みたいな豊玉もビックリのラン&ガン一辺倒だった。
攻撃だけでは長い期間戦い続けることはできない、体力が続かない。
そんな中でいかに失点を減らすかという視点にベクトルがかわったまさにその時であった。
こうやって考えてみると、当社のトップは割と企業のライフサイクルによって見事にトップを変更し、トップダウン型→ボトムアップ型に移行しているように感じる。
これは親会社の人事が秀逸なのか、たまたまなのかはわからないが見事にハマっている。
そこから久しく、当社はボトムアップ型企業となるのだが、最近ではこのボトムアップ期が長いがためにそれが当たり前になりつつあることに古参社員であるぼくなどは徐々に危機感を覚えてきている。
コロナ禍で業績も不審に陥る中、トップはボトムアップからのイノベーションに期待するも、ボトム側は現状を維持するので精一杯。
社員はトップのメッセージがないことを不満に感じ、社長は革新的なボトムアップがないことに不満を感じる。
成長が停滞し、衰退期を迎える兆しがでてきた段階では、これまでとは別の事業で巻き返しを図るのか、既存事業の再成長を目指すのか、大きな判断が必要になってくる。
その判断はなかなかボトムアップでは生まれず、再びトップダウン型に立ち戻って、目指すべき方向を改めて社員に指し示すことが必要になってくる。
企業のライフサイクルの中ではまさにここが再び成長に繋げられるか、このまま衰退期に向かうのかの別れ道。
当社ではまだトップがこの転換期と捉えていないのか、どうにかしなければとボトム側が試行錯誤をしているものの、なかなか前に進めていないという現実がある。
コロナ禍で大きく売上が減少した当社にとって、次年度は一気にコロナ前の2019年まで売上を回復するというミッションが課せられている。
これまでの延長線上だけでは、絶対に届かない高い目標。
この目標はトップダウンというよりは親会社から課せられた目標だが、こういったときこそトップの強い意志を示していくべきときであるようにも感じる。
売上を達成するために販促費を倍使うのか、利益率を落としてでも売上を取りに行くのか、はたまた企業を買収して規模を拡大するか。
いずれにしても大きな決断が必要になる。
大きな決断には経営者の覚悟が伴うので、ボトムアップでは到底実現しないだろう。
長らくボトムアップ型であった当社が、この機会にさらなる成長に向かって転換できるかは今後の命運を分ける大きな分岐点ではないかも、平社員のぼくは感じている。
もはやトップダウン、ボトムアップの話ではなくなってきている気がしないでもないが、経営の姿勢として情勢を見ながら常に柔軟にトップダウンにもボトムアップにも変化を可能にする組織というのが、やっぱ1番強いのではないだろうか。
と、強引な締め方で今回の考察はおわろうと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
