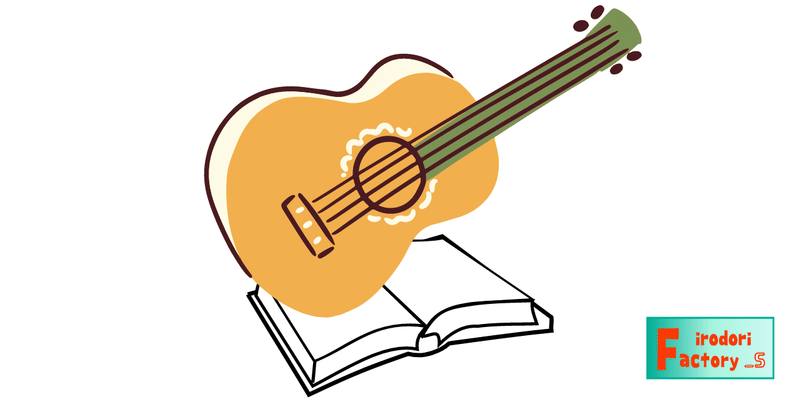
9冊目 『はじまりの日』
「小学校って何をするところですか?」
という質問を不特定多数の人にしていったとしたら、みなさん何と答えるでしょう。
「国語とか算数とかを勉強するところ」
「たくさんの友達と楽しく過ごすところ」
「1人でいろいろなことができるようになるところ」
…
こんなものがオーソドックスな反応かと思います。
今回の『はじまりの日』という本は、冒頭の質問に対し、少し違った視点で答える、そのきっかけとして紹介するものです。
・・・・・━━━━━━━━━━━・・・・・
授業参観日に小学校の中を歩いてみると、廊下や教室の壁面に掲示されている様々なものを見ることができます。
最も気になるもの、目を引くものといえば、子どもたちの書いた習字や絵などの作品でしょうか。
「うちの子のはどんな感じかな?」
「他の子はどんな作品を描いているのかな?」
「上の学年になると、こんな大人っぽい作品になるんだ。」
ふと足を止め、しみじみ眺める方も多いと思います。
けれど、もう少し注意深く見ながら校内を歩いてみると、校舎内には子どもの作品以外にも、実に様々なものが掲示されていることに気付くはずです。
◆きれいにレイアウトされた、毎月の学校行事の写真
◆「目の疲れを取ろう!」「歯の役割って?」など体の仕組みや健康に過ごすための掲示物
◆郷土料理のレシピや、箸の使い方などの食事のマナー
…
これらは、担任の先生方ではなく、担任外の先生や、養護教諭・栄養教諭などの専門性をもった先生が、「より楽しい気持ちで学校生活を送ってほしいなあ」とか「校内の子どもたちにぜひ伝えたい」という願いをもって掲示しているものです。来校する保護者が見ることを意識して、内容を考える先生もいます。
立体物を飾って見栄えをよくしたり、詳しい資料をのせて伝えようとしたりと、相当な時間や労力がかかっているだろうことは、少し考えてみるとよくわかります。
・・・・・━━━━━━━━━━━・・・・・
教員をしていた、かつての3月のことです。
ある日の放課後私が廊下を歩いていると、図書室の前でW先生が作業をしていました。見ると、本の表紙が映っている写真と、その本のオススメ文が書かれた画用紙を図書室前の掲示板に貼っているところでした。
そういえば、いつかの職員会議でW先生から「子ども向けに先生方がお気に入りの本の紹介カードを作り掲示します」という提案があり、私も画用紙に紹介文を書いたことを思い出しました。先生方の人数分貼られたカードの中に、確かに自分のものもありました。W先生は、「司書教諭」の資格をもっていて、校務分掌で図書に関わる業務を担当されている方でした。なかなか大変な仕事です。
私がこの取組で何の本を紹介したのか。それはすっかり忘れてしまったのですが、一つだけはっきり覚えていることがあります。
それは、たくさんの紹介カードの中に、『はじまりの日』というボブ・ディラン作の絵本があったことです。
ボブ・ディランという名前はもちろん聞いたことがありました。
けれど、個人的に子どもの頃から邦楽ばかり聞いていて、洋楽にはほとんど興味がなかったこともあり、どのような曲を歌っている歌手なのかは全くピンときませんでした。
ですが、その『はじまりの日』の紹介カードを眺め、その本を紹介した先生の書かれた文を読み、その1分もかからない時間の中で、自分の中に何かがひっかかりました。
「これ、欲しいな。読みたいな。」
その日の夜、スマホで注文し、翌週には自分の手元に届いた本。
それが、この『はじまりの日』でした。
早速読んでみました。
この本を読み、私なりに感じたことを表現してみます。
この本は、作者の願うことの一つ一つが短い文でスッと心に入ってきます。
この本は、柔らかなイラストが気持ちを穏やかにさせてくれます。
この本は、自分の心を見透かされているような、
この本は、自分の背中を力強く押してくれるような、
不思議な迫力があります。
そしてこの本は、少年がギターを受け取るところからスタートし、
そしてこの本は、青年がギターを少女に渡すところで終わる。
確実に変わっていく時代の流れと、
決して変わらず受け継がれていく思いみたいなものとの対比が、
なんとも言えない余韻を残してくれます。
この本は。
ちょっとした偶然によって私はこの本と出会い、お金を出して買ってしまったわけですが、
「よい出会いだったなあ。」
「よい買い物ができたなあ。」
と思いました。
・・・・・━━━━━━━━━━━・・・・・
「小学校って何をするところですか?」
多くの保護者の気付いていないところで、心ある先生方が日常的に意識してやっていることがあります。
それは、
「子どもの世界を広げるきっかけをつくる」
ということです。
先程のW先生が提案した「紹介カード」は、簡単に言うと、子どもたちに本への興味をもってもらうための取組です。
だとしたら、誰が見ているかもよく分からない掲示の取組よりも、
「毎朝10分間、読書する時間を設定する」
「長期休みには、読書感想文の宿題を出す」
といったことの方が、子どもたち全員に本を読む機会を設定できるし、効率的なのかもしれません。先ほど述べた「本への興味」を持つ子がもしかしたら増えるのかもしれません。
それでも、あえて、W先生の取組をする理由やねらいは何なのでしょうか。私は、そこに「子どもが世界を広げるきっかけをつくりたい」という強い願いが込められているのだろうと思うのです。
「何か、読んだことないけど面白そうな本だなあ!」
「あ、私の前担任だった〇〇先生が紹介している!」
「校長先生と話したことなかったけど、何か気になるな…」
決して押し付けたられたわけではないこの一つのきっかけが、この一つの出会いが、その子の新たな興味関心を広げることになるかもしれません。大げさかもしれませんが、その一冊の本との出会いがその子の将来の職業につながる可能性だってあります。
一見、非効率にも思えるこの取組。ですが、教師が押し付けるわけではなく、あくまできっかけが生まれる場をつくる。こういう演出が、ときに子どもの心を大きく動かし、子どもの世界を広げていくことがある。そういう肌感覚のある先生方が、このような取組を行っているのですね。
今回は掲示物の話を中心に進めましたが、例えば授業の場や子どもとの関わりの中でも、「世界を広げるきっかけ」を意識して行っている先生方はいます。
◆空のことにとても詳しい先生が理科の学習中にちょっとした雑学や空の不思議の話などをする。
◆発表などすることのない大人しい子のノートを授業の中で紹介し、友達の意外な一面に目を向けるきっかけを作る。その子が自信をもつきっかけにする。
◆学級会の議長団を、立候補制ではなく、全員行う輪番制にしてみる。
…
効率だけを考えたら、しなくてもよいことかもしれません。
ですが、あえて行うのです。
何が、子どもの心にひっかかるかは分かりません。
どこに、子どもの大きく伸びる可能性が潜んでいるかは分かりません。
子どもたち一人一人が成長したり、自分の可能性に気付いたりする。
私はかつて、何度もそのような場面を目の当たりしました。
教師として、強い喜びややりがいを感じた瞬間です。
『はじまりの日』という絵本は、大人である私の世界も広げてくれました。
その出会いによって、私は今WEBの世界の中で、この文章を発信しています。もしかしたら、この文章が、まだ出会ったことのない誰かの世界をちょっとだけ広げるのかもしれません。
『はじまりの日』
(岩崎書店)
作:ボブ・ディラン
絵:ポール・ロジャース
訳:アーサー・ビナード
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
