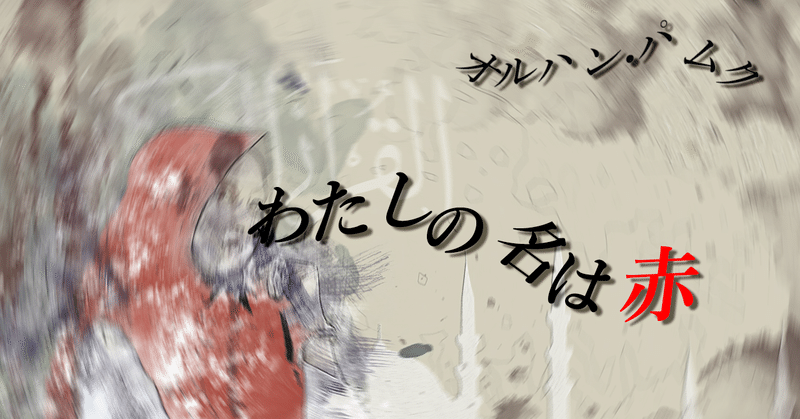
『わたしの名は赤』イスラム細密画の世界にさまよう
16世紀のオスマン帝国の首都、イスタンブルを舞台とした物語で、そのことにハードルの高さを感じる人もいるかも知れないが、作者、オルハン・パムクの文章はそんなに難解ではない。オスマン帝国はこの当時、世界で最も洗練された文化をもち、欧州の諸国をリードしていた。
また、ヨーロッパ諸国としのぎを削ったイスラム教国家、というイメージがあるが、フランスとは長きに渡って同盟を結んでいて、ヨーロッパの政治に深く関わっていた国である。アジア、ヨーロッパを股にかける世界帝国だったのだ。
主人公のカラは、12年ぶりにイスタンブルに戻ってきた。それまで、東方の都市を転々とし、帝国の高官や知事に仕えていたのだが、故郷イスタンブルから届いた一葉の手紙を手にしたことが人生の転機となった。
手紙の差出人は、彼の「おじ上」。おじ上はオスマン皇帝のために装飾写本を作る、細密画工房で働いている。このたび皇帝陛下からの勅命で、秘密裏に一冊の装飾写本を作成しており、カラにもその仕事を手伝って欲しい、という。
その装飾写本は、皇帝がヨーロッパ諸国にオスマンの権威を見せつけるために制作を命じたのだが、自国の民衆には、その存在を知られてはいけないという。なぜなら、イスラム伝統の技法とは別の手法を用いて描かれているからだ。その手法を「遠近法」という。
ご存知のとおり、遠近法というのはヨーロッパの画家によって編み出された技法で、物体を、距離が遠くなるにつれ小さく描く、というもの。オスマン皇帝は、帝国のすぐれた絵師はヨーロッパの技法をもたやすく使いこなすことができる、つまりオスマン帝国の文化はヨーロッパ諸国の文化を凌駕しているのだ、というアピールのため、従来のイスラムの細密画に、遠近法を取り込んだ装飾写本を作ることを命じたのだった。
しかし、自国民たちにとって、遠近法を取り入れた装飾写本は非常にセンセーショナルに映るだろうから、いらぬ混乱を避け、一切を秘密のうちに作成すべし、という。西洋美術に親しんだ私達は、遠近法を絵画を描くうえでの当たり前の技法だと思っているが、それが発明されたころは、そうではなかったのだ。
ましてや、伝統の手法に則って細密画を描いてきたイスタンブルの名人絵師たちにとっては、遠近法とは、刮目すべきものであり、それ以上に忌まわしいものでもあった。イスタンブルの絵師はみな、神の筆致、神の色を再現するために絵を描いてきた。人間の及びもつかない美しい世界を、神だけが知っていて、それに限界まで肉薄することが名人の条件とされていた。
ところが、遠近法というのは、神でなく人間、その絵を描く画家の視点から見た世界を紙に写し取るものなのである。遠い、近いというのは、それを描く主体にとっての尺度であり、矮小な人間の視点を中心に絵を描くことは神への冒涜につながる。
おじ上によって、秘密の細密画づくりに参加させられた名人絵師たちは皆、煩悶する。遠近法というのは確かに魅惑的な力を持っている。しかし、邪道だ。その邪道を用いて絵を描け、というのだから。
そして、細密画工房に不穏な事件が起こる。ひとりの絵師が殺されたのだ。言うまでもなく、秘密の細密画に関わっていた絵師であった。カラは、イスタンブルに戻っておじ上の細密画づくりを手伝いながら、幼い頃から恋焦がれてきたシェキュレという美貌の女性と関係を深めてゆくのだが、殺人事件は彼を巻き込み、思わぬ事態へと発展してゆく。
『わたしの名は赤』は、殺人事件の謎を追うミステリじたての小説だ。しかし、この物語をさらに魅力的にしているのが、イスラム伝統の絵画技法と、ヨーロッパで生まれた遠近法のアンビバレンツ、そして、これでもか、というほど詰め込まれた、古今の王や伝説的絵師たちのエピソードだ。
物語に登場する人物たちは皆、聞き知った物語を引用しながら、殺人事件や細密画、または神について語る。また、人物だけでなく絵に描かれた馬や木、悪魔たちもその語りに参加する。
彼らの口から発せられるいにしえの物語の断片に耳を傾け、寄り道を重ねながらメインストーリーへ戻り、またさらなる横道へと足を踏み入れるということを繰り返し繰り返し、ページをたぐってゆくこととなる。あたかもイスタンブルの名人が描いた細密画のなかに彷徨うような読書体験を、存分に味わうことができるだろう。
読んで下さりありがとうございます!こんなカオスなブログにお立ち寄り下さったこと感謝してます。SNSにて記事をシェアして頂ければ大変うれしいです!twitterは https://twitter.com/yu_iwashi_z
