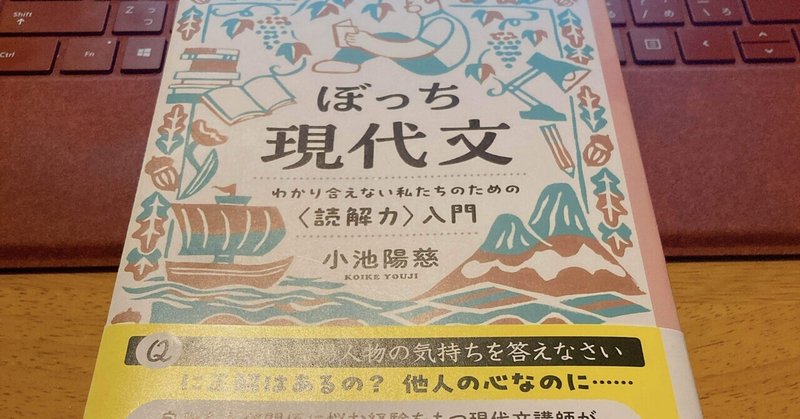
無言を分かつ ~小池陽慈『ぼっち現代文 わかり合えない私たちのための〈読解力〉入門』を読んで
みなさんもご存じの通り、小池陽慈という作家は「学習参考書の皮を被った哲学書」をバンバン世界に送り込んでいる恐ろしい人です。私としては一日でも早く「学習参考書じゃない哲学書」を小池先生に書かせる出版社よ出てこいと思っているし、もう出てきているかもしれないし、出てきていたとしても「自分にはまだそれを書くには早すぎる」と小池先生も思っているかもしれない。でも、遅かれ早かれ出るんだろうな。知人以上友人未満の私も「その本」が手に入る日を首を長くして待っています。
今回の『ぼっち現代文』も、もちろん例外ではなく、れっきとした哲学書です。しかし、ただの「学習参考書の皮を被った哲学書」ではありません。その特徴の上に「入門書の皮を被った最難関の書」という特徴も兼ね備えている魔物のような本なのです。
学習参考書としての『ぼっち現代文』
もちろん、それぞれの章の「学習ゾーン」は非常にわかりやすく書かれています。語彙、述語の機能、接続の役割などの「読み」にまつわる基本(?)的ものから、コード、語り手、異化などの文学理論で取り扱われるような項目まで、とても平易に、それでいて深く説明されています。
私の興味のスポットは「語り」に当てられているため、やはり『走れメロス』を用いた「語り手」の説明に惹かれる。意外と生徒の中の「登場人物の発話の中に含まれる心情描写」=「その登場人物の本心」という枠組みは強固です。自分自身の経験上でも、自分が思っていることと全然違うことを言うことなんてざらにあるはずだけど、フィクションの中にその経験を適用させない場面に多く遭遇します。そこに小池先生は切り込んでいく。
繰り返しますが、物語の読解において、語り手がその人物の気持ちを語ってくれないとき、私たちは、原因や言動から、その人物の心情を考えます。けれども、そこに解釈のためのお約束(コード)が見つからない場合、私たちにとって、その人物の心情は、うかがい知ることができないものとなってしまう。
もちろん、語り手が、地の文(せりふではない文)で「〇〇と思った」「悲しかった」などと語ったら、基本的にはそれを疑うことはできないでしょう。
しかし、会話として発せられた言葉については、本心かどうかはわからない。つまり、このせりふをもって、セリヌンティウスの心のうちを理解できたことにはならない。
小説を読むにあたって、極めて重要な知識であり、テクニックです。小池先生はこのあと、セリヌンティウスの「私はこの三日の間、たった一度だけ、ちらと君を疑った」というせりふが、もし本心ではなかったとしたら、というアイディアを提出しながら、『メロス』の解釈を行っていきます。
今西祐行『ヒロシマの歌』をとりあげた第8章では、語り手が知り得ている情報を操作することで、物語に大きな転換を生じさせ、読者に強い印象を与えることができる、という語り手の大切な機能も紹介しています。
やはり、「語り手」は、情報を操作しながら小説を進めていくための推進力として働く一方で、小説の中に「綻び」を生じさせ、その綻びを広げることで解釈を生み出すきっかけにもなるという、相反する機能を持つ不思議な装置であることが、小池先生の解説を読んでいると実感できます。
小池先生の解説に一つ付け加えるのならば、「語り手は中立ではない」ということ。一人称視点の語り手なら、その偏りが顕在化しますが、第三者視点(超越論的視点)の語り手は、中立な語り手に見られがちです。しかし、その第三者視点の語り手も、特定の登場人物に寄り添った語りをすることが多い。谷崎の『細雪』も、自由奔放な語り手である一方、やはり次女である幸子に寄り添った語りをしていました(もちろん一概には言えない)。
語り手は「全能」であり「中立」である、という枠組みを壊したところに、物語との出会いがある。そんなことも考えました。
今回は「語り手」にスポットを当てて書きましたが、他にも評論、小説、詩を読む上で大切な装置をたくさんを紹介してくれています。しかも「生きた文章」を用いながら紹介しているので、非常に実践的です。
ただ、この本の内容は、ただの「知識の伝達」で終わろうとはしません。それが、哲学の書であり、最難関の書である所以です。
一番近くにいるけど、一番遠くにいる「あなた」
そもそも本書は『ぼっち現代文』というタイトルの通り、「孤独」という状態とどう向き合うか、ということが書かれた書籍です。もう少し厳密に言えば「孤独ではあるし、むしろ孤独でありたいと思っているけど、その反面本当にわかりあえる他者と出会いたい」という人間関係におけるアンビバレンツな欲望とどう向き合うか、という内容です。冒頭からこじれ全開でスタートしています。
私も似たようなタイプなのでよくわかります。趣味で本を作っているけど、別に本を作っている人同士の交流なんか別になくても構わない。でも、本を作るという行為の楽しさ、大変さをわかり合うことができる友人がほしい、と思いながら文学フリマのブースに座っています。でも「友達になってください」なんて言うのは死ぬほど恥ずかしい。しかも、やっぱり内面をわかり合うなんて無理に決まってる。主義主張が違えば、本づくりのポリシーだって千差万別なはずだ…。無限ループ。このような葛藤が、本書の通奏低音になっている。
対話を通じて、相手の人格や思うところを知り、そして、私という人間やその内面を相手に知ってもらう。そのことによって、二人は、より深くわかり合うことができる―それは私たちの思う以上に、とほうもなく難しいことなのかもしれません。
親子という最も近いはずの関係ですら、私たち人間は、相手の心のうちを知ることができない―そのことへの気づきに、語り手の「私」は、深く深く、苦しんでいます。
つかもうと思っても、いつまでもすり抜けていく「他者」。一番近いところにいると思っている人でも、まったく遠くにいるように思えてしまう瞬間がある。いや、一番近くにいるからこそ、遠くにいるような感覚に陥る。それが他者という存在であり、「あなた」である。その事実を石垣りんの詩などを通して、読者に容赦なく突き付けます。
その他者性は、「無言」という境地に行きつきます。
「無言の共有」という境地
私たちは、この無言とともに生きていかなくてはいけない。
これは、最終章で宮沢賢治『なめとこ山の熊』と小十郎と熊との「コミュニケーション」を紹介した上で、たどり着いた結論です。
一体どういう意味なのでしょうか。「無言とともに生きていかなくてはいけない」。みなさんは説明できますか? なんとなく、説明できそうな気がする。語り手と読者が「無言」を分かち合うこと。「無言」を分ち合う。「無」を分つ。わかる。わかりそう。わかりそうだけど、やっぱりわからない。
ここが、私が本書を「最難関である」と定義する所以です。だって、私たちは話しながら生きていきます。メッセージの交換、コードの解読、語り、あらゆるものを駆使しながら他者とコミュニケートしながら生きていかざるを得ない。でも、小池先生は言うのです。「無言とともに生きていかなければいけない」と。そして、筆者である小池先生すらも断言しています。「私にも、わからない」と。
いや、本当にわかんないんですよ。本当に。本当に難しい。でも、でも、やっぱり無言を分ち合わなければならない。無言を分ち合わなければ、何も話すことはできない。話し始めるには、まず無言を分ち合わな分ければならない。わたしとあなたは何もわかり合うことはできないという前提を、分ち合わなければならない。
わからないのですけど―ただこれだけは付け加えておきたいのが、「無言」の「無」は、「何もない」という状態を意味するだけではない、ということです。「無」とは、いまだ何もわかっていない……ということは、これから何物かになっていくものが、ぎゅうぎゅうに詰まった状態のことなのです。
本当にそう思います。何もわかっていない状態は、これから何かになっていくということなんです。何かを作るためには、何かを合意するためには、まず最初に「今は何もない」「私たちは今何もわかり合っていない」ということを理解することが必要なんです。
もちろん、小池陽慈という作家を知っていれば、G.スピヴァクの名前が当然頭に浮かびます。サバルタンとは一体誰なのか。誰かを救済しようとする声は、本当は誰のための声であり、語りなのか。「あなたを助けたい」という声の宛先が、自分になっていることはないか。「あなたを助けたい」という言葉が、「あなた」を抑圧することになっていないか。なっているとすれば、じゃあどんな声を「あなた」にかけるべきなのか。「声をかける」という行為にすでに「声をかけてあげる/かけてあげられる」という構造が含まれているのではないか。だとしたら、その声の主は、声の主であるという立場から、退かなければならない。じゃあ、声の主から、発話の主体から退いて発話するにはどうすればいいのか。このような難題が思い浮かびます。声を出すって、本当に難しいことなんです。でも、私たちは、声を出さなければならない。声を出すために最も大切なのは、「無言」、つまり「何も話せないこと」を共有することなのではないか。
イスラエルとハマスの紛争を目にしながら、どちらかの共同体の死者を悼めば、その瞬間もう一方の共同体にとっては、その悼みは、憎しみに変わるかもしれない。では、すべての死者を悼むべきかと言えば、そうすればすべての死者を一般化し、固有性を奪うことになる(「ヒロシマの歌」で語られたように)。誰かを善、誰かを悪に設定して話し始めれば、そこには差別が、蔑視が生まれる。安易な思い込みと、安易な結論によって発生する発話は、差別しか生まない。じゃあ、無関心でいるべきなのか。絶対にそうではない。じゃあ、私たちに何ができるのか。
最初に、その「無言」を、差し伸べられない手を、分ち合うことなのではないか。そうして初めて、遠くの地で起こっている紛争のことを、私たちは話すことができる。自分たちには、何も話すことができないということから、始まる対話は、絶対にあるはずだ。
こう書いたけど、これが小池先生が考えていたことかどうかはやっぱりわかりません。私も書いてみたけど、やっぱりよくわからない。それでも、私は小池先生と「無言とともに生きなければならない」という「言葉」を分かち合うことができた。その言葉のシニフィエは、小池先生にもわからなければ、私にもわからなければ、誰にもわからないかもしれない。でも、シニフィアンは共有することができる。シニフィアンを共有すれば、対話が生まれるかもしれない。
この本を読んだ人たちには「無言を分かち合う」という難しい言説が何を指しているかを考えてほしい。そして、その考えたことを述べて、共有することが、対話を生んでいく。非常に哲学的で、非常に難しい本書ですが、「対話」のためには、必読の書であることは間違いありません。
ウィトゲンシュタインは「語り得ぬものについては、沈黙しなければならない」と言いました。それでも私たちは語らなければならない。「語り得ぬ」とみんなでわかった上で、語り合うことが大切なのです。
これ、本当に学参を読んだ感想か…?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
