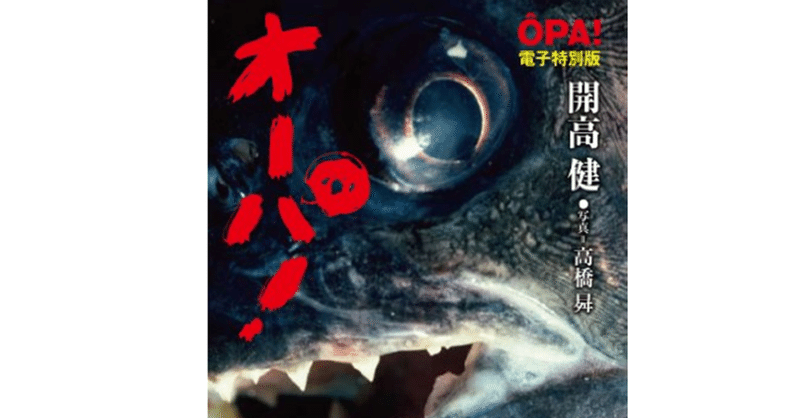
心を無に、血湧き肉躍る大アマゾンの冒険へ~開高健『オーパ!』
むせ返るような熱気、香りたつ種々雑多なスパイス。目を閉じればハチの羽音と、足元の河にピラーニャの跳ねる音が聞こえる。行き交う人々の息づく声が、暮らしが、遥か遠く大アマゾンの未明が、脳裏に迫ってくる。
何かの事情があって野外へ出られない人、海外へいけない人、鳥獣虫魚の話の好きな人、人間や議論に絶望した人、雨の日の釣師……すべて書斎にいるときの私に似た人たちのために。
巻頭で読者に向けてこう語りかける著者の言葉に、「ああ、これは僕らのために書かれた本なのだ」と嘆息する。
本書は、作家の開高健によるアマゾン釣り紀行である。開高は芥川賞など各賞を受賞した作家であるが、むしろルポやノンフィクションの名作により後世に残る作家でもある。そして熱狂的な釣りマニアでもあった。
黄金魚ドラドを追い求めて秘境に分け入り、全長3mの巨大魚ピラルクーを釣り上げる。喰われれば体に穴が開くピラーニャを警戒しつつ、黄色くとろっとしたアマゾン川の水―通称”病原菌のスープ”―をおそるおそる飲んでみる。ちょっとした遠出もままならない今このときに、悠久の大地を縦横無尽、無分別に闊歩する著者らのロマンあふれる冒険譚に、胸が疼いてやまない。
焼き畑の風景や現地日系人たちとの出会いも、開高の目を通した徹底的な観察とカラフルで詩情豊かな描写によって、すべて現実離れした情景に姿を変えていく。
頭を空っぽにして読み始め、そのままズッポリ引き込まれる。地球の反対ブラジルの地のあまりの異質・異文化に驚嘆し、狭い島国日本での日々のごちゃごちゃした雑念はどこかに飛んでいってしまう。脳の中の中空に、大アマゾンの色合いが怒涛のように流れ込む。
終盤に印象的な一節がある。
数日後にテコテコでクイヤバの空港にもどった。空港のロビーの人ごみのなかを釣竿を持って歩いていると、ふいに背後から滅形が襲いかかってきた。肩を殴られたような衝撃があり、一瞬で私は崩れてしまった。空と、水と、ジャングルと、魚がつくりあげてくれたものが、カードのお城のようにへたへたと倒れてしまった。
帰国の途につく道すがら、突然の”滅形”に襲われる著者。自身の”形”(形相・形態)が無くなっていく感覚があったのだろう。大自然のエネルギーと冒険の興奮とが織り成す真に活き活きとした自身の生命の躍動が、日本での生活へと接近するなかで徐々に輪郭を形作らなくなっていく。
開高健は、形なきものへの恐れをしばしば口にした。”滅形”という言葉は、そうした自分の生が根付く基盤であり冒険のなかで生きることが形作ってきた彼自身の根拠から、現実が遠ざかっていくことへの拒否感をストレートに表した言葉であるように思われる。型通りの生活を繰り返す日々は、彼の目には生気が抜けた人形のように映ったのだ。
逆に言うと、われわれもまた、本書のページをめくり始めることで、そうした日々のせせこましさと息苦しさからつかの間解放され、冒険の旅に足を踏み入れることができる。
いま、この無窮の展開からうける不安には歓びがひそんでいる。完璧におしひしがれて無化されたのに私は愉しい。ナーダにしてトーダ。何にもなくてすべてがあると歌うあの二つの恋歌はこの河の上でこそふさわしいのかも知れない。絶妙の暗合を感じさせられる。
大きすぎるアマゾン川は、船から岸がまったく見えないそうだ。見渡す限り、ただただ水平線だけが自分を囲んでいる。無辺際に広がる水面の上で、無限のものの恐怖があり、しかし視界にはなにもない。ナーダ(なにもない)にしてトーダ(すべて)。
言っとくけど、これは本当にすごい本だ。自然の巨大さと崇高さのまえに、久々に不安に駆られてみてはいかがだろうか。
頂いたサポートは、今後紹介する本の購入代金と、記事作成のやる気のガソリンとして使わせていただきます。
