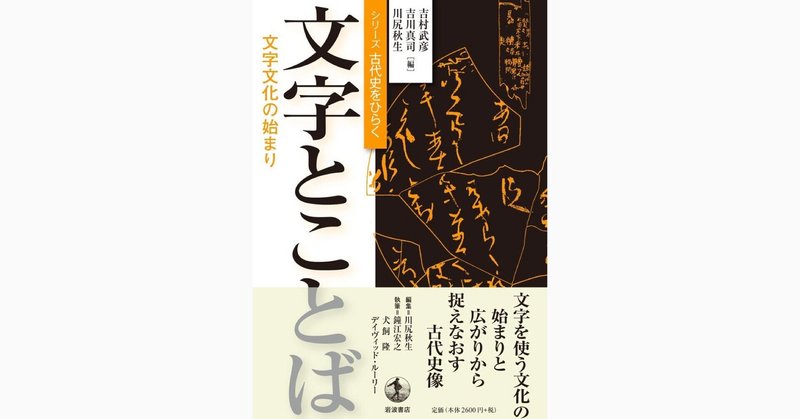
"日本人"のルーツへの問い-『文字とことば』(シリーズ 古代史をひらく)
「ひらがなや漢字はいつ、どのようにして日本で使われるに至ったのか?」
そういえば、よく知らない。
漢字が中国から来たのは知ってる。卑弥呼の時代から日中の国交があった。きっとそのへんだ。
じゃあひらがなは?ずっと昔はぜんぶひらがなだったの?
実はこれ、否、である。全然ちがった。ひらがなは漢字よりも後。意外と、みんな知らないんじゃないだろうか。
では、なぜ、どのように?
当然ながら、ことばは変わっていく。われわれがふだん当たり前のように使っている日本語も、現在のような形になるまでに多くの変遷を経ている。その紆余曲折の歴史の中には、そうでなくとも良かった意外な偶然も、のっぴきならない必然の理も、ともにたくさん沈殿している。文字とことばのルーツへの問いは、民族・文化そのものの起源への問いへも接近していく。
日本語研究のいまを伝える
いま、日本語がアツいらしい。
近年になって日本や周辺アジアで出土した大量の木簡の分析をもとに、文字とことばの関係を巡る研究が盛んになってきた。この史料に対して、考古学/文献史学の方法論と日本語学的な分析とを総動員して、あらたに見えてきた最新の成果が従来学説をどんどん覆していっているというのだ。
本書では、このような日本語研究の新展開が、4人の専門研究者による5つの論考を通して描かれていく。
さて、本シリーズ「古代史をひらく」は古代史領域を特定テーマ別にまとめた全6巻モノで、専門的な内容を初学者でも読みこなせるよう手引きすることを旨としている。
幸い日本の古代史に関心を持つ人は多く、各地の遺跡や博物館は訪問者で賑わい、古代史をテーマとする書籍や情報も巷にあふれています。いっぽうで最新の研究の進展はめざましく、より精緻なものとなっているために、その成果を専門家以外の方と共有することが難しくなっていることも事実です。
しかし、新しくわかってきた歴史の実像を知ることの興奮や喜びは、他の何にも替えがたいものです。私たち研究者が日々味わっているこの「面白さ」を、親しみやすい歴史叙述によってさまざまに「ひらく」ことを通じて、読者の皆さんにお伝えしたいと考えました。
―出版社HP「刊行にあたって」より引用
はなから専門外に向けて書かれた本ゆえ、扱う史料や方法論の緻密さを文体等でうまく抑制し、難解さに繋がらないよう心が砕かれている。近年の出土物も写真入りで多く紹介される。
また、「文字とことば」という、ともすれば淡白な語りになりがちなテーマにあって、書き手たちが素人読者の興味を誘うべく自由に学際的/領域横断的に周辺トピックを絡め取っていくのも楽しい。
文字の伝来と「自国文化」アイデンティティの拮抗
もともと、文字を書かない倭人である。どこから来たのか、どの人種の系統に由来するのか、いまだ同定されていない。彼らの使っていた言語と、現在のわれわれの文字とことばとの連続性は、少なくともこの時点では一切ないと言ってよい。
古くから中国との交流があったことはよく知られているし、漢字は文化交流のうちに日本に流れ込み、受容されてきた。しかし、そう簡単に片付けられるほどことは単純ではない。
新しいことばが元々のものから置き換わる、ないし新たに加えられるという事態は、単なる文化接触/伝来のみによってなされるものではない、より複雑な事情を必要とする。中国の政治形態を必死に模倣せんと奮闘する日本政府の取り組みを契機として、漢字が到来しじわじわと市民権を得ていった様子は、なかなかに読ませる展開だった。
翻って、ひらがながいつどのようにして生まれてきたのか、正確なところは実はまだ分かっていない。本書は最新研究を引っさげて、ここにも迫っていく。
平安時代に急激に起こってきた「国風文化」に負うところが大きいと考えてきた従来学説に対し、本書の論者たちは、より複雑で微妙な「日本人」の自意識の変遷へと切り込んでいき、大胆な仮説を繊細な史料読解とともに紹介していく。
鍵となるのは、それ以前にあった唐風文化と国風文化の間の拮抗、揺れ動き、揺り戻しである。
そしてその後に、カタカナの誕生も控えている。
この辺りの次第に興味が湧いてきた方は、本書を直接手にとってみるといい。
文化史・精神史としての言語
総じて本書に特徴的なのは、当時のアジア史の中で日本が置かれた複雑な社会状況や地政学的関係を研究の視野にしっかりと取り込み、幅広く文化・政治的諸相を描いている点である。
そうした視野がだいじなのは、言語現象が単に文法と語彙から成る静態的システムであるのでなく、時代ごとの文化・社会に固有な規定と精神の力動が表出する現象であるからである。統語/形態/語用論など端的な言語学的側面のみでこれを捉えると、やや平板になる。
ことばは、人間がものを考える際の土台であって、ある言語はその言語圏のひとびとの精神性を陰に陽に表現している。そうであってみれば、以降1,000年の日本国の基礎を形作るあらたな言語が劇的に生まれ出た時代に、人々が被った精神の混乱は想像に難くない。
揺れ動く国際情勢と入り乱れる各国文化のグラデーションのさなかにあって、「自分たちは、日本人とは、果たして何者なのか」と日々問い続けざるをえなかった彼らの惑いと切迫の息づかいが、本書にはこだましている。
奈良県のどこそこから出土した木簡も、『古事記』も『万葉集』も、行政文書から日記までもが、もろい足場で踏ん張りながら、日本的精神をなんとか立ち上げんとする古代日本人たちの痛切な叫びとして、ぜんぶ繋がっていく。
そして、言葉の研究のなかでは、このような民族の精神史が手繰り寄せられ、同時に考察されるべきなのである。
***
2010年代の論文も多く取り上げられ、研究書としての体裁を保つ一方で、著者たちの語りはどこまでも丁寧で、平明である。執筆者の座談会や、海外研究者の寄稿による「海外から見た古代日本」などの趣向も、このテーマを一層映えさせるよううまく働いていると感じられた。
2,000年の昔から現代へと向かって蛇行する言語の旅路。その端緒が、本書において開かれている。
関連書籍
頂いたサポートは、今後紹介する本の購入代金と、記事作成のやる気のガソリンとして使わせていただきます。
