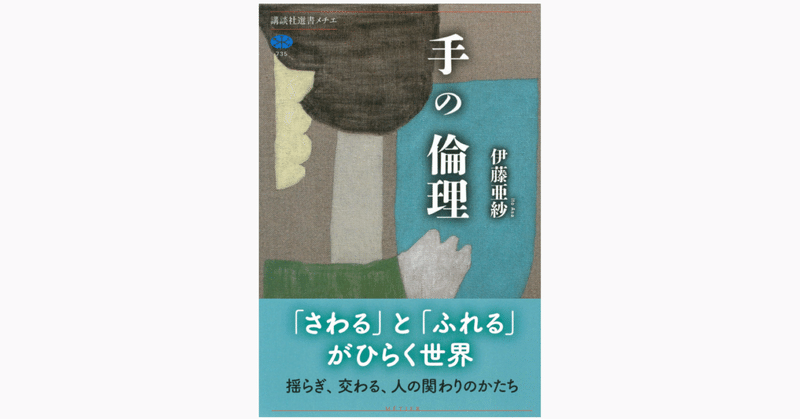
もしも『手の倫理』をタコが読んだら
ずいぶんと話題を読んだ本である。
じっさい、おもしろい。気軽に読めるし、読後はやわらかな希望の光に包まれるようなやさしい気持ちになれる。それなのに、それでいて、陰々とした思考の渦が幾重にも巻いてしまうようななにかが残る。
『手の倫理』~危うさのあわいを遊ぶ
西洋で支配的だった視覚中心のものの見方に待ったをかける、「ふれる」ことから考える倫理の本である。
美学研究者の著者は、まず「ふれる」と「さわる」の日常的な使われ方の違いに注目する。先行研究も引き合いに出しながら、われわれが普段は一緒くたにしている2つの行為の間にひそむ固定化されたものの見方をあぶり出していく。
単に「さわる」というとき、その対象は物質的なものとして意識されてあり、さわる経験の背後にあるのは〈自-他〉、〈さわるモノ-さわられるモノ〉の間の区別である。他方「ふれる」経験の方はといえば、常にふれれられる側との相互作用のうちにある。「他者」との双方向的なふれ合いを、この表現は含意している。
両者の区別を軸に、本書の議論は進む。著者自身のケアの現場での経験を踏まえながら、物に「さわる」ことと他人に「ふれる」ことの合間に立ち上がってくる倫理の問題に、深々と切り込みを入れていく。
「よき生き方」ならぬ「よきさわり方/ふれ方」とは何なのか。触覚の最大のポイントは、それが親密さにも、暴力にも通じているということです。人が人の体にさわる/ふれるとき、そこにはどのような緊張や信頼、あるいは交渉や譲歩が交わされているのか。つまり触覚の倫理とは何なのか。
接触の不確実性から生まれる不安。そのなかで他人に体を預ける。ふれることの主導権を相手に握らせる。初めて要請される、互いを信じあう関係性。信頼の大事さを訴えながら、それが無意識レベルでの共感(覚)へ、そして道徳から倫理の途へと至る本書の全体構造は鮮やかで、もはや感動的でもある。
日々無意識にこなしていた他者とのふれあい方を、それがあらわにするもっと根本的な関係・コミュニケーションの様態として新たに見直すことを促してくれる。
ただ、本書の良さはそのように単純化された肯定的なメッセージだけではない、とも思う。
遠心性コピー、その深淵なる海溝
本書を読んで、個人的に特に思い出されたのは、タコの足のことだ。
そう、タコの足。
ピーター・ゴドフリー=スミス『タコの心身問題』は、生き物好きの哲学者がタコの生態学を通じて意識の謎に迫っていくという、人間意識について考える上で外せない傑作である。数年前に邦訳が出て、よく読まれた一冊だ。
著者は作中で「遠心性コピー」という機能を紹介している。ある種の生物は遠心性コピーという複製信号を脳から各器官に送っているということが、生理学や認知神経学の分野で知られている。この信号は、自分が行った運動によって生じた外界の変化を、自分がそのまま外界の変化として知覚してしまわないようにするために使われる。
なぜそんなものが必要なのか。身に迫る危険を正しく察知するためである。
生物は基本的に外界の変化を常に各感覚器官を通じて把握し続けていて、それへ応答する形で自身の行動を決める。特にそれほど複雑な判断機構を持たない生物の場合、外的な刺激によって自身の行動パターンがある程度決まっている。「エサの信号が自分の近くを通過したら飛びつく」とか「熱かったら後ろに下がる」とか、そういった行動によって生存確率を高めているのである。
ところが、キャッチした外界の変化の信号が、自分によってなされたもののばあい、それにまた反応してしまうと、信号が無限にループしてしまったり、本当の危険に適切に反応できなかったりと、不都合が生じる。
たとえば、ミミズは通常、何かが自分の身体に触れれば、すぐに後退りする。危険が迫っている可能性が高いからだ。しかし、ミミズが這って移動する時には、常に同じように何かが身体の一部に触れていることになる。その場合、触れたと感じる度に後退りしていたら、まともに移動することはできなくなってしまう。ミミズが移動できるのは、自らがつくり出した触覚を何らかのかたちで打ち消しているからだ。
この打ち消しに使われるのが、先に書いた遠心性コピーである。「この変化/刺激は自分がやったやつですよー無視してねー」という信号を脳から筋肉などへ飛ばして、自身の影響込みのナマの知覚情報から、自身に起因する部分だけをいわば相殺する。それにより、生物は正しい状況判断と行動を継続することができるということだ。
実はこの機構は、単純な生物だけでなく人間などの複雑な脳の持ち主にも備わっている。人間がモノや他者にふれる場合にも、手の触覚器官は幾多のシナプスを通じてこの遠心性コピーを大脳から受け取っている。
これが意味するところは、人間は自身が引き起こした「触れ」に対する結果を、実際よりもマイルドな形でしか認識していないということである。つまり、触れた側は自分が触れたものに対して、触れた経験の全体をまるごと感じてはおらず、かならずある一定の度合いで「鈍感」であるということだ。
ここで『手の倫理』へと話を戻すと、幾つかの問題が生じてくる。
この出色の接触論は、自他の相互性の契機としての「ふれあい」を中心に回っていたのであった。
接続と同期。主導権を持ったふれる側と、主導権を渡したふれられる側が同じ接触の体験を共有しながら、それぞれにとっての不確かさを縮減していく動的なプロセス。そこでは、同じ一つの体験の当事者たちによる明瞭な把握が、次の生成へと変転していく次第が描かれていく。そしてまた、ここでの「ふれる」経験は、主体的な個人が能動的に選択しコミットすることで初めて可能になる事柄でもあった。その判断と結果、そして生じる倫理の問題の担い手として、自由意志を持った個人が要請されていたはずである。
しかしもし万が一、触れる側がある種の無自覚のヴェールを被らざるをえないとしたら。自分の思いとは裏腹に、遠心性コピーという生理的なメカニズムが、触れる経験のある部分をかならず遮断してしまうとしたら。
そこには自他の相互性よりもまず先に非対称性が、そして非対称であるがゆえの無知が、介入してくることになる。双方にとっての「意味」「解釈」の話ではない。それに先立つまったく純粋な知覚の次元で、「ふれる」側にだけ情報の欠損が生じるのである。「ふれる」側と「ふれられる」側で生じている現象はぴったり一致してはいず、互いに近づいていき同期しゆくはずだった接触の場はすでにして食い違っていたのである。
そうなると、そこに入り込んでいる無知は、ある一定の「さわる」暴力を生み出していはしないか。しかも、その暴力が生理的な機構に原因を持つものだとすると、倫理の担い手としての個人にその責を帰すことは当然できない。これはかなり厄介な事態と言わざるをえない。
言い換えれば、「ふれる」は人間的なかかわり、「さわる」は物的なかかわり、ということになるでしょう。そこにいのちをいつくしむような人間的なかかわりがある場合には、それは「ふれる」であり、おのずと「ふれ合い」に通じていきます。
ふれるリスクを引き受け、信頼を相互に交わし、そうまでしても無知ゆえの暴力が必ずや混入してしまうとしたら、それに対して自身の身体を差し出すことの困難さはしつこくこびりつく。触ったものと触られられたものの間には、こうして不可避なかたちで深い深い溝が横たわっている。
考えてみれば、まったく共同的で同期的な事柄でありながら、構造的な非対称をはらむものとは結構珍しい事象ではないだろうか。まなざしにおける他者の「無」以上に、この見かけの対象性とその裏切りがあらゆる重篤な倫理の裂け目を生み出しているような気もしなくもない。
再度、記号の問題
ただ、もしかするとこれは、ふれることについての予見と関わる、もう少し複雑な意味生成の場として考えたほうが良いのかもしれない。
遠心性コピーとは、要はみずからがふれたことで生じる結果を脳があらかじめ多少なり予見し、その予見分を生じた結果から差っ引くということだ。すると事の次第は、ふれるという現場で生じる共感や、その共感の不可能性よりもまず、先立つ予見の内容いかんに大きく関わってくるのではないか。相手にふれる前に、それが生じる結果を見越す。その見越しと実際の知覚のギャップを捉え、逆演算する。
見越すことが問題となるなら、これは当事者間の信頼の話にとどまらず、社会における「ふれる」ことの立ち位置などにも深く関わっているだろう。握手やスキンシップが持つ意味合いは社会や文化によって異なり、あるいはその場のシチュエーションに大きく左右される。
つまり人は、じかに肌と肌を重ねるよりもずっと以前にすでに「ふれあい」の行為に参与している。相手を目の前にしたその時にすでに、著者風にいえば「不確かさは減少し、「ふれるときふれられている」という確かさのなかで、緊張はむしろ安心に変わっていく」(同No. 1185)という位相の只中にいる。信頼が効力を発揮するのは特に接触の瞬間であるとする本書に反して、「ふれあい」とはもっとずっと社会的な網目に囚われながら時間的に伸び広がっている行為なのではないか。
著者がいう物理的コミュニケーションのまったき”接続性”に前述の疑問符が付されるなれば、より広く記号的な「ふれあい」が改めて復権され考察されるべきかもしれない。
これを個々人の視点からのコミュニケーションの技術論として捉えるならば、予見制御を行うべきか、それとも有限時間における予測制御として最適化すべきか、という話で置き換えが可能だ。まぁこれだと片側通行の伝達モデルにしかならないが、接触において「時間」という変数が前面に出る点はおもしろい。
いずれにしろ、「ふれる」と「さわる」は、自分と相手という2人だけの閉域を離れ、社会における「ふれる」ことの表象の問題へと大きく広がっていく。
タコの足に倫理はあるか
そしてここでもう1つ、『タコの心身問題』のトピックを拾っておきたい。肝心のタコにご登場いただかないと終われないのだ。その驚くべき生態に触れておこう。
同書によると、人間の神経細胞(ニューロン)は大半が脳に集中しているが、タコのような頭足類の場合にはそれが身体中に分散しており、足にあるニューロンの数は脳にある数の2倍に登る。結果として、タコの足は触覚だけでなく嗅覚や味覚などの高次の認知機能、それに短期記憶すらも備えており、いわばもう1つの脳として機能しているというのだ。身体に幾つもの脳を持ち、各々が思考しながらも全体としては一つの統合されたフィードバック系を持つ個体。自分の中で天使と悪魔が会話してるような、まったく別個の意識体験がそこに同居しているのか、それとも混線したスピーカーみたいな感じなのか。われわれ人間の意識体験からみるだけでは、これはなんとも想像し難い代物なのである。
大脳を中心とした中央管理システムではなく、体の各部位がある程度自律的に動き判断し、そして人間に次ぐほど高度な社会性を備えたタコのような動物を考えると、『手の倫理』が扱うような「ふれる主体の所在」すらも一筋縄ではいかなくなってくるような気がする。
遠心性コピーが引き起こす足の知覚のキャンセル効果により、現ナマの知覚は儚くも打ち消され、不完全な形で大脳に届くという。しかし、足にも脳があるのなら。もしも”足の脳”は遠心性コピーのキャンセル効果を逃れている(※)なら、すくなくとも足が他者に「ふれた」時点では「ふれあい」の十全な契機がいまだ残る。そうするとむしろそこでは、”足の時点”では、相互理解と信頼に向けて体験はひらかれていることになる。
そうだとして、では他者にふれているのは誰か、ふれる倫理に関わる(べきな)のは誰か、という疑問もまったく同時に生じる。
足が、倫理の担い手になるのだろうか。倫理の担い手たる資格がないとすると、この場合は誰になら、どのような条件のもとで、あるのだろう。そんな疑問の手前にはそもそもたしかに「動物の倫理」(の可能性)の問題が存するだろうし、その意味でこれはまごうことなき空論である。しかしそれを無理に飛び越えてでも、この異常事態の動向がとても気になる。
さらにさらに、個人と個人のふれあいという視点も、再考を迫られる。
みずからの内部に向けては、
このようなニューロン間の複雑な相互作用を行う身体の各部位は、外皮的には物質的な連続でありながらも、それぞれ「ふれあっ」てはいないか。自分の脳と足は、神経系は、細胞間は、内分泌系は、まったく純粋な意味でふれてはいないか。
脳と意識を主座とする人間主体は、自身の各部位に対していかなる権能を持つ(べき)か。
はたまた外部に向けては、
自身内部での不完全な交絡を鑑みると、他者との「ふれあい」が自身の内部でのふれあいと全く異なるものであるとは自明か。
自身の予見が介在しない「さわる」「さわられる」ことの方にこそ、主体による欠損のないナマの経験がありはしないか。
より先立つ始動因であり、あらゆる予見がそこから作られる素材としての暴力的で一方通行的な接触も、「ふれる」ことのデザインのいち部分として再評価する途があるのではないか。
自他のあらゆる器官の間の自律的なふれあいがあり、そして個人と個人のそれが、さらにそれらの間の交絡もあるという構造の素描は、社会的ネットワークの現状認識になにか新たな展望を開くのではないか。
むしろ、器官相互のふれあいの多層的な系列のいちばん最後の”彩り”として、そして社会「という実在のあと」に、「個人」というものが立ち上がってくるのかもしれない。
といった点も気になってくる。
***
本書『手の倫理』がこれだけ様々な疑問と素朴で拙い思考を呼び込むのは、触覚という、とても身近でありふれているけれど誰にとっても特別な行為・現象に決定的にあたらしい光が当てられたゆえだだろう。
すぐれた視点と明快な分析で「ふれる」と「さわる」の、また道徳と倫理の境界線に沿って流れていくような著者の思考は、今この時代にあって深く向き合わざるをえないテーマについて、読者自身のスタンスを再点検するきっかけを作ってくれる。
だってひょっとすると、いまこの瞬間、人間とウイルスが同じ場所で「共生」していることも、広い意味での「ふれあい」となんら変わるところがないのかもしれないし。
※…厳密には「遠心性コピー」と「随伴発射」として知られる信号の出処は複数のレベルで存在し、具体的に感覚情報処理系のどこに届くかも様々あり、現在も研究の途上のようだ。仮にタコの足に十全な知覚能力があったとして、接触のどの段階でどの部分の認知がどういう形で打ち消されるのか/打ち消されないのか、また打ち消されたという体験・表象がどのようなものなのかは、(そして仮にタコの足に人間のような統合的な意識と呼べるものがあった場合にそれをどのように感じるかは、)このあたりの機微にかなり依存しそうである。https://bsd.neuroinf.jp/wiki/%E9%81%A0%E5%BF%83%E6%80%A7%E3%82%B3%E3%83%94%E3%83%BC
頂いたサポートは、今後紹介する本の購入代金と、記事作成のやる気のガソリンとして使わせていただきます。
