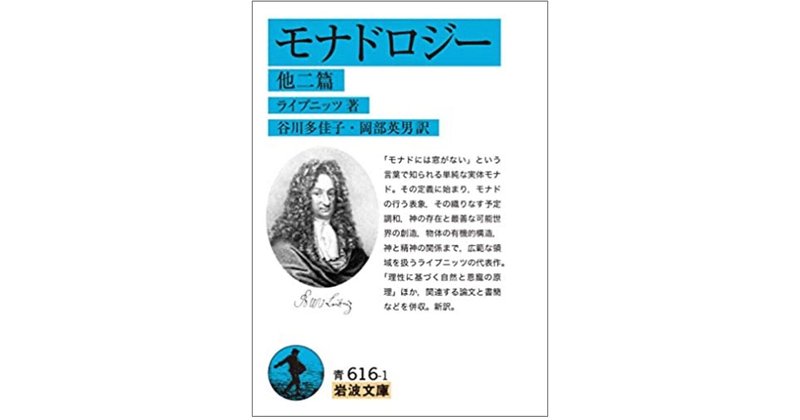
科学と神の出会う場所~ライプニッツ『モナドロジー』
この短い一篇のうちに、美しく壮大なスケールの宇宙観が稠密に織り込まれ、無限小から無限大へと余すところ無く展開されている。
哲学者であり、それ以上に偉大な科学者・数学者であったライプニッツの主著である『モナドロジー』は、世界の実在性とその認識原理を説く、近代哲学の重要書である。本書は学術論文として出版されたものではなく、文通相手に自身の思想を明確に噛み砕き、体系的に表現するために編まれたものであり、岩波版でも100p強と小ぶりである。本書には、ゆえに『モナドロジー』以外に数編の論文と書簡が収めてあり、その内容や成立背景を立体的に理解することを助ける構成になっている(目次は以下)。
モナドロジー
理性に基づく自然と恩寵の原理
実体の本性と実体間の交渉ならびに魂と身体のあいだにある結合についての新説
付録
物体と原動力の本性について(抄訳)
ゾフィー宛書簡
ゾフィー・シャルロッテ宛書簡
生命の原理と形成的自然についての考察,予定調和の説の著者による
コスト宛書簡
ブルゲ宛書簡
ダンジクール宛書簡
―「目次」
内容は難しいといえばたしかに難しいのだが、変に小難しい術語と蛇行する文章を書き散らしているようなものでは一切ない。その思想が目指すところへ向けた最短距離を寸分も違えずに明証な論理を通しており、表現されるものの複雑さに比して、表現そのものはむしろ驚くほど簡潔である。そして2019年版のこなれた新訳であることも読解の一助となっている。
予め骨格さえ押さえていれば、充実した訳注や付録の助けを借りながら、ライプニッツの描いた世界像の輪郭をそれとなく自分の脳内に立ち上がらせるところまで行ける。
モナド論の骨組み
大きさのない微小点モナド(単子)で埋め尽くされた宇宙が、ライプニッツの構想の核である。
世界は複合的で部分を持つもので満ちているが、その複合を織りなす(はずの)単一のものは、”大きさ”を持つ以上どこまでも分割し続ける事が可能である。もはや大きさを持たない無限小の点(モナド)がここで実在の基礎として措定され、それぞれのモナドは表象(知覚的なあらわれ)を持つとされる。モナドが隙間なく充満し、その表象同士が無限に連なり相互に影響し合う系列が全宇宙を構成し変転させているが、一方でその因果の連なりと帰結はエネルギー保存則により各モナドによって予め知られており、俗に言う決定論が導かれている。そして、あらゆる因果の系列の最初を起動するのが神であり、モナドの展開の無限にありうる可能性のうちで最善のものが選び取られ、現在の世界をなしている。
こう凝縮してしまうと意味が取りにくいのだが、著者の言葉はより平明で端然としている。
私の基本的な省察は、二つのこと、すなわち一性と無限についてです。
魂は単一です。物体は多ですが、無限であって、塵のごく小さな一粒でも無数の被造物に満ちた世界を含んでいるようなものです。顕微鏡は、一滴の水の中にも百万匹以上の生物がいるのを、目に見えるようにさえしました。さらに単一性とは、分割不可能で部分をもたないにもかかわらず、この多を表現せずにはおきません。円周からのすべての線が中心に集まるようなもので、中心は大きさをもちませんが、ただ一つ、すべての側に面しています。感覚の驚嘆すべき本性は、この単一における無限の統合にあります。この統合によって、それぞれの魂は、それぞれ別個の世界のように存在し、自分のやり方で自分の視点からこの大きな世界を表現するのです。このゆえに、すべての魂は、一度存在し始めたら、世界そのものと同じく存続するはずであり、すべての魂はこの世界を映し出す永遠の鏡なのです。
―「ゾフィー宛書簡」p.132
古代からの原子論とアリストテレスの質料/形相論・個体化原理、スコラの実体論などが周到に掛け合わされている印象を受けるが、そうした大掴みな説明をどこまでも拒むようなきめ細やかさと奥深さがある。純粋に形而上学的な思弁でありながら、道徳と人倫の秩序へ向かう傾向も持っている点も、本書の魅力を一層増している。
科学の手触り、魔術のまなざし
かの思想の全体を相貌的に捉えると、どこか神秘主義的な傾きが気になって、敬遠してしまう。自分も入門書の類を読んで理解している限りではどこかそう感じていた。だが、実際に本書を読み進めていくと、その印象は全然異なったものとなっていった。
古代哲学まで遡る深い哲学への造詣と、自ら生み出しもした当時最先端の数学・物理学的成果に基づいて、卓越した着眼と論証が膨大に積み重ねられている。微小点であるモナドはもちろん自らが発見した微分法を土台とした概念であるし、運動量/エネルギー/慣性モーメントなどがモナドや物体を制御していくあり方なども、(もちろん現代物理学の見地からは誤りもあるが)ごく自然に受容できる議論として示される。
イギリス経験論と大陸合理論との対立において、合理的理性の陣営の本丸と位置づけられるライプニッツではあるが、意志の力動のもとでの表象の連結として表現される世界像はむしろ認識論ど真ん中とも言える。『人間本性論』における経験論の雄ヒュームが、その哲学的な持ち場を一切離れずに徹底的に情念の幾何学に興じたのとは対照的に、実在も観念も一挙に捉え、客観的普遍的な原理を打ち立てんとする徹頭徹尾”科学者”のライプニッツがそこにいるように見える。
他方また、そうした実証科学の論理的結合の合間合間に、ある種の神秘性が紛れ込んでいまだ息を潜めているのも、やはり確かではある。神の完全性が特殊な仕方でこの世のすべてを見渡す魔術的な視角が、自然の内在的な原理につねに向かい合っている。神に基礎づけられ、目的論的に最善へと向かう精神の動きが、自然の原理と重ね合わされ「予定調和」として一個の体系へと総合される立論は、それ自体魔術的なまでに鮮やかである。
近世までの魔術思想と”視ること”に導かれた近代について、最近高山宏の本で読んだが、ライプニッツの思想はこの話の中にきれいに位置づけられるように思う。
なぜ哲学と光学が一体化していったのかは、当時のオランダ、フランドルを抜きに考えることはできない。顕微鏡の発明、望遠鏡のレンズ磨き、そして近代地図製作術の歴史は、十七世紀前半のオランダに集中している。とびきりの表象の問題だ。
...世界がばらばらだという絶望を認識論の深まりとして受けとめたマニエリスムは、でも世界はひとつ(であってほしい) という希望を魔術思想にかけた。
―高山宏『近代文学史入門 超英文学講義』Kindle版 LocationNum.774
まさにその17世紀、若きライプニッツも発明されたばかりの顕微鏡に傾倒していたという。『モナドロジー』においても、顕微鏡を初めて実用化したレーウェンフックが幾度となく引き合いに出され、レンズごしに見える微小な世界がモナド論を彩っている。そこから科学的な視座と同時に、神秘的な遠近法も引き出し、それによる世界の結合を企てていたとすれば、本書はさらに一段と興味深い論になる。
こうして、安易な対立図式のうちに見落としていたより込み入った局面を、本書の至るところに敷き詰められた煌めくようなアイディアの数々は直接知らせてくれる。カントの単なる一里塚として捉えるには、まったくスケールが大きすぎる、のである。
関連記事
事物の無限分割性に異を唱えたのが、現代量子力学。
ライプニッツ、ヒューム、カント。
頂いたサポートは、今後紹介する本の購入代金と、記事作成のやる気のガソリンとして使わせていただきます。
