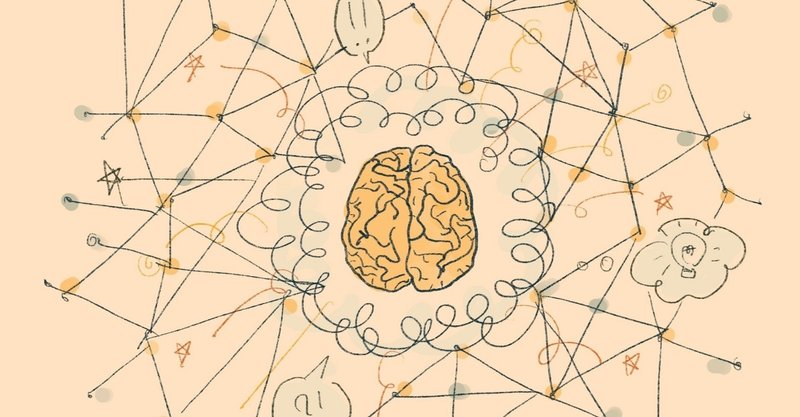
文学の意義、開かれた"読み"~『批評理論入門―『フランケンシュタイン』解剖講義』
これは良かった。すごくよかった。小説を読む全員に、ぜひとも一冊ずつ持っていてほしい。
「批評理論」の格好の入門書
文学作品の読解と批評の技法として発展を遂げてきた「批評理論」。この領域が本格的に産声を上げたのは18世紀末と、意外にも歴史は浅いのだが、現在に至るまで様々な理論が提出されており、素人にはややとっつきにくい。
本書は、そうした批評理論の全体像や、各理論の成立過程と概略を「批評史」として素描していく。ここまでなら類書にもよくまとまったものはあるのだが、本書は文学の古典『フランケンシュタイン』を題材にして、紹介したばかりの理論をこの1冊にどんどん適用していく。批評史の舞台の上で紹介される各理論を通して、同じ一つの作品がどんどん切り刻まれてゆき、そのたびに新たな読みが立ち上がり、『フランケンシュタイン』を取り巻く世界や時代精神が立体的に見えてくる。同じ作品という1つの連続性のなかで目まぐるしく読者の世界像が更新されていくことは、こうした独特な形式で編まれた本でなければ実現不可能であるし、初学者にとっては控えめにいって衝撃的な体験であった。
内在的アプローチと外在的アプローチ
著者はまず批評の技法を、小説内部の材料のみを用いて分析する「内在的アプローチ」と、小説の外部の材料(著者や他作品、文化、社会、etc...)をも分析対象とする「外在的アプローチ」に大別する。
前者は形式主義(フォルマリズム)と呼ばれるもので、本書ではまるまる前半すべてを使って、小説を構成する要素とそれらが作品にどう効果的に埋め込まれているかを明らかにしていく。ストーリーとプロットの違いに目を向けること、語り手の信頼性を注意深く分析すること、提示と叙述の使い分けを通して作者が各局面をどう読者に読ませようとしているかを見破ること。提示される要素のそれぞれは、言われると確かに作者は当たり前に考慮するだろうなというものなのだが、本格的に作り手の側に回ったことがないと気づけないものが多い。そしてこうした読解が、『フランケンシュタイン』における大量の実例を重ねながらどんどん進んでいくので、抜群にわかりやすい。自分も小説はかなり読んできた方だが、恥ずかしながら本書で取り上げられる基本的な視点の多くをほぼ意識だにせずに読み飛ばしてきたし、これらを知ったあとには確かに読みの深さと幅が変わった。もっと早く本書に出会っていればとほぞを噛む。
後半は様々な批評理論がよりコンパクトな形で示されていくが、こちらも作中における具体的な読解を伴走させていくため、イメージが湧きやすい。それぞれの理論の説明や系譜的な整理は多少犠牲にしているところもあろうが、少ない紙面の中で効果的にまとめてくれており、「批評」という行為そのものの全体や問題点に迫る思考を促す書かれ方にもなっている。このあたりは、以前紹介した筒井康隆『文学部唯野教授』も併読するとより奥行きが出る(こっちはこっちで、それ自体が小説になっているという、とてもチャレンジングな批評論である)。
文学を読む意義
過去に書かれた文学作品を読み、その面白さを受け止め、印象を語る。趣味の世界としてはそれだけである種成立してしまうものについて、理論的枠組みを通して分析する意義はなんだろうか。
本書を読むと、作品のうちに込められた意味を味わい尽くすということだけでなく、その時代を彩るメディアや文化、諸価値のネットワークの中に作品を位置づけることの重要性がわかってくる。作品を取り囲む外側の材料を通して作品の内側に入っていく理論がある一方で、文学作品という時代の<産物>を通してむしろその時代と精神とを解釈していく技法が発展してきた。文化批評、新歴史主義、マルクス主義批評などは、読者・批評者に自らのイデオロギー的枠付けに自覚的になることを求め、作品や社会、時代を相対化していく。
こうした意味合いのうちに文学作品を捉えると、歴史学の名著E・H・カー『歴史とは何か』を思い出す。カーはこの本の冒頭で「歴史的事実とはなにか」と問い、本書全体を通して「客観的な史実が存在する」という読者の思い込みを手際よく解体していく。「カエサルがルビコン川を渡る」という事実が皆が知る”史実”になる過程で通る様々な恣意的なフィルターや歴史学者たちのバイアス。避けようのない現在あるいは当時の価値体系による色メガネ、はたまた歴史の”創作性”、問題となるのはそうした事態の数々であった。こうした歴史的事実は、本書の各理論が解釈しようとする文学作品と好対照をなしている。様々に枠付けられた作者や読者、流通チャネルと解釈者たちによって特定の歴史的地位を得る古典を読み解いていくことは、複雑な精神史/観念史のネットワークに分け入り、歴史として探求していくことに繋がる。
また、歴史的事実と文学作品との間の差異もまた、重要な側面である。本源的な形式としてフィクションであること、それ自体創作性をはらむものであることは、世界を見通す切り口の鋭利さにおいて、先んじていると思われる。自分としては、神話の人類学などを持ち出すまでもなく、『孤独な散歩者の夢想』における晩年ルソーの”方法的”夢想や、中世神秘主義哲学、道化・奇想、錬金術などが果たした歴史的意義を挙げずにはおれない。こうした価値解釈の奇妙奇天烈なツールセットは、一面的でない世界の見方を読者に促す、歴史的事実にはない大きな美徳ではないだろうか。
文学作品を読解し批評するという行為が、こうしたことと地続きであると、本書は教えてくれる。
読むという荒野で
本書にあって、流石に無理矢理すぎじゃない?と思える理論(フェミニズム批評やフロイト的批評などはそう感じた)や、相互に反目する理論同士も、それぞれ重要なものとして併置されている。本書に一貫して流れているのは、外に開かれた多様で豊かな読みの蓄積の可能性は、それ自体とても重要で尊重すべきことであるという精神である。
どんな粗末な”読み”であっても、それが他の誰かが少しでも作品のうちへ、あるいは世界のうちへ深く潜っていく足がかりになる部分があれば、その言説には価値がある、と。無理やりにでもそう捉えると、その読解の仕方が正しいのか悩みながら日々拙いレビューを投下している自分なんかも、少しだけ背中を押されているような気がしてくるのだ。
頂いたサポートは、今後紹介する本の購入代金と、記事作成のやる気のガソリンとして使わせていただきます。
