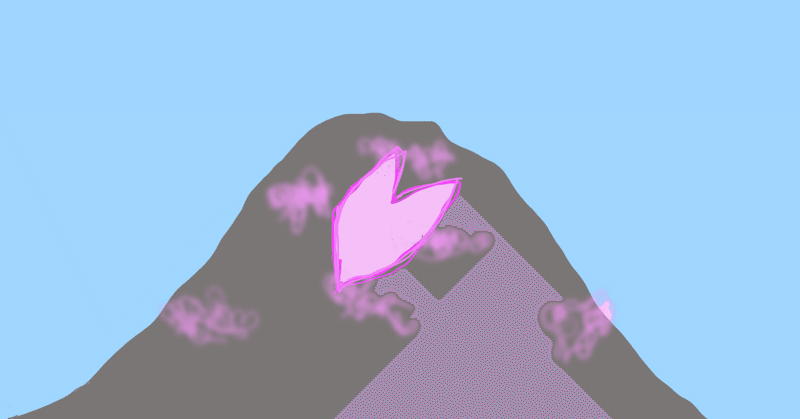
秘めるが桜【掌編小説】
おぼろ山には毎年、桜の花が咲く。
ふもとから見ると、山の中腹あたりの木々の間から、淡くかすむピンクの枝が顔を出している。あちらにもこちらにも、まるで気まぐれな春の女神の、落としたハンカチのように。
ちいさな小さな山だから、散歩がてら、一度は咲いているところを見に行こうと思っていた。
公園や河川敷にも桜はあるけれど、どことなく埃っぽくて、酔っ払いが浮かれて騒いでいたり、カップ酒の空き瓶が落ちていたりする。桜の妖艶な神秘は感じられない。やっぱり、喧騒から離れたところで桜と向かい合ってみたいのだ。そうでなければ本物とは言えないんじゃないだろうか。だって、下界の桜は、誰かが愛でるために植えたものなのだ。それならまがい物じゃないか。
道路は山を回り込んで向こう側へ続く。車を降りてほそい山道を入り、思いがけず険しい傾斜を、体を這わせるようにして登る。ときどき見通しのきくところがあれば、ふもとを見下ろして、その景色から自分の位置を確かめる。毎年眺めて、桜の位置は頭に入っているのだ。ここからならそろそろ桜が見えてもおかしくないはず。もうすこし、上か。
とつぜん空がひらけた。これ以上登れないと困ったところで、すでに頂上だと気がついた。
ちいさな小さな山なのだ。すこし真剣に登ればあっという間に登り切ってしまうのだ。
では、桜はどこに?
慎重に足場を確かめながら、こんどは斜面を下りていく。
「……あっ、これ」
しばらく進んだところに、桜の足跡を発見した。
花弁だ。緑の茂みに引っ掛かった、ほんのささやかな、薄桃色のつぶやきだ。
あわてて見上げる。首をめぐらせ、白く浮かび上がっているはずの、その枝を探し求める。
木々は黒くうっそりと頭上に覆いかぶさっていた。
結局どんなに探しても、桜の木は見つからなかった。
手にはたった一枚の花びらが残る。
遠くふもとから眺めやれば、すましてふわりと雲がかるような、淡くピンクにかすむ枝。
花は媚びない。
おぼろ山の桜は、幻惑する。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
