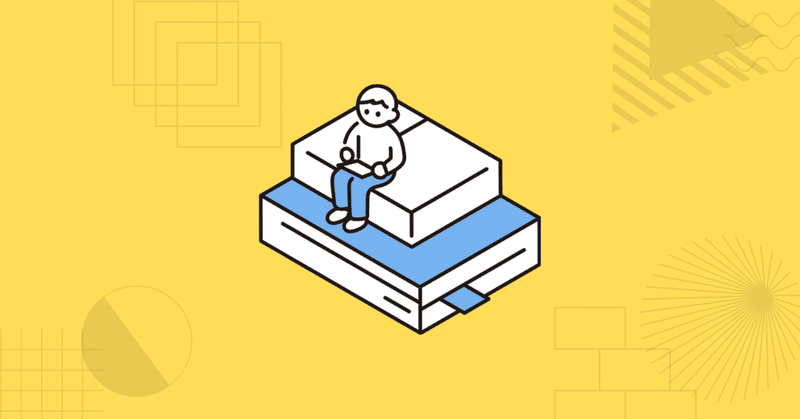
『クリティカル・ビジネス・パラダイム』を読みました。
著者の山口さんは視点がユニークで、本書も読んでいて非常に刺激を受けるものとなりました。
今まで社会運動がなぜビジネスになるのか?という点について私自身は無理解でしたが、なるほど、今までの延長線上にはすでに成長要素は存在しないとか、今後は共感性が必要になるなど言われると、確かに、とは思います。
また、この本の良いところは、問題を問題としてのみで終わらせず「どうしたら自分の確信している課題が共感され大きな社会変革が生まれるか」といった手法論にも言及しているところでしょう。
「小さな問題も、啓蒙と共感により大きな問題となり、解決へのスピード感が上がる」といった考え方や、「小さな問題もグローバルでとらえることによって大きな市場が形成できる問題となる」といったスケール論などについても、多く参考とできるところがありました。
上記のほかに覚えておきたい内容がありましたので、簡単にメモしておきます。
現状のAS-isはTo-beが思い描けようが描けまいが同じである。To-beを思い描くことで初めてAs-isとのギャップが生まれ、問題を認識できるようになる。
顧客の言うことを聞かない、むしろ顧客が正しい要求ができるよう、教育や啓蒙を進めて正しいフィードバックを得られるようにすることが、本当の意味での顧客志向である。
小さな問題も「啓発」と「共感」の拡散により大きな問題となり、解決へのスピードが上がる。
物的な要求が満たされている現在、「より環境に適応した消費生活を送りたい」「他者の問題を解決したい」といった新しい欲求や快楽が生じている。
とりあえず手元にあるものではじめる。失敗しても失うものはその手元にあるものだけ。
ローカルでは対象となる人数が少なく、普遍性の低い問題であったとしても、とも、グローバルにあまねく存在する問題としてとらえれば普遍性が高まる。
アクティビストに必要なのは「今は認められていないが、このアジェンダは必ず多くの人の共感を得るものになる」という確信。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
