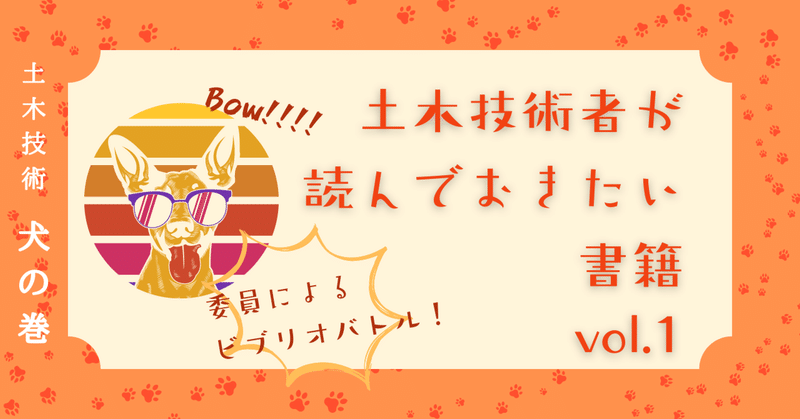
土木技術者が読んでおきたい書籍 ~委員によるビブリオバトル~ vol.1
若手土木技術者のみなさん、こんにちは!教育小委員会の上嶋です。
毎日暑いですね。暑い日には涼しいところで読書して自己研鑽してみてはどうでしょうか?
ということで、今回から犬の巻「土木技術者が読んでおきたい書籍~委員によるビブリオバトル~」がスタートしました。
栄えある初回に紹介する書籍は、『日本文明の謎を解く-21世紀を考えるヒント(著者:竹村公太郎)』です。
土木学会誌で半年に一度「私の本棚(若手会員も読みたくなる、読んでおきたい土木の100冊)」という特集が組まれているのをご存じでしょうか?この特集は「若手会員に読ませたい土木の100冊」として2021年4月号から開始されたもので、今回の書籍はその第1弾で紹介されました。土木学会誌での紹介文はこちら⇩⇩
地形・気象と関わる社会インフラを基に、 筆者独自の視点から日本人や日本文明に関するさまざまな謎を解き明かす 1冊。文明や国民性を地学的に見る、ユニークな文明論。日本で牛車や馬車が発達しなかった理由、あなたはなぜだと思いますか?
この本を紹介してくれた井川委員からのコメントです。
書籍紹介の第1弾なので,どの書籍が良いか土木学会誌「わたしの本棚」を眺めて見たところ,何冊か読んだことがある本,会社の本棚にある本がいくつかありました。
その中に見覚えはある表紙だけど,内容が思い出せない本が全く手をつけていない状態で自宅の本棚にありました。
自分で購入したのかも記憶に無い本であり,「わたしの本棚」や目次などを見てみると面白そうな内容だと思ったので,今回は「日本文明の謎を解く-21世紀を考えるヒント」を紹介したいと思います。
この本では,社会インフラを気象や地形,歴史や文明などの視点を組合わせて解釈をしています。非常に興味深い本だと思います。
私たちが生活するためには,社会インフラが必要不可欠です。社会インフラは文明とともに進化,発展を繰り返し現在の社会インフラになっています。
現在の私たちが知っている社会インフラ,私たちの知らない歴史や文明などが組み合わさり,自分の知らないことや新しい発見があり,楽しみながら読むことができました。
私たちが知っている有名な社会インフラ,歴史,文明などが多いため,本を読むことが苦手な人でも読みやすい1冊だと思います。
この本は、元建設省河川局長であった著者が月刊「建設オピニオン」に連載した38篇から15篇を選び単行本として出版されたものです。内容はとてもとっつきやすくて読みやすい本でした。私が面白かったのはこちら⇩⇩⇩
・徳川家康は当時大湿地帯であった江戸を開発して都をなぜ築いたのか?江戸に入り、家康が探し当てた「宝物」とは??
・ローマ帝国衰亡は水道インフラの発達が原因?水道によって日本人の命が脅かされたことがあった??
・ピラミッドの正体は治水事業?有明海の「からみ」干拓との共通点とは??
・タクシーの自動ドアや全自動麻雀卓が開発されたのは、日本が島国で雪国だから??
土木技術者が多彩な視点から社会インフラ整備を日本の歴史や文明を絡めて言及する一冊です。タイトルや表紙はなんだか難しい内容のように感じますが、切り口がユニークで気軽に読める本です。掲載されている15篇の中にあなたの興味のある内容がきっとあるはず。ぜひ書店や図書館で手に取ってみてください!!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
