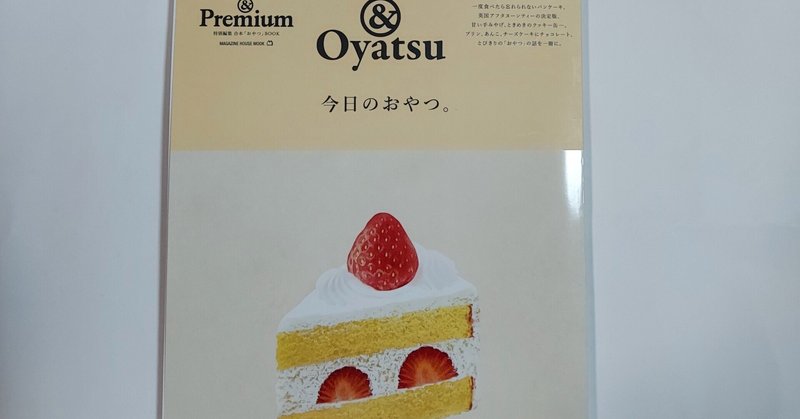
【雑記】 3/26 美容院のお供本。雑誌の魅力
今日はお休み。美容院に行きました。
そこそこまとまった時間になるので本を持参しますが、その本選びに悩みます。
条件は、あまり集中しなくても読める軽めの本で、ある程度文字が大きいこと。
途中でメモを取ったり付箋を貼ったりしたい類の本は美容院向きではないのと、裸眼視力が0.1無い私が眼鏡をはずすと単純に文字が見えないからです。
しかし、今日は、美容師さんが持ってきてくれた雑誌が「当たり!」だったのでそちらを読んでおりました。
雑誌は、いつも適当に美容師さんが見繕ってくださるのですが、家庭画報、婦人画報が出てくると、私にとっては当たり、なのです。特集によってはサライもOKです。
料理や収納など実用系の雑誌は、メモ取れないのがもどかしいですし、等身大のファッション誌の「服やバッグや靴、メイクなどは、今はこうあるべき」という圧に委縮してしまいます。
一方で、家庭画報などハイクラス向けの雑誌だと、紹介されている物やレストラン、旅行プランなどは、自分とかけ離れすぎていて、美しい写真や記事に憧れはしても物欲は湧かないので遠い国のおとぎ話レベルで楽しいのです。
「雑誌」は、今まで自分が興味のなかったことや知らなかったことに出会うきっかけを与えてくれる「未来のタネ」を拾う場だと思っています。
本日『家庭画報』2023年4月号 桜花爛漫 から拾ったタネ。
1.連載 季節のオノマトペ/山口仲美氏「わくわく」
「わくわく」と「どきどき」の違いについて。
あなたは4月からの新しい生活に「わくわく」していますか?「どきどき」していますか?どちら?という問いかけ。
緊張や不安の交じり方の違いということ。
進級などを控える子どもや異動する人に聞いてみると適切にフォローができるかもしれません。
2.連載 健気な草花たち/小林浩幸氏
「キュウリグサ」について。
忘れな草に似ているけれど、もっとささやかな青い花。忘れな草として詩歌に歌われたものの中には本当は「キュウリグサ」が混ざっているのでは、との指摘。
うーん、「ワスレナグサ」のロマンティックな名前に比べて「キュウリグサ」では詩にしにくいですよね・・・。イヌノフグリとかヘクソカズラとかもう少し名付けなんとかならなかったのか、というもの、野山の草花には多いです。
3.大阪造幣局の桜の通り抜けと「桜画」の世界
造幣局にあるたくさんの桜の品種について、桜守の方々の取り組みとともに紹介しています。
そして、この記事で江戸時代中期に桜だけを描く「三熊派」という60年ほど続いた流派があったことを知りました。
三熊思考に始まり4人の画家が桜の品種や銘木を精密に繊細に描いたそうで、その描かれた品種と造幣局にある品種を比較する記事などを興味深く読みました。
4人のうち2人は女性絵師とのことで、「桜画」のことをもっと調べてみたくなりました。
4.日本全国いちご図鑑やいちごパフェ
イチゴ、可愛くて美味しくて私も大好きです。
春が来たな~という感じがして幸せになります。
5.香川漆芸の技を取り入れたフランク ミュラーの時計
溜息が出るほど美しいです。これはほんとに高値の花。。。
6.広告面から、カステラの福砂屋の卵供養について
福砂屋さんでは、カステラの重要な原料のひとつ、卵に感謝するために「卵供養」を行っているそうです。
鳥インフルエンザの影響で鳥たちも沢山処分され、卵も値段が高騰しています。そんな今だからこそ目に留まった情報です。日々何気なく使っている食材ですが、卵にも鶏にも感謝してありがたく頂かないといけないですね。
これらの拾ったタネから興味をもったことを調べたり、関連した本を読んだりして、今まで知らなかった世界を知るきっかけとなります。
今の時代の中で「雑誌」は苦戦しているようで歴史のある雑誌が休刊・廃刊になっていっていますが、色々な話題が散りばめられた雑誌という形態は魅力的なんだけどなあ、と思っています。
*見出し写真は最近購入した雑誌
やっぱりイチゴが魅力的
