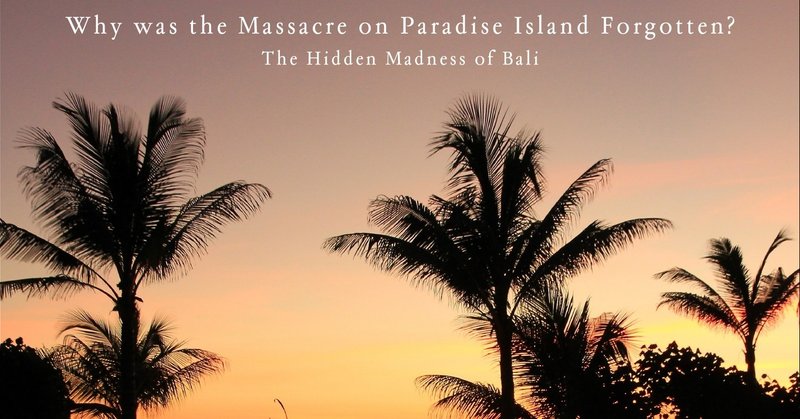
ダークツーリズムへの誘い
(2020/08/11記)
非常事態宣言こそ解除されましたが、息苦しい毎日が続きます。
想像以上に過酷だったコロナ禍とステイホーム。旅行や出張どころか、日々の通勤通学、買い物といった気軽な外出さえままならない。正直、こんな事態を経験する日が来るとは、夢想だにしていませんでした。
逼塞を余儀なくされた読書人の間では、カミユの『ペスト』(新潮文庫:八二五円)がずいぶん読まれました。石弘之さんの『感染症の世界史』(角川ソフィア文庫:一一八八円)や速水融さんの『日本を襲ったスペイン・インフルエンザ』(藤原書店:四六二〇円)なども多く手に取られたようです。
それは即ち、初めて直面する事態に当惑した現代人が歴史という人類の「経験」を訪ね、拠り所を求めたということだったのでしょう。
今回ご紹介するのは、まだ時間はかかるでしょうが、いずれ事態が沈静化したとき、ぜひ訪れて欲しい、人類の苦い旅路の記録です。
そこには現代を生きる我々にとっての得がたい学びと、生存への手がかりがあります。書物によって歴史を知り、その場に身を置くことで人類の経験を自らの体験にする。再び、旅する自由を手にする日のための準備運動としてご参照いただければ幸いです。
こうした試みはダークツーリズムと呼ばれ、すぐれた入門書も出版されています。
たとえば『ダークツーリズム入門』(イースト・プレス:一六五〇円)や『人類の悲しみと対峙する ダークツーリズム入門ガイド』(いろは出版:一五四〇円)などは、写真や読みどころが豊富で、このテーマを知る上で格好のテキストと言えます。
単なる「戦跡めぐり」と勘違いされることもあるダークツーリズムですが、実際には近現代につながる問題のルーツをたどるというコンセプトから、災害や貧困、差別や核、公害、巨大事故など、人類が経験し、あるいは生み出してきた様々な出来事に光を当て目を向けることを目的としています。
両書に挙げられた延べ一〇〇箇所以上にのぼるリストは、まさに人類の「負の遺産」マップといっても過言ではないでしょう。
以前、何度かインドネシアのバリ島を訪れたことがあるのですが、先頃、倉沢愛子さんの『楽園の島と忘れられたジェノサイド』(千倉書房)を読み、あの、光あふれる南の楽園にかつて凄惨な大量殺戮の嵐が吹き荒れたこと、独裁政権によりそれが半世紀にわたって隠蔽されてきたことを知った衝撃は非常に大きなものがありました。
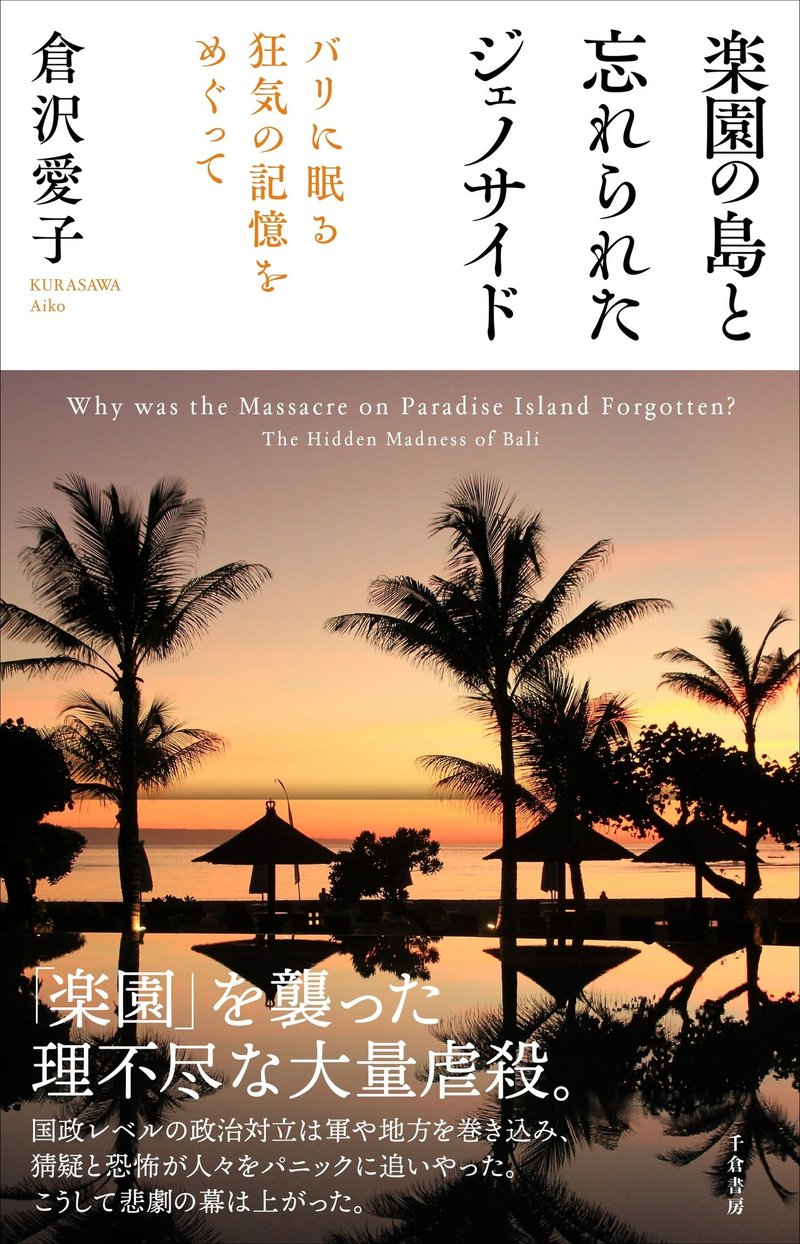
観光の折、談笑しつつ歩いた野辺やビーチに、きちんと供養することさえ禁じられた多くの人々の遺体が現在も埋まったままだというのです。改めて訪れたとき、以前とは風景が一変して見える予感がしています。
アジアではもうひとつ、一九七〇年代に発生し、当時の全国民の四分の一から三分の一が犠牲になったとも言われるカンボジアの大虐殺とキリングフィールドを忘れるわけにはいきません。
国家が国民を殺戮するという不条理の背景に、山田寛さんの『ポル・ポト〈革命〉史』(講談社選書メチエ:一七六〇円)の力を借りて迫り、ポル・ポト派のその後を調査した長瀬一哉さんのすぐれたルポルタージュ『クメール・ルージュの跡を追う』(同時代社:一六五〇円)を読むことで、大国のエゴやイデオロギーの犠牲となった三〇〇万にも及ぶとされる人々の命運に思いを馳せるのです。
日本では、近代化の過程で悲劇的な公害病に襲われた熊本県の水俣が挙げられます。
石川武志さんの『MINAMATA NOTE』(千倉書房)は、四十年以上前、病に苦しむ人々の生活を撮影した現地を再訪し、町や港の風景や懸命に生きる患者たちの変化の様子を並べて見せる野心的な写真集です。

水銀に汚染された広大な干潟は埋め立てられ、見渡す限りのバラ園になりました。いま、その場に立っても、そこが悲劇の現場であったことを示す手がかりはどこにもありません。写真の中だけに息づく光景は、私たちに無言の訴えをもって迫ります。
ヨーロッパに目を向ければ、世界を震撼させた原子力発電所のメルトダウン事故で有名なチェルノブイリがあります。
評論家の東浩紀さんが、二〇一三年から二〇一八年にかけて、同地を訪ねるツアーを主催していたことをご存じの方もいるでしょう。そのきっかけの一つとも言えるのが、『チェルノブイリ・ダークツーリズム・ガイド 思想地図β vol.4-1』(ゲンロン:一五四〇円)です。
編者の東さんを筆頭に、『はじめての福島学』(イースト・プレス:)の著者・開沼博さんや、ジャーナリストの津田大介さんを執筆陣に迎えた同書は、福島の原発事故を眼前にしてチェルノブイリがどのような意味を持ちうるのかを問い、観光に一つの活路を見いだす同地の姿をレポートします。
同書は『福島第一原発観光地化計画 思想地図β vol.4-2』(ゲンロン:上下巻kindle版のみ。各八一五円)と対をなしており、被災地に足を向ける際にはなんとしても一読しておきたい書籍となっています。
ダークツーリズム自体も研究の対象となるなか、第一人者として知られる井出明さんが二〇一八年に刊行した『ダークツーリズム拡張』(美術出版社:二七五〇円)は、ダークツーリズムを切り口に、人類にどのような世界認識の拡張が可能かを考える一冊で、特定の学問ジャンルに収まらない知的興奮に満ちています。
第一章「マレー半島で考える戦後七〇年」に始まり、途中「美術」や「食」へと脱線しつつ、第七章「満洲というプリズム」、第八章「ダークツーリズムで観る長崎」へと進んでゆく筆は、私たちがこれまで読んできた「紀行文」の常識を革新するものかもしれません。
近現代に入って人類が引き起こした悲劇は、テクノロジーの発展と共に規模を拡大する傾向にあります。あえて挙げませんでしたが、ダークツーリズムの入門書には、ほとんどすべてにアウシュビッツに関する言及があります。
ユダヤ人虐殺は、それほど人類にとって痛切な経験だったと言うことなのでしょう。
とりわけユニークなのは、近年、多方面に活躍の手を伸ばす社会学者の古市憲寿さんが、アウシュビッツをはじめ、ローマ、沖縄、知覧、真珠湾、板門店、上海などなど、世界の戦争博物館・平和祈念館をめぐり「戦争とは何か?」を問うてまわった『誰も戦争を教えてくれなかった』(講談社+α文庫:九三五円)です。
ピュアな観察眼と諧謔に満ちた筆致が交錯する本書は、アウシュビッツ・ビルケナウ博物館を前に、戦争の生み出す死や暴力を「魅力的」と断じ、ダークツーリズムを「楽しい。わくわくしてしまう」と、何のてらいもなく言い切ってしまいます。
そんな若き批評家に不快を覚える人がいるかもしれません。しかし、実際にその場に身を置いた人が感じ、発した言葉として、私たちはそれもまた受け入れる必要があります。
私はアウシュビッツを訪れる際には、本書とフランクルの『夜と霧 新版』(みすず書房:一六五〇円)を携行するつもりです。おそらくはそのどちらもがリアルだと思うからです。
古市さんは『誰も戦争を教えてくれなかった』のなかで、博物館の役割を「閉じ込めること」と看破します。
しかしその一方で、『ミュージアムと負の記憶』(東信堂:三〇八〇円)を編集した竹沢尚一郎さんたちが議論するように、一つの展示をもって「複数の意義の提示は可能なのか」、公共空間としての役割故に、その展示も「公的意味づけの再現にすぎないのか」といった、ミュージアムサイドからの真摯な応答も行われており、こうした議論は各地の展示、旧跡、遺構を訪ねる上で是非とも踏まえておくべきでしょう。
また、戦争に代表される「残酷」に「魅力」を感じてしまう人間の心理については、加賀野井秀一さんの『猟奇博物館へようこそ』(白水社:二六四〇円)という補助線を引いておきたいと思います。
メルロ=ポンティやソシュールといった近代を代表する知性が「恐怖をおぼえつつも魅惑された」、グロテスク極まる、故に「驚異」と「好奇」に満ちた華麗なコレクションを、数々の図版と共に眺めるうち、人間性の根源にある業が浮かび上がってくるようです。
同書のサブタイトルが「西洋近代知の暗部をめぐる旅」であることもどこか象徴的です。
詰まるところ、ダークツーリズムを理解する上でキーワードとなるのは「記憶」だと考えられます。
たとえば、個人としての人間が、忘却によって苦悩や辛酸から救われるケースは散見されることですが、逆に、人類の経験した悲劇や過誤にあって、最も慎むべきことは、それを忘れ去ること、なかったことにしてしまう行為だと言えるでしょう。
東日本大震災からの復興においても、被害を受けた建築物を記念碑的に残すのか、それともすべて撤去して作り替えるのか、様々な議論があったことは記憶に新しいところです。
そうした作業にかかわった建築家の五十嵐太郎さんが『忘却しない建築』(春秋社:二五三〇円)で物語る、記憶の風化に対する怖れと復興支援への想いに触れてから見る、仮設住宅や防潮堤、震災遺構の姿は、やはり別の景色と言って良いものです。
建築家の提唱する「負の記憶も含めて重層的な歴史が積み重なったまちづくり」はそのまま、ダークツーリズムを通じて人類の悲劇、負の遺産に学び、それを我が事として考えていこうとする態度と通底します。
コロナ禍を乗り越え、人類が再び旅する自由を得たとき、さあ、あなたはどこへ向かいますか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
