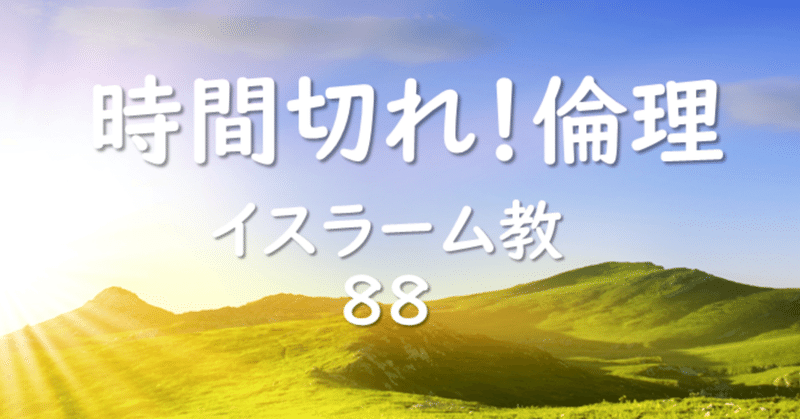
時間切れ!倫理 88 イスラームの教え 商業倫理・ハラールなど
またイスラーム教は商業倫理を重視します。ムハンマド自身が商人でしたから、商売を悪いものとは考えません。キリスト教も仏教も商業をあまり良いものとは考えません。商人は汗水たらして働きませんね。右のものを買ってきて、左に売ってその差額で儲ける。そんなことで儲けるのはおかしいではないか、というのがキリスト教や仏教の基本的な考え方です。
イスラーム教はそうではない。公正な取引で商人が儲けることは良いことだと考える。アフリカからインドネシアまで、イスラーム教は広まっていきましたが、これは商人によって広められた面が大きい。まだイスラーム教が伝わっていない地域の商人たちは、ムスリム商人がやってきて取引をするようになると、自分達も入信して、同じ商業ルールに則っとったほうが商売しやすい。こうしてイスラーム教が広まっていった面は大きいです。
ジハード、聖戦と訳します。本来の意味は「神のために奮闘努力をする」ことです。 これが転じて、イスラーム教を広めるための戦いのこともジハードというようになっています。
「啓典の民」とは、ユダヤ教徒とキリスト教徒のことです。ムハンマドは『旧約聖書』を認めています。ユダヤ教徒もキリスト教徒も『旧約聖書』を信じていますね。自分達と同じ経典を信じているということで、イスラーム教徒はユダヤ教徒、キリスト教徒に仲間意識を持って、これを「啓典の民」と呼びます。ただユダヤ教徒とキリスト教徒が同じようにイスラーム教に仲間意識を持っているかどうかは別問題です。
ムスリムの旅行者がたくさん来日するようになって、有名になったのが食事の戒律です。
例えば豚肉は絶対に食べません。これはムハンマドがそう教えているのですね。豚を汚らしい不潔な動物だと考えていたようです。豚って何でも食べるのです。昔、中国ではトイレで豚を飼っていました。便所は二階建てになっていて、 人間は二階で用を足す。豚は一階にいて、上から落ちてくる人間の便を食べていた。そのくらい何でも食べるので、不浄の動物と考えたようです。
羊の肉とかは食べても良いのだけれども、屠殺する時には、ちゃんと戒律に則った儀式をしなければならない。コーランの一説を唱えて神様に祈りながら動物の首の動脈をナイフで断ち切って命を奪う。そういう処理をしない肉は食べては駄目です。なんとなく理由は分かりますね。羊でも鶏でも命なので、神に祈りながら、苦しみを与えないように瞬時に命を奪う。こういう手続きを大事にしたのでしょう。
このような手続きを踏みながら処理した肉、これをハラールといって、日本でもムスリムが多く利用するようなスーパーでは、食材にハラール認証のシールが貼ってあって、ムスリムが安心して食べられるようにしています。
女性のヴェールなどは、特に決まりはないようです。各地域の伝統に従ってやっているだけで、イスラームの戒律ではないようです。トルコに行けば女性もアメリカ人と同じようなファッションで歩いていますね。モンゴル時代にモロッコから中国まで旅をしたイブン・バットッゥータというひとの『三大陸周遊記』という旅行記があるのですが、これを読んでいても、ヴェールに関しては地域によって違いがあったことがわかります。女性がどのような装いをするかは、イスラーム教というよりは、その地域や民族の伝統の影響が大きいようです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
