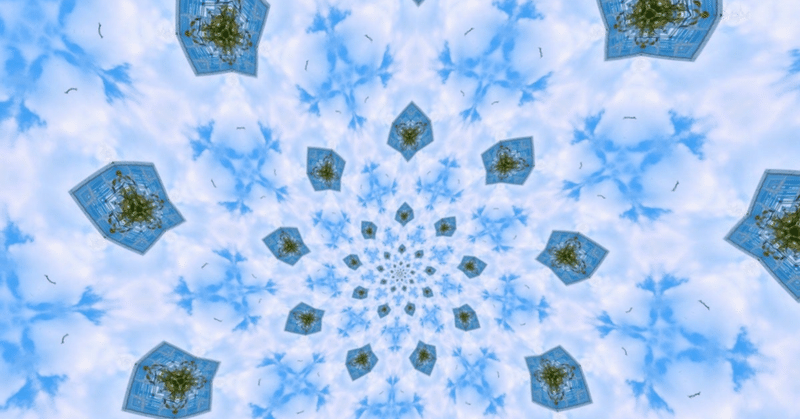
イノヴェーションが起こる時
大層なお題を書いてしまった。。。
ただ今日ふっとそんな言葉が思いつき、相手には言ってないフレーズがこれだった。
ある業務を依頼されてやり取りをしていた際、相手は恐らくこちらの作業の細かい手順や効率的なことは、わからないためどちらが良い悪いではないのだけれど、主観的な見方のすり合わせとして、編集作業の中で、残す部分と省く部分について少々議論になった。
私は省く派、相手は残す派、作業の効率や正確性、伝達性の表現を維持する最低限のこと、等々の論点からみて、一応判断したつもりだったが、私から説明をしていた時、ふっと表題の言葉が出てきた。
ああ、多分この場面では似つかわしくない言葉かも、とも思った。きっと、最近聞いた、イーロン・マスク氏の仕事方法などの影響かもしれない。
加えて抽象度の高い低い、人生や企業の戦略や世界観についての蔵書を読んで自分の気が高ぶっていたからかもしれない。何から出たのかわからないけれど、今も、「無くす」「省く」ことが、イノヴェーションの糸口につながる一つの入り口なんだという仮説の上で動いている。
思い込みかも知れない、多少は当たっているかもしれない。わからない。
でも、わからないでいいとした。また「わからない」に光を当てて、上手に付き合っていこうと思う。わかったつもりで動くと、だいたい執着につながって、執着の前提の上でさらなる思考の執着の論理式ができあがり、戻ろうとしても、最初にあったであろう他の選択肢の根っこに戻るのには相当な時間を費やすことはなんとなくわかるから。
手放して、また忘れて。残ったものも手放して。
何か残ったら、そこにヒントがある気もする。
ホ・オポノポノを学んで以来、そんな思考回路も定着してきた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
