
荷物に聴いてくれ(短編小説・改訂)
彼は日常生活の中で異様に大きな荷物を引きずって歩いていたので誰からも相手にされなかった。
その荷物を引きずって歩く姿がいかに醜悪なものであるかを彼は充分に知っていたのだが彼にはそれをどうすることも出来なかったのだ。
彼はバスに毎日同時刻に乗ってくる美しい女に恋をした。
彼女はどうやら近所の大学生のようだった。
そう、彼はバスの運転手だった。
老いた醜い運転手。
だが彼は本当は若者だった。
まだ二十四、五の青年だった。
しかし彼は老いていたのだ。
何故なのか誰にも解らない。
彼の母親にすら解らなかった。
そのことを人に聴かれるたび彼はまるで消しゴムで半分消されてしまったような煤(すす)けた笑いを漏らしてこう言った。
『知らないよ。
荷物に聴いてくれ』と…。
彼の肩に食い下がった荷物のせいで彼の運転は容易ではなかった。
異常な重力を帯びた上でのハンドルの操作は彼の腕に化け物じみた筋肉を作り、荷物の重力と圧力のために彼のいかついスチール製のような肩は歪(いびつ)な形でめり込み脊椎は激しく湾曲し、まるで西洋の怪談に出てくる傴僂男(せむしおとこ)のようなイメージを彼に与えてしまっていた。
おまけに顔はというと齧歯類(げっしるい)を思わせる何とも厭な顔立ちで、人を芯から不快に突き落とす奇異(きい)な容貌だったのだ。

彼女がバスを降りる際、
彼に向かって恐らく内気なのだろう、まるで小鳥が鳴くような声で
『ありがとう』
とどこかピアニッシモを想わせる、囁くような声で礼を言うのを聴くのが彼には堪(たま)らない悦びだったが、同時に彼女に自分の醜い姿を視られる恐怖と悲しみは彼の心臓を握りつぶし全身を針のように刺した。
ある日、彼は崖から飛び降りる思いで彼女のあの麗しくも音楽的な響きを持つ『ありがとう』に
『どういたしまして』
と、うわずり掠(かす)れたほとんど聴き取れない声で答えた。
そして浮かべない方がまだ人生ましだとでも言いたくなるほど滑稽な笑みを精一杯浮かべて彼女の顔を見た。
彼はその瞬間まさに地面に叩きつけられたような気がした。
彼女の顔が鈍い恐怖と若干の逡巡そして何よりも彼を打ちのめしたのは彼女が全身で彼に哀れみを表していたからだ。
美しいその瞳は彼の姿を映すのを拒みながらも、何処かでその感情に必死でブレーキをかけ、彼女の中で彼への生理的な嫌悪感と哀れみとが、せめぎ合い戦っているのがうかがわれた。
彼にはそれが何よりも痛手だった。
これ以上無いほど気骨(きぼね)を折って丁重に優しく、然しながらより正確にと願いを込めてねじ込んだ木捻子(もくねじ)が途中で砕け折れ、それが飛んで自らの額を割ったような気がした。
彼は今まで何度も荷物から逃れようと苦肉の策を繰り返した。
ある時は荷物を滝壺に投げ込み、ある時は燃え盛る焼却炉に投じたこともある。
そしてまたある時は船上から削岩機のごとく海底をえぐり、竜巻のように旋回する渦潮の中央に向かって棄て去り、またある時は一度入ったら二度と出られぬと言われる樹海が一望できる高い崖の上に立ち、絶望的とも言える鳥瞰図めがけて獣のように怒りの咆哮を上げながら投げ棄てたこともあった。
しかし荷物はいつも彼がハッと気づいた時にはいつの間にか彼の体の中から生えてきたかのように立ち戻ってきているのだった。
荷物が棄て去られ彼の元へ帰ってくるたびにどういう訳か一枚づつ古い膜を払拭したかのように荷物は少しずつ真新しくなっていった。
どんどん荷物は小綺麗になり、
同時に少しずつだが健康的ともいえる重さを増していった。
まるでそれは血や肉を持つ一つの肉体のようだった。
それにつれて彼の肩に掛かる重力も増し、彼の異形態振りも、いよいよ酷くなっていった。
‶俺はいつかこの荷物に殺されるかもしれない″
と彼は思った。
彼はある朝目覚めた時、
荷物がいつもより並外れて重いことに気がついた。
お陰で起き上がる時に、ひっくり返ったゴキブリのように七転八倒し十五分後にやっとの思いで立ち上がり、壁にすがりながらヨロヨロと一歩一歩踏みしめて鏡の傍(そば)へと全身全霊で歩み寄った。
確かに荷物は前よりも遙かに大きくなっていた。

彼は絶望のため息をつきながら荷物を振り返りギョッとした。
なんと荷物が幽(かす)かではあったが脈打っていたのだ。
『荷物は生きている!』
彼は目の前が真っ暗になった。
彼は暫く自失茫然としていたが、やがて、はたと気がつき夢中になって荷物を自分の肩から下ろそうとした。
その途端、彼の肩から背中、
そして腋の下にかけて激痛がピリリと走り彼の体を雷鳴のように貫いた。
彼は訳の解からぬ痛みと恐怖で短い叫び声を上げ、混乱しながら飛び上がった。
飛び上がった瞬間、またもや荷物の重みで硬いツルツルした寄せ木細工の床の上へもんどり打ってひっくり返った。
あまりの痛みに彼は最初ひっくり返ったまま目をギュッとつむり、声の出ない口を黒い穴のように開け全身をピクピクと痙攣で引きつらせた。
やがてギュッと固くつむった目尻から濁り切った褐色の病んだ老人の尿のような涙が、まるで絞り出されたかのように、強く一粒だけ胡桃(くるみ)の渋皮のように渇いた肌の上を流れ落ちた。
何故?
何故だ。
何故こんな目に遭うんだ?
俺より悪い人間はもっといるだろう。
決して人を許さない人間、人を軽蔑し小莫迦(こばか)にすることによってしか自分の曲がった優越感を満たせない人間、何故神は彼らではなく俺を罰するのか。
何故?何故だ。
理由はただ一つ、俺は偶々(たまたま)生まれつき神にとって虫の好かない奴だった。
忌々しい見るのも厭な失敗作だったのだ。
だから俺は権利を奪われた。
だから俺は人生を荷物なんかに乗っ取られようとしている。
今まさに……!
今まさに!乗っ取られようとしているのだ。
彼は声を出して荒れ野に棲む獣のように哭(な)いた。
しかし彼の母親は、彼の部屋の戸を叩こうとはしなかった。
彼の母親は彼の年子の兄に全ての希望を掛けていたので、もう彼のことはすっかり諦め切っていたのだった。
ああ、彼女に逢いたい
彼は胸に痛く想った。

逢って俺のこの苦悩を洗いざらい全部打ち明けたい。
彼女に総てを聴いて貰えたなら、そしてもし受け入れられて彼女の胸に固く抱き締められ思いっきり泣く事が出来たなら…
俺は…もう死んでもいい!

彼の心は痛んだ。
そう、まさに心が痛んだ。
彼は心が痛むということは実際にはあり得ないことだと思っていた。心が痛むのではなく実際には心臓が痛むのだと思っていた。
何故なら心というものほど不確かで曖昧なものはないからだ。
それが痛むなどとは、ただの切ないロマンティシズムから生まれたどこか甘ったれた比喩に過ぎないと思っていた。

人は酷く悲しかったり辛かったりすると少なくとも通常の状態ではなくなる。
精神状態はもとより肉体上もかなりの変化が現れる。
喉が萎縮し、心臓がドキドキし胸苦しく、そして最後には正確に『痛い』とはいえないかもしれないがそれに近い圧迫感と軋(きし)みを心臓の辺りに感じるのだ。
それはその人間が興奮状態に陥るために生じるノーマルな反応であって『心』が痛むという物語的な喩(たと)えはただの感傷論に過ぎない、彼はずっとそう思っていた。
しかし、今、実際に心が痛むのだ。

そう、もしかしたら医学的にもこの何十年か百年か先の未来、
‘’心の実在”というものが問われるようになるかもしれない。
目には見えないが、だいたい心というものが人間の体のどこら辺にあってどのくらいの大きさを持つものなのか、心に血液型のような個人による差異はあるのか、
いずれにしてもこれだけは彼には解っていた。
心は熱を発するものなのだ。
まるでラジウムのように。

たとえそれが心などではなく、
あくまでも脳というセンシティヴで尚且つ複雑な映写機が創り出す壮大なプラネタリウムのようなもので、心という独立したものは、脳無くしては決してあり得ない、と医師や学者達がいくら弁を奮ったとしても、俺の矮小な頭脳はせめてあやふやな心のほうを信じたいのだ。
まるで目には見えない不思議なものを信じるように、
その中へ埋没して逃げ込める何か深遠なものを求めるかのように、
だって脳なんて信じたところでなんになる?
こんな俺の頭脳を信じたところで
ますますこの世界が虚しくなるだけじゃないか、
痛い痛い頭蓋骨の中で俺はずっと独りぽっちだったというのに…。

彼は暫く泣き疲れ、その後は呆(ほう)けたようにそんなことをひっくり返ったまま考え倦(あぐ)ねていた。
自分の絶望的な運命を今や他人事のようにそっちのけにして違う夢想から夢想へと軽々とさながら飛び石の上を跳んで渡る子供のように彼は無限の扉から扉へと知らず知らずに飛び移っていった。
しかし彼は思った。
転々とあちこちに預けられていた幼少時代も俺は酷く寂しかったがある施設に預けられていた頃、
その施設の屋内にまるで公園にあるかのような本当に立派なブランコが建っていて、それにガキの俺が座って揺れている時にいろんな夢を見たものだった。
あのブランコに座って日がな一日揺れていた頃は自分も世界も全部が揺れて、揺れて…。
壊れた振り子みたいに自分がどこか別の地点にそのうちひび割れた青空を突っ切って飛び移ってゆくだろうと容易に信じることが出来たんだ。
今はそう夢想することすら叶わない。
ブランコの上から見た施設の天井にペンキで描かれた引き千切られた羊のような、たどたどしい白い雲が浮かぶ青空が粉々に自分の上に砕け落ちてきて、でもどんな色も、どんな形も、どんな一致も、どんな不一致も、どんな賛美も、
どんな揶揄(やゆ)も、どんな道徳心も、どんな自堕落も、どんな均衡も、そしてどんな時代の破片も、一滴の声すらも、
俺の上には落ちてはこない。

どんどん砕け散り、そこから見える空は更に青く、青すぎるほど青く、まるで歴青(チャン)で出来た空にパイプを造る時のようにツルツルに磨き立てた海泡石の雲がわざとらしいほど愉快にピカピカ、
キラキラ、ニヤニヤ、
たくさん浮かんでいたんだ。
まるでピアノ線でどこからか吊り下げられたように、それらは俺の中でまるでチェシャ猫のように生き生きと優しく笑いかけながら、時にクレッシェンドに、
時にデクレッシェンドに、
揺れていたんだ。
するとその青すぎる空から白すぎる鳩が翼ではなく白すぎる腕を伸ばし、その輝かしい腕に掴まると俺はがらんどうの施設の吹き抜けを置き去りにして冷たい灰色のブランコからやっと自由に羽ばたき寂しい独りぽっちの沸点から別の汀(みぎわ)へと飛び移り、まるでフラッシュをたいた瞬間のような光の速度で俺は今の世界を別世界へと変えていけたのに…
今は何も変えられない!

まるでヒヤシンスの球根から飛び出した根のようなものが彼の荷物の表面から何本も白いミミズのようにニョキニョキと生え、それが更に彼の肩口から、背中一面、
そして腰に届くほどの広範囲をびっしりと覆っていた。
その白い根は彼の寝間着のリンネルを通り抜け皮膚を突き抜け彼の筋肉の基底層にまで到達し、
今やしっかりと根付いていた。
とうとう荷物は彼の躯(からだ)の一部となったのだ。
いや、彼が荷物の一部になったのかもしれなかった。
いずれにしても彼より荷物の方がずっと立派で見栄えもしたからだ。
俺は神の創り給うた大いなる失敗作だ。
そう、大いなる失敗。
ただのそこいらの如何物(いかもの)とはわけが異う。
神は俺に盲判(めくらばん)を捺した訳じゃない。
心血を注いで創造した挙げ句、
最後の最後で仕上げをとちったのだ。
そう、それは可成のものだった。
その最後の些細なミスひとつで、神の今までの努力は水の泡になるほどそれは俺という被造物全体に大きく響いた。

そう、大きく響いた。
もう手の打ちようがなかった。
修正不能の被造物は、修正の手を施せば施すほど新たに深刻な傷を増していった。
やがて神は諦めた。
そして、神はやがて俺を通して、自分に、そして俺に、無意識的なまでに常時ヴォワイヤン(視者)として生きる運命を与えたのだ。
そのことを通して、神は人間に近づき俺は神に近づくのだ。
もしかしたら神はそうやって孤独な自分を罰しているのかもしれない。
目を背けたくとも決して背けることの出来ないこの醜い俺を通して…。
俺は寵児だ。
神の御落胤(ごらくいん)だ。
この醜い傴僂男を神は愛してやまないのだ。
なんてこった!

俺のこのふためと見れない醜い姿はまさに神の痛いほどの偏愛の顕われなんだ。
彼は突然爆音のような嗤い声を上げた。
寄せ木細工の床の上でひっくり返ったまま身をよじらせて嗤った。
突然の不気味な哄笑に、部屋の外にいた母親と彼の優しい兄とは思わず不安な目と目を見合わせた。
さっきまで泣いていたかと思ったら今度は沈黙、今は嗤っている。
母親は流石に彼の身を案じたのか彼の部屋の戸を怯えながらそっと叩いた。
笑い声はピタリと止んだ。
そして少しの間冷ややかな沈黙が守られ、その後不可解なバタンバタンというまるで一人相撲でもしているかのような音が暫く続き、やがてドアがギィっと重々しく軋んでわずかに開けられた。

そのほんの少しの隙間から彼の青黒く鬱血して泣き膨れた、平素よりもいっそう醜く自分よりもはるかに年老いた息子の顔が覗いた時、母親は虚を突かれて思わず後退った。
『なんだい?』
まるでウシガエルが啼いているようだ、と母親は思った。
『あなた、大丈夫なの?』
彼女は口の中が急速にカラカラに渇いていくのを感じた。
喉の奥に薄い膏紙(あぶらがみ)を貼り付けられたようで彼女は唾を飲み込もうとしたがその唾すら出ず、すべらかに声を出すことがどうしても出来なかった。
『泣いたり笑ったり何かあったの?』
『なんでもない。』
『なんでもないってあなた……
ちょっといつもより様子が変よ。』
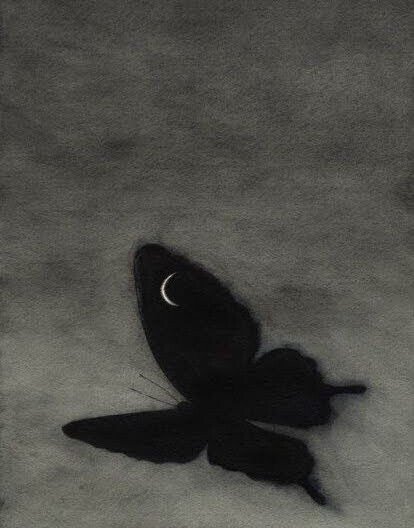
そう言い終わって彼女は思った。
いつもより……そう、いつもよりずっと変だ。
いつも変だが今日はもっと変。
彼は異様に前につんのめって、
それも小刻みに今にも倒れそうな樹のようにユラユラと揺れている。まるで立っているのがとても重労働だとでも言わんばかりだ。
『なにがあったの?
どうしたの?』
そう言い終わって母親は、息子が頼むから二度とそんな顔はしないでくれと言いたくなるような笑みをニタッと浮かべるのを見た。
そして次の瞬間、彼女は益々、
後退って、やがて彼女は独りでどんと音を立てて背後の壁に追い詰められた。
突然、息子が狂ったように自分のパジャマを目の前で引き裂き始めたからだ。
そしてすっかり裸になると彼はかなりの時間をかけてゼイゼイと苦しげに肩で息をしながら、ゆっくりと後ろを向いた。
そして母親に自分の背負っている荷物を見せた。
荷物はその異常な重さでやや彼の肩からずり落ちてぶら下がっていた。
そしてまるで巨大なチーズが糸をひいて粘り下がっているかのように白い神経のような根っこが無数に彼の肩や背中からニョキニョキとミミズのように生え、その荷物としっかり繋がって彼の躯からねっとりとぶら下がりまるで生きものの尻尾ように息子から独立した自らの意思でユラユラと不気味に揺れ動いているのを母親は見た。
その白い根っこのようなもので荷物は彼の躯からぶら下がり支えられ辛うじて落下を免れていた。
"こんなもの!
重さに耐え切れなくなって下に落ちてしまえばいい!
でももしそうなったら……
俺は死ぬかもしれない“
と彼は思った。

‶こいつは今や俺にとって駱駝の瘤(こぶ)のようなもので、決して取り去ることが出来ない代物なんだ″
彼は瘡蓋(かさぶた)だらけの歪んだ唇を噛んだ。
‶こいつのお陰で俺は命を保っているようなものだ″と…。
そして背後に母親の怯えたような甲高い悲鳴を聴いた。

『なにそれは!?なんなの?
一体?あなたそれ一体どうなっちゃったの?』
“彼女はいつも俺に質問ばかりする”
と彼は思った。
“俺の質問には本当に答えてくれたことは一度だってなかったのに。
彼女はいつも俺に無理な質問ばかりする”
彼はため息をついて言った。
『知らないよ。
荷物に聴いてくれ。』
翌日、また翌日と、荷物は日増しに育ち、彼はもうバスの運転手を辞めて部屋に閉じこもってばかりいた。
母親は食事を持ってくる以外はもう部屋に近づこうともしなかった。
母親は自室に閉じこもったきり全く外に出てこなくなった息子の事を考えた。
“あれ"は本当に私の息子なのだろうか?
もしかしたら誰か悪意ある人に赤ん坊の時にすり換えられたのかもしれない。
私の本当の赤ちゃんは何処か知らない土地で元気に美しく、そして悧巧な青年に育っているのかもしれない。
彼女は畳の目を数えながらゆっくりとお茶を飲んだ。
畳の目を数えるなどという、
およそ誰も考えもつかないなんの役にも立たない不可能なことを彼女はそうと気づかず完璧にやってのけた。
畳の目は7兆6億2千あった。

彼女は、ふと自分の飲んでいる冷え切った緑茶に浮かぶ茶柱がすっくと立って浮かんでいることに唐突に気がついた。
昔、茶柱が立っていると良いことが起きる、と私は信じていた。
年寄りの言うことをみんなが信じた時代があったからだ。
私も娘時代その中に居た。
迷信や様々な貌(かお)を持つ神々に見守られた時代の中に…。
そして今やその時代の記憶だけが圧倒的な私の背景となって私を守り支える一枚岩として今の私の価値観を支え、私を生かしているのだ。
私は、私の系譜を見たことも誰かに訊いたこともない。
識ろうと思えば識れるのだが誰もそんなことに興味など持たない、なんのドラマもないと思っているからだ。
そしてその通りなんのドラマもない。平和に朴訥に生きることにドラマなど必要だろうか?
その時代に生を受け、育った人間は皆そういう人ばかりだ。
近所の顔見知りの中で育ち、
謎は何ひとつ無く、偶さかあっても指のささくれを見つけるようにそれらは治る。
当たり前のように両親、家族の中で食べて寝て覚めてやがて文句を言いながらも巣だつように。
周りも皆、退屈かもしれないが深刻に傷つくことも傷つけられることもない互いに優しい人々ばかりだ。
変革を厭い、時代の生んだ価値観に追従し、それを決して曲げようとしない意固地だが穏和で地道な善い人ばかり、

悪人はいない。
私が降服を望んだのは、それが一番他者からの好意的情感や共感あるいは時にはわずかであっても助力を受けるのに容易かったからではあるまいか。
と言うよりは降服以外のものがその頃の女達には何も無かったからかもしれない。
そう、勝利以外の勝利が世の中ではまるで何もないように…。
自由闊達な夢は成人後、全て奪われ私たちはハイエナのように下を向いて歯を食い縛って生きてきた。
何故歯を喰い縛らなければならないのか。
そんな必要も特に無かったであろうはずなのに。
若い頃の私はそのようなことについて思弁してみたことなど全く無かったにも関わらず無自覚にいつも耐えてきたのだ。
私はただ、自分もまた、他人の人生においてもまた、波風立てず平穏に生きられたならそれで良かったので、人にも自分にも余り期待も持たなかったし同時に無関心に近かった。
本など読んだこともなかったし、音楽といえばたった一つエリーゼの為にしか知らなかった。
そのエリーゼの為にを一体誰が作ったのか知らない。
そんなことに興味など無い。
でもそれが一体なんなんだろう?
いろんな音楽を知り本を読んだとしても莫迦で不幸で薄っぺらいインテリはたくさんいる。
私はただ幸せな主婦で妻で母になりたかっただけだ。

自分自身に全く無関心という訳では無かったが、自分を超える何か大きな力が在り、私はそれがただ一体何なのかもよく理解しないままに見えない力によるその巨大な鋳型に形造られ、または決して自分の意には染まぬものの堅牢で安全にと目の前に敷かれたレールの上をただただ周りと一緒に走り、抜きつ抜かれつもなく足並み揃えて走る、それが何よりも大切だった。

そのことについて疑ってみたことなど露ほども無かった。
つまり個人としての自分の展望や野心にはそれほど興味が無かったのだ。
もう既に大体先が見えているような気がしていたからかもしれない…。
自分は何よりも周りの一部でなくてはならなかったから…。
自分は小さな小さな歯車の一部なのだ。
歯車はいつも適切に動き皆と異(ちが)う動きをしてはならない。
それでも私は一度だけ変革を望んだ。
それは私自身が望んだのでは無かったのかもしれない。
私の愛する人が望んだことだから自分も望んだと錯覚していたのだと思う。

デモ隊のリーダーに恋をしたことがあったからだ。
左翼の女と言われるのが嫌で私は恋が終わった後そのことをじっと胸に秘匿し続けた。
今までどんな親友にもどんな恩人にもこのことは決して言わなかった。私は誰にも何も言わず夢も見ず愚痴もこぼさなかった。
その私に何故あんな子供が産まれなくてはならなかったのか。
私が何をしたというのだろう。
何もしなかったではないか。
私はただの一人の温和(おとな)しい女でしかなかった。
だから罰(ばち)が当たったとでも言うのだろうか。
私は誰にも言わなかった。
親友にも恩師にもそして家族にも私は逆らわなかった。
私は心を地中深く埋めて石のように謐かで温和しい女だった。
罰せられる理由はそれ以外他に何も思いつかない。

神は、熱くもなく冷たくもなく生ぬるい人間を一番嫌うという、
だからかしら…と彼女は思った。
彼女は茶柱をぼんやり見つめながら心の中で泣きながら叫んだ。
『だからあんな子が私に与えられたというの!?』
そして次の瞬間彼女は深い深い、ため息のような、
重い重い石の棺の戸が立てる軋轢の音のような、
遠く昏い海で鳴く鯨の声ような、洞窟の奥から響いてくる何者なのか解からない謎の声のような…。
そんな不思議な声を聴いた。
慟哭とも咆哮ともつかぬ不気味な声を聴いた。
それは紛れもなくあの畸形の息子の上げた声に違いなかった。
いやいや違う、と彼女は心の中で否定した。あれはもう畸形という痛ましい人間に起きた悲劇を感じさせるものなどではない、
あれはもうなんなのか解らない。あれはもう紛れもなく『人間』
ではない。
一体『あれ』はなんなのか?
たぶん私には一生解らないだろう。

『あれ』は人間にしろ化け物にしろ、果たして本当に現身(うつしみ)なのかどうかも私には解らない。
深く長く怖ろしい慟哭が止むと、彼女は暫く時間を置いてからゆっくりと重々しく立ち上がった。
そして二階に上がり息子の部屋の戸を叩いた。
何も応答がない。
もう一度叩いた。やはり何も返ってこない。

彼女は息子がふた目と見られぬ醜悪な悪鬼と化して目の前に躍り出てくるのではないかと怖れながらも思い切って扉を開けた。
部屋は暗く厚いカーテンが閉ざされていたが、カーテンの隙間から射す明るい昼間の光によって部屋の中は薄ぼんやりとではあるが正確に見ることが出来た。
誰も居ない。

彼女は息子が何処かに隠れていて突如おぞましい半人半獣のような姿で今にもどこからか飛び出してくるのではないかと思い、心臓が横隔膜の上で踊り狂ったがその平和な静寂はいつまでも続いた。
部屋の中にはスズメの啼く声だけがまるで映画のワンシーンのように優しく同時に空々しく響いていた。
息子の名を彼女はその時まで辛苦に対する日にち薬のように忘れていたが急に思い出すと二、三度呼んではみたもののやはり応えは無かった。
彼女は思い切って息子の部屋へと入った。
そしてカーテンを一気に引き開けた。
カーテンは彼女が立てた悲鳴のような音を立てて開きその瞬間、眩しい純金の光がまるで煌めきの洪水のように暗い室内に溢れかえった。
窓がわずかに開いていた。
彼女は押入の中、タンスの中、と隈(くま)なく調べたが息子の姿はどこにも無かった。
在ったのは例の荷物きりだ。
荷物は非常に巨きくなっていた。
‶まるで人独りぶんぐらいの大きさはあるわ″と母親は思った。
よく見るとあの白い根っこのようなものが引き千切られたように荷物の表面に干からびて垂れ下がり、荷物の周りにもいくつか枯れた粗朶木(そだぎ)のようにパラパラと散らばっていた。
きっと荷物が余りにも巨大になり過ぎてこの白い根っこで支え切ることが出来なくなり、とうとう千切れてここに落下してしまったのだろう、と彼女は推測した。
息子はもしかしたら荷物から逃れてやっと自由の身となり何処かへ逃げ去ったのかもしれない。
あるいは逃げ去る途中、自分の肉体の一部である荷物を失ったことにより衰弱しどこかで野垂れ死にしているのかもしれない、
あるいは…。
彼女は顎の下にこぶしをあて、
人独りぶんの大きさの巨大な荷物を疑っと見た。
その彼女の横顔を一陣の風が涼やかに、まるで慰撫(いぶ)するかのように吹き過ぎていった。
窓の隙間から見えるアスファルトの径(みち)が遠く白く輝いて見えた。
母親は明日の主婦同士の茶話会の予定が急に頭に浮かび、それをいつもの通りキャンセルしたことを今更急に惜しく思った。
今からならまだキャンセルをキャンセル出来るだろうと彼女は思った。
そしてまだ茶柱が立っているのかどうか確かめに行こうと、階下へと足取りも軽く鼻歌まじりに降りていった。



The End
2016年note
掲載
2021年9月改訂
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
