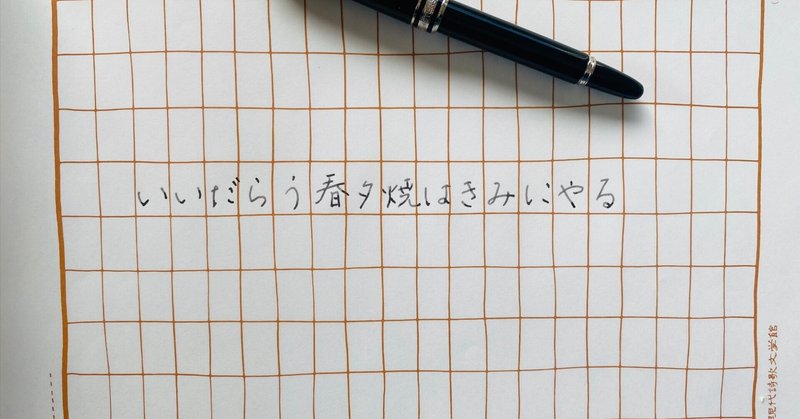
豪奢な夕焼
電車に乗っていた。
電車に乗るときは、ぼんやり外を見るか本を読むかのどちらかである。
わたしの向かいのシートにもぎっちり人が隙間なく座っている。みな手には長方形のスマートフォンを持ちそれを宙に浮かせて、指先を滑らせながら、滑らせながら何らかをみている。
スマートフォン、スマートフォン、スマートフォン、スマートフォン、スマートフォン、スマートフォン、スマートフォン、であったシートに途中で変更があった。
一人が席を立って下車して、別の人が乗り込んで来て座った。
その結果、スマートフォン、スマートフォン、スマートフォン、スマートフォン、スマートフォン、本、スマートフォンになった。
本は、そこに書かれてあることへの興味ももちろんあるけれど、わたしは本というものの実存そのものにたまらなく惹かれる。それはもう留めようのない感情で、その熱意に目減りはいまのところ見られない。
右から2番目に座った男の人の本が気になる。
わたしのこれまでの観察によると、電車の中で本を読んでいる割合が高いのは高齢男性である。次に中年男性、中年女性。この男性は中年に見えた。
ちょっと本を読むタイプと違う風貌だった。
金髪で髪の毛を立てている。左耳にはちょうどちくわを輪切りにしたくらいの太さと直径のぎんいろのピアスが光っている。革の黒いパンツはふとももにぴったりしていて、光沢がある。赤いジャンバーには金の糸で縫い取りがされていて、鷹のような鳥が大きく羽を広げている。
このような人が読む本をぜひとも知りたいと思う。
見た目で人は判断してはいけないというけれど、わたしは見た目はかなり重要じゃないかと思っている。むしろ人は見た目じゃないかと思っている。
それをくつがえしてほしいと思う。
『純粋理性批判』とか、『全体主義の起原』とか、『山崎方代全歌集』とか、『ガラン版 千一夜物語』などを次々思い浮かべて、おもしろく思う。
ちょうど本を少し持ち上げたときに表紙が見えた。
『覚えない記憶術』とある。
なんだか愛らしい、と思う。
金髪に髪を逆立てて、革のパンツをかっこうよく履いている人が、公衆のまなかで『覚えない記憶術』を読むのか、と感慨に浸る。
人って、愛らしいなとふたたび思う。
いろいろあって、いろいろやって、いろいろな人が今この車両にたまたま一緒にいて電車に運ばれている。
その中のひとりが『覚えない記憶術』を読んでいる。
この人が覚えないで記憶したいことってなんなのだろうか。
覚えないで記憶したいことがわたしにあるかな、と考えてみるけれど、とくに思いつけない。
できると言われたらやっておかないとなんとなく損だと思いそうだけれど、今のところ思いつけない。
また駅につき、左端の人が下車した。
あたらしく人が乗り込んできて空いた席に座った。その人はすぐにかばんから本を取り出して、そのせいで本、スマートフォン、スマートフォン、スマートフォン、スマートフォン、本、スマートフォン、というならびに変化した。
左の人が読んでいるのは文庫だった。
紺色の制服を着た高校生らしい女性だった。文庫は岩波で、「ほう」と思って失礼でないほどに観察する。『谷川俊太郎詩集』とある。
いいなあ、と思う。詩を読む人は、どうしたって手放しでいいなあと思ってしまう。
「朝のリレー」を思い出す。
カムチャッカの若者が
きりんの夢を見ているとき
メキシコの娘は
朝もやの中でバスを待っている
わたしが膝にかばんを抱えて、電車に乗り、前に座る人を観察しているとき、その前に座る5人はスマートフォンを覗き込んでいる。その間に座るひとりの男性は、金色の髪を天に向けて逆立て『覚えない記憶術』を読んでいる。左端に座った高校生は詩集を読んでいる。
電車はどんどん上っていく。
午後のひかりは、だんだんと夕方のひかりに変わっていく。
7人の人の座る電車の青いシートの後ろの窓には夕焼けが広がっている。
その夕焼けに目を止める人は誰もいない。
横に並んだ7人の人と夕焼けはゆっくり午後を上っていく。
そうしているこの間にも、生まれてこようとしている人がいるだろう。
そうしているこの間にも、死んでいこうとしている人がいるだろう。
その間の時間にあって、わたしたちはけして永遠でない時間をまるで永遠のように感じながら電車に揺られる。
夕焼けはますます豪奢に広がる。
わたしの並びに座っている人は、みな手の中のスマートフォンを眺めるか、頭をふかく埋めて眠っている。
誰にも見られない夕焼けは、どんどん豪奢になる。
なんというか、わたしたちはどんどん動いているのだ。
生きているということは、ずっと転がって、動いて、とどまらないのだ。
なま、なのだ。
そのなまの中で、わたしは夕焼けを見ている。
ランドセルを背負った男の子が電車に乗り込んできて、扉脇に立った。
扉のガラスから外をじっと見ている。
豪奢な夕焼けは、太古からそうであったようにゆったりと広がる。
わたしは夕焼けを見る者がわたしの他にいることに心強さを感じて、かばんから本を取り出す。
ハン・ガンの『引き出しに夕方をしまっておいた』。
わたしが本を読むのを観察する人がいるといいな、と思ってあたりを見回すけれども、そんな人はこれまで一度もいた試しがないのだった。
八歳になった子に
アメリカインディアン式に名前をつけてと頼んでみた
しんしん降る 悲しい雪
これが 子どもがつけてくれた私の名前
(「血を流す目2」)
ふと目を上げると、電車はもうすぐわたしの降りる駅に着くところだった。
窓の外の夕焼けはもう終わりの色になっている。
いつの間にか本を読んでいた男性も高校生もいなくなっていた。
わたしもかばんに本をしまって、電車を降りる。
わたしも電車からいなくなった。
夕焼けを見ていた男の子はまだ電車に乗り続けていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
