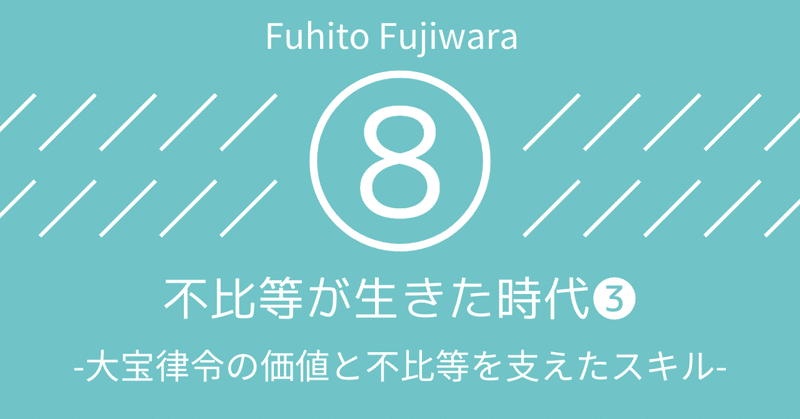
不比等が生きた時代③ -大宝律令の価値と不比等を支えたスキル-
大宝律令を完成させた藤原不比等。教科書に太字で書かれるこの用語は、日本が日本であるために欠かせないものになります。
不比等が成し遂げた大宝律令の重み
ここまで、古墳時代あたりから大宝律令までの流れを追ってきましたが。
なぜこんなに長く書く必要があったかと言われると、大宝律令というものが当時の政権にとってどんな意味があったかを知るには、ここまで戻る必要があるからだと思ったからです。
農耕の発達で集落がクニ、その実力者が豪族に。彼らの生活を支える技術は朝鮮や渡来人に依存していたため、豪族はそれぞれネットワークを構築していた
5世紀に朝鮮半島各国の争いが激化。渡来人が日本列島に定住し、技術が定着。それを囲いこんだ豪族が力をつけていき、最終的にはヤマト朝廷が力をつけ、朝鮮とのネットワークも独占
統一国家・隋が中国に登場し、朝鮮半島は緊張状態に。それに乗じて朝鮮への影響力を高めたい崇峻天皇と、慎重に情勢を見極めたい蘇我馬子が対立し、馬子が勝利。隋に使いを出す
隋では政務をめぐって非合理と断じられ、国力の強大さも痛感。ヤマト政権は国力を高め、隋(後に唐)と対等に立ち回るため、彼らに学びながら律令国家の構築を始める
蘇我氏は隋・唐・朝鮮各国とバランス良く交流するが、、唐・新羅vs高句麗・百済の構図へのスタンスの違いなどから乙巳の変が起こり、王権は中大兄皇子・中臣鎌足らの元へ
大化の改新以降、中大兄皇子と孝徳天皇が対立。そのうちに、友好国・百済が唐に滅ぼされ、復興を狙った白村江の戦いでも惨敗。日本は朝鮮・中国との交流や影響力を失い、中央集権による国力向上は政権維持のためにも欠かせないものに
唐・新羅の戦争が勃発したことで、外的脅威のリスクが低下。ヤマト朝廷でも天智天皇崩御後の動乱が落ち着き、律令体制への移行を加速
律令国家としての歩みは100年前、蘇我馬子が隋へ使いを出したことから始まりますが、なぜ隋の建国や朝鮮情勢の緊張が、ヤマト朝廷にとっても自分ごとだったのかを理解するには、その前から知っていく必要があります。
そしてこうして見ていると、(陸続きということもありますが)“朝貢国”である朝鮮各国は、中国王朝の介入の脅威に常にさらされている状態に感じます。そこにも、ヤマト政権が“独立国”としてのスタンスを取りたかった切実な理由があるかもしれません。
大宝律令は、この律令国家移行に向けた集大成。自らを律令国家として唐(当時は周でしたが)に認めてもらう、政権の安定的な存続をかけたプロジェクトだったと思われます。藤原不比等をはじめとした19人の編纂メンバーが行った大宝律令の制定というのは、ただ初めて法律をつくったということでなく、日本が独立国として存続し続けるためにも欠かせないものだったようです。
大宝律令の運用・修正
とはいえ、大宝律令はヤマト朝廷にとっては初めての律令。実際に運用を開始すると、様々な矛盾点や現実に即さないことが起こったようです。例えば703年には、一部の地域の調(地域の特産品などの納税)の品目を変更するなどしています。
また、703年から各地で大きな飢饉が発生したことで、律令で定められた税(租庸調)の運用についても、一部の減免などの適宜対応を行っています。
708年には和同開珎を発行し、本格的に貨幣経済を導入しようとします。712年には貨幣(銭)を一定額貯蓄し政府に収めたものに位を与える蓄銭叙位令を施行することで、貨幣経済の促進と政府への銭の集約を狙おうとします。(ただしこの策は、現実の貨幣流通量自体が多くなかったり、税が租庸調という現物での納税となっていたこともあったりしたため、あまり大きな成果は上がらなかったようです)
707年ごろからは平城京への遷都の計画が始動します。この計画は元明天皇期となった708年に正式決定し、2年後の710年に平城京へと都が遷り、いわゆる奈良時代が始まります。
また文武天皇存命中の707年ごろから、遷都の計画が始動します。理由はよく分かっていませんが、当時の都である藤原京が地理的に不衛生な場所にあったからという説や、より大きな都をつくる必要があったからなどの説があります。また703年に遣唐使が帰国した際にもたらされた、最新の唐(当時は武則天が「周」と改名していますが)の都の情報が何かしらの影響を与えたのかもしれませんが、それもよく分かっていません。
いずれにせよ、この計画は元明天皇期となった708年に正式決定し、2年後の710年に平城京へと都が遷り、いわゆる奈良時代が始まります。
不比等を支え続ける不遇時代に培った力
これらの一連の政策は慶雲の改革とよばれ、ここでの修正点を踏まえて、後に不比等は大宝律令の改訂版である養老律令の編纂を開始していきます。いずれにせよ、こうした現実に即した修正・調整をしていくにあたり、法律や文章に秀でた不比等の実務能力は重宝されていたようで、彼の立場・影響力は朝廷内でも徐々に大きくなっていきます。
こうして彼の業績を追っていくと、彼の朝廷内での立場を支えているのは、田辺氏に預けられていたときに学んだ読み書きや法律の能力であることがよく分かります。父と兄を幼くして失うという難しい状況の中で得たスキルですが、結果的にこれが彼の栄達を支えていくわけですから、やはり常に置かれた状況で最善を尽くすということは大事だと感じます。
次回
不比等が朝廷内で地位を高めていく過程と
政治家としての彼
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
