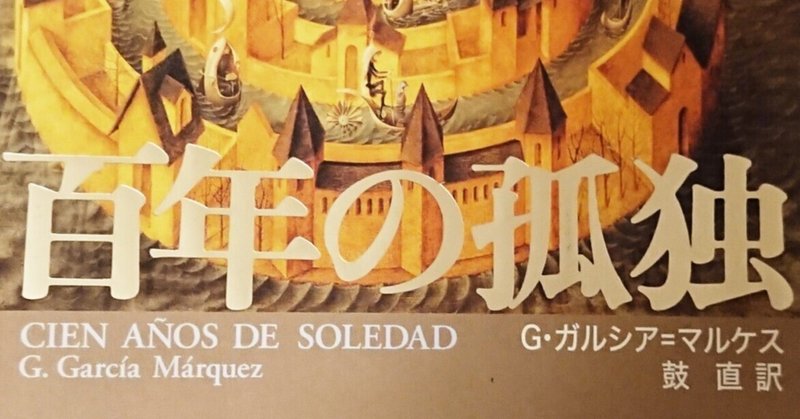
読書記録「百年の孤独」
川口市出身の自称読書家 川口竜也です!
今回読んだのは、G・ガルシア=マルケス 鼓 直訳「百年の孤独」新潮社 (1999) です!

・あらすじ
メルキアデスの遺した書によると、「この一族の最初の者は樹につながれ、最後の者は蟻のむさぼるところとなる」と記されていた。
ウルスラ・イグアランがホセ・アルカディオ・ブエンディアと結婚するに当たり、一つだけ気がかりなことがあった。彼女のいとこに「豚のしっぽ」を持つ子どもが生まれたことがあり、その二の舞いだけは避けたいと。
2人が定住することとになった「マコンド」は、時折やってくるジプシーたちから新しい学問や技術を教わる、まさに外界から遮断されたような小さな町だった。
錬金術師となったホセ・アルカディオ・ブエンディア。彼は卑金属を貴金属に変える技法や、賢者の石の研究に明け暮れ、子どもたちに全く関心を向けなかった。
2人の子どもであるホセ・アルカディオ、アウレリャノ、アマランタは父親からの愛情を注がれず、ホセ・アルカディオはジプシー達と共に放埒の旅に、アマランタは誰にも貰い手がないまま生涯を終えることとなる。
自由党と保守党が戦争になる前、アウレリャノは当時の町長ドン・アポリナル・モステコの七人の娘の一人、レメディオス・モステコと結婚するも、妻は早々に自家中毒で死んでしまう。
だがアウレリャノはそれに悲嘆に暮れる様子もなく、戦争ではアウレリャノ・ブエンディア大佐と名乗り、32回反乱を起こし、妻の名前を知らない17人の子供を持つことになる。
ホセ・アルカディオとトランプ占い師のピラル・テルネラの間に生まれたアルカディオが街の守護と統治を行う。サンタ・ソフィア・デ・ラ・ピエタと結婚して3人の子供を持つも、戦犯として殺害される。
戦争が終わりを迎えると、アウレリャノ大佐の子供であるアウレリャノ・トリステがマコンド行の鉄道を引き、小さな町に産業改革が起こる。大手のバナナ会社が設立され、人の出入りも多くなった。
アルカディオの子供であるアウレリャノ・セグンドは、街の賑わいに乗じた祭りでフェルナンダ・デル=カルピオと出会い、後に結婚することとなるが、情婦のペトラ・コテスとの関係を断ち切ることはできなかった。
バナナ会社と労働者との間で大規模なストライキが起こった際には、ホセ・アルカディオ・セグンドが先頭に立つも、軍隊の手により3000人もの労務者を死体を海に捨てることになった。
以前のような静けさが訪れたマコンド。5年に渡って振り続けた雨と、10年間の干ばつにより、もはや一族がこの地に定住する以前よりも酷い状況かに思えた。
雨が上がると共に、120歳は超えていたウルスラ・イグアランの生涯を終える。盲目でありながらも誰よりも忍耐強く生きた彼女亡き後、もはや一族の終わりは近づいていたと言える。
アウレリャノ・セグンドの子どもの一人、レナータ・レメディオスがバナナ会社の工員であるマウリシオ・バビロニアとの間に生まれたアウレリャノ・バビロニアは、孤独の中でメルキアデスの遺した書の解読に明け暮れる。
「宿命的な孤独」の運命を背負う一族。最後は「愛によって生を授かった者」の誕生とともに、マコンドという町とともに終焉を迎える。
去年の夏、図書館の覆面本企画で手に取った池澤夏樹さんの「現代世界の十大小説」NHK出版にて語られていたのをきっかけに、いつかは読みたい1冊として頭の片隅には入れていました。
それから約半年経ち、先日の神保町は「春の古本まつり」にてこの本に出会ってしまう。自称でも読書家を名乗りたいがための、ある種の意地もあったが、3週間掛けてようやく読み終えた次第。
大筋はブエンディア一族の誕生から衰退を遂げるまでの物語ではあるが、たびたび現実的な面(戦争やストライキなど)と神秘的な側面が交わる。
それ故に、読んでいて飽きることはなかったのだが、同じ名前と出来事の連鎖に、誰の話をしているのだと人物相関図を見返しては、本筋に戻るという繰り返しであった。
タイトルにもなっているように、この物語では「孤独」という言葉が何度も登場する。宿命的な孤独とも呼ばれる、呪いのような運命を背負って。
彼が自分よりもはるかに暗く、曽祖父と同じように人を寄せつけぬ、孤独の闇の世界に生きていることを知った。
「孤独」とは、必ずしも一人で生きていることではない。
家族や友人に囲まれていようと、多くの人から尊敬されようと、孤独を感じることがある。逆に人に囲まれていなくても、孤独とは思わない人もいる。
この一族の宿命的な孤独とは、いわゆる「愛の欠如」である。
子孫が生まれている時点で、全く愛がないとは言い難いけれども、それも若気の至りというべきか、愛を知らないがゆえの悲劇と言うべきか。
また、ブエンディア一族は往々にして、身内が亡くなった後の喪失感が少ない。最愛の人を失ったがための孤独がなく、その宿命を当たり前かのように受け入れてしまっている節がある。
その孤独を埋めるために、仕事に打ち込む姿もあるが、最後の最後は孤独のまま死んでいく。誰のことも愛せない者は、誰からも愛されることもないのだ。
メルキアデスの書の解読に注力していたアウレリャノ・バビロニアもまた、父無し子として家族から忘れられた存在ではあったが、最後の段になり、ようやく「人を愛することとは何か」に気づく。
もっとも、難しい話ではない。仲の良い身内が亡くなったら悲しい、最愛の人と性ではなく、愛によって育むことの大事さ。
それは、孤独を知るからこそでもある。人は誰しも孤独という業を背負っているからこそ、愛することに尊さを感じるのではなかろうか。
たとえそれが、世の中の誰からも知られることなく終わりを迎えるとしても。
読み終わった今となっては、なんとも長い旅を終えたという気分しかない。それではまた次回!
今日もお読みいただきありがとうございました。いただいたサポートは、東京読書倶楽部の運営費に使わせていただきます。
