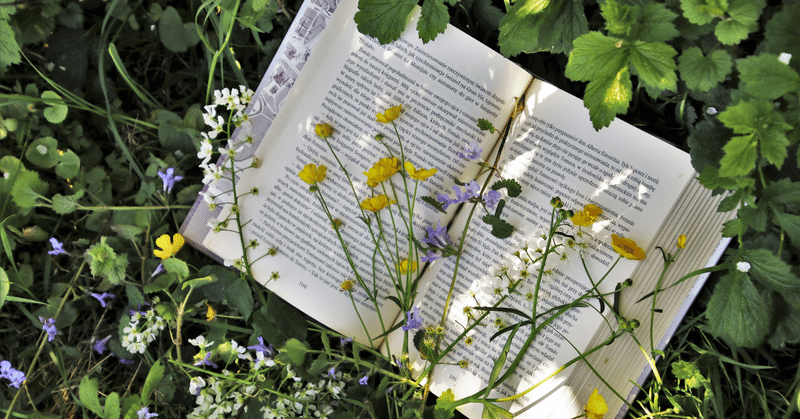
「積ん読」を解消するために|オンライン読書会というコミュニティ
「積ん読」という言葉を初めて耳にしたとき、率直に「うまい造語だな!」と感じました。
「いつか読もう」と思いつつも手付かずの状態になっている書籍を指す言葉です。
自身の場合、最近はKindleで本を購入することが多いので、物理的にはスペースをとっていませんが、ストレージの中に積み上げられた状態になっています。また、購入まで踏み切っていなくとも、「読みたいリスト」に入っている本まで数えるとかなりの量です。
思えばここ2ヶ月ほどは、ほとんど本を読んでいませんでした。調べ物の際に書籍を参照する程度だったと思います。小説に至ってはめっきり読む機会が減ってしまいました。
「本をたくさん読んだから偉い」という訳ではありませんが、やはり定期的に一定のインプットをしないと、質の良いアウトプットが難しくなります。
自身の主宰しているレッスンでもよくお伝えするのですが、インプット/アウトプットどちらかに偏りすぎてもいけないし、両者のバランスがとても大切だと考えています。期間限定でどちらかに集中的に取り組むのは良いと思いますが、長期的にはこの両輪が機能していないと、うまく進むことができません。
最近の自分を振り返ってみると、アウトプットにだいぶ偏っていたように思います。定期的に新しい学びをインプットする仕組みが必要だなと考えています。
インプットの方法は様々です。最近であれば、動画視聴という方法があると思います。誰かの話を聞く、という方法もありますよね。中でもとりわけメジャーなのは読書ではないでしょうか。場所や時間などの制限がさほど多くなく、手軽に取り組める手段です。
「積ん読」もだいぶ溜まってきたので、何とかして少しずつ読み進めていきたいなと思っています。
そんなとき、ふと思い出したのが「オンライン読書会」の経験でした。簡単に内容をお伝えすると、【複数人で同じ時間にオンラインで集まって、各々で本を読み、終了後にそれぞれの本の内容を紹介する】というものです。
一人で読書するのとは、またちがった新鮮な面白みがあります。読後に自分が読んだ内容を他の人に紹介することで、インプットした内容が頭に定着しやすいです。
「ラーニングピラミッド」でも示されている通り、単純に読書をするだけよりも、アウトプット(討論や他の人に教える経験)をした方が学習の定着率は高いと言われています。

ラーニング・ピラミッドとは、学習方法と平均学習定着率の関係を図示したもの
こうした観点からも、オンライン読書会は効果的のある取り組みだなと感じます(参加者の条件が合うのであれば、もちろんオフラインでも良いかもしれませんね)。単に「積ん読」を解消するだけでなく、それを「学び」に繋げることができたら、より一層有意義なものになりますよね。
実はかねてから自身でもオンライン読書会を主宰してみたいなと考えていました。うまく仕組みがつくれそうであれば、ぜひやってみたいです。
皆さんのオススメの「積ん読」解消法があれば、ぜひ教えてください。
みな
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
