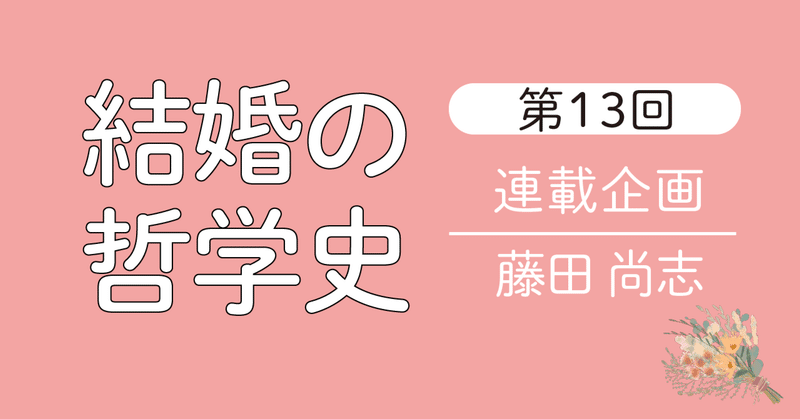
連載第13回:『結婚の哲学史』第3章 第2節 (つづき)
結婚に賛成か反対か、性急に結論を下す前に、愛・ 性・家族の可能なさまざまなかたちを考える必要があるのではないか。昨今、結婚をめぐってさまざまな問題が生じ、多様な議論が展開されている現状について、哲学は何を語りうるのか――
九州産業大学で哲学を教える藤田先生による論考。今回はキェルケゴールの「逆説弁証法」の特徴を解説し、「レギーネか、キリスト教か」という問題を考えます。
↓これまでの連載はこちらからご覧ください
***
2.逆説弁証法の二つの特徴
キェルケゴールの思想はしばしば「段階」的思考としてまとめられる。美的段階に飽き足らなくなり、倫理的段階で精進するも挫折し、宗教的段階に移行する…といったストーリーである。また、それら三段階のあいだの移行について語る際にしばしば「飛躍」ということが語られもする。キェルケゴールは自らの思考を「質的弁証法」、ヘーゲルのそれを「量的弁証法」と呼んで区別し、〈挫折による飛躍〉を具現するソクラテスの対話術に回帰しようとしたのだ、と。
だが、これだとヘーゲル弁証法と根本的に何が違うのか今ひとつよく分からない。そこでヘーゲル弁証法と対比する形で、キェルケゴール的な弁証法に迫ってみたい。ポイントは二つである。
1. 段階か領域か?
2. 飛躍とは何か?
むろんこの二つの問題は絡み合っており、完全に切り離して論じることはできないが、私が読んだごく限られた文献の中で言えば、一点目を最も明快に説明してくれているのは、藤野寛の『キルケゴール――美と倫理のはざまに立つ哲学』(岩波書店、2014年)であり、二点目を難解な表現ながら何とか示唆しようとしているのは、テオドール・アドルノの『キルケゴール――美的なものの構築』(原書1933年、邦訳:山本泰生訳、みすず書房、1998年)である。以下では、この二著に拠りながら上記二点についての解明を試みたい。
2-1.段階か領域か
藤野(2014)はその第8章「美的宗教性に打ち込まれる楔としての実存倫理」においてきわめて明快に問題を定式化しており、時に小さな異論を差し挟むとしても、大枠としてはほぼそのまま辿り直すことになる。
美的・倫理的・宗教的という三つのカテゴリーを用いて自らの思考を定位する際、キェルケゴールは「段階」という言葉も「領域」という言葉もどちらも用いている。もちろん意味内容はずいぶん異なり、「段階」は上下関係・序列関係を示し垂直性を強調する言葉であるのに対し、「領域」は並列的な関係を示し水平性を強調する言葉である。
前回紹介したジョン・スチュアートの研究からも裏付けられるように、前期キェルケゴールにはヘーゲル的ヴィジョンへの強い共感が見られる。例えば、『あれか、これか』第二部の「結婚の美的妥当性」を見てみよう。
結婚とは自由でありかつ必然であるが、しかも同時にそれより以上のものである。なぜなら初恋に際して行使される自由とは、本来的にはむしろ個人の人格がまだ自然の必然性から抜け出て純化され、意識にもたらされるには至っていない心的自由のことだからである。
ここには量(自然の必然性)から質(意識)への転化という仕方で、エロス的・美的直接性から反省による媒介を経て倫理的自由を選び取り決断するという「段階」的な思考がある。ただし、各段階を独立的・実体的に捉える粗野な段階的思考ばかりが語られていると考えるのは早計である。『あれか、これか』第一部の規定を確認しておこう。
ついでながら、ここまでのところで私が「段階」という言葉を使い、これからも引き続き使うとしても、まるで一つ一つの段階が独立性を有し、一つの段階は他の段階の外部にあるとでもいうかのように、この表現が過度に強調されることがあってはならない。あるいは、私は「変容」という表現を用いるほうが適切だったのかもしれない。異なる諸段階が相合わさって、直接的な段階を形作るのであって、そこから分かってくることは、個々の諸段階とは、むしろ一つの評価の開示であり、すべての評価は最後の段階の豊かさの中に合流するということだ。そしてこの最後の段階こそ本来の段階なのである。それ以外の諸段階は、独立の存在を持ち合わせてはいない。
いわゆる単純な段階論でないことは明らかだ。だがそれにしても、「すべての評価は最後の段階の豊かさの中に合流する」とは、その時点での最終段階(「歴史の終わり」と言ってもよい)の視座からすべての段階が事後的に評価を与えられるということであり、やはり大局的に見れば、低次から始めてより高次の段階へと成長・発展してゆくプロセスを概念化しようとするヘーゲルの歴史哲学的な発展論であることに変わりはない。藤野によれば、「この発展論的発想こそ、初期のキルケゴールがヘーゲルから――というよりも、ヘーゲルをも含む時代思潮の全体から――受け継いだものである。言い換えれば、これはキルケゴール本来の発想ではない」(藤野 2014:230)。本来のものではないので、時とともにキェルケゴールの思考のなかで影が薄くなる。「段階」という言葉は「領域」という言葉にその座を譲ることになる。
では、キェルケゴール本来の発想とはどのようなものか。藤野によれば、それは「発展の論理を取り出そうとする関心ではなく、区別することへの関心、差異への関心」(同上)に由来するものである。
区別の時代は過ぎ去った。体系〔ヘーゲル〕がそれを乗り越えてしまったのだ。我々の日々にあってなお区別を愛する者は変わり者である。
ここで言う「区別」とは、キリスト教を似非キリスト教から区別すること、より正確に言えば、真のキリスト教から、キリスト教と紛らわしいほど酷似していながら、しかしそれではないもの(美的な装いをまとうキリスト教もどき)を次々と分離し駆除していくプロセスのことである。要するに、後期キェルケゴールの思索の中心は、この区別の基準をどんどん厳格なものにしていき、デンマークのキリスト教界の中で一見それらしくキリスト教的に思えるもの、しかし実際にはキリスト教ならざるものを削ぎ落していき、真の「宗教的なもの」を露呈させていく作業であり、布教とは真逆の純化・粛正の戦いを敢行することであった(藤野 2014:231)。
たしかに、キェルケゴールは非常に早い時期から、ヘーゲルの「段階」概念と弁証法的運動に興味を持っていたが、「媒介」という概念自体を批判しようとしているのではなく、むしろ媒介が有効な領域とそうでない領域をできるだけ注意深く区分けしようとしているだけなのだというスチュアートの指摘(Stewart 2003 : 600-601)は、この藤野の分析とうまく折り合うように思われる。前期の「段階」的思考のあいだから、すでに「区別」の思考が働いていたということであろう。藤野は、段階説の証拠としてしばしば引用される『あとがき』の次の一節を「時として、彼の根本志向に反して暴走する」「区別への、差異化へのキルケゴールの執心」と捉えているが(藤野 2014:231)、第二期に達した思考を前期的・ヘーゲル的に定位したのだとすれば、それほど外れているとは思われない。
諸領域は以下のような関係にある。直接性/有限な分別/イロニー/お忍び姿としてのイロニーをともなう倫理/フモール/お忍び姿としてのフモールをともなう宗教性――そして最後にキリスト教が来る。その目印は、実存を逆説的に強調すること、逆説、そして不条理なものだ。
この前期の「段階の飛躍」から後期の「領域の区別」へという図式はきわめて分かりやすいのだが、やはり「飛躍」とはどういうことかは問われねばならない。
2-2.飛躍とは何か?
アドルノは『キルケゴール』で次のように述べている。
領域のほうが「飛躍」において動かされる。ただ諸領域が総体として変化する。飛躍とは、美的から倫理的への、倫理的から宗教的への展開を意味する――しかしそれぞれの個別的内実、すなわち性格が転換することではない。
通常「飛躍」という言葉で私たちがイメージするのは「ある領域から別の領域への飛躍」であり、したがって「領域の移動」ということだろう。ところが、領域のほうが飛躍において動かされるのだという。そして、飛躍が生じたとき、諸領域の個別的な内実(つまり美的・倫理的・宗教的といった性格)ではなく、ただ総体として変化する(美的から倫理的へ、倫理的から宗教的へと展開する)のだという。どういうことだろうか。
アドルノの『キルケゴール』で印象的な言葉は、「佇立」である。〈その場で動く〉(aufder Stelle Bewegen)〈弁証法的に動く思考が領域の中に留まること〉(in der Sphäre Verbleiben des dialektisch bewegten Gedankens)である。〈先へ進む〉ではなく〈立ち止まる〉、過程ではなく休止・息継ぎ(Cäsur)。自己はめぐりめぐる反復の中に停滞し、佇み続ける。「断続的な休止 intermittierenden Zäsuren」(Adorno 1962 : 149)のうちで展開する「断続的弁証法 intermittierende Dialektik」(Adorno 1962 : 142)をアドルノが多くの場合、キェルケゴールの弁証法を「領域弁証法」(Dialektik der SphärenあるいはSphärendialektik)と呼んでいるのもこの佇立的な性格と関係しているのかもしれない。
このような視点から、つまり佇立的含意に注意しながら、藤野が引用しているルカーチのテクストにおける「区別の精神とでも呼ぶべきものをキルケゴールの思考の急所をなすものとして浮き彫りにする表現」を読み返してみよう。
キルケゴールの哲学の最も深い意味とは、生の絶えず揺れ動く移り行きの中に固定点を、溶けゆくニュアンスの混沌の中に絶対的な質の差異を定めることだ。そして、異なっていると認定された物事を一目瞭然に深く異なるものとして提示し、いったん区別されたものが、いかなる移行の可能性によってぼやけさせられたりすることがないようにすることだ。こうして、キルケゴールの誠実とは、次のような逆説を意味するものとなる。かつて存在した際を最終的に止揚してしまう新たなる統一性へとすでに癒着してしまっていないものは、永遠に、互いに区別されたままにとどまる、ということだ。
区別について論じていると飛躍とはどのような事態なのかという話につながり、逆もまた然りである。だからこそ、私たちは最初に逆説弁証法の二つの特徴を完全に切り離して論じることはできないと述べたのである。
さらに正確を期するならアドルノは、ヘーゲルには領域内在的弁証法しかないのに対し、キェルケゴールにはそれに加えて領域間の「飛躍」の弁証法もあるという。主体が或る領域から飛躍する場合、領域自体には変化は生じない。あくまでも特定の領域に内在する主体に変化が生じるだけである。先にヘーゲルの章で引用した有名な『精神現象学』序論の一節をもう一度思い出そう。
しかし死を忌避し、荒廃から免れてあろうとする生ではなく、死に耐え、死にながら自己を維持する生が、精神の生である。精神は、自己自身が絶対的に分裂した状態で自己自身を見出してこそ、自己の真理を獲得する。精神がこの威力でありうるのは、それが否定的なものから目を背ける肯定的なものであるからではない。(…)むしろ精神の威力は、否定的なものに面と向かってそれを直視し、そのもとに身を置くという、まさにこのことだけによっている。この身を置くことは、否定的なものを存在に転換する魔力である。この力は,さきに主体と呼ばれたのと同じものである。
否定的なもののもとへの滞留、どんなに怖くても目を逸らさない、恐るべき死から目を背けないというのは、キェルケゴールと同じである。違うのは、「否定的なものを存在に転換する魔力」が主体そのものだという視点である。そのような英雄的な倫理性が主体に備わると考えられるくらいなら、キェルケゴールがキェルケゴールである必要はなかっただろう。また同時に、諸領域総体が変わることと「反復=受け取り直し」との根本連関を考慮に入れるなら、藤野が「否定性の哲学者キルケゴールの発言全体の中でも、特異な、例外的な、きわめて珍しいもの」でありつつも、「彼の思考を終始一貫して背後で支えるものだった」と評価する『イロニーの概念について』の次の一節は重要な意味を持つ。
キリスト者は戦いのもとに、疑いのもとに、痛みのもとに、否定的なもののもとにとどまるのではない。そうではなく、勝利を、確信を、至福を、肯定的なものを享受するのである。
これに対してキェルケゴールの「飛躍」が私の考えるように「佇立」なのだとすると、私自体が諸領域であり、私の中で諸領域総体が変化するのであって、私自身は変化しない。アドルノはこの著作の別の文脈で(Adorno 1962 : 61)、intérieurというフランス語を用いて、主体の「内部」と、キェルケゴールの著作内でそれを比喩的に表現しうる「インテリア」の二重性に注意を促しているが、今私たちが問題としている(私自体が舞台となっている)文脈においても機能する語かもしれない。
主観が、そしてその具体的な個人の人生が、その間を媒介するのではない――主観をその舞台とし、その内部で、領域は過ぎ去り、別な領域が開かれる。
主観を舞台とし、その内部で領域が過ぎ去り、別の領域が開かれるとはどういうことだろうか。倫理的な領域にいると思い込んでいたのに、未だ美的な領域にいたのだと悟る瞬間がある。苦い思いとともに理解する。私は一歩も動いていなかったのだと。だが、そのように未だ自分は美的な領域にいるのだと分かること自体が、美的なものと倫理的なもののより深い「区別」を行なうことなのではないか。次の一節でアドルノが「総体としての諸領域の衝突」と呼んでいるのは、そのような「区別」を行なうという主体の行為であるように思われる。
総体としての領域たちがぶつかり合う「衝突」の連関は、彼の領域弁証法の図式を与えてくれる。
ただし、そのような「区別」は決して完全に主体的・能動的・意識的なものではありえないだろう。「キェルケゴールの弁証法は、その根源においても、その展開においても、それのために構想されたはずの人格を飛び越えてゆく。そして自律的自我の支配要求は否認される」(Adorno 1962 : 137-138)。だからといって、ヘーゲル的な「媒介」のような積極的無限性なのでもない。ヘーゲルにおいて、プロセスの連続性に「意味」が与えられるのは或る意味で「神的」というほかない絶対的な事後の観点からのみである。これに対して、キェルケゴールにおいて無限の総体性は、限りある人間の意識には拒まれている。したがって諸「領域」は総合の手を逃れる。有限の場ではただ「区別」がなされるほかない。ヘーゲルとは異なり、矛盾はもはや概念=無限の総合の中に止揚されない。私は引き裂かれたまま、佇立する。この総体的矛盾とその引き受けが「飛躍」と呼ばれているのではないか。
以上のような「飛躍」についての理解が仮に正しいとして、藤野が「区別」について指摘している次の二つの特徴に対して、私たちはさらにそこに「佇立」の側面が見られることを確認しよう。
1)美的なものと倫理的-宗教的なものの区別
キェルケゴールの宗教性とは、外部の世界の体験が機縁を与えるものではなく、もっぱら自己自身との関係、悪に染まった自己自身との関係に定位して、宗教が経験の地平に現れる(倫理的な問題を回路として宗教と出会うという意味で)倫理的な宗教性であり、その侮れない脅威となるのが美的宗教性である(藤野 2014:236)。
キェルケゴールが「美的なもの」をキリスト教にとっての脅威と見なすのはなぜなのか。それは、彼が「美的なもの」の核心を「観照」という姿勢、つまり「利害関心とそれへの気遣いのうちに囚われる人間の制約されたポジションからの脱却」を目指す(よく言えば中立的、悪く言えば無関心な)態度のうちに見てとっており、「解脱」などの脱俗的・超俗的な言動のうちにある宗教的なものと少なからぬ共通点・親和性をもちうることに危険性を感じ取っているからである(藤野 2014:237)。
2)人倫と実存倫理
では、美的な宗教性と倫理的な宗教性のあいだで楔として機能し得るものとは何か。それこそが実存的な姿勢である。藤野は「実存」という言葉がキェルケゴールにおいて二様の意味で用いられていることに注意を喚起する。一つは「生」「生き方」「人生観」といった通常の事実記述的な意味であるが、もう一つは「自己の否定的現実という強い意味」であり、この場合は規範的な意味が込められている。この後者の意味の場合、「美的に実存することはありえない」(藤野 2014:238)。美的に生きるか、実存的に生きるかという二者択一こそキルケゴールが迫るものである以上は。
さらに言えば、この実存倫理は、自己自身の徹底した凝視とその否定的現実との対決を求める際に、「他者との関係、社会との関係を二の次にすることを辞さない、いやそれどころか、それを捨象することを要請しさえする」「異様な倫理」である。異様だというのは、倫理学は通常、カント的道徳やヘーゲル的人倫も含め、社会の中で他者との共同の生を実現するためのものとされるからである。
この特異な倫理は、普遍性を志向し、他者との関係、社会関係の調整をこそ関心事とする通常の(人倫という)意味での倫理概念から、きっぱりと差異化されていなければならない。この個人の倫理、単独の生の倫理が、倫理概念から普遍性の契機を切り離すことでどのように獲得されていったのか。『おそれとおののき』における思考実験はその中心的ドキュメントであった。
以上、ヘーゲル弁証法との対比を念頭に置いて、キェルケゴールの弁証法の特徴を見てきた。だが、肝心の「逆説」についてはまだほとんど触れられないままであった。これについては、次節の『おそれとおののき』読解の際に合わせて解説することにしよう。
3.レギーネか、キリスト教か?
本節の目的は、キェルケゴール的な思考の本質について、ヘーゲル的な弁証法との差異化を図りつつ、それを逆説弁証法として特徴づけることであった。それ自体はおおむね達成できたと思うのだが、次の第三節でキェルケゴールの結婚論を展開していくうえで、一つ気懸りな点がまだ残されている。それは、以上の概略を読んで、「キェルケゴールはレギーネとの結婚とそれに伴う現世の世俗的幸福を諦め、キリスト教信仰の純化に専念・邁進した」という風に理解されてしまっているのではないかという懸念である。もしそのように理解された方が多いとすれば、それはまったく私の望むところではないので、最後に「レギーネか、キリスト教か」という点について話をしておきたい。なお、私がここで参照するのはキェルケゴール研究ではなく、アウグスティヌス研究である。具体的に言えば、山田晶『アウグスティヌス講話』(初版:新地書房、1986年。講談社学術文庫、1995年)中の「アウグスティヌスと女性」という重要な講演である。
宗教と愛
古来、偉大な宗教者の中には、女性との不思議な関係のある人が多い。古いところでは釈迦、新しいところではキェルケゴール。釈迦は、王城の中で非常に幸福な生活を送っていたが、外に出て生老病死という四つの苦を見て無常を感じ、可愛い妃を捨てて出家したと伝えられる。キェルケゴールはキリスト教会の番兵たる使命を感じ、番兵がどうして妻を持つことができるかと思い詰め、可愛い許婚者のレギーネ・オルセンを捨てたと言われる。こうして彼らの女性との関係は、たいてい「悲劇」に終わっている。だが、その「悲劇」が彼らを宗教的にも人格的にも深いものにする重要な契機になっていることは疑いえない。ただし、彼らが例外的な天才だから、日常のモラルを容易に破壊できたわけではない。凡人と同じ苦しみを果てしなく苦しみ抜いたからこそ、何千年にもわたって人の心を打つのだ、と山田は述べる。
アウグスティヌス(Aurelius Augustinus, 354- 430)は、キリスト教徒の母モニカ(聖人)と異教徒の父パトリキウスの子として、北アフリカのタガステ(現在のアルジェリア東部)に生まれた。若い頃から弁論術の勉強をし、370年頃からローマに次ぐ大都市カルタゴへ遊学。同年、父が死去(死の直前に受洗)したが、この頃ある女性と同棲するようになる。当時を回想して「私は肉欲に支配され荒れ狂い、まったくその欲望のままになっていた」と『告白』で述べており、身分上の障壁のためか正式に結婚することもなかったが、ほぼ15年間彼女と共に暮らし、アデオダトゥス(Adeodatusラテン語で「神の贈り物」の意)という息子(372-388)をもうけ、女性に対し「閨(ねや)の信実」を守った、ともアウグスティヌスは述べている。
ところで、この女性との関係が、アウグスティヌスの運命を決定したのだ、と山田は言う。アウグスティヌスの有名な『告白』は、実は例の女性に捧げられているのではないかと思われるほどだ、と。『告白』によれば、アウグスティヌスは、370年、16歳の頃、この女性と同棲し、385年、31歳の頃にこの女性と、ミラノで別れている。その女性は、一人息子のアデオダートゥスをアウグスティヌスのもとに置いて、アフリカへ帰って行ったと書いてある。こうして16歳から31歳までの間、この女性と暮らしたことがアウグスティヌスの生涯に大きな影響を及ぼす。
①母親
まず第一に、母親と不和になる。母は彼がこういう女性と一緒になったことで非常に悲しみ怒って、一緒に食卓につくことを拒否する。母親の立場からすれば、名家を継ぐ可愛い長男の将来を考えて、苦労して学校にやったのに、入学するかしないかのうちに、素姓の怪しい女と一緒になってしまった。これは母親としては耐えられないことである。
②真実の夫
アウグスティヌスは16年間なぜ結婚しなかったのか。当時のローマの法律上、アウグスティヌスとは身分が違いすぎるので、合法的結婚として認められなかったから、「妾」(コンクビーナ)としていただけのことである。
その頃、私は一人の女性と同棲するようになっていましたが、それはいわゆる合法的な婚姻によって知り合った相手ではなく、思慮を欠く落ち着きのない情熱に駆られて見つけ出した相手でした。けれど私は彼女一人を守り、彼女に対して閨の真実を尽くしました。
アウグスティヌスは、16年間、この女性に対して真実の夫だったのである。また二人の間には子供ができたが、これも大変可愛がった。したがって、二人の関係は、今で言えばいわゆる内縁関係であり、妾という関係ではなかった。
③ローマへ、そして別れ
383年、29歳のアウグスティヌスはローマへ旅立つ。アウグスティヌスは、息子をローマへやりたくない母を騙して、こっそり船に乗って出て行き、384年にミラノへ移った頃には女性と息子と一緒に住んでいる。ところが、385年、母モニカが息子の後を追いかけて、ミラノにやってくる。ここでいよいよ大詰めがきて、アウグスティヌスはこの女性と別れ、まだ幼い良家の子女を娶ることになる。しかも、一人息子を残して、女性は独りでアフリカへと帰っていく。今から見ると、この仕打ちは非常にひどいように見える。しかし、逆に言えば、それまで十六年間、絶望的な反抗を続けてきたということではないのか。
一方、女性のほうの気持ちはどうであったか。アウグスティヌスが当時のエリートコースを進もうと思えば、ふさわしい身分の令嬢と結婚しなければならない。自分は早晩、彼と別れなくてはならないと予感していたのではないか。夫と子供に対する愛に惹かれながらここまで来たけれども、ここで別れなければならない。しかし、それを恨むよりはむしろ、ここまで自分をかばってくれたアウグスティヌスに感謝するような気持で、おそらく別れて行ったのではないか。そのことは、アウグスティヌス自身のわずかな言葉の中に読み取ることができる。
これまで閨(ねや)を共にしてきたその女性は、婚姻の妨げとして、私の傍らから引き離されたので、彼女にしっかり結びついていた私の心は引き裂かれ、傷つけられて、だらだらと血を流しました。そのとき彼女はあなたに向かって、今後他の男を知るまいと誓い、私の傍らに彼女から生まれた私の息子を残して、アフリカに還ってゆきました。
アウグスティヌスだけを「夫」とし、アフリカへ帰っても、他の男とは結婚しないと、「あなたに向かって」――「あなた」というのは「神」のことである――誓って去ってゆく。『告白』には、その女性と息子アデオダートゥスとの別れのことは何にも書かれていないが、夫との別れがあったように、当然息子との別れもあったはずである。言い伝えによれば、その女性はアフリカに還った後、修道院に入り一生を終えたと言われる。
④肉の弱さ
ここでアウグスティヌスの心は分裂する。つまり、一方において出世のためにその女性と片をつけながら、他方でその別れた女性への愛着が残っている。愛着には、その女性に対する真実の愛と、長い間の生活で習慣となった肉欲の愛という二つの要素が含まれている。
これまで一緒に生活してきた女性はもういない。将来の出世のために婚約した女性はまだ幼く、二年経たなければ一緒になれない。その淋しい空白を満たそうと、第三の女性に手を出してしまう。あの女性は二度と他の男とは一緒にならないと神に誓って別れていったのに、その彼女に倣うこともできず、肉の弱さに負けて、別の女を引きいれた。これは、アウグスティヌスの生涯における最大の汚点といってもよいだろう。
しかし、このことを誰よりも苦しみ、深く悲しみ、後々まで悔いているのは、アウグスティヌス自身である。おそらくアウグスティヌスが『告白』の中で、一番苦しんで書いたのは、この部分ではないか。アウグスティヌスは、まさにこのことを書くためにこそ、『告白』を書いたようにすら思われる。アウグスティヌスは、ふたたび教会に接近してゆく。出世も許婚も捨て、名誉も肉欲も諦めて、信仰の道に入っていくことを決心する。
⑤ミラノの回心
すでに精神には、意志すべきは信仰に専念することだと分かっている。だが、精神が命じても意志できない。最後の抵抗は、内面のドラマとして描かれる。つまり、一方には「古なじみの女ども」という表現のもとに象徴的に描かれている「情欲」、他方には「貞潔」が威厳ある女性の姿で現われる。その両者の間に立って悶え苦しむアウグスティヌスの耳に、隣家から繰り返し歌うように、「取れ、読め、取れ、読め」という子供の声。思わず傍にあったパウロ書簡を手に取ると、次のような箇所が目に飛び込んでくる。「主イエス・キリストを着よ。肉欲を満たすことに心を向けるな」(ロマ書13:14)。ここで遂にアウグスティヌスは改心する。これが386年に生じたと言われる有名な「ミラノの回心」である(387年、母モニカがオスティアで没した後、アフリカに帰り、息子や仲間とともに一種の修道院生活を送ることになる)。
⑥「古なじみの女たち」と「貞潔の女神」
アウグスティヌスは、回心に際して、最後まで「肉欲」にこだわる。これは人々に異常な感じを起こさせるほどだ、と山田は注意を喚起する。アウグスティヌスは特別に性欲が強かったのか。どうして肉欲にそんなに罪悪感を感じるのか。それは、まったく彼に固有の、いわば彼にとって運命的に課せられた女性との別れの経験があるからに他ならない。
もしもそのように女性を愛していたのなら、どうして他の女性と婚約したのか。また別の女性を引き入れたりしたのか。問題はここにある。おそらくアウグスティヌスは、大いに考え抜いた末に、母親や友人たちの勧めに従って女性と離別したのであろう。しかし、彼女がアウグスティヌスに貞潔を誓って去っていった後に、失われたものの大きさにはじめて気がついたのではないか。しかし女性はもう帰ってこない。彼女はいわば「貞潔の国」に行ってしまった。もしもアウグスティヌスが彼女に再会しようと思うならば、彼自身、その「貞潔の国」に行かねばならない。しかし、自分はその国に入ることができるだろうか。
このような状況を前提するとき、『告白』に記された回心のドラマは、本当に理解される。普通、「貞潔」の女神は、カトリック的理想の生活、これに対して、「古なじみの女ども」は、過去にアウグスティヌスが関係した女たちのように理解されている。しかし、この解釈は間違っている。「古なじみの女たち」とは、現実の「女たち」ではなく、彼の内に執拗に残る肉欲である。そしてあの女性は、今はもう「貞潔の国」にいるのだ。貞潔の女神の後ろに隠れているのである。そこで、神の声を聴き、光に照らされ、励まされて、思い切ってその女神の胸に飛び込む時、アウグスティヌスは同時に、もはや永遠に離れることのできない愛の絆によって、別れていった女性と再会し、一つになる。彼にとって、「古なじみの女たち」の囁きを振り切って、「貞潔の女神」の胸に身をまかせることは、別れた女性への未練を振り切って教会の信者になることではなくて、教会の中で、祈りにおいて、別れた女性と再会することだったのである。
エロスとアガペーの総合としてのカリタス
以上のような背景を考慮に入れることで、キリスト教神学の基礎を築いた古代ローマ末期の教父アウグスティヌスの思想の見え方が大きく変わってくる。その代表例が、アウグスティヌスの思想全体に中心的な地位を占める「愛」の説である。これはまったく新しい愛の見方であって、カリタスという独特の第三のものを生み出した。カリタスとは、エロスでもない、アガペーでもない、いわばそれらの綜合である。
私は山田に続く形でキリスト教的結婚観に関しても脱構築的な読解を試みたいのだが、残念ながら現在その余裕がない。今はただ、アウグスティヌスとこの女性の関係について言われていることが、mutatis mutandis、キェルケゴールとレギーネについても言えるのではないかと示唆し、第三節に向かうことにしたい。
次回:5月10日(金)更新予定
↓これまでの連載はこちらからご覧ください
#結婚 #結婚の哲学史 #藤田尚志 #連載企画 #ニーチェ #ソクラテス #ヘーゲル #シューマン #キェルケゴール #レギーネ #フーリエ #ドゥルーズ #特別公開 #慶應義塾大学出版会 #Keioup
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
