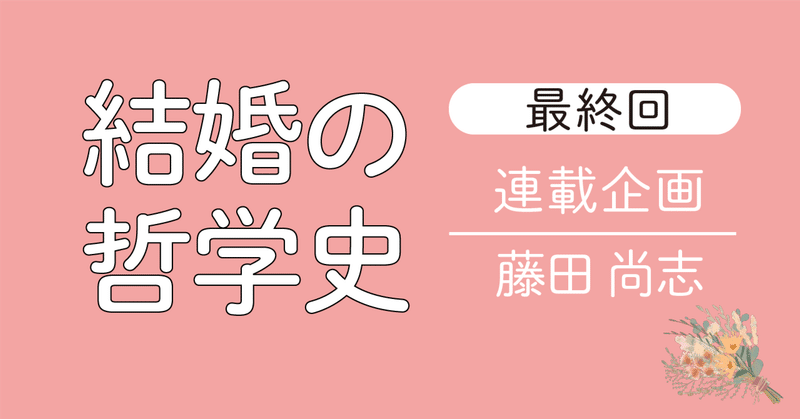
連載最終回:『結婚の哲学史』第3章 第三節 「返し与える」とはどういうことか――『おそれとおののき』を読む
結婚に賛成か反対か、性急に結論を下す前に、愛・ 性・家族の可能なさまざまなかたちを考える必要があるのではないか。昨今、結婚をめぐってさまざまな問題が生じ、多様な議論が展開されている現状について、哲学は何を語りうるのか――
九州産業大学で哲学を教える藤田先生による論考。これまで14回にわたった連載も今回が遂に最終回です。今回はいよいよキェルケゴールの愛・性・家族論に入ります。
↓これまでの連載はこちらからご覧ください
***
1.恋愛・セックス・結婚の哲学者キェルケゴール
キェルケゴールを扱う本章では、第一節で彼の生きた時代と生涯を概観し、第二節では彼の思想を「逆説弁証法」として概括した。本節ではいよいよ彼の愛・性・家族論を扱うが、残念ながら今回はその入り口を示すだけにととまらざるをえない。
まず本節前半では、江口聡の「恋愛・セックス・結婚の哲学者としてのキェルケゴール」を参照する(2023年の口頭発表の際の原稿が公開されており、これから論文化されるようだ)。キェルケゴール研究から出発し、英米圏のセックスの哲学を精力的に紹介している江口は、つい最近もラジャ・ハルワニの大著『愛・セックス・結婚の哲学』(名古屋大学出版会、2024年)の翻訳を刊行したばかりである。本論考にとって大変重要な示唆を多く含む江口の論考に対してコメントすることで自分なりのキェルケゴール読解の概要を示し、次いで本節後半の『おそれとおののき』読解を通じて具体的にその一端を示すよう努めたい(残念ながら『人生行路の諸段階』読解については機会を改めざるをえない)。
*
江口によれば、偽名著作の半分以上が直接的に恋愛と結婚をめぐる考察であるキェルケゴールの「愛・セックス・結婚の哲学は現代的な問題意識に近く、非常に興味深いものを含んで」おり、「近年は英語圏のキェルケゴール研究者でも『愛のわざ』を中心にキェルケゴールの恋愛哲学が頻繁に論じられて」(17頁。本セクションにおける頁数のみの引用はすべて江口2023)いるそうだが、文献表にキェルケゴール研究の先行文献が一切ないところを見ると、この視点からの研究の蓄積はまだあまりないということかもしれない。
江口自身の解釈はこうだ。一方で、「キェルケゴールの愛・結婚・セックスに関する〔思考の〕最大の特徴は、〔『あれか、これか』の〕Aが楽しもうとしている〔美的な〕享楽的恋愛だけでなく、〔判事〕ヴィルヘルムが称揚する〔倫理的な〕夫婦愛ですら道徳的な優越性はない、というところにある」(16頁)。「つまるところ、『あれか/これか』と『諸段階』の姉妹作品は、一方では通俗的なロマンチックな恋愛の幻想を滑稽に打ち砕きながら、情熱と情欲の生活の不毛さをも指摘し、また一方では善良なる通俗的結婚倫理/性道徳が現実には陥ってしまう偽善性を暴きたてているのだ」(12頁)。
江口はここで、私たちが藤野とともに確認した「領域の区別」、つまり倫理的領域にいると思っていたまさにその場所に美的なものを嗅ぎつけ、より鋭い批判的区別を打ち立てるという挙措にキェルケゴールのたて一方の本領を見てとっている。
ただし、以上はキェルケゴールの「愛・セックス・結婚の哲学」の「個人に関わる倫理」という半面にすぎない。他方で、キェルケゴールには「社会的な倫理、あるいは対人的な倫理」(13頁)があり、それは実名での大著『愛のわざ』(1847年)に現れている、と江口は言う。そこでは、キェルケゴールが「ロマンチックな恋愛に関して(キリスト教からして)最大の問題点と考えていた事柄」すなわち「恋愛や友愛は実は自己愛の一種でしかない」(13頁)という点が指弾され、「結婚生活においても、キリスト教的には、お互いに対する愛ではなくまずは神に対する愛がなければならない」(16頁)とされる。真の「愛」は「本来的にはキリスト教的な隣人愛」(15頁)なのである。
これはやはり「領域の区別」である。今度は宗教的領域にいると思っていたまさにその場所に単に美的ないし倫理的な領域を嗅ぎつけ、より鋭い批判的区別を打ち立てるという挙措にキェルケゴールの他方の本領を見てとっている、ということであろう。
では、この二つの「領域の区別」間の関係はどうなっているのか。江口は両者の関係を「実名著作/偽名著作」の区別として捉え、そこに英語圏倫理学の「規範的/記述的・理論的」の区別を重ねる。前者の「建徳的」著作群は「直接的に倫理的・宗教的な規範やアドバイスや命令を含んでいる」のに対し、後者はそれらを含んでいない。聖書・福音を権威として実名著作が奨励する「キェルケゴール的な愛は(…)まったくキリスト教的な愛であると感心せざるをえないが、そんな愛は発表者には興味のもてない事柄である」(17頁)と江口はにべもない。
すると、私たちの理解が正しければ、江口にとってキェルケゴール的な「愛・セックス・結婚の哲学」の本領は、偽名著作=美的著作に含まれる記述的・理論的側面にあり、それはとりわけロマンティックラブの欺瞞性(自己愛性)の批判であるということになる。彼の理論的コアは、キリスト教的イデオロギーに縛られた実名著作=建徳的著作群とは切り離し可能であるという結論になりそうである。
だが、私にはこの道はきわめて危ういものであるように思える。「最初期から『愛のわざ』までに至るキェルケゴールの「愛」論はこうしたキリスト教理解に基づいているはず」(16頁)であるのに、それをすべて切り落とすというのは代償があまりにも大きすぎはしまいか。江口の解釈は、キェルケゴールの本領を「キリスト教」や「信仰」にのみ見てとり、偽名著作やレギーネとの関係を軽視する解釈方針と真逆のようでいて、実は表裏一体であるように思われる。キェルケゴールの全体像から出てくる愛・セックス・結婚の哲学を捉えようとはしていないという点がどちらにも通底しているからだ。私としてはむしろ、「聖書の文字通りの理解、原理主義的理解がキェルケゴールのセックスの哲学だろう」(16頁)という点を再検討し、キェルケゴールのキリスト教理解を原理主義とは別様に捉えたうえで、それは彼の愛・セックス・結婚の哲学と切り離しえないという方向を取ったほうが、より彼の哲学の核心部分に近づけるように思える。
前回私たちが「キリスト教か、レギーネか」というセクションで、山田晶のアウグスティヌス読解を範として示唆しようとしたのは、まさにこの方向であった。
今一度思い出しておこう。アウグスティヌスの『告白』において、通常「貞潔」の女神は、カトリック的理想の生活であり、「古なじみの女ども」は過去にアウグスティヌスが関係した女たちのように理解されているが、山田によれば、この解釈は間違っている。「古なじみの女たち」とは、現実の「女たち」ではなく、彼の内に執拗に残る肉欲である。そしてあの女性は、今はもう「貞潔の国」におり、貞潔の女神の後ろに隠れているのだ。そこで、神の声を聴き、光に照らされ、励まされて、思い切ってその女神の胸に飛び込む時、アウグスティヌスは同時に、もはや永遠に離れることのできない愛の絆によって、別れていった女性と再会し、一つになる。彼にとって、「古なじみの女たち」の囁きを振り切って、「貞潔の女神」の胸に身をまかせることは、別れた女性への未練を振り切って教会の信者になることではなくて、教会の中で、祈りにおいて、別れた女性と再会することだったのである。
無論このような甘ったるい記述は所詮ロマンティック・ラブと神の愛の混同にすぎない、という意見もあるだろう。いずれにせよ、アウグスティヌスの思想全体に中心的な地位を占める「愛」の説はまったく新しい愛の見方であって、エロスでもない、アガペーでもない、いわばそれらの綜合としてのカリタスという独特の第三のものを生み出した、というのが山田の見立てである。私たちには、江口の引くキェルケゴール『愛のわざ』の次の一節は、同様の方向で解釈することも可能であるように思われる。
しかしながら、いかなる愛、いかなる愛の表現も、世間的にも単に人間的にも、神への関係から引き離されてはならないのである。(…)各人は、彼が愛において恋人・友人・恋人たち・同時代人に関わる前に、まずもって神に、神の要求に関わらねばならない。
キェルケゴール的結婚が「男女の二者間の恋愛や結婚ではなく、あくまで神と信仰を媒介にした三者関係としての結婚」(16頁)であるとして、神を第三者として二人の間に置くという行為が、恋愛を〈非恋愛的〉に、結婚を〈非結婚的〉にする、と江口が考えるのはなぜか。それは江口が「現代のセックスの哲学者たちが熱心に論じている問題群に対応し先取りしている」ものとして、「美的著作での恋愛論にあらわれるキェルケゴールの疑念」(8頁)を、恋愛の「(当事者によって主張されている)排他性、唯一性、そして恒常性」の否定と考え、神への愛(アガペー)と人間への愛(エロス)を二律背反的に峻別しているからだ。だが、キェルケゴールが考えている愛とは、所有と放棄が表裏一体であるような愛ではないか。
彼は彼の生活の内容であるところの恋を、無限の意味において断念する。(…)しかし、ついで奇蹟がおこる。彼はなお一つの運動を、ほかの何ものよりも不思議な運動をおこなう。つまり、彼はこう言うのである、それでも、彼女がわたしのものとなることを、わたしは信じます、それは背理なものの力によってなのです、神にあってはあらゆることが可能である、ということによってなのです、と。背理なものは悟性の固有の範囲内にある差異には屈しない。(…)しかし、この所有はもちろん同時に放棄でもある。
ここで彼が「背理なものの力」と呼んでいるものは、「逆説」と言い換えてもいいだろう。しかし、江口への問いはここまでにしておこう。ここから先は私たち自身が答えるべき問題である。私たちはキェルケゴールと神とレギーネの関係をどう考えるのか。問題の鍵を握るのは、「所有にして放棄」である「返し与えること」である。
2.イサクの燔祭と『おそれとおののき』
「イサクの燔祭」ないし「イサクの奉献」とは、旧約聖書『創世記』第22章第1-19節に描かれた逸話である。「燔祭」とは、旧約聖書『レビ記』でモーセが定めたユダヤ教(およびキリスト教)の供犠のうちで最も高貴なものとされ、雄牛・羊・山羊・鳩といった供物が供壇で焼尽され神に捧げられる儀式である。ギリシア語で「すべてを焼き尽くす」を意味する「ホロコースト」は元はこの儀式に用いられる語であったそうだが、今では第二次世界大戦中のナチスによるユダヤ人大量虐殺を指す言葉としてむしろ知られているだろう。
アブラハムはある日、不妊の妻サラとの間に年老いてからもうけた愛する一人息子イサクを燔祭の生贄に捧げるよう神によって命じられる。彼は朝早く起きて、燔祭のたきぎを割り、ロバに鞍を置いて、ふたりの若者とイサクとを連れ、モリヤ山に向けて出発した。三日目に神が指示した場所に到着したアブラハムは、イサクと二人で礼拝を行なってくると告げ、若者たちにはロバと一緒に待つように指示する。
7 やがてイサクは父アブラハムに言った、「父よ」。彼は答えた、「子よ、わたしはここにいます」。イサクは言った、「火とたきぎとはありますが、燔祭の小羊はどこにありますか」。
8 アブラハムは言った、「子よ、神みずから燔祭の小羊を備えてくださるであろう」。こうしてふたりは一緒に行った。
9 彼らが神の示された場所にきたとき、アブラハムはそこに祭壇を築き、たきぎを並べ、その子イサクを縛って祭壇のたきぎの上に載せた。
10 そしてアブラハムが手を差し伸べ、刃物を執ってその子を殺そうとした時、
11 主の使が天から彼を呼んで言った、「アブラハムよ、アブラハムよ」。彼は答えた、「はい、ここにおります」。
12 み使が言った、「わらべを手にかけてはならない。また何も彼にしてはならない。あなたの子、あなたのひとり子をさえ、わたしのために惜しまないので、あなたが神を恐れる者であることをわたしは今知った」。

キェルケゴールの代表作の一つ『おそれとおののき』は、彼が仮名著者「沈黙のヨハンネス」として、このイサクの燔祭におけるアブラハムの心理状態を考察した著作である。副題は「弁証法的抒情詩」であるが、著作自体は明らかに反ヘーゲル的様相を呈している。「序想」を見てみよう。キェルケゴールは皮肉を込めてこう書きつけている。「ヘーゲルを理解するのは困難であるという。しかしアブラハムを理解するのはわけのないことなのである。ヘーゲルを乗り越えていくのは奇蹟であるが、アブラハムを越えて出るのは容易なことなのである」(5:54)。彼がアブラハムとヘーゲルを対立させているのは一目瞭然であろう。キェルケゴールは、ヘーゲル哲学を理解するのに長い時間をかけてきた結果、どうにか分かったつもりであるとし、「少し生意気に思われるかもしれないが、どんなに骨を折ってみても理解できない個所がところどころにあるのは、ヘーゲル自身に十分はっきり分かっていないからだ」(5 : 55)と豪語している。ところが、とキェルケゴールは続ける。
ところが、アブラハムについて考えてみようとすると、まるで手も足も出なくなってしまうのである。瞬間ごとにアブラハムの生命の内容であるあの恐ろしい逆説が私の目につく。瞬間ごとに、私ははね返され、私の考えは、〔…〕毛筋一本の幅ほども先へ進まない。
ここで彼が「逆説」という言葉を用いているのは決して偶然ではない。
さて、私の狙いはアブラハムの物語のうちにある弁証法的なものを、幾つかの問題の形式で取り出して、信仰というものがいかに途方もない逆説であるかを知ろうというにある。つまり、殺人をさえ神の心に適った神聖な行為とすることができるという逆説、イサクをアブラハムに返し与えるという逆説、この逆説は思惟の捉えうるものではない。信仰とは、思惟の終わるところ、まさにそこからはじまるものだからである。
私たちが、キェルケゴールの弁証法を反ヘーゲル的なものとし、それを「逆説弁証法」と名付けるのはこのような彼の姿勢に由来する。彼は『おそれとおののき』の中で三つの問題を取り上げているが、ここでは私たちの問題関心と特に関係するポイント二つを取り上げよう。
3.ヘーゲルとの対決①倫理的なものの目的論的停止
「問題1.倫理的なものの目的論的停止というものは存在するか?」の中で、仮名著者「沈黙のヨハンネス」は、アブラハムと対比するために、一見似ている(「倫理的に正当」と見なされる)三人の悲劇的英雄を引き合いに出している。古代ギリシアのアガメムノン、旧約聖書のエフタ、そして古代ローマのブルータスである。彼ら三人の共通点は、倫理的なものの領域のなかで自らの子どもを犠牲にしていることである。中でもアガメムノンの例は、娘がまったく無実であるという点、現代人には理解が難しいように思える神託が下されているという点でもアブラハムの事例とよく似ている。
トロイに対するギリシア軍の遠征隊長であったアガメムノンの船団は、荒れ狂う嵐のために出航することができなかった。嵐を起こした女神の怒りは、彼の娘イピゲネイアを犠牲にすることによってのみ鎮められると占者から伝えられたアガメムノンは、国家のために不本意ながらもイピゲネイアを殺める…。
アガメムノン的倫理とは、共同体の危機に際して私情より公益を優先し、共同体・民族・国家のために子どもを犠牲にするという倫理である。「個人的道徳<共同体的倫理」となっているが、法や習俗など客観的原則の遵守を「倫理」の条件と考えたという意味では、ヘーゲル的であるとも言える。思い出しておけば、ヘーゲルにとって「法的=正しい」行為とは、社会的公共性に貢献する行為であり、倫理的なものとは、実際に共同体の成員が認めていることであった。要するに、ここでアガメムノンとアブラハムの対立とされているものは、実はヘーゲルとキェルケゴールの代理戦争なのである。では、争点はどこにあるのか。
倫理的義務の停止か、倫理的なものの目的論的停止か
アガメムノンにおいて問題となっているのは、倫理的義務の停止である。まず注意すべきは、倫理的義務の「停止 Suspension」とは、義務の「放棄」ではないということである。たしかに娘を犠牲に捧げる時点で「義務>愛情と哀惜」となってはいるが、その特殊状況が解決されれば義務の停止は解除され、娘への哀惜・悲嘆という倫理が再開される。第二の注意点は、何を理由として義務が停止されるかという点である。ここでは、二つの普遍的・倫理的義務が互いに葛藤する状況にある。一方には、一家の長として、自分の子供を守る=家族の安寧を図る義務があり、他方には、国家の長として、国家の福祉を考える義務がある。つまりここでは、父としての義務と、長としての義務が衝突している。アガメムノンは、〈国家に対する義務〉を〈娘に対する義務〉より優先したのであるが、彼のこの判断は決して非倫理的なものではない。彼は或る倫理的義務を別の倫理的義務に優先しただけであって、その選択もまた倫理的なものにほかならない。いや、アガメムノンは娘を犠牲にしながらも依然として倫理的なものの領域内にいるというよりは、むしろそれによってヘーゲル的「倫理」の中核に組み込まれてすらいる。犠牲者である娘自身も、自らの不幸を嘆き悲しみつつ、最終的には自ら犠牲を望んだのであり、その意味で共同体の構成員の誰もが正当と(心ならずも)認めた、むしろ共同体全体の意志に沿っているからだ。
これに対して、アブラハムの態度は、「倫理的なものの目的論的停止」と呼ばれている。これは、あらゆる既成の法や習俗といった倫理的なもの自体の停止ということであり、「目的論的」停止とは個人的理由ではなく、「信仰のため」というより高い目的のために倫理を停止するということである。アブラハムのイサク奉献は、民族の安全保証のためでも、国家の危機脱出のためでもなく、ただ信仰のためであるという意味で、彼は倫理的なものと関わりをもたない。
アブラハムのこの姿勢もまた義務であるが、ヘーゲル的な「倫理」ではないという意味で“非倫理的”な義務である。彼は最愛のものに死を与えようとするのだが、しかも共同体の大義のためといった「それらしい」、人間的な理解の範囲内に収まる理由を与えることができない。その意味で彼の行為は普遍的ではなく特殊的であり、神に対する絶対的で単独的な義務である。
デリダは『死を与える』の中で、この義務を〈人間的責任の彼方〉、〈義務という普遍概念の彼方〉と見なし、次のような注釈を加えている。犠牲とは、憎んでいる者に死を与えることを言うのではなく、裏切るという形で最愛の者を捧げることだ。憎むとは、死を与えるまさにその瞬間、最愛の者を裏切ることだ、と。
憎しみの対象としてではなく(それならばあまりにも容易だ)、愛する対象としてあるような近親者に対して、犠牲としての死を与えなければならないということである。私は彼らを愛するかぎりにおいて、憎まなければならない。憎むべきものを憎むのならば、そのような憎しみはあまりにも容易で、憎しみとは言えない。憎しみとは、最も愛する者を憎み、裏切ることである。憎しみは憎しみたりえず、愛に対する愛の犠牲でしかありえない。愛していない者については、憎む必要もないし、誓いに背くことによって裏切る必要も、死を与える必要もないのだ。
これはしかし、先に(第3節第1項で)『愛のわざ』に見られた論理ときわめて近接した何かである。「キリスト教的愛の内面性は、自発的に、己れの愛に対する報酬として恋人(対象)から憎まれていようとするのである。(…)それはいかなる報酬も持たない。愛されるという報酬すら持たないのである」(創言社10:190)。あるいは、「キリスト教的に解した場合、約束を守ることが恋人から憎まれることを意味するとすれば、愛を約束することがいかに困難にならざるをえないかが明らかになるであろう」(10:189)
真の「憎しみ」というものがあるとすれば、それは憎むことが不可能なものを憎むのでなければならない、とデリダは言う。キェルケゴールによれば、真の「愛」というものがあるとすれば、それは愛することが不可能なもの(何の報酬も期待できないもの)を愛することなのである。
4.ヘーゲルとの対決②秘密の倫理、倫理の秘密
そもそも一人の人間が、神と直接の関係をもつことは可能なのか。「自分は神から直接命令を受けた」という理由で、一般的な道徳的義務を“停止”しようとする者がいたら、疑いの目で見られて当然である。だが、アブラハムの置かれた状況を十分に知った人ならば、少なくとも彼同様の「信仰の騎士」であれば、彼の行動を承認できるのではないか。しかし、キェルケゴールは安易な一般化を戒める。「個別者は、同じ境遇にある他の個別者にならば、自分を理解させることができる、と想像されるかもしれない。(…)一人の信仰の騎士は、他の信仰の騎士を助けることは決してできない。個別者が逆説を自分に引き受けることによって自ら信仰の騎士となるか、それとも決して信仰の騎士にならないか、そのいずれかなのである」(5:119)。「逆説を引き受ける」ことの核心部分に「秘密を守る」ということがある。これが「問題三.アブラハムが彼の企図を、サラ、エリエゼル、イサクに黙して語らなかったのは、倫理的に責任を問われるべきことであったか?」で扱われる問題である。
名と秘密
ここでキェルケゴールが仮名・偽名という秘密の名前を用いて著作を書いたという点に触れておこう。仮名・偽名とは、姓という自分が親から(西洋社会において多くの場合、父方から)受け継いだ公式で合法的な名、つまり「父の名」を秘密にする行為である。伝統的な「責任」ないし「倫理」が常に「自分の名のもとに語る」、つまり国家-市民社会-家族のヘーゲル的三位一体システムによって保証された「父の名のもとに語る」ことを前提していたのだとすれば、仮名著者「沈黙のヨハンネス」をはじめとする多くの仮名・偽名で語られたキェルケゴールの「責任」ないし「倫理」とは何であろうか。
沈黙と秘密
イサクの問いに対するアブラハムの奇妙な答えを思い出そう。「燔祭の子羊は神が備えてくださる」。デリダは、アブラハムは答えなかったのではないという点に注目する(Derrida 1999 : 86)。アブラハムは沈黙もせず嘘もつかず、秘密を守りつつ答えたのだ、と。この場合、アブラハムの「秘密」とは二重である。つまり一方で、神がイサクを捧げるように命じる意味も理由も知らないという意味で、神のアブラハムに対する秘密があり、他方で、そのような神の命令が下ったことを妻サラにも息子イサクにも語らないという意味で、アブラハムの家族に対する秘密がある。
分かりやすい例を挙げよう。『泣いた赤鬼』という童話がある。村人たちと仲良くなりたいという赤鬼の願いを聞き入れた親友の青鬼は、自分が村で乱暴狼藉を働くという芝居を打つ。赤鬼が村人たちの窮地を救うことで仲良くなるという作戦である。この話のポイントは、青鬼の「沈黙」にある。青鬼の村人への迷惑行為は決して倫理的ではなく、せいぜい「友達への友情のため」という人間的な次元の目的を理由とした「倫理的なものの停止」である。だが、少なくとも村人たちに対して赤鬼との計画について沈黙を貫き通すことは、キェルケゴール的な意味では“倫理的”である。「もし僕がこのまま君と付き合っていると、君も悪い鬼だと思われるかもしれません。それで僕は旅に出ることにしました。長い長い旅に出るけれども、いつまでも君のことを忘れません」。ただ、これを赤鬼にすら告げずに旅に出たとすれば、よりキェルケゴール的な倫理となったのではないか。
「倫理的=自分の意図の明示」がヘーゲル的な意味での倫理であるとすれば、アブラハムには語らず、秘密を守り抜くという非ヘーゲル的な倫理がある。この秘密をキェルケゴールは「隠れ」(デンマーク語原書ではSkjulthed、英語全集版ではhidenness、ペンギンクラシックス版ではconcealment、仏語Tisseau訳ではintérieur caché)とも呼んでいる。
もし個別者が個別者として普遍的なものよりも高くにあるということに根拠をもつ隠れというものがないならば、アブラハムの態度は弁解の余地がない。なぜなら、彼は倫理的な審級を無視したのだからである。それに反して、そのような隠れがある場合には、私たちは、媒介されない逆説の前に立つ。
キェルケゴールは「アブラハムが語ることができない」という事態を「アブラハムは媒介されえない」とヘーゲル用語で言い換えている。アブラハムが自らの行為の意図を語らなければ、誰も彼を理解することはできない。「普遍的なものは媒介にほかならない」(5 : 137)と明言している以上、普遍的なものもまたヘーゲル弁証法の別名である。「語る」という行為が必然的に「普遍的なものを言い表す」ことになる以上、アブラハムが自己の意図を語ろうとするや否や、彼の立場は「試練」となる、とキェルケゴールは言う。「普遍的なものの上にあるような普遍的なもの」を言語で表すことはできないからである。そこでヘーゲル的「倫理」は、誘惑(まどわし)となる。
アブラハムは語ることができない。なぜなら、彼は一切を説明するような言葉を口にすることができないからである。それが試練であることを、そして注意すべきことに、倫理的なものが誘惑であるような種類の試練であることを語ることができないからである。
ここで自ら「逆説」と呼ぶものに対してキェルケゴールは、「個別者が個別者として普遍的なものよりも高くにあるということに基づくもの」という定義を与え、「ヘーゲル哲学は正当な隠れをも、正当な測りえないものをも認めない」(5 : 137)と喝破している。通常、責任は公表性や非-秘密や真理性と結びついているが、明らかにヘーゲル哲学はその代表と見なされている。言語は本質的に普遍的なものであり、個物は普遍に媒介されて初めて伝達可能なものになる、個物そのものを語ることはできないというのがヘーゲル的なテーゼである。したがってヘーゲル的な哲学・倫理・政治に“秘密”はないし、「秘密の倫理」も存在しない。だが、青鬼が村人にすべてを語ることが倫理なのだろうか。アブラハムが神の命令と自分の状況を人に語れないのは非倫理的なのだろうか。
倫理と秘密と文学
アブラハムは要求された犠牲の秘密を明かさなかったという意味では“沈黙”した。「語らない」ことによって、彼は倫理的なものの次元を踏み越える。だが、たしかにまた“真実”を“語って”もいる。虚偽ではない何か、物語の読者には(後になればイサクにも、少なくとも部分的には)その意味が判明するような何かを。だから彼は語り、また語らないということができる。答えることなく答える。答え、また答えないということも。デリダは、『聖書』におけるこのイサクの燔祭の記述に文学の起源ないし原型を見て取っているが(Derrida 1999 : 163ff)、ある種の拡張を施せば芸術全般についても言えるであろうし、私たちの関心から言えば、結婚の脱構築にも示唆的である。
キェルケゴールにとって通常の(ヘーゲル的な意味での)「倫理」とは、近しい者(家族・市民社会・国家)に私たちを縛りつけるものであり、「語る」とは、言語という媒介を通じて普遍性を獲得する代わりに単独性を喪失することである。「語ることは私たちの心を慰める。なぜならそれは私を普遍的なものへと翻訳してくれるから」(5 : 186)。こうして、真の“責任”が放棄されることになる…。だが、秘密を守り、語らない“倫理”もあるのではないか。秘密・偽名の倫理というものも存在するのではないか。それこそが、宗教的領域における“飛躍”、あるいは私たちがアドルノとともに佇立と呼んだものの内実、少なくともその一端であるように思われる。
秘密の倫理の脱構築
アブラハムのように沈黙に耐え、秘密を守ること。それは例えば、イエス・キリストが「右の頬を打たれたら左の頬を差し出せ」(マタイ5: 39)という言葉で表現しようとした極限的な倫理にも見られる飛躍=佇立かもしれない。通常の倫理的な要請とは普遍性に従うことだが、そのようにして語ることは、責任の明確化といううわべのもとに自己正当化や決断に対する釈明を作り出しているだけかもしれない。謝罪会見を開き、ひたすら“社会的制裁”を受け続けるポーズをとりつつも、言葉を尽くして透明性を確保し公明正大であろうとすることが「倫理」であるとは限らない。むろん、左の頬を差し出したら必ず「倫理的」であるわけでもない。ただ、キェルケゴールはイサクの燔祭という特異な例のうちに、決断の瞬間に単独性に引きこもるという形で責任をとるという可能性を見出しているのである。
アブラハムを論じるキェルケゴールから見れば、通常の倫理の普遍性は、語り・答え・釈明という媒介を通じて私の単独性を解体してしまうという意味では、“無責任”ですらある。沈黙の倫理、秘密の倫理は、置き換え(反復)不可能で絶対的な単独性に基づく非倫理的な「倫理」であり、それをこそキェルケゴールは「宗教的」と呼んでいるのではないか。釈明せず、責任をとって保証せず、応答しないという非倫理的な倫理をこそ、彼は「逆説」ないし「躓き」と呼んでいるのではないか。
だが、このような逆説的な倫理は、論理的に成立可能なものであると同時に、実際にはほとんど成立不可能なものである。キェルケゴールの体系を求心力と遠心力の拮抗で表すとすれば、遠心力は間違いなく「宗教的なもの」であり「秘密の倫理」である。
*
言うまでもなくキェルケゴールはイサクの燔祭のうちに、自らのレギーネとの婚約破棄を見ている。次の一節で「白髪の翁」と呼ばれているのがアブラハムであり、「可愛い子ども」がイサクであるということはもはや自明であろう。
あの婚約の年の内容は、私にとっては実は、お前は婚約してもいいのか?お前はあえて結婚するのか?という良心の呵責に思い煩った苦しみばかりであった。ああ、悲しいことに、そのあいだ彼女は、この可愛い子どもは、私と並んで歩いたのだ。そして許婚だったのだ!私は白髪の翁のように老いていたし、彼女は子どものように若かった。〔…〕はるか遠くかすかに希望を認めた時、私は彼女を魅了する喜びを抑えることができなかった。彼女は愛らしくも子どもであった〔…〕 。
そしていろいろと苦しんでいたにもかかわらず、私たちが別れた時にも、彼女は子どものようであった。けれども、関係は断たれざるを得なかった。そして私は、彼女を助けるために、残酷な態度を取らねばならなかった――見よ、それが『おそれとおののき』なのだ。関係がきわめて恐ろしいものになっているために、ついにエロス的なものがまるで存在しないかのようになっているのだ。〔…〕私は老人になってしまって、彼女がほとんど性別には関わりなく愛される子供のようになったほどであった。見よ、それが『おそれとおののき』なのだ。
アブラハムはイサクを神に捧げることによって、イサクを殺さずに済んだ。天使(神のみ使い)が彼を押し止めた(わらべを手にかけてはならない。また何も彼にしてはならない)のは、「あなたの子、あなたのひとり子をさえ、わたしのために惜しまないので、あなたが神を恐れる者であることをわたしは今知った」からである。捧げられるのは最愛の者イサク=レギーネでなければならず、そうしてそのような最愛の存在を捧げたからこそ、「与え返される」ということ、それがキェルケゴールの望んだことではなかったか。「望んだ」という言葉を強調したのは、彼はその目的を完遂するために諦めきることができないと繰り返し痛切に自覚したからであり、それもまたキェルケゴール的な思考の本質的な特徴をなしているからである。前節第2項でヘーゲル弁証法と比較する際に引用したのとは違う箇所を引いておこう。
ああ、悲しいかな、わたしはこの運動をなすことができない。わたしがこの運動にとりかかろうとするや否や、わたしの頭はぐらぐらしてくる。
最後の運動、信仰の逆説的運動は、わたしにはできない。それが義務であろうと何であろうと、できるものならしたいどころか喜び勇んでしたいのだが、わたしにはできないのである。
キェルケゴールにおいて逆説が思考可能な倫理の論理となるのは、彼が立ち止まり続けることによってである。だが、では、「所有と放棄の一体化」は実現不可能なアイデアなのか。マルクスは或る意味でこの方向を突き詰めようとしたともいえるだろう。
*
『おそれとおののき』の読解をまとめておこう。そこにはヘーゲルとの二つの対決があった。第一は、結婚の「倫理」の再検討であり、第二の対決は、倫理と「秘密」の関係の再検討である。ヘーゲルから学ぶべきことは、結婚とは社会・国家・共同体に関わることであり、「公=パブリック」に関わることこそが「倫理的」である、ということであった。だが私たちは、キェルケゴールとともに、常に共同体的に公明正大に語り合うことだけが結婚の倫理のすべてなのか、と問うことができる。倫理的なものの目的論的な停止に該当するような個人間の関係構築は決して「倫理的」でありえないのか、と。キェルケゴールによれば、単独者でも共同体と対峙することは可能である。婚約破棄の経験をイサクの燔祭的に捉えることが可能であれば、「秘密の倫理」は存立可能である。たとえ他の誰にも理解されないとしても。だが、私たちがレギーネの書簡から読み取ったのは、彼女がそれを理解した可能性であった。フーリエがヘーゲルの近代的結婚観(一夫一婦制)を拡大し、選択的結婚制度(単婚・複婚・全婚)を幻視したとすれば、キェルケゴールはヘーゲルの近代的結婚観(家族的・社会的・国家的な公明正大性)とはまったく異なる道、「逆説の狭い小径」(5 : 132)を、この「秘密の倫理」(徹底的に私的・単独的で、しかもいわゆるロマンティック・ラブに還元されない愛の絆)とともに切り開いたと言える。
キェルケゴールについてはまだまだ言い足りないこと、考え切れていないことが多々ある。『人生行路の諸段階』読解もそうだが、匿名で発表した最初の論文「女性の偉大な能力に関するもう一つの擁護」以来、キェルケゴールについて回るミソジニー(女性蔑視)的傾向をどう捉えるかについてはフェミニズム的な再読解(Céline Léon and Sylvia Walsh (eds.), Feminist Interpretations of Soren Kierkegaard, Pennsylvania State University Press, 1997)、中でもキェルケゴールのうちにécriture féminineを見てとる研究などを考慮に入れたいところである。だが、これらについてはまたの機会を待つとして、一旦ここで筆を擱くことにしよう。
*
どれくらいの方が読んでくださったかは分かりませんが、お読みいただいた方にはお礼を申し上げます。また大変お忙しいなか毎月の打ち合わせでは辛口のコメントで叱咤激励してくださった編集部の村上 文さん、連載開始以来毎週アップするという大変な作業を引き受けてくださった営業部の吉川 真央さんには格別の感謝を捧げます。(藤田)
最後に編集部より
全14回の連載をお読み下さった皆様、ありがとうございました。ここで一度連載は終了しますが、ご好評につき連載継続を決定致しました!!次回は7月26(金)に再開を予定しております。引き続きご期待下さい!
↓これまでの連載はこちらからご覧ください
#結婚 #結婚の哲学史 #藤田尚志 #連載企画 #ニーチェ #ソクラテス #ヘーゲル #シューマン #キェルケゴール #レギーネ #フーリエ #ドゥルーズ #特別公開 #慶應義塾大学出版会 #Keioup
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
