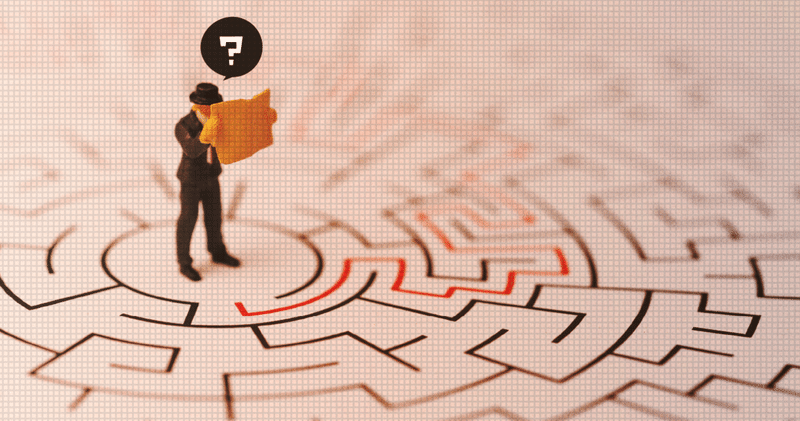
今さら"35歳"を持ち出す無意味
かつて、35歳を超えると転職市場で得られる選択肢の数が急激に減少することが『35歳転職限界説』なる定説として語られていました。
“失われた10年”を終え、「転職」や「中途採用」がある程度市民権を得た2000年代においても、私たち人材紹介会社が取引先から預かる求人の多くは、「35歳未満」と明記されたものでした。(2007年に行なわれた雇用対策法の改正により求人の年齢制限は禁止されました)
では、なぜ「35歳まで」だったのでしょうか。
個別に事情は異なりますが、概ね以下のような理由からだったように思います。
a (35歳までの)特定の年齢層の不足を埋めたい
b できるだけ給与を低く抑えたい
c 管理職ではなくメンバーを採用したい
d 管理職より年齢の高い人を入れたくない
e 入社後に長く働いてほしい
f 歳をとるにつれて(新たな環境への)順応性が低下する
g 歳をとるにつれて能力的な伸びしろが小さくなる
aは技能の伝承などを考慮するとやむを得ないところがありますが、それ以外は今後の社会や労働市場の変化を考えるとどれも違和感を感じざるを得ない理由です。
2021年4月から70歳までの就業機会の確保を企業の努力義務とする法案が既に可決しており、労働人口の更なる減少や健康寿命の長期化のトレンドを見ると、“70歳”がいずれ“75歳”になっても何ら不思議ではありませんし、実際にその議論は始まっています。
そして、もし75歳定年になったとしたら、22歳から始まるビジネスパーソンとしての人生の折り返し点は46歳。
そこで「35歳まで」に限定した採用を行なう企業は著しく人材確保の機会を逸することになります。
一方、歳をとるにつれて順応性や能力的な伸びしろを失うと見られている私たちが行なうべき努力は、『学びを止めない』ことではないでしょうか。
特に、立場や年代、ジェンダーなどを超えた「議論」の習慣は、私たちに“思考の若返り”の機会を次々と与えてくれます。
そしてその「議論」に参加する上で重要なことは、その場に有意義な「問い」を投げかけることです。
そう考えると、f や g というのは、「答(解)」を考えることに終始する人に対する懸念だったように思えます。
「解」よりも「問い」を考える、そんな知的習慣を身に付けたいものです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
