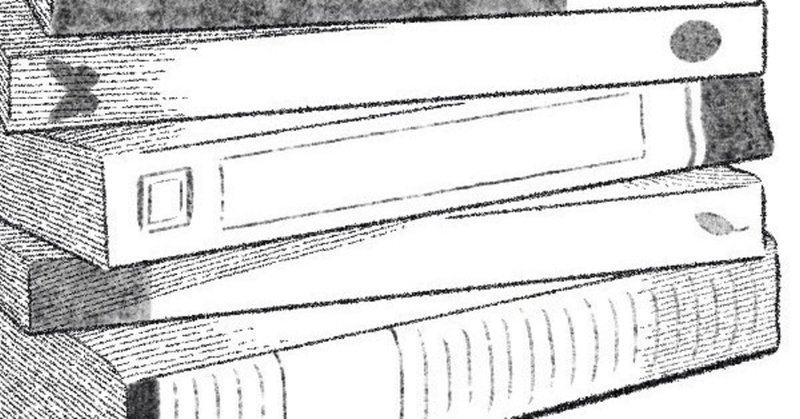
読後感
次の本を読もうにも、どうにも前に読んだ本が消化しきれずに、なにか体全体に溜まったもやもやした読後感を、形にして吐き出さないと気が済まない、そんな読書を経験したことがあるだろうか。かく言う私自身がいま、そんな読書をしてしまった当事者であり、この文章を書いている。
読んだ本は、井田真木子 著「ルポ14歳」。この著者の名前を知っている人は、あまり多くないように思う。私自身も、彼女の名前を知ったのはごく最近のことで、それまでは名前すら聞いたことはなかった。
彼女は、2001年に44歳でこの世を去ったノンフィクションライターだ。かつてプロレスが隆盛を極めた頃、神取忍やクラッシュギャルズ、中国から来た天田麗文などの当時の女子プロレスラーの目を通して日本社会をみつめた「プロレス少女伝説」で、大宅壮一ノンフィクション賞を受賞している。
井田真木子の文章は、どこか逼迫感を感じさせる。彼女の取材方法は、対象となる人物の人生そのものを変えてしまうような深い関わり方をして、その過程を丸ごと本にするとでもいうようなものだ。つまり、公と私の区別がなく、どこまでも仕事に没入していくかのようで、著者自身が何かに追われているかのような、逼迫感、切迫感、焦燥感がどこか文章全体から漂っている。
「ルポ14歳」は、44歳で逝去した彼女が、亡くなる3年前に上梓した最後のノンフィクションの著作だ。その内容は、タイトルからなんとなくの察しがつくように、バブル後の社会における少女たちの援助交際や売春、それを取り巻く家族像を、日本とアメリカを横断的に取材することで浮き彫りにしたものだ。
「どうして、あれほど恐怖を感じたのでしょうなあ。まず、朝五時には見かけないはずの人たちだったからでしょうな。とにかく”普通”の人たちなんですよ。私は以前、青少年課にいたことがあります。しかし、朝五時に始発電車をめがけて集まってくる子供たちは、いわゆる補導対象の子供として私が認識している像を超えておったんですな。普通の子供なんです。大人にしても同じです。私とたいして変わらない勤め人風ですな」
「ま、すり鉢みたいな街だと思うんだな、渋谷は。そのすり鉢の上部と底とではかなり違う住民意識というものがあって、街に対するイメージも上部と底とでは一緒にできないところがあるということです」
そんな風にして、バブル後の渋谷の街の描写からこの物語は始まる。ここで使われた「普通」という言葉は、この著作を通しての1つのキーワードだ。
「うち、普通のうちなんです。私も普通の子でしたし、うちの親も普通の親なんです。おとうさんはサラリーマンですし、それって普通のことでしょう?」 彼女は、他の被取材者の多くと同じように呪文のように”普通”を言い募る。だが、彼女と彼女の実父との間におこったことはそれほど”普通”ではない。 「びくってしたけど、おとうさん、ものすごく酔ってるんです。ふらふらで、まったく何も見えていないみたい。私もどうしようかって悩みましたよ。でも、おとうさん、何も見えてないでしょう。だから…」 だから? 「ま、いいかって思ったんです。おとうさん、わからないんだもん。ま、しょうがないかって。”抜けば”いいんでしょう。要するに。わからないうちに。だから、抜いたの。別に本番やるわけじゃないんだし」
普通であること、周りと同じであること、そうした姿勢を強要する学校、あるいは世間体だけを取り繕おうとして子供には無関心な家族。そこから反発するように街に繰り出し家に帰らない少女たちもまた、普通であることを望んでいる。見えない誰かの眼差しに怯えながら、周りと同じにすることでしか空っぽな私を維持することができない、とでもいうようなこの気持ち悪さは、今の日本にも相通じている。この本を読んで、なかなか読後の金縛りから抜け出せないのは、今のひどい日本の状況が自分が生まれる前後からすでに存在していて、決して、今が突然悪くなったのではなく、この時からすでに日本は壊れていたということを正面から叩きつけられたからだろう。
それに加えて、やはり重くのしかかってきたのは、著者の井田真木子さんの尋常ではない書くことへの執念が、特にこの著作を読んでいて強く感じるものがあったからだろう。それは、彼女にとって、他ならぬ生きる手段だったのだろうと思う。
この2つのことが同時に感じられたのが、物語の最後に挿入された、井田自身の告白だった。
「もう家庭も家族も、親も子供たちも、少ない例外を除いて、ほぼ壊れたんです。壊したのはほかならぬ私たちで、私たちは取り返しのつかないことをしたんです。まず、それを認めることです。すべては、まず取り返しがつかないほどまでに壊れたんです。私たちの大半は廃墟の中にいる。それを自覚する。廃墟の中でどうやって生き延びるのか。それが問題です。難問だけれども、たったひとつの希望は、私たちの多くが廃墟の中にいるということです。まずは、自分が廃墟の中にいるとみんなに言うことですね。しかし生き延びようとしていると言うことです」 あんたはいつからその”廃墟”を感じ始めたんだね。ロジャーがいつになく柔らかい口吻で尋ねる。 「十三から十四の間です。八歳のときに強姦されましてね。そのときには自分が何をされたのかわからなかった。十歳を超えるあたりから少しずつ事情がわかりはじめて、十三歳から十四歳の間に、衝動的飲酒というんでしょうか、定期的に大量のアルコールを飲んではふらふら出ていって、廃ビルの地下に酩酊状態で転がっているという行動を起こしはじめました。十五歳からは、その行動は顕著でした。その行動を抑制できるようになったのは、二十三歳から二十四歳の間です。しかし、その間も学校にはちゃんと行っていました。成績は悪くなかったし、誰にも、そんな行動をとっていることを悟られなかった。でもこれは珍しいことじゃないですね。驚くほど多くの人が、十歳以下で同じ経験をして、十三、十四歳くらいで、売春や薬に走っている。その行動は約十年続き、幸運な人間は、その行動を抑制できる年齢まで生き延びる。ただし、自分だけが汚れた十年間を抱え込んでいると思っている人は多いですね。私が経験したのは悲劇でも特異な体験でもないですが、自分の中に廃墟を感じ始めたのは、たしかに、十三、四歳の間です。そして今は四十歳ですが、まだ生き延びたいと思っています」
このモヤモヤとしてつかみどころのない、いいとも悪いとも言えない読後感から抜け出すには、もう少し時間がかかりそうだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
