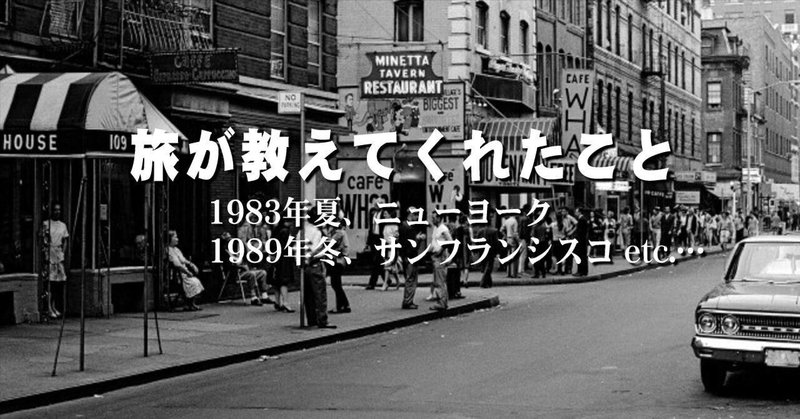
旅が教えてくれたこと (12) 2002年冬、北京
■その1
秋にベルギーを旅した、同じ2002年の12月、思いがけない成り行きから北京へと行くことになった。当時の僕は、香港には何度も仕事で行ったことがある他、中国本土は仕事でシンセン、広東、上海などを訪れたことがあった。しかし、なぜか北京へ行く機会はなくその時が初めての訪問となった。以下は、飲み屋での会話がきっかけとなって訪問した、13年前の北京の話である。
ところで、この時以後にも北京には数回行ったが、いずれもまだ日中関係が今ほど悪化する前である。個人的には北京で街歩きをしていて特に不快な状況、危険な状況に陥ったことはなかったが、最近はそうでもないらしい。仕事で北京に駐在している友人の話では、ここ数年は明らかに現地の人が日本人を見る目、接触のし方が変わったという。国と国の関係は、個人旅行のあり方にも大きな影響を及ぼすし、国家間の関係や歴史的事実に関する知識や配慮がないと、安全で快適な旅行は難しい。
朝10時過ぎに成田を離陸した全日空機は、一路北京へ。真冬の北京が寒いことは十分にわかってはいるものの、機内アナウンスで「ただいまの現地の気温は零下3度…」と聞いた時には、「この気温の中で夜遊びするのは厳しい」と、少し怯んだことは事実だ。
それでも4時間弱の短いフライトを終え、午後2時前には北京国際空港に降り立った。通関はスムーズ。とりあえず空港の地下にあるカフェでバカ高いコーヒーを飲み、タクシーに乗った。目指すは、知人の「金さん」のお宅である。
「金さん」と言っても、「遠山の金さん」とは関係がない。ハルピン出身で、幼少の頃からバイオリンを学び、プロを目指して北京の音楽院に進学、その後諸般の事情で来日して池袋西口で餃子店を営んでいた「金さん」である(2015年現在この店はない)。
ある夜、金さんのお店で餃子をつまみにお酒を飲んでいたら、金さんから「北京の実家で外国人向けのゲストハウスをやりたい。ついてはホームページを作って欲しい」との依頼を受けた。早速簡単なホームページを作ったのはいいが、肝心のゲストハウスの写真がない。じゃあ、僕自身が金さんの北京の実家に泊まってデジカメで写真を撮ってこようか…、なんて話をしたのが、今回の北京行きのキッカケである。北京へ行く話を、当時連載を書いていた自作PC専門誌の編集者に話したら、ついでに当時「中国の秋葉原」「中国のシリコンバレー」と言われて注目されていた「中関村」を取材してきて記事を書いてくれと言う。それで、クリスマスも近い年の瀬の12月になんとか4日間の日程をやりくりして北京にやってきたというわけである。
さて、北京空港で乗ったタクシーは、高速道路を走る。自慢じゃないが、僕は中国語は全く話せない。そこで旅行前に、金さんに「この紙をタクシーの運転手に見せればOK」という、行き先メモを書いてもらってきた。メモを見せると運転手はすぐにわかったらしく、一安心。20分ほどで、中心部の東、朝陽区望京西というところにある金さんの自宅に到着した。「嘉潤花園」という建物だが、なんと40階建てに近い高層マンションだ。
金さんの母上には笑顔で出迎えて頂いた。まずは、その夜を過ごすことになるベッドルームに案内されたが、清潔で居心地のよさそうな部屋である。これはもうアメリカやヨーロッパのB&B(ベッド&ブレックファスト)と同じだ。ダイニングでお茶をご馳走になってから、午後の北京市街へと出掛けることにした。
金さんのお宅の前でタクシーを拾い、とりあえず繁華街へと向かう。北京といえば天安門広場…、ということで、とりあえず毛沢東の巨大な肖像画がある天安門へと向かった。夕方の4時頃というのになんとなく薄暗く、遠くの景色が霞んで見える。零下5度前後と思われる極寒の中、かなり多くの観光客がいる。外国人も多いが、中国人の観光客が非常に多い。地方から北京へ出てきた人達だろう。多くの人が、天安門の前で代わる代わる記念写真を撮影している。
次いで広大な天安門広場を南へ歩いて縦断し、前門へと向かった。冷たい灰色の空の下、風も強くともかく寒い。時間はまだ夕方の5時頃なのに、もう薄暮の雰囲気だ。考えてみれば、早朝自宅を出て機内食を食べただけで、朝からロクなものを口にしていない。ちょっと時間が早いが、冷えた体を温めるためにも食事をすることにした。
前門はすごく賑わっている。寒い中にも関わらず、人手が多い。前門に近い一帯はレストラン街である。特に北京ダックの店がたくさん並んでいる。なんでも、この辺りが北京ダック発祥の地とのことだ。看板に「北京ダック」と大きく書かれた適当なレストランに飛び込んだ。北京ダックとビールを中心に、いくつかの小皿料理を注文する。
北京ダックには、いろいろな食べ方があるらしいが、当地では皮だけではなく身も一緒に食べる方が一般的とのこと。適当にオーダーしたら、大きなお皿に山盛りのダックが運ばれてきた。しかも日本円で千円ちょっとの値段だ。ダックも小皿料理もなかなか美味しく、満足した。
夕食を終えるて外へ出ると、寒さは一段と厳しい。食事で体が暖まったところで、賑わう前門一帯を少し散策し、タクシーに乗って王府井に向かう。
夜の王府井は、ネオンが煌々と輝き、実に賑やかである。零度以下の気温にも関わらず、歩行者専用となった広い道路いっぱいに人が歩いている。いくつかの巨大なショッピングセンターやデパートにも入ってみたが、ここはもう銀座あたりの専門店街と変わらない。いや、ショッピングセンターの規模と品揃え、そして人出が多いことは、銀座以上だろう。ブランドショップが並び、スターバックスコーヒーなども飲める。1994年に上海を訪れた時にも驚いたが、北京の発展振りはそれ以上の驚きだ。というのも、上海やシンセンは経済特区として発展してきたわけだが、北京はどうも「社会主義の中華人民共和国の首都」のイメージがあり、あまり華やかなイメージがない。ブランドショップの前でサンタクロースの衣装を着た店員が呼び込みをやっている…という北京の繁華街の姿には、かなり新鮮だ。裏通りに入ると、昔ながらの露天街があり、こちらもまたすごい賑わいだ。ともかく人の多さには驚きである。屋台の店を冷やかしたり、王府井界隈の胡同(フートン)をうろついたり、近くの繁華街を散歩する。
さて、あまり遅くなっては申し訳ないと思い、10時前には金さん宅へと戻ることにした。途中タクシーの運転手が「嘉潤花園」をなかなか見つけられず、迷いに迷って、帰宅が11時近くになってしまった。金さんの母上には、起きて待っていて頂いたのだが、心配をかけてしまった。帰宅後は、出発前夜にほとんど睡眠をとっていなかったこともあり、パタっと寝てしまった。
翌朝は、8時過ぎに起床すると、既に朝食の用意が出来ている。お粥や饅頭などテーブルいっぱいの豪華な朝食だ。金さんの母上と姉上が作ってくれた朝食は非常に美味しく、お腹いっぱい食べた。朝食後は、しばし金さんの母上と歓談し、午前10時頃に「再見!」と挨拶しながら金さん宅を辞去する。今日は、王府井のホテルへと移動する予定だ。
出発の前日にインターネットで予約しておいたのは、王府井にある「松鶴大酒店」というホテル。安くてロケーションのよいホテルを探して適当に予約したものだ。
タクシーがホテルに着いたのはまだチェックインタイム前の10時頃である。フロントで荷物を預かってもらって、出かけようと思っていたのだが、部屋が用意されていたのですんなりチェックインできた。値段の割に広くてよい部屋で、満足である。
■その2
ホテルの部屋に荷物を置くとすぐに、今回の旅行の目的の1つである「中関村」の取材へと向かった。中関村は、北京の中心部から北西に車で30分ほど、当時も今も一帯は北京大学を始め多くの大学が集中している文教エリアだ。またこの中関村は、当時から「北京のシリコンバレー」と呼ばれていて、コンピュータ・電子部品関係の企業が林立していることで知られていた地域だ。また「北京の秋葉原」とも呼ばれていて、電子部品やコンピュータの販売店も多いと聞いていた。
ちなみに2015年現在の中村関地区には、長さ200メートルほどの「創業大街」(創業通り)が政府の旗振りで生まれ、ネットカフェが並び、生まれたばかりの会社のオフィスになっており、起業したい人向けの手続きサービスや、投資機関の出先出張所も揃っている。
中関村に着いてタクシーを降りると、巨大なビルが林立している。それらのビルには「○○電子城」と書かれており、たくさんの人が出入りしている。とりあえず、手近な「電子城ビル」に飛び込んだ。
さて電子城の中はと言えば、ビルの中を小さなパーツショップが埋め尽くしている。秋葉原駅前の旧「ラジオ会館」や総武線横の旧「東京ラジオデパート」の規模を大きくしたようなところだ。そうえいば、バンコクの「パンティップ・プラザ」に非常に良く似ている。僕が飛び込んだビルは、1階から6階までをびっしりと数百軒のコンピュータショップが埋め尽くし、そこを押すな押すなの状態で買い物客が歩いているのだ。すごい熱気である。最初は呆然としたが、気を取り直して1軒1軒お店を見ていくことにした。
マザーボード、CPU、ビデオカード、各種周辺機器など、売っているパソコン関連商品は、基本的に秋葉原と全く同じえd、当時の最新パーツばかりだ。2002年当時だから、Socket478やSlotAマザーが所狭しと並べられ、CPUはPentium4が中心だ。ビデオカードもGForce4やRADEON9000など2002年当時の最新の製品ばかり。その他、スピーカー専門店やケース専門店、メディア専門店などお店の構成も秋葉原と同じだった。ちなみにマザーボード、CPUなどパーツの価格もほぼ日本と同じか、少し安いぐらいだ。ケースやスピーカーは日本よりも安い。パーツショップだけではなく、完成品のパソコンを売っている店やデジカメ専門店などもある。完成品パソコンの価格も、日本のショップブランド製品とほぼ同等で、Celeron1~1.4GHzクラスのデスクトップPCが3~4万円程度である。デジカメだって、日本で買える新製品は全て購入できる。2002年12月中旬の時点で、日本でも発売直後のNikon「COOLPIX3500」などが展示してあった。日本製デジカメの価格は、日本の安売り店よりちょっと高いようだ(むろん、全てが2002年当時の話である)。そして、中関村はある程度英語が通じる店が多い。
この電子城ビル1箇所だけで、おそらく秋葉原の全PCショップと同じぐらいの数のお店が入っている。こうしたビルがいくつもあるのだから、これはもう中関村は秋葉原とは比較にならないほど巨大な電子マーケットである。そして、規模の大きさや店の多さもさることながら、人の数に驚く。たくさんのコンピュータショップやパーツショップの入った巨大なビルの中が、人波でごった返しているのだ。活気もまた、秋葉原以上である。中関村を「北京の秋葉原」と呼ぶなんてとんでもない。逆に秋葉原を「日本の中関村」と呼ぶべきだと思った。
いやぁ…中国はすごい。北京はすごい。コンピュータ関係は進んでいる…と聞いていたが、聞きしに勝る現実を見たのであった。
ちなみに中関村で、日本ではもう購入しにくくなった「Slot1→Socket370変換アダプタ」を見つけたので、40元(600円)程度で購入した。
中関村の取材を終えた僕は、次にもう1つの「北京の秋葉原」である朝陽区の電脳ビル「百脳匯」の取材へと向かった。当時既に北京市内でパソコンや周辺機器を入手できる場所は、中関村だけではなかった。当時はもっと中心部に近い北京市内にも小規模な電脳ビル(パソコン街)がいくつか存在した他、一部の百貨店などでもパソコンコーナーの品揃えを充実させ始めており、市中心部から遠い中関村まで行かなくてもパソコン周辺機器やパソコンパーツが入手できた。そんな北京市内の電脳ビルの中で、朝陽区の「百脳匯」は、北京のパソコンユーザーにはかなり有名な場所だった。当時は、中関村のショップもこの「百脳匯」を競争相手として意識するほどの集客力を誇っていた。
百脳匯がある朝陽区は、北京市内のハイセンスエリア。各国の大使館、外資系企業向けのオフィスビルや高級ホテル、ショッピングセンターなどが多く、外国人向けの高級マンションやおしゃれなレストラン、ディスコ、バーなどもたくさんある。さらに地元住民の中でも外資系企業などに勤める高所得者層が住むマンションがたくさんあるようだ。有名なバー街「三里屯」も朝陽区だし、百脳匯はその三里屯にも近いところにある。
百脳匯の周辺には、デパートや映画館、カフェなど、おしゃれな店がたくさんある。すぐ隣にスターバックスもあるので、買い物に疲れたらゆっくりとコーヒーを飲みながら一休みできる。
百脳匯へは、王府井や東単あたりからだと、タクシーで15分ほど。中関村の電子城群と較べれば小規模な電脳ビルだが、それでも地上4階に渡って200店程度のパソコンショップ、パーツショップが入っているので、ここでパーツや周辺機器は全て揃う。だから北京に滞在中に、「マウスが壊れた」「モデムケーブルやLANケーブルが欲しい」など、ちょっとパソコンの周辺機器などが必要になったときには、中関村まで行かなくとも、この百脳匯へ行けばOKだ。
パソコンや各パーツの価格は、ほぼ中関村と同じ。ということは、日本の秋葉原とほぼ同じ価格か、それより安いぐらい。パソコン本体はむろん、マザーボード、HDD、ビデオカード、CPU、メモリなど、自作に必要なパーツや周辺機器は何でもある。むろん、秋葉原や中関村と同じレベルの最新のパーツを販売している。地域性を反映してか、どの店も心なしか中関村の電子城内のショップよりもオシャレな雰囲気だ。中関村ではあまり見かけない、CUBE型ケースを採用したベアボーンキットなども展示されていた。また、バルクパーツの店だけでなく、メーカー系のパソコンや周辺機器、デジカメ等を販売している店も多い。VAIOショップでは、SONYの最新型のノートPCやデジカメが、日本の量販店と変わらない価格で販売されている。パソコンゲームを中心に販売する、ソフトショップが多いのも特徴だ。
しかし、逆に言えば中関村の電子城内のショップのような「怪しげな楽しさ」はない。また、中関村のように人でごった返している感じもない。ちょっとおしゃれな高校生、大学生ぐらいの若い子が、たくさん買い物にきていた。ビルの前には、トランクに詰めたコピーソフトの売人がたくさんいるのが愛嬌だ。コピーソフトは、OSでもゲームでも何でも5元(65円)で買えた。
取材を終え、いったんホテルへ戻って一休みした後、夕食に出かける。ホテルから歩いて「東単」側に出て、そのまま南下した。東単は、ファッション関係のお店が多い。日本の原宿や渋谷にあるのと変わらないようなブティックも並んでいる。建国門内大街に近いところで王府井へと続く巨大なショッピングセンター「東方新天地」に入った。地下街を歩いていたら、巨大なフードセンターがあったので入ってみた。
中には、ずらっといろんな料理のお店が並んでいる。要するにバンコクやクアラルンプールなどにも多いクーポン食堂だ。最初に食べたい分だけの金額のクーポンを買うのだが、驚いたことにクーポンはICカードである。しかも、多接点のスマートカードだ。2002年当時は、日本でもICカードを使っているクーポン食堂には、まだ多くはない。当時から最先端技術を駆使する、北京の小売事情を目の当たりにした。
さて、ここでは、ウイグル式の羊肉の串焼き、雲南式のチャーハンなど、いろいろと変わった料理を食べてみた。どれも美味しい…というわけではないが、まあ面白い食事となった。
お腹がいっぱいになったところで、ショッピングを続ける。考えてみたら、北京へ来てから「みやげ物」を何も買っていない。僕は、中国茶や薬なんかに興味はないし、いかにも中国風の小物、置物なんてもっと興味がない。中国では、お土産にしたいような物が何もない。とはいいうものの、土産物屋やスーパーマーケット、屋台などを冷やかして歩くのは楽しい。大きな書店なんかにも立ち寄ってみたり、夜の東単界隈を満喫した。
■その3
3日目は、前門付近の路地にある胡同の探索に向かった。
胡同は、よく知られている通り、古くから庶民が生活する北京の路地だ。車1台がやっと通れるほどの狭い路地に、路地に面した小さな家が立ち並んでいる。厳密には、旧北京城内の路地を「胡同」と称するそうだから、明の時代以降に出来たものと考えてよいのだろう。もとはモンゴル語の「xuttuk」という「井戸」や「集落」の意味を表す言葉から来ているとの説もある。元・明・清代に建てられた「四合院」という伝統様式の家が建ち並んでいる。
かつては北京城内に数千を越える胡同があったそうだが、北京の都市化、近代化とともに急激に数を減らし、特に1990年代以降の中国の経済発展に伴う市内再開発によって、ますますその数を減らしている。2008年に北京オリンピックを控えた中国政府と北京市が、市内からこの胡同を一掃しようとしたが、結果的には2015年現在も北京市内の一部地域にかろうじて残っている。最近では観光客だけでなく、北京の市民すらが、郷愁をそそられる場所として見物に来るそうだ。その胡同が近々北京市内からなくなるかもしれない…、当時はそんな話を聞いていたので、残っている胡同をじっくりと歩いてみることにした。
冬の胡同には、路地いっぱいに練炭の匂いがたち込めていた。ガス調理設備や近代的な暖房器具が完備していない胡同では、練炭が調理、暖房のエネルギー源に使われている。自転車に練炭を山積みしたたくさんの「練炭売り」が、路地を行き来している。どの家の前にも、使い終わった練炭のカスが山積みになっていた。
胡同の足は自転車だ。どの家の外にも、必ず2~3台の自転車が置いてある。狭い路地に対して直角に、人1人がやっと通れるほどの、さらに狭い路地が続いている場所もたくさんある。10mほどで行き止まりになっているそうした路地には、日常生活に遣う道具がたくさん置いてある。干してある洗濯物が見え、子供が遊んでいたりする。
胡同の中には、生活に必要なものが何でも揃っている。あちこちに日常雑貨を売る小さなお店があった。こうしたお店では、普通の電話を店の前に置いて「公衆電話」のように使わせてくれる。また胡同では家にトイレがないのが普通で、あちこちに共同便所がある。共同浴場もあった。鶏や鳩を飼っている家も多い。
前面付近の胡同探索を終えた後は、「天壇」へ行ってみることにした。
北京にある「天壇」は、1420年(永楽18年)に完成した(完成は1421年という説もあり)。1421年といえば、昔読んだ「1421~中国が世界を発見した年」という本を思い出すが、あの鄭和を送り出した明の永楽帝の治世だ。天壇こそは、中国に現存する最大の祭祀建造物であり、世界遺産にも指定されている。あまり知られてはいないが、故宮を東西南北から取り囲むようにして、地壇、日壇、月壇があり、そして「天壇」があるのだ。
天壇は内壇と外壇に分かれ、祭祀は主に内壇で行われる。南には圜丘、北には祈年殿がある。天壇の南側は四角形、北側は円形で、古くから中国に伝わる「天は円形で地は四角形」という宇宙に対する考え方を象徴している。天壇は、中国にとっての「秩序」そのものだ。
その天壇の中でもっとも有名な建築物が、五穀豊穰を祈る本殿の「祈年殿」。3層の大理石の壇上に建てられた祈年殿は、直径30m高さ38mの円形の3階建て木造建築で、釘を一本も使わずに建設されている。頂上部には瓦が葺かれ、到るところに金めっきが施されていた。
天壇は中華帝国の中心でもあり、宇宙の中心でもある。古来、中国の皇帝は「天子」と呼ばれまた。それは、唯一皇帝だけが「天と交信できる」からだ。冬至の日に皇帝はこの天壇に登り、自らが宇宙と一体化した存在となって「天の声」を聞き、それを臣下や民衆に伝えたという。
凍えるような冬晴れの北京、柔らかい冬の日差しを浴びて蒼穹に屹立する祈年殿は、神々しさを漂わせていた。
お昼になったが、その日食べるものは決まっている。「羊肉のしゃぶしゃぶ」だ。金さんの甥の青年が安くて美味しい店に連れて行ってくれるという。
羊肉のしゃぶしゃぶは中国東北地方の代表的な料理だが、北京を代表する料理でもある。ちなみに羊肉のしゃぶしゃぶのことを「シュワンヤンロウ」と言い、「サンズイに刷」という漢字を書くが、これは残念ながらパソコンでは表記できない。
ハルピン水餃子の金さんによると、北京に住む人はみな羊肉のしゃぶしゃぶが大好きだそうだ。冬はもちろん体が暖まるし、暑い夏でもスタミナがつくので人気があるとのこと。そこで今回は、この北京の人々の好物である羊肉のしゃぶしゃぶを食べに行くことにしたのだ。
案内されて訪れたのは、朝陽区にあるしゃぶしゃぶ専門店で、広くてきれいなお店だった。店名からすると、牛肉のしゃぶしゃぶも売りになっているようだ。
まずは、スープが入った人数分の1人用コンロ(固形燃料らしきもので加熱)がテーブルの上に置かれる。スープには、香味野菜や香辛料らしきものが入っているが、中国語でその名称を聞いても種類はわからない。次にタレが運ばれてくるが、これはちょっと辛味のある味噌のようなタレと、醤油っぽいタレの2種類が運ばれてきて、その2種類を店員が混ぜてくれえう。その他に、テーブルの上には何種類もの漬物が並べられた。
注文したのは大量の羊肉と牛肉、豚肉、そしてイカ(ホタルイカのような小型のイカ)だ。肉はいずれも、超薄切りにされた肉片が丸められて大量にお皿に盛られている。他に野菜(青梗菜、レタス)が盛られたお皿も来た。
後は、沸騰したスープの中で肉をシャブシャブと洗って、タレにつけて食べればよい。基本的には、日本で食べるしゃぶしゃぶと同じ。薄くスライスされた羊肉は、一瞬スープにくぐらすだけで火が通り、ともかくあっさりしているので、食が進む。牛肉も豚肉も実にうまい。タレも美味しい。ビールを飲みながら羊肉をお腹一杯食べて、心も体も暖まった。ちなみにお勘定は安く、2人でお腹いっぱい食べてビールも飲んで1000元(約1,200円)程度と格安。北京の冬は、体が温まる羊肉のしゃぶしゃぶに決まりだ。
さて、その夜は三里屯でカフェやクラブをハシゴするつもりだった。いったんホテルでゆっくり休んだ後、夕方になって三里屯へと向かった。ホテルからタクシーで15分ほどで三里屯に着く。歩道に面してカフェやクラブが並び、どの店もまぶしいほどネオンサインが輝いている。人通りも多いが、呼び込みも多い。開けたドアからは生バンドの歌声やカラオケの歌声が聞こえてくる。呼び込みに誘われるままに、小さな店に飛び込んだ。客は圧倒的に外国人が多く、しかも白人ばかりである。メニューも全て英語だ。外国製の主要なビールの銘柄が何でもあり、カクテルの種類も豊富である。あまりうまくない生バンドの演奏を聴きながら、ポップコーンをつまみ、ビールを飲む。中国人バンドの演奏を聴きながら飲んでいると、何だか中国にいる感じがしない。かといってアメリカやヨーロッパのクラブやカフェとも雰囲気が違うし、日本のライブハウスの雰囲気でもない。不思議な感覚だった。
三里屯は、大通りを挟んで北地区と南地区に分かれる。北地区でビールを飲んだ後は、南地区へと向かった。夜が遅くなればなるほど、人出が増えてくる。南地区で見つけたお店は「Durty Nellie's」という、アイリッシュパブ。ギネスの看板に誘われて入ってみた。
Durty Nellie'sは、三里屯の中ではかなり大きなクラブだ。奥の方には、ビリヤード台なんかも置いてある。欧米人の客で満員である。何だか、みんな大騒ぎしている。大好きなギネスの生が飲めるのはたまらないが、1パイントのカップの値段は日本とあまり変わらない。飲んでいるうちにお店の中にはどんどん客が入ってきて、皆立って飲んでいる。
そうこうしているうちに、生バンドの演奏が始まった。小さいクラブのバンドは、たいてい2人か3人で、カラオケをバックに演奏するスタイルだが、ここのバンドは5人フル構成だ。いきなり始まったのが、「サンフランシスコ・ベイ・ブルース」。なかなか演奏も上手い。ロック、ブルース、ポップスと何でもやるが、70年代の曲が多いのが気に入った。
ギネスのお代わりを飲んでいい気持ちになっていたら、突然ピンクフロイドを演奏し始めた。アマチュアの生バンドがピンクフロイドを演奏するというのは、とても珍しい。曲は「Wall」である。
「深夜の北京のクラブで、ギネスを飲みながら、生バンドの演奏するピンクフロイドを聴く」…、何とも不思議なシチュエーションである。一瞬、自分がどこにいるのか、何をしているのか、わからなくなってくる。
雑多な人種で熱気溢れるクラブの中で、ピンクフロイドを聴きながら、真冬の北京の夜は更けていった…
最終日、飛行機は午後の便だ。正午過ぎにタクシーに乗れば、搭乗時間には十分に間に合う。そこで、夜遊びの後でちょっとつらいが、早起きをして故宮を見物に行くことにした。
故宮は広い。まあ、こんなものか…という感想である。明、清の皇宮であり、その歴史的価値や建築物の壮大さも含めて、けっして軽んじてよい場所ではない。ここで暮らした明、清の皇帝の強大な権力と膨大な家臣団の姿が思い起こされはする。がしかし、なんとなく映画のセットのような寒々とした感じがしないでもない。
1時間ほど故宮を見物して、出発までにはまだ時間があるので、最後に前門一帯をもう1度散策することにした。寒いと思ったら、雪が降り出している。前門は、有名レストランが並ぶ前門大街沿いよりも裏通りの方が楽しい。大柵欄街あたりを中心に路地から路地を歩く。小雪が散らつく寒空の下、饅頭や惣菜を売る屋台が並び、自転車に乗った新聞売りが声をあげて行く。小さな食堂、古い旅館や浴場なども多く、楽しい雰囲気である。ついつい時間を忘れて、路地探索に熱中してしまった。気がつくと、ホテルへ戻ってチェックアウトしなければならない時間だ。部屋で簡単に荷造りを終え、チェックアウト後にタクシーで空港へと向かった。
この時の旅には、もうひとつ忘れられない思い出がある。金さんの家を辞去する日の朝、金さんのお母さんと朝食を食べながら話をしていた。実は、金さんのお母さんは日本語をかなり上手に話す。彼女の年齢は2002年当時に70代後半、ハルビンの生まれで、日本の国民学校に通っていたのだそうだ。彼女が小学生だった頃のハルビンは満州国の主要都市でありであり、複数の国民学校があった。
そのお母さんが僕に、「この歌の歌詞を知っていますか? 好きな曲だけど曲の名前と歌詞がどうしても思い出せないのです」といって、「ララーラ ラーラ ラーラ」と口ずさんだ曲は「早春賦」であった。それで、僕がうろ覚えながら「春は名のみの 風の寒さや 谷の鶯 歌は思えど 時にあらずと 声も立てず 時にあらずと 声も立てず」…と歌ったら、「ああ、そんな歌だった」と自分でも何度も歌っていた。
幸いなことに金さんのお母さんは、子供が日本に住んでいることもあって特に日本という国に対する悪感情を持っていないようだったが、僕は中国でこの世代の人と話す時には、その人の歴史や背景について深く考える必要があるなぁと、あらためて思った次第だ。
「五族協和」「王道楽土」を建国理念に掲げた満州国ではあったが、実際に日本人が中国人に何をしたのか、日本の満蒙開拓移民団が中国人の土地をどうやって奪っていったか、歴史が教えている通りである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
