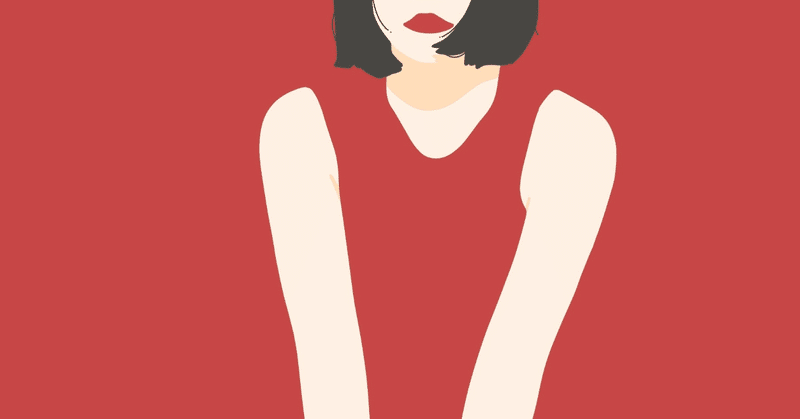
真夜中に 乳と卵
産むんじゃなかった。
母は、私を見下ろしながら、あっけらかんと言い放った。私が何歳のときか忘れてしまったけれど、そのパンチラインに正面から殴られて、眼前がチカチカと点滅したことを憶えている。私はただ、リカちゃん人形の洋服をもう一着買って、とねだっただけなのに。あの小さな小さな服の代償は、私のアイデンティティを粉々にすることだった。
わたしは、いらん子。
瞬時にそう思うと、さきほどまで魅力的だったリカちゃん人形の洋服は、ただの布切れに見えて、私はそれを元ある場所へ戻し、母に何も言わずにおもちゃ売り場を後にした。そして、父が座っているベンチへ行き、その横に腰かけた。
泣くことも、怒ることも、話すこともできなかった。
たぶん、黙りこむことで、いまにも決壊しそうな心を防御していたのだろう。それからあとのことは憶えていない。ただ、肌感覚で云えば、ひとり、湿った判然としない空間へ放り込まれたような気分だったことは、朧げに記憶している。
☽ ☽ ☽
夜が沈殿して、上澄みを掬い取ったような透明な薄明るい月光が、カーテンの隙間から部屋を照らす。その光線を使って、むかしのケロイドになった古傷をなぞるような気分だった。
眠れない。
私はそう思うと、布団の中から這い出て、夜の底にストンと仁王立ちした。こういうときは本を読もう!と闇に順応した眼で本棚の前へ移動して目を瞑り、人差し指で本の背表紙をなでながら安定のドラムロールを口にする。「ドゥルルルルルルル(結構リアル)。ジャンッ!」と言いながら目を開けて、本を取り出してから照明を点けた。ぐらっとした眩しさを感じて目の奥がジンジンする。闇に溶けていたものが形や色を取り戻したように、発光しはじめた。薄目で指差した本を見ると、小説『乳と卵』だった。
第138回芥川賞を受賞した川上未映子さんの短編小説。私は、本棚から小説を抜き出すと、心がぐうっと縮こまるような気がした。いまの私にぴったりのドラムロール選書は、こころに食い込む。私は、その装丁をていねいに視た。紅白の波が盛り上がっては沈み重なり、ゆれている。そして、気が済んだあと、表紙をめくった。
あらすじは、豊胸手術に取り憑かれ上京してきた姉である巻子と、思春期を迎え言葉を発することを拒否しているその娘の緑子、そして、巻子の妹である主人公の夏子が過ごす三日間を主軸にストーリーは展開されていく。
この小説は、句点がほとんどなく読点が続き、小気味良い言葉のリズムの羅列が押し寄せてくる。それはまるで、クロールを泳いでいるような気がした。文章を泳いで読点が息継ぎのような、そんな心持ちになる。
この文章に抵抗があったのはひとは、なんだこれは、という拒絶感が芽生えるかもしれないけれど。私の眼は、上から下へ文章を絶え間なく追いはじめた。
物語の芯にあるものは、母と娘の確執と、女が女に対して感じる憐憫と、小さな理解が描かれていた。そして、私がフォーカスしたのは緑子だった。それは、かつての私のようだったから。
思春期の緑子は話さない代わりに、ノートへ書いて会話をしていたり、日記を書いて、自分の性と生にまつわる疑問や、少女から女性への体の変化に対しての不安や、ラベルのついていない自身に対しての違和感や焦燥感がむき出しの言葉で綴られていた。私には、沈黙し内省することで、自己を保とうとする心理がとても、というか、突き抜けるくらい理解できた。そして、それを理解できない、大人たち。
私も小学生高学年のときに、緑子と同じようなきもちだった。これから女として乳房が膨らみ、丸味を帯びていくであろう身体への戸惑い。学校で教わる教科書通りの性教育。スポブラをつけはじめた同級生。生理の日はパンツとブルマの二枚ばきがいいと言う噂。初潮を迎えたら赤飯を炊く謎。なぜ自分は生まれてきたのか。
それらを不思議に思いながらも初潮を迎え、赤飯を食べ、乳房は膨らみ、スポブラをつけ、生理のときはパンツとブルマの二枚ばきになり、夏子のように夜中に生理の血で汚れた下着を洗うときのなんとも言えないきもちになり、その間も棒のような手足が丸味を帯びて生々しくなってくる毎に、デキモノみたいな違和感や焦燥感は小さくなっていき、女になった。
たぶん、緑子も苦悩しながら飽きたりた道を通って大人になるはずだ。
そして、緑子は、どこか「私が生まれてきたばかりに巻子は苦労している。」というきもちがある。それからが顕著な部分がストーリー終盤にあった。
あたしは、お母さんが、心配やけど、わからへん、し、ゆわれへん、し、あたしはお母さんが大事、でもお母さんみたいになりたくない、そうじゃない、早くお金とか、と息を飲んで、あたしかって、あげたい、そやかってあたしはこわい、色んなことがわからへん、目がいたい、目がくるしい、目がずっとくるしいくるしい、目がいたいねん、お母さん、厭、厭、おおきなるんは厭なことや、でも、おおきならな、あかんのや、くるしい、くるしい、こんなんは、生まれてこなんだら、よかったんとちやうんか、みんな生まれてこやんかったら何もないねんから、
口を噤んでいた緑子は、こころから自分のきもちを巻子へ伝える。このときの緑子は、エナジーの質がすごい。はじめて、母親へ伝えたい、という想いが溢れている。生きていることで発生するくるしさをぶちまける。動きのある言葉に息が詰まりそうになった。
その言葉は、「産むんじゃなかった。」と言われたあのころの私の叫びに似ていたから。
じゃあなんで産んだ?親は選べない?辛い、悲しい、苦しい、消えたい。
こころから血が滴り落ちるような気がした。
肉体を駆使しても言葉にならない感情を作者は鮮やかに描きだしていた。不器用にぶつかりながらも、相手を理解しようとする母子。突き抜けるような言葉の応酬。
拝読後には、じわーっとあったかい何かが胸の奥で溢れ出した。私が母から言われた「産むんじゃなかった。」は、誰にも癒すことはできないけれど、緑子が言葉にしてくれたおかげで、ちょっぴりすっきりした。
時計を見ると、午前三時を過ぎたころだったので、私は本を閉じて、余韻を味わいながら意識は闇へ溶けた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
