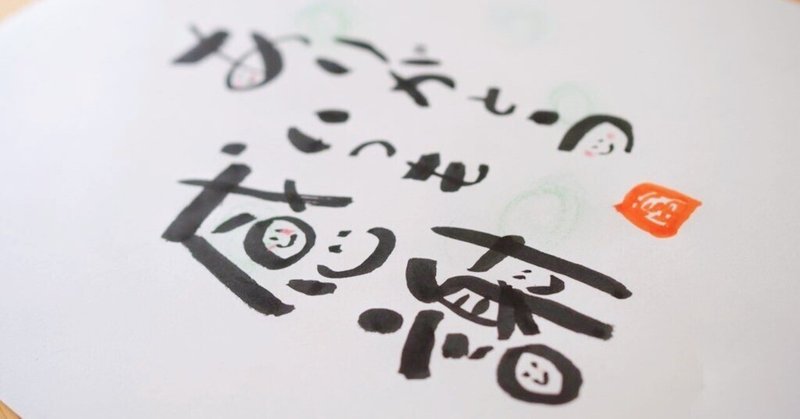
人はなぜ感謝を忘れるのか。
プロゲーマー・梅原大吾氏がラジオで語っていた話にすごく刺激を受けたので、自分なりにまとめ直しました。
テーマはタイトルの通り、「人はなぜ感謝を忘れるのか」です。
梅原氏の話を要約すると以下のような論理になっています。
「感謝」は、される側だけでなく、する側も気持ちいい。
感謝の気持ちは感情の中で最も幸福度が高いものである。
ゆえに感謝し続けることができれば人生は幸福になる。
しかし人間は往々にして感謝を忘れる。なぜか。
まず「感謝」が時間軸上において〈いつ〉起こるか考えた。
感謝は〈未来〉の事象に対しては起こらない。
〈過去〉の事象に対する感謝は純粋な感情のはたらきではなく、道徳・倫理に起因するはたらきである。
(そもそも道徳や倫理が何に起因するものであるかという議論の余地はあるが、話のニュアンスからすると梅原氏はこれらを理性に起因するものとして捉えている。対して感謝があくまでも感情の一種であると再定義している)感謝が感情であるならば、時間軸上において〈現在〉以外に起こりえない。
感謝とは現在・現状に対する満足を示すはたらきである。
感謝は現在への集中であり、現在を「最高」と定義することである。
ゆえに人間が根源的に持つ「より以上」を求める性質とは相反する。
例えば人間が自転車の発明に感謝(=満足)し続けたら、自動車や飛行機は発明されない。
仮に全員が徹底して感謝を忘れない世界があれば、その世界は発展性がないと言える。
感謝を忘れることは人間の欠陥であると考えていたが、発展のためには必要なことである。
このように考えれば、感謝しない人に対しての怒りの感情をいくらか抑制できる。
感謝は忘れるものである。どんなに腹が満たされても必ず再び腹がすくのと同じことである。
だからこそ〈過去〉をフォローするための道徳・倫理といった概念が発達したのではないか。
私には記事にしたくなるほどインパクトの強い論理でしたが、梅原氏の聞き手をしている方にはそれほどでもなかったようです。
私がこの話に衝撃を受けるのは、私自身が感謝の気持ちの薄い人間だからかもしれません。自分にとって都合がいい話ということになりますから。
▼ 私の性根のストリップ記事▼
ちなみに私は哲学的には実用主義の立場です。
真理が客観的か否か、事実であるか否かによらず、『その人にとって有用であるならば(役に立つのであれば)それは真理である』と考える立場です。
その立場からすると、「感謝しない人に対しての怒りの感情をいくらか抑制できる」という部分が話のミソになります。これは私に限らずほとんど全ての人にとって有用ではないでしょうか。
自分が所詮相手の〈より以上〉を満たせなかったのだと思えば、感謝が返ってこなかったことを自分の糧にもできるでしょう。
話の出発点がポジティブなことも素晴らしいと思いました。「感謝は気持ちいいのになぜ忘れるのだろうか」と。
これ、同じテーマを考えるにしても逆の視点から出発する人が多いのではないでしょうか。つまり、自分が感謝される側に立って「相手から感謝が返ってこない。むかつく。なぜだ」と。憶測ですが。
感謝されないことを問題にする奴と、感謝できないことを問題にする奴。どちらがカッコイイかは言うまでもありません。
テーマは違いますが、昔読んだ『食と文化の謎』という本を思い出しました。かなり面白かった記憶があります。
本著はカニバリズム(食人)について、「なぜ人間を食べる人間がいるのか」と自己を除いた事象として考えるのではなく、「なぜ我々は人間を食べないのか」と自己を含めた事象として考察していました。
論理の一歩目から自分を除外することなく、むしろ自分自身の問題に置き換えてから出発する――こういう考え方は常に保持したいものです。
閑話休題。感謝について考える話に戻りましょう。
梅原氏の論理の秀逸なところは時間軸を交えて感謝を捉えた点です。
犬を飼っている人はわかると思いますが、飼い犬はほとんど常に全力で感謝してくれます。人間よりよほど感謝を忘れません。
これは梅原氏の論理にしたがえば、動物が人間に比べ〈未来〉を想定する力が圧倒的に弱いからだと説明できます。遠くの未来を想定できないのですから、〈より以上〉を求める性質もそれだけ弱く、ゆえに〈現在〉の比重が大きくなり感謝に集中できるというわけです。
幼児にも全く同じことが言えるでしょう。
また、若人より年配者のほうが感謝できるようになるとも考えられます。未来への期待値は加齢と共に下がっていくのが自然ですから。
無論、動物にせよ幼児にせよ弱者ほどへつらわなければやっていけないという単純な事実もはたらいているとは思いますが。
なお、梅原氏は感謝における過去と現在を区別しましたがこれは蛇足と思われます。
過去に対する感謝の念(動画では道徳・倫理と呼称するもの)の本質が理性(孔子的)であれ、直観(ムーア的)であれ、情動(エイヤー的)であれ、現在までの充足感と〈より以上〉という未来への欠乏感を対比して考えるにおいて、それは瑣末な問題に過ぎないのですから。
(そもそも道徳や倫理が過去にのみはたらくものとも言えません)
日常化した行為に対して感謝を忘れがちになることも同様に説明できます。
例えばパートナーが毎日家事をがんばってくれていることに感謝し続けるのが難しいのは、そこに〈より以上〉がないからでしょう。日常生活の雑事における〈より以上〉がすぐ頭打ちになるのは当然のことなのですが、それでも無意識に〈より以上〉を求め続けてしまう。梅原氏も言っていますが、これは人間の醜さと言えるでしょう。
では老子の言うように足るを知り、〈より以上〉を求めなければ人間は幸福になるのでしょうか。
個人の幸福論としてはいいかもしれません。
が、これを社会全体の規範にしてしまうのは、例えばラッダイト運動のようなものの擁護にまで繋がりかねないので直感的には反対です。個人の最善が社会の最善とは限らない一例です。実用主義の観点から言ってもそれが有用であるとは思えない。
社会全体の規範にしないということは、自分から感謝すること(足るを知ること)は意識しても、他人から感謝が返ってくること(他人に満たされること)は期待してはならないということです。
孔子は「仁」と「礼」を説きました。
仁とは内面、礼とは表に見える作法・規範を指します。
「足るを知る」は仁の領域ですが、感謝は必ずしも仁の話に限らず礼の話でもあります。したがって、内面において〈より以上〉を求めつつ表向きは感謝しておく、ということは十分可能です。
孔子は、仁と礼は一体であり仁がなければ礼の意味はないと言います。が、私は内面と外面(本音と建前)が一致しないことを必ずしも悪いこととは思いません。それが透けて見えるような人に好意を持ちませんが。ただ『うんともすんとも談義。』に書いたように内面と外面が一致した上で嫌悪される私みたいになるより余程いいでしょう。
感謝と〈より以上〉はこうして両立できると私は考えます。
最後に哲学者・カントの考え方を紹介します。
カントは、道徳とは目的を達成する(見返りを得る)ための手段ではなく、それ自体が目的であるべきと唱えました。
カントならこう言うのでしょう。
ごちゃごちゃ言ってないで感謝せよ。
感謝(道徳的行い)とはそのはたらきを掘り下げるまでもなく、とりあえずやること、それ以上でもそれ以下でもないのだ――。
シンプル! 笑っちゃうくらいシンプル!
ゆえに有用ですね。たしかに、感謝に回数制限はありませんから、出し惜しむ必要はなさそうです。
☆ついでにもっと過去記事紹介☆
カントは道徳を先天的なものとし、人間が従う法則であると捉えています。
先天的に備わる法則とするのですから、他者とのコミュニケーションや社会性といった、後天的に把握・獲得する要素を度外視して考えているとも言えます。道徳とは人間が社会性を持つ生物だからこその概念であるはずなのに、これでは順序が逆に思えます(あるいは社会性自体がもはや先天的なものと化しているのだろうか……)。
ゆえに宗教が混じったニオイがするし、柔軟性があるとも言えませんが、その分マッチョでストロングでちょっぴりリスキーな考え方です。私はこうした考え方も嫌いではありません。
「ごちゃごちゃ言ってないで――」のパターンに触れているが以下の記事になります。
感謝が他人への次なる要求に等しくなりうること(人間が所詮カント方式では道徳を捉えられないこと)については、以下のエッセイでも少々触れています。
お察しの通り、うすーく哲学が好きな私であります。
似た者さんにはこちらも読んでほしいです。
