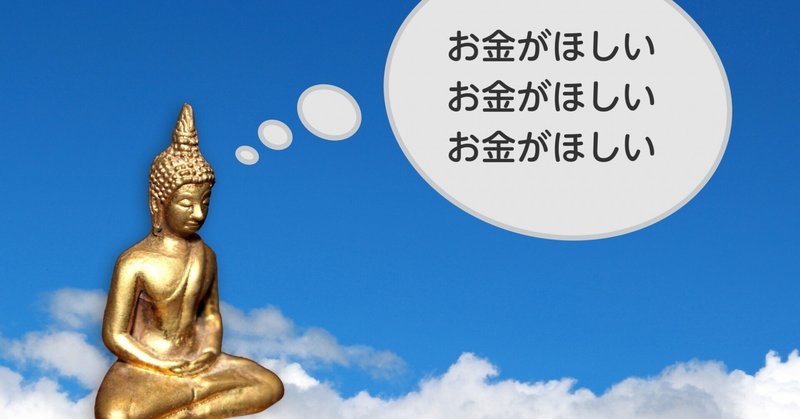
我々はなぜ働くのか。
私も久々に内田樹氏の著書でも読もうかな、なんて思ったのはオポポ(書くリーマン)さんの以下の記事の影響でした。
記事の中で取り上げられているのは『昭和のエートス』という一冊。内田氏の2008年の著作です。私は未読でした。
結局まだ読んではいないのですが、もうnote書いちゃいます。本当は良くないとわかってはいるのです、ヤフーのトピックスだけ見てニュース語るみたいなものですからね。でもやっちゃいます。
というわけで、オポポさんの三か月も前の記事を踏まえ、十五年前に出版された本に言及してきます。
■気になったのは労働の項目
内田氏が学生や若者に言及する時は常に、「近頃の若いモンは!」が思想の出発点にあるのが明確で良いですね。誰を刺したいのかよくわかる。
本著作におけるターゲットは「やりがいを求めて離職転職する若者たち」のようです。
労働の本質とは、個人の努力が集団の利益に「かたちを変える」ことに存ずる。
クリエイティブであるためには人に抜きん出た個性が必要である。
(また、その願望は軽々に口にしない方がいい)
私たちが労働するのは自己実現のためでも、適正な評価を得るためでも、クリエイティブであるためでもない。生き延びるためである。
オポポさんによる少数の引用からも、おおむねもっともだと感じられる指摘が並びます。
が、違和感を覚える件もありました。
個人の努力が個人の専一的に還元されることを求めず、逆にできるだけ多くの他者に利益として分配されることを求めるような「特異なメンタリティ」によって労働は動機づけられている。それが納得できない人は労働に向かない。
まず、ここで「動機」という単語が用いられるのは不自然です。
内田氏自身が「労働は生き延びるためのものである」と結論づけるのですから、労働の動機もまた「生き延びること」になければおかしい。
動機とは、「行動ないし決意における直接の心理的原因・きっかけ・目的」を指す言葉ですから、
「成果を分配することを労働の動機(≒目的)とすべきだ」と、
「生き延びるため(=目的)に労働するのだ」を両立させるには、
「生き延びるためには成果を分配しなければならない」
――が真でなければなりませんが、これは偽です。実際には成果を分配しなくても生き延びる手段が存在するので。
そもそも「労働」とは、
「人・事・物に働きかけることによって主に財貨(あるいはその他何かしらの報酬)を得ること」
であり、内田氏の「労働の本質」論――個人の努力が集団の利益にかたちを変えること――は、あらゆる労働の内の一種(が持つ性質)を取り上げているに過ぎません。
例えば、(犯罪ではあるが)他人から財貨を奪う一方でも生きられるし、自給自足を突き詰める(自作した食物が報酬になる)ことも理論的には可能です。そして本来、これらも広義では労働に当たります。
つまり、内田氏は「労働」の定義を初めから持論に沿うよう都合良く限定して考えていると言えます。そのような操作をした上で語られる「労働の本質」論は説得力に欠けるし、持論に沿うように労働の定義を限定できるなら「そりゃ何とでも言える」のです。
■労働とは手段である
労働の目的が生き延びることにある、という説には全く同意です。反論の余地もないでしょう。したがって労働の動機も、やはり生き延びることにあります。
この目的を踏まえると、労働は手段であると言えます。
そして、労働という手段にもいくつかの種類(分別可能な性質の差異)があり、その内の一つとして「集団で取り組む」性質を持つ労働があります。
集団で取り組む労働は、それによって得られた財貨・報酬を集団の中で分配することになります。これが現代における労働の主流です。
なぜこれが主流になったかは、狩猟採集社会の時代を想起するとわかりやすいでしょう。
個人で狩りをするより集団で狩りをした方が、より大きな獲物(=報酬)を、より効率的に獲得できるのは想像にかたくありません。
個人で狩りを成功させ、自己の生命と生活を保障し続けることは、とりあえず集団に属することで報酬の分配にあずかるより遥かに難度が高いです。それだけ抜きん出た能力を必要とします。
(クリエイティブであるためには人に抜きん出た個性が必要である)
それでもなお個人での狩りを希望する場合、それが実現するまでその本心は隠しておいた方が良いと言えます。
なぜなら、その本心が明るみになった場合、集団への献身性が低いとみなされるからです。
集団は集団に献身的な者を好み、そうでない者には排他的であるのが常です。合理的にはその人の能力が集団の目的に有用であれば本心がどこにあろうと関係ないはずですが、実際には、集団だからこそ生じる抑圧の発散や集団に属する者の連帯を強めるために排斥は行われます。
(その願望は軽々に口にしない方がいい)
■「成果を分配するための労働」はおかしい
目的、動機、労働といった言葉の定義と内実を掘り下げていくと、「成果を分配するために労働する」という意思表明(ましてそれが本質であるという主張)は日本語として論理的にデタラメな嘘八百であるとわかります。
しかし、この概念は、集団に属する者が共有するのに(彼らに共有させるのに)極めて都合の良い建前ではあります。結局この建前に耐えられないなら個人で闘える力を身につけるしかないし、この建前を妄信できる人が「(現代において主流の)労働に向いている」という内田氏の言は確かに正しいでしょう。
また、「生き延びる」の主語を個人ではなく社会(国家)にすれば、「成果を分配する労働」はおそらく必須です。
しかし、かと言って、成果を分配することを個人の労働の動機に適用できると考えるのは甘い理想論と言わざるをえません。それが叶うなら、共産主義がもっと世界中で流行・隆盛していることでしょう。
社会にとって都合の良い思想をそのまま個人の思想に落とし込めると考えるのは、社会主義的イデオロギー臭が強すぎて私には受け入れがたいものでありました。
