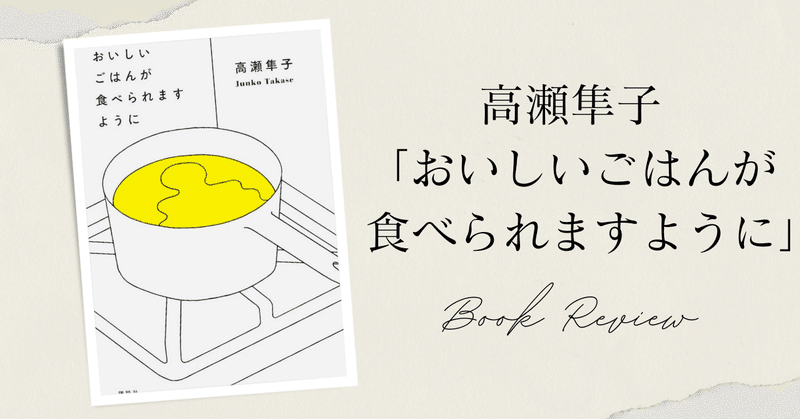
「優しいマジョリティ」への違和感|【書評】高瀬隼子「おいしいごはんが食べられますように」
2022年上半期(つまりは最新の)芥川賞受賞作となった、本書、高瀬隼子の「おいしいごはんが食べられますように」。受賞発表からすでに4か月ほど経ってはいるのですが、いまさらになって興味をひかれ、読んでみました(読書って、なぜか、「いまさらになって興味をひかれ」ることの連続な気がします。しませんか?)
結論からいってしまえば、おもしろかったです、むちゃくちゃ。おもしろすぎて、ぞっとしました。読みはじめるや、巻を措く能わず(という漢文訓読調が口をついてしまうほどの速さで)、一気に読了してしまいました。

本書がどういう小説なのかといいますと、単行本の帯からそっくりそのまま文言を引用しますけれど、「職場でそこそうまくやっている二谷」「皆が守りたくなる存在で料理上手な芦川」「仕事ができてがんばり屋の押尾」、という3人の登場人物を中心にした、恋愛小説、ないしは、お仕事小説です。
二谷は男性、芦川と押尾は女性。すなわち、ひとりの男とふたりの女、の話です。
そう書いてしまうと、ちょっと、綿矢りさ的な小説の構図(ふたりの男とひとりの女という関係性をえがいた夏目漱石とは逆の構図ですね)を想起しますが、うん、たしかに、「勝手にふるえてろ」とか「かわいそうだね?」とか、あのあたりの時期の綿矢りさの中編小説っぽいふんいきがある、といえば、いえなくもないかもしれません。
小説は、二谷と押尾のふたりで視点人物を切りかえながら、話が進んでいきます。わりと小説の最初のほうで、このふたりが居酒屋で飲み食いしている場面があって(というか、この小説、飲食の場面が異様に多い、いや多すぎる)、そこで、押尾がこういうセリフを発します。
「それじゃあ、二谷さん、わたしと一緒に、芦川さんにいじわるしませんか」
というわけで、二谷、芦川、押尾の3人のなかで、二谷と押尾はある種の「共犯関係」にありつつ(といってもその関係性は最後にあっさりと破綻するのですが)、二谷は二谷で、「皆が守りたくなる存在で料理上手な芦川」と、肉体関係をもったりもしています(このふたりは、ほとんど、恋人どうしのような関係です)。
で、この小説を魅力的にしているのが、この、芦川という女。ひとえに、この女性の存在にかかっている。
小説のなかでも、「弱弱しさの中に、だから守られて当然、といったふてぶてしさがある」といった形容をされているように、芦川というこの女は、ただ「弱弱しい」というわけではなく、どことなく、その「弱弱しさ」を盾にしているような底しれない不気味さがあります。
あるいは、「笠に着ている」と表現してもいいですが、その「弱弱しい」芦川が体調が悪いといって会社をしばしば早退することを、職場の同僚も上司も黙認しています。それがなおさら、とくに「仕事ができてがんばり屋の押尾」にとっては鼻持ちならず、一方的な嫌悪感をつのらせていくのです。
芦川は、いわば、「陽キャ」。ルックスもよく、性格も天真爛漫。芦川はじぶんだけ仕事を早退けすることの「罪悪感」からつぎつぎと手づくりのお菓子を職場にもってくるようになるのですが、そういう姿は、ますます同僚や上司からの「覚えをめでたくする」ことになります。
そうして、いつしか、「弱弱しい」存在であったはずの芦川が、(二谷と押尾をのぞく)職場の大勢の無意識的な中枢に居すわることになります。そう、この小説のおもしろいところは、ほんらい「マイノリティ」の属性であるはずの「弱さ」が、いつのまにか「マジョリティ」の属性に転化してしまう、という、まさにこの点にあります。
そのことは、逆に、そうして「弱さを笠に着た」芦川を受け容れられない「強い」押尾たちのほうが「マイノリティ」に転落することを意味しています。そうしてある「事件」をきっかけに、押尾は職場を退職するまでになるのです。
押尾さんが負けて芦川さんが勝った。正しいか正しくないかの勝負に見せかけた、強いか弱いかを比べる戦いだった。当然、弱い方が勝った。そんなのは当たり前だった。
押尾が退職しただけではなく、まるで玉突き事故のようにして、二谷も人事異動によって別の支社へと移ることになるのですが、こうしてとうとう、「弱弱しさというマジョリティ」による、「強者というマイノリティ」の排除が完成するのです。
このおそるべき価値の転倒をえがいてみせたこと、わたしはここに、この著者の、現代社会にたいする観察眼(感受性)の鋭さを感じました。
いま、わたしたちの社会には「多様性」や「共生」といった言葉が飛びかい、「弱者」を優しくまなざすこと、もとい「弱者の立場に立つこと」は、問答無用の「正義」とみなされています(いませんか?)
もちろん、しばしばそれは「正しい」ことではあるのですけれど、いっぽうで、その「弱者」がじつは「弱者」のふりをした「構造的強者」であるケースもすくなくはありません。でも、そんなことをこの「正しい」社会で大声で指摘しようものなら、炎上、必死。二谷や押尾のように、「優しいマジョリティ」の「正義」によって、コミュニティから排除されてしまうのが関の山です。
この、いわば「弱さ(弱者)と強さ(強者)が倒錯したコミュニティ」というものへの強烈な違和感、ないし皮肉が、「おいしいごはんが食べられますように」というタイトルに込められている(と、わたしは、そのように読みます)。
小説の最終盤、「優しいマジョリティ」によって職場から排除されることになった二谷と押尾が、やはり居酒屋で飲みかわす場面がありますが、そこで発される押尾のセリフが、じつに、じつに、重い。鋭い。やや長くなりますが、非常にだいじな部分なので、2か所、引用します。
……おいしいって人と共有し合うのが、自分はすごく苦手だったんだなって、思いました。苦手なだけで、周りに合わせてできてはしまうんですけど。甘いのが好きとか苦手とか、辛いのが好きとか苦手とか、食の好みってみんな細かく違って、みんなで同じものを食べても自分の舌で感じている味わいの受け取り方は絶対みんなそれぞれ違っているのに、おいしいおいしいって言い合う、あれがすごく、しんどかったんだなって、分かって。
「わたしたちは助け合う能力をなくしていってると思うんですよね。昔、多分持っていたものを、手放していっている。その方が生きやすいから。成長として。誰かと食べるごはんより、一人で食べるごはんがおいしいのも、そのひとつで。力強く生きていくために、みんなで食べるごはんがおいしいって感じる能力は、必要じゃない気がして」
「みんなで同じものを食べて」「おいしいおいしいって言い合う」、これが、均質化された「優しいマジョリティ」の感覚です。でも、二谷も押尾も、そういう均質化された感覚にはなじめずに、「一人で」ご飯が食べたい。でも、そのことを「優しいマジョリティ」は許してはくれない。絶対に。
著者はさすが天賦の才能がある(と、この一作をもってまちがいなくそう断言していいと思います)小説家だけあって、直截的にはそう書いてはいませんが、端的にいえば、「弱さ」はときに「暴力性」を孕みかねない。それも、弱さを演じているがゆえにいっそうタチの悪い「暴力性」を。
そしていうまでもなく、「弱弱しい」ひとに寄り添ってみせるポーズを安易にしてみせる人びともまた、無自覚なまま、その構造的な「暴力」に加担をしているのです。
「小説でしか表現しえないもの」とはなにか。その的確な答えのひとつを、この小説にはっきりと確認できた思いがしています。
最後までお読みいただき、まことにありがとうございます。いただいたサポートは、チルの餌代に使わせていただきます。
