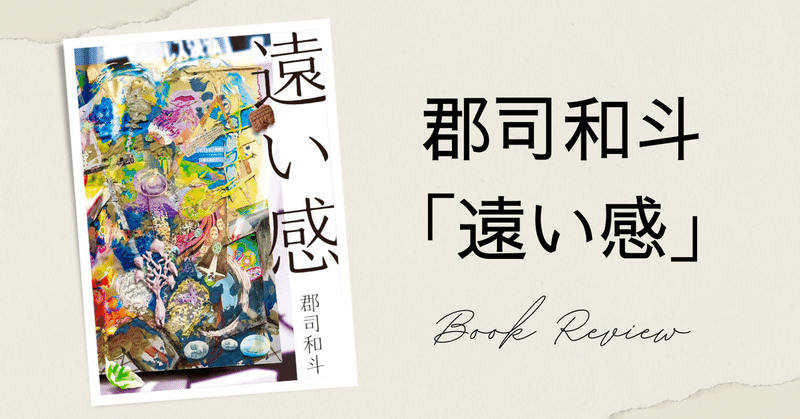
存在「感」について|【書評】郡司和斗「遠い感」
水道代払わずにいて出る水を「ゆ、ゆうれい」と呟いて飲む
これは、郡司和斗が短歌研究新人賞を受賞した連作「ルーズリーフを空へと放つ」におさめられている一首だが、はじめにこの歌を読んだときは、「ゆうれい」は「水」のことをいいかえている、とそぼくに受けとめていた。穂村弘も、郡司の第一歌集となる本書の栞文のなかで、「『水道代払わずにいて出る水』は『ゆうれい』」と書いている。
……あれ? と、ふと思う。これは、そんな単純な歌なのだろうか? いま目のまえにみえているはずの「水」をみて「ゆうれい」とつぶやく。それって、なんだか、ちょっとおかしい気もする。そこにある「水」は触知可能なリアルな実体であり、そうして触れられるはずのものを「ゆうれい」と言う、そこに、かすかな違和感がある……。
そこで、あらためて考えなおしてみる。すると、ここで「ゆうれい」と呼ばれている正体というのが、「呟いて」いるその人物、あえて短歌界のジャーゴン(専門用語)で表現するならば、作中主体である〈私〉のことなのではあるまいか、と、だんだんそのようにも思えてくる。
「ゆ、ゆうれい」とどもりながら「呟いて」、しかも、その「水」を「飲む」。きっと〈私〉はそのようにして、〈私〉じしんの存在を、いや、希薄な存在「感」を確認しようとしているのだ。

消火器を抱いていないと青空に落ちてゆきそう 見ていてほしい
鉄橋に立つと何かを落としたくなるみずいろの気持ちがわかる?
あなたといてあなたはしずか明け方の洗濯物は乾かずにある
くそでかい感情って結局なんなんだ海辺につづくだんだん畑
水面にいくつか波紋 降っている感じはしないのに降っている
存在と、存在感と。似ているようで、それらはまったくちがう。前者はリアルに触れられるものだけれど、後者は、ある「ムード」としてしか感覚できないものだ。郡司の歌は、そのムードをなんとかして(つかみえないと知りながら)つかもうとする姿勢から生まれているようだ。
ぐんちゃんと呼んでください 手を後ろに組んでささくれちらちら剝いた
みずからの存在感がうたがわしいとき、ひとは、みずからを傷つけることによってそれをたしかめようとする。「ぐんちゃんと呼んでください」という、はにかんだ、明るいコミットメントの意思表示とはうらはらに、「ぐんちゃん」は後ろ手のささくれを「ちらちら」剥かずにはいられない。もしかすると「ぐんちゃん」は、自分じしんとの距離以上に、他者との距離を、他者の存在感をもはかりかねているのかもしれない。
近い感 草むらにカップ焼きそばのお湯を捨てたら先に食べてて
遠い感 食後にあけたお手拭きをきらきらきらきら指に巻いてる
近いこと パントマイムの壁越しに真顔で見つめ合う 遠いこと
他人よ 雪が積もればいくぶんかきれいな街の雪を踏み抜く
誤解を解きたい人ばかり増えている だから誤解が増えるのだろう
他者との(ディス)コミュニケーションを歌った歌も、この歌集にはいくつか見受けられる。いわばタイトルチューンにもなっている「遠い感」の歌がまさにそれだが、他者との距離をただ「遠い」と表現せずに、あえて「感」をつけたところに一首の妙があり、ひいては、歌集全体をつらぬく的確なトーンにもなっている。
近い感。遠い感。存在感。「ムード」だけで交感されてゆく現代的な関係性や実存を、郡司の歌は、かろやかに、さわやかに、しかし、深く、鋭くえぐりだしている。「あとがき」によれば、本歌集には333首の歌がおさめられており、それらは「十八歳から二十四歳」までのあいだにつくられたということだが、とんでもねえ。とんでもねえ、早熟な、才能だ。
エレクトリリカル・パレード・みんな不幸の才能がある・ワールド
はたして、リリカルであることを宿命づけられた才能は、不幸であるのか、どうか。その答えはすぐにはわからないけれども、ひとまずはこの「遠い感」という稀有な歌集をことほぎつつ、このさきに郡司のみせてくれるだろうパレードを楽しみに待つことにしよう。そうしよう。
最後までお読みいただき、まことにありがとうございます。いただいたサポートは、チルの餌代に使わせていただきます。
