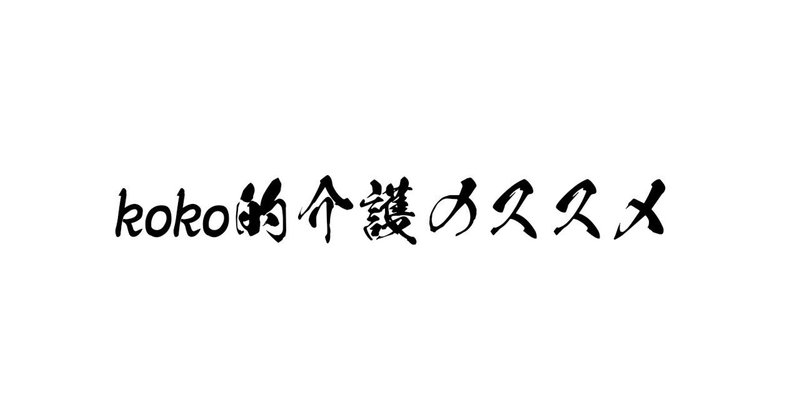
介護現場における主観的なコミュニケーション
こんにちはkokoです!
前回の記事を読んでいただけたでしょうか!まだの方は目を通してもらえると励みになります。
コミュニケーションにおいて大事なことは何か
みなさんがコミュニケーションにおける大事にしていることって何ですか?
それぞれたくさんあるのではないかと思います!
わたしは基本的な部分だけ上げてみたいと思います。
高齢者と会話する時の話し方
会話の内容や聞き方
目線の高さ
ざっくりこの3点で考えてみましょうか。
今日はこの1番だけを取り上げていきたいと思います!
1.高齢者と会話する時の話し方
みなさんはどうでしょうか。完全敬語で話をしますか?基本は敬語で時折くずして話をしますか?全く敬語を使わないで話をしますか?
まず、仕事で会話をするときなのか、親族と会話をするときなのか、ここで大きく変わってきます。
親族と会話をするときは敬語の方もいるかと思いますが、使わない方が多いと思います。
ですので、この①では仕事で高齢者と会話するパターンでの話をしていきたいと思います。
この①、高齢者施設では永遠の課題の一つだと思います
なぜなら主観的な観点が強いからです。
職場の規定で会話する時は敬語。と規定で決めていれば話は変わってくるとは思いますが、そこまで決めている所は少ないと思います(あるのかな?)
とはいえ、基本は利用者様の尊厳を守るために言葉遣いには気を付けるようにと教えられるはずです。
まず逆の立場になって考えてみましょう
あなたが高齢者になって介護サービスを使ったときに職員からの言葉はすべて敬語のほうがいいですか?基本は敬語だけどタメ語も織り交ぜながらの方がいいですか?すべてタメ語の方がいいですか?
答えは3通りに分かれると思います。
この逆の立場で考えることが介護では重要ポイントになります。
今後も逆の立場で考えるというワードを繰り返し出していきますので、覚えておいてもらえると嬉しいです(そのくらい重要)
私が働いている経験の中であった1つのケースを紹介します。
とある介護職員がいました。
その職員はとてもエネルギッシュで勢いがあります。
ご利用者様と会話する時はタメ語です。内容も友達と会話をしているの?って思うほどプライベートな部分まで話を聞いていたりすることも多々ありました。ある日、その会話を聞いていた他のご利用者様から相談がありました。「聞いているこっちが嫌な思いをする」と。
すぐさま上司がその職員に対して注意をしました。するとその職員は悪びれる様子もなく「自分とその方との関係性の中での会話だから問題ない」と言い放ちました。
この職員は、利用者との関係性は十分構築できているから問題ないと思っています。
みなさんはどう思いますか?
この職員は主観的にしか考えていないからこそ、このような事態に陥ったと私は思っています。
これもまた私の主観かと思われるかもしれません。ですがこれを客観的に考えてみてください。
逆の立場になって考えてみましょう!
客観的に考える重要性
第三者がそれを見たり聞いたりした時に不快な思いをしないか
わたしは基本この点で判断をします。
先ほどのケースで考えてましょう。
・関係性が利用者様とできているから問題はない
そもそも、それはその職員が勝手に思って判断しています。(主観)
第三者からクレームがありました。(客観)
逆の立場になって自分が同じことを言われたらどう思うのか(客観)
客観的に考えるとわかりやすく判断ができると思います。
逆の立場になって考えても、自分なら嫌じゃないもん!って思うこともあるかもしれません。
ですが
まず嫌な思いをした人がいるという事実を認めてもらわなければなりません。
そして、人間は人それぞれ生きてきた背景・価値観・思いが違うことを理解しましょう。
そうしないと客観的に物事を考えることはできません。
私自身いろいろと失敗してきました。
振り返って、反省して、次につなげていく。
この繰り返しに尽きます。
こういったグレーゾーンの部分はとても難しい点です。
そして、言葉にして指導していくのもとても難しいのです。
多少言葉が崩れた会話をしていても、会話している相手や、聞いている周りが不快な思いをしなければ平気だと思いますが
少しでも ん?っていうのを感じたら、それは問題ありだということです。
会話は言葉遣いだけではないんですけどね・・・声のトーンや口調等いろいろ要素はありますが、今回はポイントを絞らせてもらっています。
少し感覚的な話になってますが、だからこそ的確な答えのない難しい問題なのです。
ではそんな場面をみたらどうする?
この記事を見ている介護の世界で活躍しているみなさん、わたしが話してきた内容を当たり前に見てきていると思いますし、悩んでいる人もいるかもしれません。
わたし自身悩んできました。(現在進行形)
職員から「〇〇さん、こんな言葉遣いをしていました」と報告を受けるわけです。利用者様に不快な思いをさせるのは上司として見過ごすわけにはいきませんから、すぐさま面談をして話をします。
でもこうも思うのです。
必ずしも上司が注意する必要もないと思っています。
なぜならその場面をみた当事者が直接注意をしてはいけない決まりはないからです。
でも直接、人に注意を促すのって嫌ですよね。
でも考え方を変えてみてください。
注意すると思うから言いづらくなる
普段から色々言い合える職員同士でも注意するのは嫌ですよね。
けど普段から色々言い合えるのですから、アドバイスだと思って言えば言いやすい、言われたらアドバイスだと思って受け止めたら受け止めやすくなると思いませんか?
もちろん双方がこのような認識のもとで成り立つ話です。
理想論だと思う方もいるでしょう。
実際にわたしは職員たちにこのように言い聞かしてきました。
最初は言うのをストレスに感じたでしょうし、言われた職員も言い返したりしていました。そのたびに間に入って納得するまで話しました。
するとだんだんと確執もなくなり、直接話をして解決できるようになったのです。すると、利用者様とのコミュニケーションだけでなく、職員同士のコミュニケーションの向上にもつながりました。
考え方ひとつで変わるのです。
わたしが一番おそれていたのは、上司や同僚に言うことによって嫌われてしまうのではないかと思って注意ができない。悪いものがそのまま見過ごされてしまう環境でした。
悪循環の極みです。
わたしが言っている内容は上司の協力ありきでの話だと思います。
けれど、悪いことを悪いと言えない環境は同罪だとも私は思います。
理想論や綺麗事だと思う方もいるでしょう。
でもその理想論や綺麗事に誰かが取り組まなければいい環境って生まれませんよね。
その辺はまた管理者に向けた記事の中にでも書いていこうと思います。
今回は 1,高齢者と会話する時の話し方 について話させてもらいました!
言葉遣いにポイントを当ててしまいましたが、言葉遣いや会話の内容だけではなく、声のトーンや口調、言葉の早さもコミュニケーションにはとても大事なポイントです。
次回は 2,会話の内容や聞き方 について記事にします!
長い記事になりましたが、最後まで見てくれたことにとても感謝します。
良ければフォローや♡もお願いします!
ではありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
