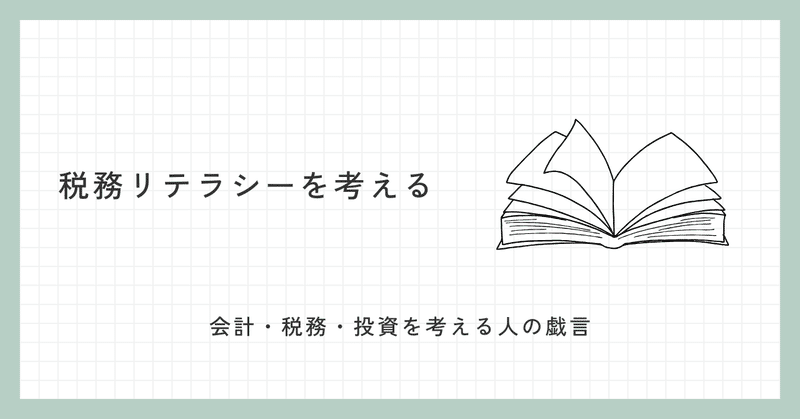
税務リテラシーを考える +ご挨拶
1.はじめに
この記事を開いていただき、ありがとうございます。
おこめといいます。
そのうち、名前を明かして書くかもしれませんが、
現段階ではこれで進めようと思っています。
プロフィールの欄より十分察せることではありますが、私は会計・税務の業界におり、
多くの中小企業の方々と仕事をする日々を送っています。
仕事上、お金の話に多く関わるため、
その経験に基づき、会計・税務・投資・税理士試験その他、何か本質的にプラスになる情報を発信できたらいいかなと思っています。
2.そもそもの税務リテラシーとは
(1)世間から見る税金のイメージ
金融リテラシーという言葉が少しずつ認知され始めている一方で、
税務リテラシーという言葉は一応存在するものの、
世間で認知されるようなレベルではありません。
製造業から転職して会計・税務の業界に入ってまだ8年ではありますが、
世間の人々が”税”に対してどれだけ認知しているか、
私の率直な印象では、
・強制的に徴収されるもの
・なんか負担が大きい
・ある日突然支払いがやってきてしんどい
・とりあえず税務調査は恐ろしい
というざっくりとした認識をされているような気がします。
また、SNSなどで他の税理士等の方々の発信を見て、
どうしてもキャッチーな内容("◯◯でお得に節税!"とか)になっていて、
節税の話の一方で、基本的な税の話があまり触れられずほったらかしになっている状態なので、もっと広域で理解されるよう情報展開すべきだと感じていました。
(2)自分と税の距離
ここで、この記事を読んでいただいている皆様に質問です。
・自分に課せられている各種税金、どれがいくらか把握していますか?
この問い、サクっと答えられた人は普段から相当な把握をしている方だと思います。
普段から税に触れる私でも、
給与がこうなっている→割合かけてこれくらいだな
という認識の仕方をしています。
サラリーマンの方は毎月の額面給与からどのようなものがいくら引かれているか、興味を持たれている方は多くはないと思いますし、手取り額しか把握していない方もいると思います。
個人事業を営まれている方は余計に分かりにくいと思います。年間を通して決まりますので。
(3)取り掛かりとして
自分を取り巻く税を認識するために、
必要な話はこの2点かと推定しています。
①身の回りに負担するものがどれだけ転がっているか、全体像を把握する
②それらの計算と支払い(控除)のルールを理解する
直近でもインボイス制度の導入による負担増を訴える話がありますが、これも(辛口な表現ですが)ルールの理解不足が遠因と思うところも多いです。
※インボイス制度については、企業に多くの事務負担(=人件費、設備投資)を強いながら税収増がわずか年間2,500億増と経済合理性の面では出来の悪い話だと思っています。
なので、身近な税を少しずつでも理解することは、自分の事業や家計を理解すること、そして金融リテラシーの向上にもつながる話だと考えていますし、
そのためにも、少しずつでも記事を展開し、皆様の理解を深めていただければと思ってこの記事を書いています。
3.次回予告?
多くの人がまず触れる税(特に社会保険や所得税、住民税)を理解するのに、
給与明細の読み解き方を切り口にテーマを展開してみようと思っています。
まだ決まってはいないけど。
記事を書くのにまだ不慣れですが、トライしてみます。
実り少ない記事ですが、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
