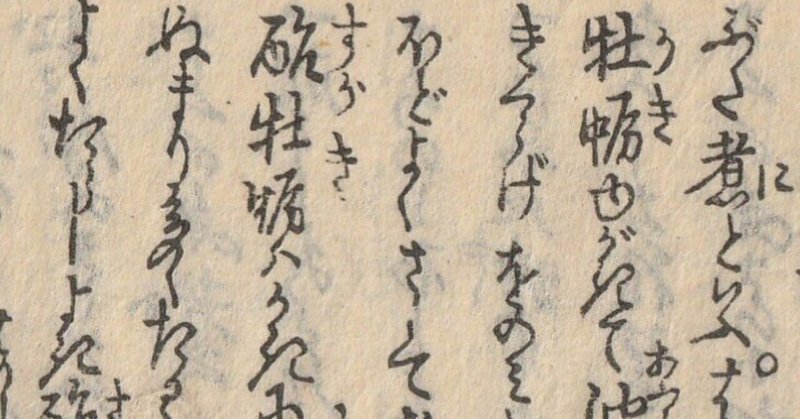
江戸時代の季節のお惣菜10・11・12月編。古文書『女中嗜日用宝』を訳してみた
前回、遅ればせながらタイトルの月が旧暦だったのに気づき、現在の新暦に直すと今回は12・1・2月という冬の惣菜になります。そして今までいろんな話題を提供してくれた、この『女中嗜日用宝』の最終回となります。
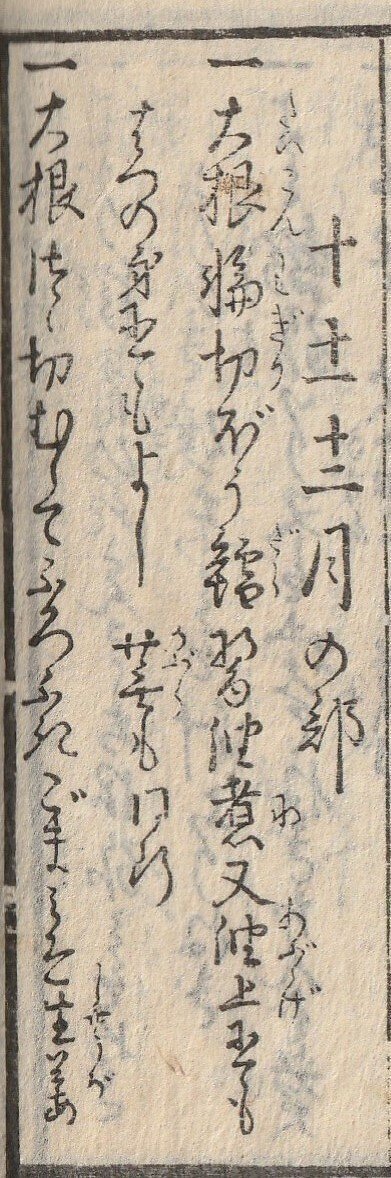
10・11・12月の部
●大根の輪切り・棒鱈の醤油煮。
または、油揚げでも、マグロでも良し。
大根の代わりにかぶでも良し。
※原文の「はつの身」とはマグロのこと
●大根を笹切りにして蒸し、ふろふきにして
ゴマ味噌生姜で。
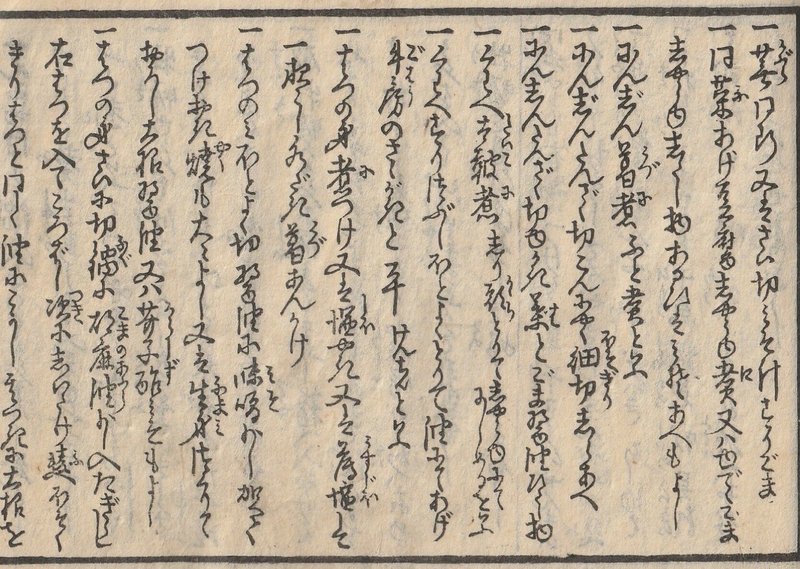
●かぶも同じくふろふきゴマ味噌生姜で。
または、さいの目切りにし味噌汁すりゴマで。
●かぶ・揚げ豆腐の醤油煮。
または、茹でてゴマ醤油のお浸し。
あるいは、味噌和えも良し。
※原文の「蕪菜」とはかぶの異名
●人参葛煮(太煮という)。
●人参短冊切り・こんにゃく細切りの白和え。
●人参短冊切り・湯がき葉のゴマ醤油のお浸し。
●クワイ太鼓煮(上下を切り落とし、醤油で
煮しめたものをいう)。
●クワイをすりつぶし、ほどよく取って
油で揚げ、ゴボウのささがきとの一皿
(けんちんという)。
●マグロの煮つけ。または、塩焼き。
または、薄塩で一夜置き、水炊き葛あんかけ。
●マグロを程よく切って醤油に味噌を少し加え
漬け置いて焼くのも大いに良し。または、
生の身でお造りにし、おろし大根醤油で。
またはからし酢味噌でも良し。
●マグロを細かく切り、鍋にゴマ油を少し
入れて煮立たせ、マグロを入れて転がす。
次にしいたけと麩を細く切り、マグロと
同じように油で転がす。さらに大根を
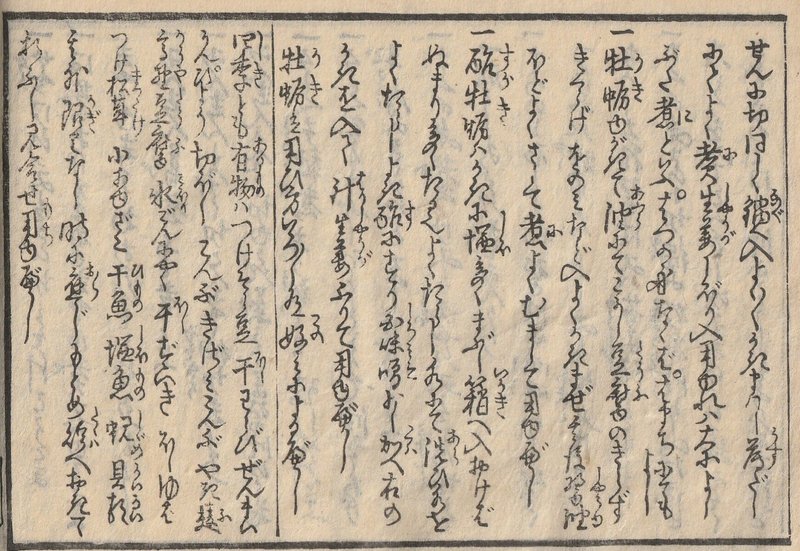
千切りにし、同じく鍋に入れてじっくり
かき回し、薄だしでよく煮る。
生姜を絞り入れると大いに良し。
これをぶた煮という。
マグロがなければハマチでも良い。
●牡蛎を湯がいて油で焦がし、豆腐のおから・
きくらげ・鯨の尾の身などを入れて
よくかき混ぜ、その後醤油をほどよく
加えて煮て、よく蒸して食べる。
※原文の「きらず」はおから・卯の花
※原文の「をのみ(尾の身)」は鯨の背びれ
から尾の付け根までの肉
●酢牡蛎は牡蛎に塩をたくさんまぶして
ざるに上げておくと、ぬめりが多く垂れて
くるのでよく垂らして水で洗い、
水気をよくきって、良い酢にすり白味噌を
少し加え、牡蛎を入れて針生姜を
ふりかけて食べる。
※針生姜=生姜を針のように細く切ったもの
牡蛎は食べ方がいろいろあるので、
好みに応じること。
____________________
どの季節にもあるものは、
漬けそら豆・干しわらび・ぜんまい・かんぴょう・
切干昆布・刻み昆布・焼き麩・高野豆腐・
氷こんにゃく・干し芋茎・干し湯葉・
つけ松茸・小鮎・雑魚・干魚・塩魚・しじみ・
貝類・そのほか限りなし。
※芋茎=サトイモやハスイモなどの葉柄
時に応じて手に入れて貯えておき、
折に触れて見合わせながら使うこと。
____________________
【たまむしのあとがき】
今まで食材の旬に関しては、さほど気にしない人生を送ってきたのですが、このシリーズを訳しながら、旬の大切さについてしっかり考え、少しずつ実践するようになりました。
古文書から自分の生活を見直す。
自然とそうしたことが出来るようになってきたように思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
