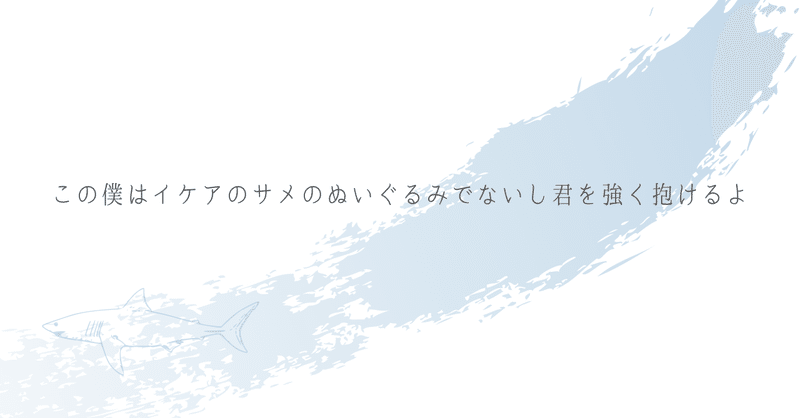
【サンプリング小説】この僕はイケアのサメのぬいぐるみでないし君を強く抱けるよ
この僕はイケアのサメのぬいぐるみでないし君を強く抱けるよ
引用:Twitter @uzume_no_hijiri(あめのうずめ 様)
僕たちは、心を巡る感情が余りにも沢山で複雑だ。
だから人間は、喜怒哀楽を表に出してコミュニケーションを行っている。
僕は人間の、心に収まり切らなくなって表情が変わる瞬間というものが堪らなく好きだ。
それが笑顔だろうが泣き顔だろうか、はたまた怒りだろうが、感情が表に出る瞬間を、全て美しいと思う。
その瞬間を記憶に残し続けるにはどうしても頭が足らなくて、気付けば自然とカメラを手にするようになっていた。
大学2年の夏の時である。
彼女が僕に笑いかけた時、僕はシャッターを切るのを忘れて彼女を見つめ続けた。そんなことは初めてだった。
彼女の笑顔は目に焼き付いたまま、今もずっと離れないでいる。
「そういえば遼、大学を辞めるらしい」
もうすぐ冬が始まりかける11月の下旬頃。
そんな噂話を聞いたのは4限目終わり、学食を目指して歩く道中だった。
遠藤も学食に着くまで待ちきれなかったのだろう。ザワザワと生徒が行き交う騒がしいBGMの中で、僕たちの会話は続いた。
「なんでまた、今時期に」
遠藤は一瞬不可思議な顔をした。恐らくこの男は、遼とよく一緒にいる僕なら何か知っていると思ったのだろう。
残念ながら、何も知らなかった。
僕が最後に遼と会ったのは、もう2ヶ月も前だった。
その時は何も聞かなかった。
大学を辞めることも、ましてやそんな素振りもなかった。
ただ彼は一言ポツリと呟いた。
「由紀ちゃんと別れるかもしれない」
それは僕が記憶している、彼の最後の言葉だった。
遠藤も同じく気に掛けていたようで、彼は食堂で何を食べるかもろくに決めぬまま、会話を続けた。
色の薄い350円のカレーをぐちゃぐちゃに混ぜながら
「由紀ちゃんはどうするんだろうな」と言った。
僕たちは同じ写真サークルのメンバーだった。
サークル内の恋愛は、必然的に注目の的となる。
大体毎年数組のカップルが誕生して、数年後生き残るのはほんの僅かな倍率だ。
だから遠藤も、遼と由紀ちゃんのことは興味本位でしか無いようだった。
遠藤のその言葉に、僕は返事出来ずにいた。
ただカツ丼をかき込むフリをして、遼の言葉を思い出していた。
遼は、由紀ちゃんと別れるかもしれない。
不思議と嬉しさは沸かなかった。それよりも、由紀ちゃんを手に入れたくせに自分の都合で振り回す権利がある遼を腹立たしく感じた。
由紀ちゃんは悲しむのだろうか。
僕は彼女が眉を潜める瞬間を、カメラに収めてみたいと思った。
サークルの活動は火曜日と金曜日が基本である。
僕たち3年生は引退の際に展覧会を開くことになっているので、
今時期は忙しくしていた。
大学公認のサークルは、狭いながらも部室を用意して貰っていて、
最近は部員が増えてきたこともあり、窮屈な空間に小さな机を並べ、数多の写真にあーだこーだと評論するのである。
その中で自分の気に入った写真を、大きく印刷して展覧会に出す。
遼はやっぱり、今日も来なかった。
「あいつ、今まで全部出してたのに最後の展覧会で出さねえつもりかな」
遠藤は不満げに呟いていた。
それもその筈で、遼の写真はサークル外からも人気があった。それはモデルが可愛いからだという理由もあるし、確かに遼の写真には、素人にも分かるような魅力があった。構図とか光とか、そういう技術云々だけの話では無い。
彼の持つ雰囲気が、写真に投影されていたのだ。
それは写真を見るだけで遼が撮ったと分かるような、僕たちに勝ち目のない個性だった。
それが凄く憎かった。僕は親友である彼の作品を、今まで直視出来ずにいた。
「由紀、お前今回モデルしてないの?」
遠藤は少し離れた席で事務処理をしていた由紀に、あろうことか大声で聞いた。
部室の空気が、一瞬止まったような感覚になったのが分かる。
皆動向を気にしているのだ。
由紀ちゃんの顔は、ピクリとも動かなかった。
「してないですねぇ」
彼女の表情は滅多に変わらない。
愛想が無いとか感じが悪いとかそういう訳ではなく、ただ感情を表に出すのが得意で無いのだ。
彼女が心から笑っているのを見たのは2回生の夏合宿の時と、
それから遼が撮る写真の中くらいだった。
もう1つの質問は、デリカシーの無い遠藤すら続けることが出来なかった。
由紀ちゃんが業務に戻るのを確認すると、
他の部員たちも各々の作業に戻った。
部室の空気が、また円滑に流れ始めたような気がした。
由紀ちゃんは、僕らより1つ年下だ。
色白で品があって、少しとっつきにくいのが彼女の第一印象だった。
彼女が入部してすぐ、まだ石濱さんと呼ばれていた頃は、
彼女の無表情さに僕たちは容赦なく毒づいていた。
「いつも怒ってそう」
「何を考えているかわからない」
実際彼女は誰とでも仲良くするような社交的なタイプでは無くて、数名の女子と関わるのが好きなようだった。
僕は彼女のことを、面白みの無い人間だと思っていた。
コロコロと表情が変わる女の子の方が可愛げがあるし、何より僕の美的感覚をくすぐった。
彼女が自然と「由紀ちゃん」と呼ばれるようになったのは、
その年の夏合宿の頃だった。
夏合宿は毎年1週間、いつも大阪に行くと決まっている。
堺市の方に長年お世話になっているギャラリーがあって、
年に一度そこで3日間の展覧会を行うのだ。
部員は順番に在廊することになっていて、実際は自由時間の方が遥かに多い。
展覧会2日目の昼頃だったかと思う。
僕が在廊の時間を終えて休憩室へ戻った時、
遼と由紀ちゃんが随分と離れた席で2人、ポツンとスマホを触っていたのである。
遼は僕の姿に気がつくと、片手を軽く挙げて
「お疲れ。飯でも食いに行こうぜ」と言った。
遼はいつもだらしなかった。
ファッションもこだわりが無くて髪もボサボサで、元々の顔立ちはそんなに悪くないけれど、全ての良さを隠してしまうような風貌をしていた。
周りからも遼については、写真以外何も興味が無いのだと思われていた。
僕も挨拶がわりに片手を挙げて、それから由紀ちゃんの方を見た。
由紀ちゃんは部屋に1人でいることも、特別気にしては無さそうだったが、それ以上に自分の良心が傷んで問いかけた。
「石濱さんも時間あるなら、一緒にどこか行く?」
少し勢いよく顔を挙げた彼女は、予想外だったのか驚いていたのだろう。
ほんの少し間が空いて、それから
「あの、私。水族館に行きたいです」
と、静かに呟いた。
大阪には海遊館という場所があったのを知っていたので、
僕たちは行き方を調べてJRと地下鉄を乗り継いだ。
大阪の電車はとても騒がしい。
人々の声量も何故か大きく感じるし、
地下に潜っている電車が駅のホームを通過する瞬間、
なんとも言えない轟音が耳の中に響く。
こんなにもうるさい電車の中で、普段からあまり口数の多くない2人に挟まれた僕は、大変気まずかったのを覚えている。
「海遊館、行ったことないんだよなあ」
と呟くと、遼は
「俺も」
と返事をする。
普段はそれだけで無言になることも苦痛に感じたりしないのに、
1人増えるだけで空気がこんなにも変わるのだ。
僕が白で遼が灰なら、彼女は黒の威力を持つ。
それだけ僕にとって、彼女の存在は異色であった。
「石濱さんは、水族館とか好きなの?」
僕は彼女の目をしっかり見ることが出来ず、目配せするようにして尋ねた。
「水族館というより、サメが好きなんです」
電車が大阪港に着く。
席から立つ直前、彼女は僕の方を見た。
「1人で待ってるの寂しかったんです。ありがとうございます」
彼女から石鹸の香りが漂っていることを、この時初めて認識した。
駅から5分程歩いて海遊館が見えてきた頃には、
僕も遼も随分と写真を撮る気に満ち満ちていた。
2人のカメラはメーカーが違うので、扱い方も全く違う。
自分のカメラの良さを熱く語るが、お互い影響されて乗り換えるといったことはさらさら無かった。
そうやって僕たちは、外観から中の小さなクラゲまで、
思い思いにシャッターを切って、たまに由紀ちゃんにポーズの指定をしては
モデルらしいこともやって貰った。
元々切れ長の目にシュッと高い鼻を持つ彼女は、薄暗く大人びた空間の中でクールな雰囲気を出すのがとても上手かった。
矢印に沿って順序通り進んでいると、彼女は看板を指さした。
サメのコーナーに思わず早歩きになった彼女についていきながら、
僕と遼は顔を見合わせた。
こんなにもはしゃいでいる彼女を見たことが無かったのだ。
元々大々的に掲げているだけあって、とても立派な水槽の中に、
巨大なジンベイサメが悠々と泳いでいた。
同じ水槽を泳ぐカラフルな魚やイワシやエイ。
皆が引き立て役だとでもいうように、サメは主役顔をして堂々と泳いでいる。
僕と遼が大きな水槽を撮る為に少し離れてカメラを向けていると、
由紀ちゃんは小走りで水槽の前へ向かって、それから静かにサメを見上げていた。
僕たちは水槽を撮っていた筈だった。
それなのにいつの間にか、彼女にフォーカスを当てるように、
無邪気に見つめる彼女に距離を近づけていた。
遠くで泳いでいたサメがこちらに向かってやってきた時、不意に彼女が僕たちの方へ振り返った。
「先輩!見て!」
彼女はサメを見て欲しかったのだ。
分かりきったことなのに、はしゃいだ彼女の笑顔を見つめたきり、目が離せなくなりカメラを下ろした。
この笑顔を、カメラで残してはいけないと思ってしまったのだ。
そんなことは初めてだった。
隣では遼のカメラから、シャッターを切る音がした。
その時撮った遼の写真は、コンクールで最優秀賞を獲ったのだった。
それから遼と由紀ちゃんが付き合っていると聞いたのは、2ヶ月程経った頃だった。あの時も僕たちは食堂にいた。
遼から直接聞いた時、腹の奥の方がツンと痛んで、僕は彼女に気があったことを嫌でも知ることになった。
それから遼が大事な展覧会やコンクールに出展するときは、必ず由紀ちゃんが映っている。
遼は、彼女の自然な表情しか作品にしなかった。
僕には到底及ばない距離に彼が立っていることを、本当は随分と前から気が付いていた。
だから、彼が大学を辞めて海外に写真を撮りに行くと噂を聞いた時も、
それが当たり前のような、諦めに近い感情しか湧いて出なかった。
「先輩。この板はどこに置きますか」
卒業展覧会の前日。
大学の多目的室を展覧会仕様にしなければいけない僕たちは、
殆どが体力勝負の業務に追われる。
他の女の子たちが率先して軽い物を運ぶ中、由紀ちゃんは男子部員に負けじと大きな板を運んでくれていた。
「それは裏が見えないよう囲いにしたいから、向こうに」
遠藤はこういうとき、部長らしい顔つきで部員をまとめていく。
写真だって大きな作品になる程、運ぶ負担は大きくなる。
セカセカと順番に作品を運び出して、
漸く汗を拭きながら小休憩に入った時だった。
「すみません。少し早いんですがお先に失礼しても良いですか」
申し訳なさそうに挨拶にやって来たのは由紀ちゃんだった。
僕たちは一瞬遠藤の顔を伺ったが、遠藤は頷きながら
「良いよ、お疲れ」と言った。
それもその筈で、毎回最後まできっちりと作業をする彼女が早退するなど、
余程のことがあるに違い無かったからである。
僕たちは満場一致で、駆け足で帰っていく彼女の後ろ姿を見送った。
会場に作品が並ぶとそれらしくなるので、
僕はその時が好きで毎回最後まで残っている。
今回引退する3年生はA1サイズ、他の部員はA4サイズに印刷をして作品を並べていく。
大きな作品が行儀良く並んでいる中、間の1つ分はぽっかりと空いたままだった。
『白樺 遼』
空間の少し下に、名前の札だけが貼ってある。
遠藤はその隙間を見ながらため息をついた。
「詰めるか、それとも過去の作品を飾るかだな」
「過去の作品は、見る人が見ればバレるんじゃ」
幾らかの議論が行われた後、
「最優秀を獲った作品なら、逆に気付かれても大丈夫だろう」
という案に落ち着き、その日は解散となった。
皆が次々と帰って行く中、僕は殆ど出来上がったブースを一周して、
他の作品を見回った。
植物が好きで花ばかり撮る人もいる。
僕のように人物ばかり撮る人もいる。
そんな中で僕の足を止めたのは、由紀ちゃんの作品だった。
由紀ちゃんの写真には、大きなサメのぬいぐるみを持った遼がいた。
躍動感があって人物にはブレが入っているけれど、遼であることに間違い無かった。
いつの写真だろうか。不自然に薄暗いし、なんだか急いでシャッターを押したような突拍子のない写真だったが
暫く姿を見ていない彼は、確実に生きていた。
写真の中は遼しか映っていなかったけれど、そこは2人だけの世界だった。
シャッターを押した彼女は、笑っているに違い無かった。
僕はその瞬間、今まで隠していた嫉妬心を自覚せざるを得ず、
ズキズキと傷む心を置いていくように、その場から急いで離れたのだった。
次の日は1限に授業が無い人から集まることになっていた。
なんだかあまり寝た気にもならず、おおあくびと共に
朝早くから学校へ向かった。
展覧会の日は大抵一番に教室へ向かって、
アンケートやチラシの整理をすることに決めていた。
そうやって形が完成していくことが心地良かった。
会場の電気を付けると、
昨日と変わらぬ景色が目の前に広がった。
「なんだ、早かったな」
突然声が聞こえたのは、敷居の奥側からだった。
3年生の写真が並んでいるコーナーの方からだ。
丁度写真を貼るために作った仕切りに隠れていて、姿は見えずにいた。
しかし付き合いの長い僕には、その馴染みがある声の主を想像するのは
難しいことでは無かった。
「遼か」
僕は、声のする方に近付いた。
そこに遼は、当たり前のように立っていた。
「こんなに早く来ると思わなかったな」
大きな写真を体全体で支えながら、壁に貼っているところだった。
「なんでこんなギリギリに。皆困ってたんだぞ」
彼の姿を見た嬉しさ半分、怒ってやろうと口を開いた時に、
身体で隠れていた写真が全貌を見せた。
由紀ちゃんが泣いていた。
今泣いたばかりだというように、綺麗に一筋の涙を流している写真だった。
「これ、いつ撮ったんだ」
遼は相変わらずボサボサの頭のままだった。
彼は返事をしなかった。
そのまま写真のバランスを見て、教室の角に置いていたスーツケースを手に取った。
「オランダに行ってくる。暫く帰って来ないよ」
彼は少し疲れているようだった。
「由紀ちゃんは」
返事はしないと思った。彼もするつもりは無かっただろう。遼は扉の前まで歩くと、思い直したように立ち止まり、僕のいる方へ向き直した。
「最後に由紀の泣き顔を撮らせてくれ。
昨日はそう言って別れたんだ」
遼は軽く手を挙げた。
それきり振り返らず、姿を消したのだった。
腹立たしかった。
由紀ちゃんを泣かせたことも、
泣き顔すら美しくシャッターに収めてしまうことも。
全てが到底、及ばなかった。
遼が由紀ちゃんと別れたことも、嬉しいとは思えなかった。
それほどに僕は彼女のことを、
彼女の幸せしか願えない程に、好きになってしまったのだ。
遼と会ったことは、誰にも言わなかった。
見たことのない彼の作品が展示されていることには勿論皆気付いたが、
僕も同じように驚いた。
とても大きな写真に写った、大きな涙。
その皮膚を這う水には、写ってもいないのに男の気配がした。
由紀ちゃんが来るまで1人で落ち着かずにいたが、彼女は何食わぬ顔をして学校へやって来た。
本当は、あの時1人寂しく座っていた夏合宿の時のように
心で感じていることはあるのだろうけど、彼女は表情に出さなかった。
予想通り遼の作品目当てにやって来る生徒は多く、
皆由紀ちゃんの涙を眺めては感嘆の声を漏らしていた。
遠藤は満足げに頷いていた。
由紀ちゃんはただ顔色1つ変えず、3日間の展覧会を乗り切ってみせた。
僕はただ、時折遠くから由紀ちゃんの様子を見つめた。
遼が大学を辞めたと聞いたのは、それから四日後のことだった。
「それでは皆様、3年生へお疲れ様でしたの意を込めて、乾杯ー!」
折々、液体の入ったグラスを合わせて一斉に乾杯を始める。
後輩たちは皆、伝統を守って先輩の席へ挨拶に来る。
声が重なり、周りが一体何を話しているのか認識するのは難しかった。
「先輩が部活に来なくなっちゃうの、寂しいですぅ」
「次は引退合宿で会いましょう!」
各々が、思うままの惜別の言葉を手向けて回る。
「先輩、お疲れ様でした」
例に漏れず由紀ちゃんは、僕の前へとやって来た。
その声に少し緊張しながら、軽くグラスを合わせる。
重たくて分厚いグラスからは、カチャンという音が響いた。
由紀ちゃんが持っているグラスからは、オレンジの香りがして、彼女らしいと思った。
彼女は軽く一礼をして、それから次の先輩の元へ歩き出そうとした時だった。
「由紀ちゃん」
気付けば僕は、彼女のことを呼び止めていた。
由紀ちゃんは小さく返事をして、こちらに向き直した。
「少し話さない?」
彼女は表情を変えるまま、「はい」と首を縦に頷いた。
それから律儀に全員への挨拶を済まし、僕の元へやってきた。
「どうしましたか?」
特に、何か言うつもりは無かったのだ。
遼と由紀ちゃんが別れたという噂は、あっという間に広がった。
それでも彼女は元々深く詰められるようなキャラクターでも無かったし、
皆自然に周知の出来事として受け入れたようだった。
あとはほんの少し、「白樺君と別れるなんて勿体無い」という声が聞こえたくらいだった。
僕はビールのジョッキを一気に飲み干して、
それから思い詰めたように一点を見つめた。
実際は、話題を探していたのだ。
彼女と今日で終わりにならない為の、ズルくて情けない話題を。
「去年有志で出した作品集があっただろう」
部員の有志でお金を出し合って、1冊の本を作ったことがあった。
その中に僕と遼と、由紀ちゃんはいた。
「あれがどこかに行ってしまって。もし良ければ貸してくれないかな」
由紀ちゃんは、クールで人の顔色をあまり伺わないのだけれど、
きちんとグラスを両手で持って飲んでいた。
そこがまた彼女の素顔の一面な気がして、見れると嬉しかった。
「じゃあ、この後良ければ渡しますよ。2冊持ってるので」
彼女は何も恐れていない瞳で、僕の方を真っ直ぐに見ていた。
あまりに突然の展開に戸惑った僕は「後日でも良い」と提案したのだが、
彼女は頑なだった。
そこに他意は無く、あくまで善意、それだけだった。
「すぐ渡せますよ。ここから近いんです、私の家」
僕は新たにやって来たジョッキのビールを早々と口に放り込んだ。
そうでもしなければ正気が保てず、このまま時間がグルグルと戻ってしまうような気がしたのだった。
「由紀は電車じゃ無いもんね?」
帰り際同期と話す由紀ちゃんを横目に、心臓は今にも踊り出そうだった。
彼女は頷くと同期と別れ、素直にこちらへ向かってやって来た。
「ここから10分程歩きますが、それでも良ければ」
由紀ちゃんは愛想笑いをしない代わりに、
僕の目をじっと見つめてくる。
「あれ、藤木は電車じゃねえの??」
同期の声に、僕は曖昧な返事をした。
由紀ちゃんの提案を断る筈もなく、僕たちはゆっくりと歩き始めた。
本格的な冬の前ではあるけれど、夜はかなり肌寒い。
僕は由紀ちゃんに道を誘導して貰うため、半歩後ろを歩いた。
店から5分も歩けば静かな住宅街といった感じで、
車が2台ギリギリ入るくらいの道路を、僕たちは静かに歩く。
由紀ちゃんの靴から、コツコツと小さな足音が鳴る。
低めのヒールを履いていることに、そこで漸く気が付いた。
「あの作品集に載ってる先輩の写真、とても素敵でした」
由紀ちゃんはチラッと僕の方を振り返りながら話し掛けた。
彼女が言うことに嘘はない。
あの時載せた写真は霞草を両手に抱えた同期の女の子がモデルだった。
確かにモデルを上手く撮れたとは思う。
だけど残念ながら、あれは彼女の生きている写真とは言えない。
モデルが上手かった。僕が言う通りに表情を作った。それだけの写真だった。
遼はあの時も、由紀ちゃんの写真を撮っていた。
「あの建物の2階です」
彼女が少し離れた建物を指さした。
5階建ての古びた建物だ。上品な彼女のことなので小綺麗なマンションに住んでいると思ったら、意外だった。
「ボロボロなんです」
彼女はきっと、建物のことを言っていたのだろう。
儚くて健気な彼女に思わず触れてしまいたくなる。
だけど遼は、離れた筈のあいつはいつも由紀ちゃんの背景にいる。
鉄で出来た階段が、カシャンカシャンと音を鳴らす。
201号室。古びた形の鍵を差して、扉を開けた。
「どうぞ、散らかってますけど」
「え?」
僕の驚きの声は、由紀ちゃんには届かなかった。
無造作に靴を脱ぐと簡単に揃え、彼女はバタバタと真っ直ぐ部屋へ入って行く。
少し悩んで、小さく「お邪魔します」と言った。
小さなワンルームは、今までの彼女のイメージを覆すようだった。
促されるまま床に座ると、部屋を軽く見回す。
あまり一部を見つめないように、不自然にならないように。
勝手に想像していたお嬢様のような繊細な雰囲気を、僕は漸く取り壊すことが出来て少し嬉しかった。
だけどこれは、僕しか知らない秘密では無い。
これだけ時間を掛けて、やっと一歩近付いたに過ぎなかった。
彼女は順番に並べてある作品集を本棚から取り出すと、そのまま身体の方向だけ変えて、僕に手渡した。
「お茶淹れますね」
一度遠慮をしたが「静岡茶があるんです」と言われ、それじゃあとお願いした。
彼女の家に入ったことに、罪悪感は無かった。
親友だった遼はもう由紀ちゃんと別れているし、すぐに駆けつけられる場所にも居ないのだ。
本当は言い訳に過ぎなかった作品集を開いてみる。
遼のページには、生き生きとした由紀ちゃんの笑顔が写っていた。
「これってさ」
意を決して口を開くと、由紀ちゃんは廊下に付いているキッチンに立ちながら返事をした。
現実とは思えなくて、細やかな幸せに胸が縮まるような切ない気持ちがした。
「これって、なんで笑ってるの?」
由紀ちゃんがその正体を確かめに近付くと、写真を見て一瞬眉を潜めた。
由紀ちゃんが表情を変えた。
間近で彼女の感情の変化を感じる嬉しさに、唇の端を噛み締める。
「忘れちゃいました」
彼女が寂しそうに微笑んで、僕はそれ以上聞くことが出来なかった。
今慰められれば、どれだけ良かったかと思う。
僕の言動で彼女の心が軽くなるならば、それ程幸せなことは無かったのだ。
だけど何かが邪魔をして、僕は静かに黙るしか無かった。
「それより、私が1年生の頃夏合宿でサメを見に連れて行ってくれたことがありましたよね」
由紀ちゃんはすぐ表情を隠して、いつもの調子で話し始めた。
「私あの時見たサメが、今でも一番好きなんです」
「由紀ちゃん」
ヤカンの沸騰する音が僕の声をかき消して、彼女はいそいそと台所へ向かった。
ベッドの枕元には、サメのぬいぐるみが置いてある。
「お前か」
こいつに見覚えがあった。
あの時の写真を撮っている由紀ちゃんの笑顔が、何故だが頭に浮かび上がった。
彼女が写真を撮っている姿を、見ていたわけでも無いのに。
由紀ちゃん。
あの時のサメが一番好きなのは、好きな人と見れたからだと思う。
あの時から由紀ちゃんは遼のことが好きだったのだ。
由紀ちゃんの目の前に居る僕と、遠く離れたお前。
今すぐ由紀ちゃんを抱きしめられるのは僕なのに、遼は今もそうやって、サメとなって僕の恋路を邪魔するのだ。
お前は由紀ちゃんを抱きしめることも出来ないのに。
僕は一生、勝てないと言うのか。
由紀ちゃんは、緑茶を淹れた湯飲みを持ってやって来た。
「私、お茶淹れるの上手いんですよ」
彼女は僕に湯飲みを渡す。
彼女の淹れたお茶を飲むのは、これがきっと最初で最後だろう。
「由紀ちゃん、写真撮らせてくれない?」
由紀ちゃんはお茶を啜りながら、
「私ですか」と言った。
一瞬悩んだ素振りを見せて、それから「良いですよ」と小さく笑った。
彼女が恥ずかしそうに笑っている。
僕はあの時の笑顔を頭からかき消すように、一生懸命シャッターを切った。
よろしければサポートをお願い致します!頂いたサポートに関しましては活動を続ける為の熱意と向上心に使わせて頂きます!
