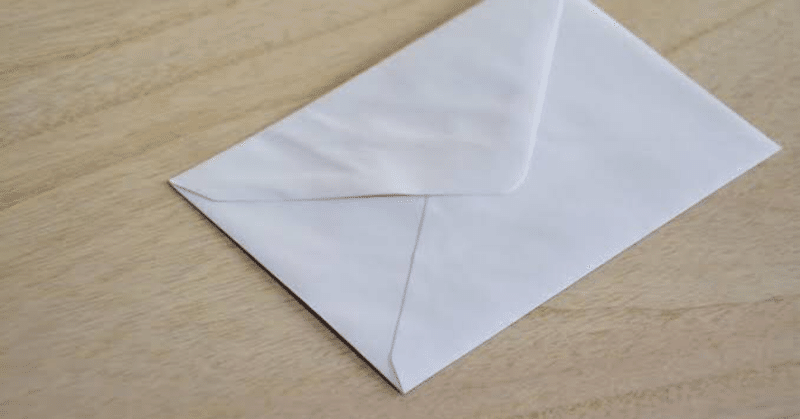
短編 『366日目のキミへ』
真っ赤な郵政カブが、潮風を浴びながら目的地へと向かう。七月も終わる頃、本格的な夏を彷彿させる熱気の中、先へ先へと車輪が駆動する。日が沈みかけた夕暮れ、本日最後の郵便物を届けるために、僕はオートバイを走らせていた。オレンジの光に反射した海を傍目に、海岸を使うルートで配達するのが、日課の楽しみだった。
海岸を抜けて、山道を少し登った坂の上に、小ぢんまりした古い建物へカブを停める。入り口に立ち見上げるように視線を移すと、塗装が少し剥がれている看板には、『しおり』と書かれている。このお店の名前だ。
引き戸の取っ手を掴み、少し力を込めて開こうと試みる。重々しく、けれども軽快な音を立てながら扉が開く。お店へ足を踏み入れると、漂ってくる紙やインクの匂いに懐かしさを感じた。
「あら、ごきげんよう」
入り口のすぐ正面に佇む、黒いエプロンを身につけた店主が、僕に気がついて声を掛ける。埃取りを手に、古びたレジカウンターを掃除している最中だった。
「こんにちは、しおりさん」
僕にしおりさんと呼ばれた店主は、軽く手を振り返してくれる。歓迎されているようでなによりだった。
『しおり』は、僕が毎週訪れる古本屋だ。一週間に一度、このお店の店主であるしおりさんへ手紙を配達している。およそ一年、この場所へ欠かさず手紙を届けていたからか、しおりさんと次第に打ち解けて、少しだけ他愛ない話をする仲になった。一週間にひと時しか訪れないこの時間を、僕は気に入っていた。
「今日もご苦労様」
言いながら、しおりさんが僕の手にあった手紙を受け取る。いつもと同じように、白い無地の封筒だった。封を切り、中に入っていた便箋を取り出すと、笑みをこぼしながら手紙へ目を走らせていた。
彼女は僕よりも年上のはずだが、表情豊かな反応や時折見せる仕草のせいで、ある種の幼さを感じさせていた。
「キミと初めて会ってから、そろそろ一年が経つね」
手紙を読みつつ、僕の顔は見ずにしおりさんが呟く。
「一年なんて、あっという間に過ぎてしまいましますね」
周りの錆びついた本棚を見回しながら、僕は答える。古くても寂れていても、この雰囲気に包まれた『しおり』は居心地が良い。
僕が初めてしおりさんに出会ったのは、配達物をこのお店に届けた八月六日だった。あの日も夏の暑さを身に感じながら、『しおり』に荷物を届けに来た。
引き戸を開けた先にいたのは、一人の女性だった。お店へ入って来た僕を見つけると、人懐っこさのある笑顔で出迎えてくれた。
お店の灯りが切れてしまったの、と僕から受け取った荷物を開ける。中に入っていたのは真っ白な電球だった。『しおり』は小さな建物だが、本棚や天井は高く、しおりさんが無事に電球を取り替えられるか少し心配だった。
壊れそうな木製の椅子に足を掛けて、手を伸ばしながら電球を入れ替えようとするしおりさんを、緊張しながら見守っていた。結局、中々手が天井に届かない姿を見かねて、僕が手伝って電球を取り付けた。
お店の去り際、しおりさんから本当にありがとうね、と声を掛けられた。心からの笑顔を向けられてなんだか気恥ずかしくなり、そのまま『しおり』を後にした。
そしてその一週間後に、手紙を届けるためにまた『しおり』を訪れ、次第に顔見知りとなっていった。
「そういえば、聞きたいことがあるんだけど」
過去に思い馳せていた僕は、声を掛けられて現実に引き戻される。
「なんでしょうか」
反射的に聞き返すと、しおりさんが長い黒髪を左耳にかけながら、言葉を続ける。
「私が毎週貰っている手紙、キミは何も聞いてこないね」
言われて、僕はしおりさんから顔を背ける。
初日に『しおり』へ電球を届けてから、僕は何かしらの広告や書類を、毎週しおりさんへ配達していた。そして半年ほど過ぎた頃から、しおりさんへ宛てられた便箋も届けるようになった。その手紙は必ず白い封筒に入っており、『しおり』の住所以外は封筒に書かれていなかった。
「気にならないわけじゃないですけど、一応仕事で来てますから」
『しおり』へ配達した後、僕は数分くつろいでから郵便局へ帰っている。その時間が心地良くて、勤務中であることを忘れがちになってしまっていた。ましてや、他人の配達物の中身を知りたがるなんて、言語道断だ。
「そっか。それは残念」
本当に残念そうに、しおりさんはカウンターに置いてあった缶コーヒーを開けながら呟く。
「何が残念なんですか」
首をひねりながら僕は尋ねた。毎回しおりさんが、あの便箋を微笑みながら読んでいる姿を知っていたからだ。
「このお店、来週で閉めちゃうの」
苦笑いしながら、しおりさんが答える。その笑みは、後悔なのか諦めなのか、見ていて納得出来るような表情ではなかった。
「そう、だったんですか」
出来るだけ平静を装いながら、僕は辛うじて言葉を返す。僅か一年の付き合いとはいえ、毎週訪れていた場所が無くなるのは、ショックだった。
「キミが毎週配達に来なくなるのも寂しいけど、この手紙も届かなくなると思うと、更に寂しいな、って思ってね」
しおりさんは感慨深そうに、周りにある無数の本を見渡した。 床に転がっていた段ボールが、この場所を去るために使われるものだったんだと、今更になって知った。
僕はしばらく考え事をした後、しおりさんに告げる。
「それじゃあ、そろそろ行きます」
気をつけてね、と気兼ねなくしおりさんが手を振ってくれた。踵を返してカウンターから出口へ向かったが、引き戸を開ける前に、僕は立ち止まって一度だけ振り返った。
「必ず、来週も来ます」
少し目を見開いたしおりさんは、そっと微笑みながら僕を見送ってくれた。
日が半分ほど沈んだ夕焼けの中、再び赤いカブを走らせる。『しおり』から郵便局への帰り道は、毎週通っていたため体が覚えている。ごく自然に進路を辿るバイクに乗りながら、頭の片隅で僕は考え事をしていた。
僕は、人と話すのが苦手で、言葉を選ぶのも話すのも下手くそだ。けれども、何回考え込んで悩んでも、僕がしおりさんに伝えたいことは一つだけだった。
次の週の八月六日、最後の便箋を届けに『しおり』へ向かった。この日が最後だと分かっていたからか、お店の引き戸に手をかけた時、少し緊張が走った。勢いよく戸を開き、『しおり』に足を踏み入れる。
「こんにちは」
扉の先で作業をしていたしおりさんを見かけて、挨拶する。声が少し震えていたかもしれない。
「…ごきげんよう」
僕に気づいたしおりさんが、いつもより少し間を空けて挨拶を返してきた。床には古い書物と段ボールが大量に転がっていて、店内の棚に残っている本はあと僅かだった。
「もう少しで、作業が終わるの。少しだけ待っていて貰ってもいい?」
棚の上にある本の埃を払いながら、しおりさんが言う。棚に残っている本と梱包された段ボールの量からすると、およそ十五分程で作業は終わりそうだった。
「せっかくなので、僕も手伝いますよ」
ネクタイを緩めてシャツの一番上のボタンを外すと、首元に少しだけ余裕が出来た。多少は、動く作業にも取り組めそうだった。
僕の言葉にしおりさんは、何か言おうとして口を噤んだ。その後、困ったような笑みを浮かべながら、ちょっとだけお願いね、と素直に受け入れてくれた。
僕は残っている本を手に持ちながら、しおりさんの指示に従ってしばらく作業に没頭した。
初めて会った日も、この『しおり』の電球を付け替える仕事を手伝っていた。それからも幾度となく訪れた場所だからこそ、最期の瞬間を見届けられるのは、寂しくて嬉しかった。
一通り作業が終了したところで、僕としおりさんは一息ついた。
「最後まで手伝ってくれて、ありがとうね」
言いながら、しおりさんは僕に缶コーヒーを渡してくれた。僕はお礼を言いながら、缶のプルトップを開けて少しだけ口にする。何故だか、苦味の広がっていく感覚が、今は心地良かった。
「お店を開いて五年近く経ってたけど、あっという間だった気がするよ」
コーヒーを飲みながら、しおりさんが誰に向けてでもなく呟く。ここに通い始めてからずっと聞きたかったことを、僕はしおりさんに尋ねた。
「しおりさんは、どうして本屋を始めようと思ったんですか」
しおりさんは僕の質問に少しだけ首をひねり、空を仰いで考え始める。それほど考え込むような疑問だったのだろうか。
やがてしおりさんは、たどたどしく言葉を紡いでいった。
「多分、私は本屋じゃなくても良かったのかもしれない」
その答えが、少し意外だった。色んな本が好きで、それに囲まれている空間が居心地が良い、というふうに以前言っていたからだ。
「べつに、本が嫌いなわけじゃないよ。むしろ大好きだと思う」
僕の表情に何か出ていたのか、しおりさんが慌てて取り繕いながら続ける。
「でも、本が好きというより、私は物語が好きなの」
照れ臭そうに笑いながら、しおりさんは自分の気持ちを誤魔化すみたいにコーヒーを再び口にする。
「物語、ですか」
「そう。本は勿論だけど、ドラマや映画でも、音楽でも、そこには物語があるの。誰かが創り出したそこにしかない世界が、私は好きなんだよ。だから、そういう意味ではレンタルショップとかでも良かったかもしれないね」
しおりさんは真剣な眼差しで、がらんどうとなった店内を見渡す。
「でもやっぱり、この場所が変わっていくのは寂しいし悲しいよ」
曖昧な表情で、僕に笑いかける。
多分彼女は、この場所に対して笑顔で見送りたいし、涙を流して別れを告げたいのだろう。しおりさんよりも僕の方が想いは軽いだろうけど、少しだけ気持ちが汲み取れた。
僕は決心して、自分が持ってきた郵便鞄から白い便箋を取り出した。
「しおりさんに、これを」
いつも通りに手渡すと、彼女ははにかみながら手紙を受け取った。封を丁寧に切っているしおりさんに、僕はゆっくりと口を開いた。
「大丈夫、知ってたよ」
しかし、僕の言葉を遮る化のように、しおりさんが先に告げる。何を言われたか頭が回らず、思わず聞き返す。
「何が、ですか」
封を切り終えたしおりさんは、優しい笑顔で手紙を開く。一通り目を通した後、手紙から僕へ視線を移す。
「知ってたよ。毎週この手紙をくれていたのが、キミだったこと」
僕は思わず言葉に詰まる。それは、予想していなかった。
「宛名が書いてなかったけど、言葉の選び方がキミの感じと似てたからね。それに、前書いてもらった文字の筆跡が同じだったから」
咎めるわけでもなく、少しだけ笑みを浮かべて彼女が続ける。
「キミが本を好きなことも、この場所を大切に想ってくれていることも、私は知ってるよ。だから、ありがとうね」
言いながら、しおりさんはカウンターの引き出しから取り出した物を、僕へ差し出す。それは、白い便箋だった。
震える手で受け取りながら、僕は落ち着いてきた頭で必死に言葉を紡ぐ。
「今日、本当は伝えるつもりで来たんです。この一年のことを」
しおりさんは、僕の言葉に対してゆっくりとかぶりを振る。
「毎週、十分伝えてもらったよ。話すのが苦手なら、無理しないで大丈夫だからね」
たしかに、他人と面を向けて話をするのが苦手だと、半年ほど前に届けた最初の手紙に書いていた。ちゃんと、僕の綴った言葉を、読んでくれていた。
思わず零れそうになる涙を堪えながら、ありがとうございます、と小さい声で伝える。今はそれだけしか出来なかった。
少し照れ臭そうにしながら、しおりさんは思い出したように僕へ告げる。
「手紙は、明日になったら読んでね。今日はダメだから」
その後、何度理由を聞いてもしおりさんは答えてくれなかった。何気ない話を挟みながら、『しおり』で過ごす最後の時間が過ぎていった。
しおりさんと別れて郵便局へ戻り、いつもより少し遅く退勤する。忘れないように、自分の鞄へ白い便箋を入れようとした。
ふと、受け取った便箋を裏返してみる。右隅の方にしおりさんの住所と連絡先が小さく載せてある。そして、真ん中に綺麗な字で宛名が書かれていた。
『366日目のキミへ』
この手紙は、もう『しおり』へ通うことのない、明日からの僕に向けてのエールだった。
今すぐに、一文字ずつ内容を噛み締めながら読みたい気持ちを抑えながら、僕は大切な手紙をそっと鞄にしまい込んだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
