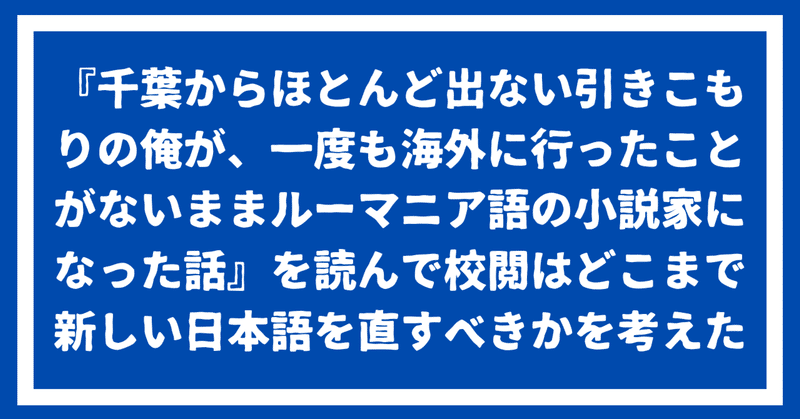
僕が言いたいのは永遠
『千葉ルー』
なかでも俺が一番好きなのが「永遠と」という言葉だ。どうして「延々と」が「永遠と」になってしまったんだろうか。これについて考えると胸が高鳴る。何より響きがいい。「永遠と」なんて、これだけで詩じゃないか。おそらく俺と同じような考えをした人々が、この言葉を「延々と」の代わりに使い始め、徐々に広まりだしたんだろう。そして衆目に触れることで間違いとも言われるようになった。
俺としてはこういう言葉が間違った、もしくは奇妙な日本語として駆逐されるのは惜しい。留保とともに考察され、そして正しいとされる日本語とともに共存していってほしいと願っている。
エッセイ『千葉からほとんど出ない引きこもりの俺が、一度も海外に行ったことがないままルーマニア語の小説家になった話』(済東鉄腸、左右社、2023年、以下『千葉ルー』)には、そのタイトルが示すように、大学生活や就職がうまくいかず自宅にこもっていた著者が一本のルーマニア映画に出会ったことからそれまで縁もゆかりもないルーマニア語に目覚め、書籍や映画、そしてインターネットを通じて同国から遠く離れた千葉に居ながらにして独力で「日系ルーマニア語」作家を標榜しながら突き進んでいく勇ましくも愉快な足取りが綴られています。
いかにして著者が習熟至難であるはずのこのマイナー言語に長じていったのかは本書を読んでいただくとして、本作は外国語を通して日本語を見つめ返した本としても読むことができます。
「永遠」と「延々」
そのうちのひとつが冒頭に示した一節です。「永遠(と)~する」という言い回し、耳にした方はどれだけいるでしょうか。インターネットで検索すれば、「永遠と見てられる」「永遠迷子になった」といった用例はいくつも見つかります。
「どうして『延々と』が『永遠と』になってしまったんだろうか」と書かれていますが、この言い回しが広まった契機のひとつとして、プロ野球のダルビッシュ有選手によるツイッターでの2010年の発言は大きかったのではないかと思います。

私もしばしばプールに行くことがありますが、コースを往復してきても休息せずそのままくるりとターンして泳ぎ続けるおじさんの姿をよく見かけます。そんなおじさんがぐるぐると描く無限の円環の軌跡は、なるほど「延々」よりか「永遠」と言うにふさわしいかもしれません。
とはいえ「永遠」ではなく「延々」では?と問うた読者の気持ちもよく分かります。何はともあれ辞書を引いてみましょう。
【延延】[副・形動ト タル]とぎれることなく長く続くさま。「―と続く悪路」「―五時間に及ぶ議論」
【永遠】(前略)注意「延々」と混同して、「永遠と」の形で副詞として使うのは誤り。「× 永遠と話を聞かされる」
【延々】⦅ト タル⦆〈いつまでも/どこまでも〉長く続くようす。「―十時間・早くやめればいいのに―と話した・―百キロに及ぶ」
【永遠】(一は省略)二⦅ト タル⦆〔俗〕延々。「―と続く道」〔二〇一〇年代に広まった用法〕
明鏡と三国がこの「永遠」の用法に言及しています。双方最新版で新たに加わった記述で、明鏡はハッキリと「誤り」とし、三国は俗語扱いです。「いけボ」のような新語を取り上げる一方で正誤へ踏み込んだ解説が特色と自負している明鏡に対し、三国は、自らに寄せられがちな「新語辞典や俗語辞典で何でもありだ」という意見を誤解だと序文で否定し、言葉を映し出す鏡、正す鑑というふたつの「かがみ」を任じています。

巨大戦艦
『千葉ルー』では、辞書への言及もあります。
辞書は船であるって例えがあるよな。でもそれで表される船っていうのは得てして小舟みたいなものだ。だけど俺の頭に浮かぶものは違う。小さな船じゃない、巨大戦艦だ。日本語とみなされないものを、そして時には他の言語を排撃する戦争の道具だ。それでいてこういう戦艦にこそ深く魅せられる人々がいるよな。辞書も正にそんな感じで、他でもない俺自身がそれに魅せられた一人なんだ。
三国の編集者にしてみれば多少言いたいところもあると思いますが、この「巨大戦艦」という評には、日ごろ私自身が手にしている冊子についても考えないわけにはいきません。『記者ハンドブック』のことです。
記者ハンについては何度も言及してきました。往年に比べると用語への断定的な表現や指示はかなり減ってきているとはいえ、無数の記者が書く記事をひとつのフォーマットにまとめる性格上、辞書を上回る規範性を有しています。最新版で新たに誤用と見なされるようになった「スマホゲームに課金する子ども」という文章に「課金は払う立場ではなく払わせる立場」として修正を提案するたび、道端の若芽を引き抜いているような気分になることがあります。
「永遠泳いでる」といった用法が新たに生まれたのは、「延々泳いでる」には宿らないニュアンスがあるからでしょう。「延々続く宴会」と書いた人はそろそろ帰りたいと思っているはずで、「いつまでも」を肯定的に捉えた手ごろな熟語として編み出された「永遠と見ていられる」を、誤用と切って捨てるには抵抗もあります。
ただその一方で、仮にこの用法の「永遠」が記事に登場したら、私は校閲記者として躊躇なく指摘を入れます。そもそも校閲に回る前にデスクが直してしまうことでしょう。三国の〔俗〕という記号が示す通り、仲間内ではなく新聞記事で用いるにはまだふさわしくないからと判断するためです。「巨大戦艦」を意識するのはこんな時で、校閲記者は自分自身の言語感覚と、言うなれば戦艦の乗組員としての感覚の微妙なズレの間で絶えずバランスを取っています。
そこにいない
などとちょっと気取ったことを書いても、実際は外の天気も分からないフロアの奥で、刷りと記者ハンとパソコンを代わる代わる見つめる日々。昔、「中東某国の指導者の就任した月が間違っている」と指摘して現地の記者に外電記事を直してもらったことがあるのですが、直った記事を前に「この国、どのへんにあったっけな……」とぼんやり思ったのを覚えています。現地の専門記者に、過去記事のデータベースを引っ張り出して修正を要求する。それであんたは何を知っているのかと自嘲めいた気分になることは、新聞の校閲記者としてしばしばあります。激流が渦を巻く豪雨の被災地にも、怒号が飛び交う凄惨な事件現場にも、校閲記者は「そこにいない」のです。
そんなことを思い起こしたのは、『千葉ルー』の最後に置かれたこの一節に行き当たったからでした。
この本はまず俺自身のために書いたんだけども、俺みたいなやつのためにも書いてる。(中略)実際に外国に移住したり、世界を飛び回ったりして、外国語で小説とか詩を書いたり、文学を研究しているって人間に比べて、自分なんかウンコやんってへこんでるアンタだ。というか今はコロナで全部が酷いことになってるから、日本中にそんな風にへこんでる人々が溢れている。
だが俺はアンタにこそ、他にはない可能性があるって信じてるよ。何でってそれは俺だからね、自分なんかダメダメだと思い続けていたかつての俺。外国に行く必要がないとは言わないよ、行ける機会があるんなら行くべきだ。だが今立っているその場所でもやれることがある、その場所でこそ成し遂げられることがある。
校閲にとっての「その場所」は、机の前です。言葉を正し、誤りを排し、目に見える働きを残すのではなく、大きな過ちを「残さない」ことが至上命令の部署です。軽々しく何かを分かったつもりにならず、さりとて過剰に留保をつけて何も知らないと誇ることもせず、この場所で言葉のためにできることは何なのかを、これからも探り続けねばなりません。

