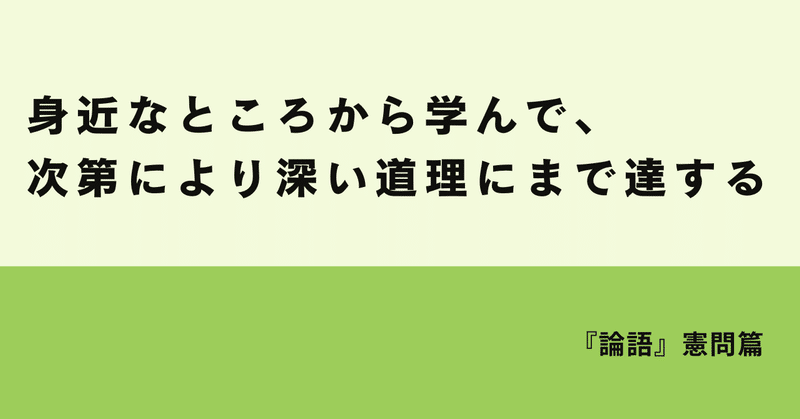
人生を豊かにする中国古典の名言#50
【今日の名言】
下学して上達す
(読み:カガクしてジョウタツす)
身近なところから学んで、次第により深い道理にまで達する、という意味。
晩年の孔子が、自らの在り方について述べた言葉になります。
つまり、
いきなり難しいことから学び始めたのではなく、身近にある簡単なことから学びを進めていったからこそ、より教養を深めることができた
ということですね。
晩年の孔子は、自分の夢や志が実現されるのを諦めていた節があります。
礼や政治、歴史に人材育成など、ありとあらゆることに詳しかった孔子ですが、最後まで、彼の夢である「仁のあふれる世界」を作ることができなかったからです。
はじめはどこかの国政に関わり、仁の思想を広げようとしていたのですが、孔子の夢を理解してくれる君主はなかなか現れませんでした。
一時期、祖国の魯で国政に携わっていたこともあるのですが、仕えていた君主がクーデターにあって孔子自身も亡命することになり、結局は在野で弟子の育成に励む日々を送ることになったのです。
『論語』を読んでいると、孔子の初期の言葉からは夢と理想を実現する気迫が伝わってくるのですが、晩年の孔子の言葉からはある種の諦めといいますか、どこか達観したような印象を受けます。
我を知る莫きかな
(読み:ワレをシるナきかな)
自分を理解してくれる人がいないのは残念だ、という意味。
晩年の孔子は、時々こういったつぶやきを残しています。
ちょっと寂しそうですよね。
この言葉を聞いた弟子の子貢(しこう)も「どうしたのだろう?」と疑問に思ったようです。
孔子に質問しているので、ちょっとその内容を見てみましょう。
子貢が先生にお尋ねして言った。
「自分を理解してくれる人がいない、というのはどういう意味でしょうか?」
先生が言われた。
「天を恨みはしないし、人を咎めたりもしない。私は身近なところからコツコツ努力して道理を極めるところまで達したのだ。そんな私のことを理解してくれるのは天だけだろうよ」
太字の部分が今回ご紹介している言葉ですね。
子貢は「私は理解していますよ、先生!」という気持ちを込めて質問したのだと思いますが、このときの孔子は悟りを開いたような状態だったのでしょう。
もはや自分のことを真に理解してくれるのは天しかいないのだ、と諦めたかのような口調で話しています。
もしかしたら、どこか遠い目をしていたのかもしれません。
でも、孔子はそれほどまでに懸命に努力を続けてきたのです。
必死に努力してきたからこそ、反動も大きかったのでしょう。
ですが、孔子の夢は実現しなかったものの、彼の努力は『論語』という書物の形で、後世の我々にまで伝わっています。
著名な経営者や偉人にも『論語』の愛好家は多く、孔子の思想は確かに受け継がれ、間接的に世界に影響を与えているのです。
2500年ほどの時を超えて、私たち日本人の心にも「仁」の思いが根付いています。
色々なことがある現代だからこそ、今一度「仁」の思いを大切にして、優しい世界を作っていきたいですね。
今回の名言は以下の記事でも取り上げています。
皆さんの気づきや学びになれれば幸いです🍀
スキやフォローもいただけますととても励みになります!
「学びになった」等のコメントもとても嬉しいです😊
いつも応援いただきありがとうございます!
前回の名言はこちら👇
次回の名言も公開しました!
メンバーシップも始めました!
学びにつながる記事を定期的にメルマガとしてお届けします。
初月無料ですので、お気軽にご参加ください🍀
サポートをいただけますと励みになります!いただいたサポートは資料の購入や執筆環境の整備などに使わせていただきます!より良い記事をお届けできるように頑張ります!
